
【今日は何の日?】令和07年02月04日|今日の記念日・出来事・暦など
令和07年02月04日(火)は?
レディース・ユニフォームの日

オフィス向けのレディースユニフォームのカタログ販売などを行う企業によって結成された「レディースユニフォーム協議会」が制定しました。
日本の制服文化を背景に、女性にとってのオフィスユニフォームの必要性や、その役割・効用を広く発信し、ユニフォーム市場の活性化を目指すことが目的です。
日付は、この日が立春となることが多く、全国的に春夏用の展示会が開催される時期であること、そして数字の2と4を組み合わせると「ユニ(2)フォー(4)ム」という語呂合わせになることから選ばれました。
日本では制服が社会文化として深く根付いており、オフィスユニフォームは企業のイメージアップやスタッフ間の一体感の醸成に大きく貢献しています。
この記念日を通じて、ユニフォームの持つ魅力や価値が再認識され、より多くの企業や個人がその効用を理解し活用することが期待されています。
また、近年ではデザイン性や機能性に優れたユニフォームが増えており、働く女性たちの多様なニーズに応えるラインナップが展開されています。例えば、環境に配慮したエコ素材の採用や、動きやすさを重視したストレッチ素材の活用などが挙げられます。
高齢者安全入浴の日

一般社団法人高齢者入浴アドバイザー協会が制定。
高齢者に適切な入浴指導を行うこの協会は、冬季に入浴中の死亡事故が増加する現状を受け、高齢者が安全に入浴できるよう意識を高める目的でこの日を設けました。
日付が2月4日である理由は、いくつかの語呂合わせに由来します。「不老不死」という言葉を「風呂で死亡事故のない『風呂不死』」にかけ、「不(2)死(4)」と読み替えています。また、「入浴」を数字で表すと「入(2)浴(4)」となることも関係しています。さらに、2月4日は立春の頃であり、暦の上では新しい一年の始まりにあたります。この時期に安全な入浴を願う意味も込められているのです。
日本の入浴文化は豊かで、心と体を癒す大切な習慣です。しかし、高齢者にとって入浴はリラックス効果がある一方で、体調の変化やヒートショックなどのリスクも伴います。この記念日を機に、高齢者の安全な入浴方法について見直してみるのも良いかもしれません。
具体的な安全対策としては:
入浴前に脱衣所や浴室を暖める:
急激な温度差を避け、ヒートショックのリスクを減らします。適切な湯温を設定する:
湯温は41℃以下に設定し、長時間の入浴を避けるようにしましょう。家族とコミュニケーションを取る:
一人での入浴が不安な場合は、家族に声をかけておくと安心です。体調が優れないときは無理をしない:
めまいや疲労を感じる場合は、入浴を控えることも大切です。
高齢者だけでなく、私たち全員が安心して入浴を楽しむために、日頃から安全に気を配ることが重要ですね。
妊娠の日
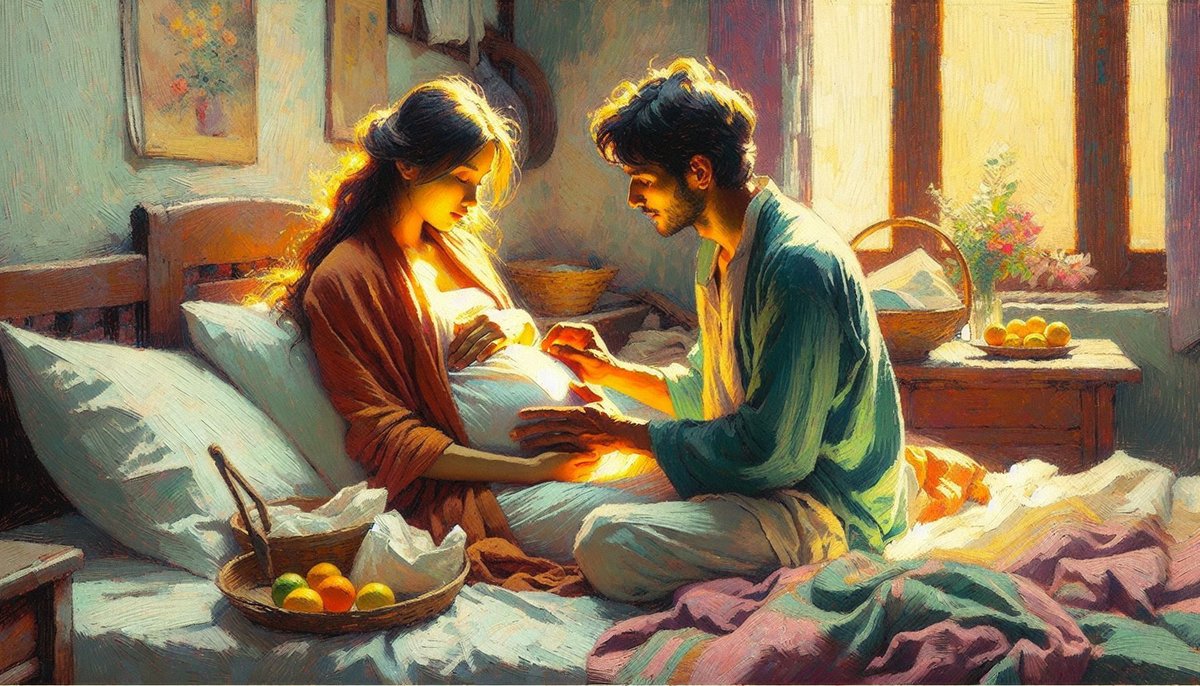
妊娠前から出産後まで女性をサポートするジュンビー株式会社が制定。
出産を望む女性たちが、希望どおりの未来を手に入れ、産後まで健やかな毎日を過ごしてもらうことを目的としています。そのために、妊娠や出産に関する情報や商品を提供し、女性たちの不安や疑問に寄り添っています。
日付が2月4日である理由は、数字の2と4を「妊(2)娠(4)」と読む語呂合わせからきています。この語呂合わせによって、多くの人々に覚えてもらいやすくし、妊娠や出産について考えるきっかけとなることを意図しています。
妊娠や出産は、女性にとって人生の大きな節目であり、喜びと同時に多くの不安や疑問も伴うものです。この記念日を通じて、正しい情報の提供やサポート体制の強化が促進され、より多くの女性が安心して新たな命を迎えられるようになることが期待されています。

近年では、妊活に取り組むカップルが増えており、情報収集や専門家への相談の重要性が高まっています。また、働く女性の増加に伴い、仕事と妊娠・出産・育児の両立が社会的な課題となっています。こうした背景から、企業や社会全体での支援体制の整備が求められています。
旧暦:1月7日
六曜:先勝(せんしょう・せんかち・さきかち)
急ぐことは吉。午前は吉、午後は凶。
先勝には「先んずれば必ず勝つ」という意味があり、「万事において急ぐと良いことがある」とされる日。勝負事にも良く、先手必勝とも言われますが、時間帯によって吉凶が変わり、午前(14時)までが吉、午後からは凶となります。
葬儀などの弔事を行っても問題はないとされていますが、お通夜に限っては夕方から始まり夜通し続くこと、加えて翌日は友を引き連れる「友引」の日になってしまうため、営むことを避けるべきと考えられています。
六曜(ろくよう・りくよう)とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つの曜を指し、日にち毎に縁起の良い、悪い、を判断する考え方です。
「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「大安」→「赤口」の順で繰り返されています。
六曜は中国から始まり、日本には鎌倉時代に伝わりました。江戸時代には縁起の良し悪しを判断するものとして広まりました。
六曜は根拠のない迷信と見なされることもありますが、日本の文化の一部として受け入れられています。
日干支:甲辰(きのえたつ/こうしん)
日家九星:五黄土星(ごおうどせい)
二十八宿:翼宿(よくしゅく)
耕作始め、植え替え、種蒔きに吉。
高所作業、結婚に凶。
十二直:満(みつ)
全てが満たされる日。
新規事、移転、旅行、婚礼、建築、開店などは吉。 動土(地面を掘り返して土を動かす)、服薬は凶。
七十二候:東風解凍(はるかぜこおりをとく)
第一候。立春の初候。
春風が川や湖の氷を解かし始める頃。
春の季語にもなっている東風(こち)は、春先に吹く東寄りの柔らかな風のこと。春本番の穏やかな風とは異なり、まだ冷たさの残る早春の風です。
「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花、主なしとて春を忘るな」
菅原道真のこの句をはじめ、多くの和歌や俳句に東風は詠まれてきました。
動植物などの名詞を伴って「梅東風(うめごち)」「桜東風(さくらごち)」「雲雀東風(ひばりごち)」「鰆東風(さわらごち)」「朝東風(あさごち)」など、時間や時期に応じた名で呼ばれることもあります。
一年の始まりでもあるこの候は、春の兆しとなる柔らかな風が吹き、冬の間に張りつめた厚い氷を解かし始める、まさに春の訪れを表しています。
まだまだ寒さは残りますが、ようやく春の足音が聞こえ始めました。
七十二候は、一年を七十二等分し、それぞれの季節時点に応じた自然現象や動植物の行動を短い言葉で表現し、約五日間ごとの細やかな移ろいを子細に示したものです。
暦注下段:
大明日(だいみょうにち)

七箇の善日の一つ。
「天と地の道が開き、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」という意味があり、「太陽の恩恵を受けて、全ての物事がうまくいく」とされる何事にも縁起のいい日。
他の凶日と重なっても忌む必要がないとも言われています。
復日(ふくにち)
重日と同じ効果があるとされる日。
この日に善行を行うと、重複して大吉になる
とされています。
暦注下段とは、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶についての暦注のことで、単に下段とも言われています。古代中国から続く占術である農民暦が基になっています。
科学的根拠がない迷信としての要素が多く、明治時代に旧暦からグレゴリオ暦へ移行するときに政府によって禁止されましたが、当時の庶民は密かに使用し続けました。それ以前にも何度か当時の朝廷や政府によって禁止されることもありましたが、根強く残り続け、現代では自由に使用できるようになりました。それだけ庶民に強く支持されてきた暦注とも言えます。
選日:天一天上(てんいちてんじょう)

方角の神様である天一神(てんいちじん)が天に上っている期間。
癸巳(みずのとみ)の日から戊申(つちのえさる)の日までの16日間のこと。
この間は天一神の祟りがなく、どこへ出かけるにも吉とされています。
天一神が天に昇っている間は、代わりに日遊神(にちゆうしん)と呼ばれる神様が天から降りてきて、家の中に留まるといわれています。この神様は不浄を嫌うため、家の中を清潔に保っていないと日遊神がお怒りになり、祟りを起こすともいわれています。
いいなと思ったら応援しよう!

