
手話体験はもう古い?鈴木さんが教えてくれたこれからの福祉教育とは。
このツイートをしたところ、福祉教育についての相談をDMで頂きました。
そこで今回は、「これからの福祉教育」について書きたいと思います。
子どもに体験させたい福祉アプリ
— エイ先生 (@zikatu1) January 28, 2021
・こえとら(耳)
→筆談アプリ
・Seeing Ai(目)
→カメラであらゆる物を識別
・よめるんです(読)
→作った文章を音声で流せる
・発達障害簡易チェッカー
→障害は特別じゃないと気づけるアプリ
手話体験も大事だけど、壁を越えるためのアプリ体験も大事! pic.twitter.com/oAF7SIU6pi
鈴木さんの話
「生活で困っていることはありますか?」
これは、去年の8月に手話教室をした時、児童がゲストティーチャーの聴覚障害者の方にした質問です。
その聴覚障害者の方(鈴木さん(仮))は、しばらく考えてから、こう答えました。
「生活で困っていることねー、んー特にないかなぁ。今はアプリで結構いろいろ便利になったからね。」と。
この言葉は、それまで、学習を重ねてきた子どもたちにとって衝撃でした。
というのも、私も含め障害者はきっと困っているだろう。そしてその助けになりたい。というのが学びのモチベーションだったからです。
それ以外にも鈴木さんは、児童からのいろいろな質問を嫌な顔一つせず答えてくれました。
・朝はスマホのバイブで起きること
・手話を使えない友達とは、LINEでやりとりしていること
・テレビは字幕放送が増えたから手話がなくても楽しめること
・買い物はネットショッピングで宅配で届くから困らないこと
・聴覚障害者でも、実は手話を使える人は少ないということ
などたくさんのことを教えてくれました。
私たちの生活がアプリやネットで便利になったように、障害者の方の暮らしも、大きく変わっているということに気づかされた瞬間でした。
もちろん鈴木さんのような方ばかりではないと思いますが、この鈴木さんとの出会いから、4年生の福祉学習は、「障害者を助けよう」というねらいから「なぜ鈴木さんは、困っていないのか」という問いについて学んでいくことになりました。
アプリがコミュニケーションの壁を壊す
そこから児童と一緒に、福祉アプリについていろいろと調べてみると、様々な障害者支援のアプリがあることが分かりました。
冒頭で紹介したツイートはそれらのアプリの一部をツイートしたものです。
これらのアプリを体験した子どもたちは、
「これなら、手話が使えなくてもコミニュケーションが取れそう」
「困っている人がいたらこのアプリを使って助けてあげたい」
「耳が遠いおばあちゃんにも紹介したい」
など、アプリを使うことで、コミニュケーションの壁をグッと下げることができると実感していました。
また、「こんな風に誰かを助けるアプリを作ってみたい」という子もいました。
今現在は、プログラミングを使って、「福祉に役立つロボット作り」をテーマに学習を進めています。
ここからは、1年間福祉教育について子ども達と共に学び続けてきた分かった気づきを元に、「これまでの福祉教育」と「これからの福祉教育」についてまとめます。
これまでの福祉教育
これまでの福祉教育は、体験がメインでした。
手話体験、点字体験、車椅子体験、アイマスク体験。
そうした体験を通して気づいたことをプリントに書き、模造紙にまとめ、全校生や保護者に紹介する。
そのような活動をしてきました。
きっと多くの学校でも似たようなことをしているのではないでしょうか。
相手の生活や立場を経験することで、その人の気持ちに気づかせる。
そして、その上でどのような支援が必要かを考える。
いわば、障害者を理解する「ハート」の教育です。
それが福祉教育だと思っていました。
しかし、「鈴木さんはなぜ困っていないのか」という問いを考えていく上で、ハートだけでは、本当の意味での福祉にはつながらないと考えるようになりました。
これからの福祉教育
改めて、福祉教育とは何か?と考え、調べた時に、一番しっくりきたのが川崎市の社会協議会の考え方です。
一部抜粋しながら紹介します。
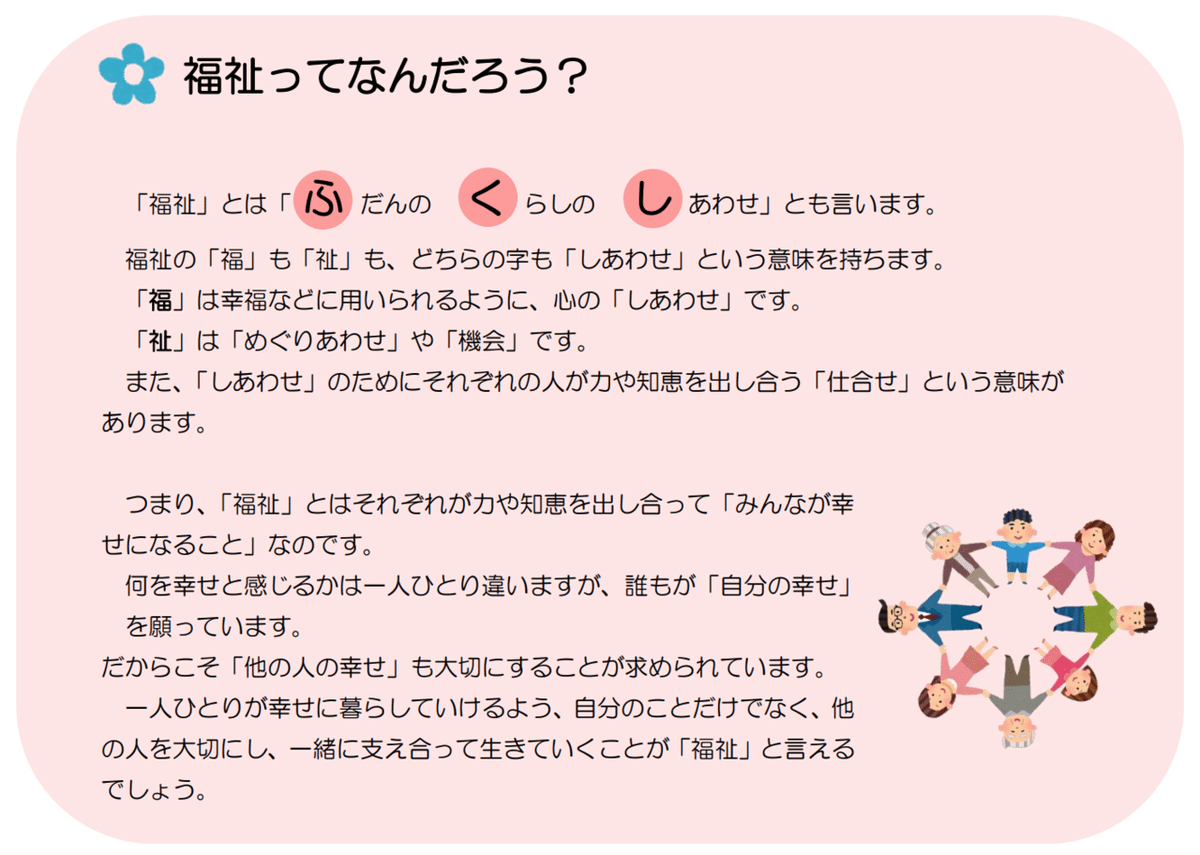

つまり、福祉教育とは、障害者理解だけではなく、みんながよりよく暮らせるための問題を見つけ、それを解決するアイデアを考え、形を作っていく。いわば、問題解決型の学習です。
障害者を助けるという点で考えると、目の前の人を助ける直接的な支援と、目の前にいない人の問題を解決する間接的な支援があるということです。
わたしはこの間接的な支援を児童に分かりやすいように「デザイン」とよんでいます。
これからの福祉教育は、気持ちで助ける「ハート」だけではなく、アイデアで助ける「デザイン」が一つのキーワードになると思います。
相手を尊重する「ハート」と、暮らしをよくする「デザイン」の発想力を育むことが、みんなの「ふだんのくらしをしあわせにする」福祉社会の実現に必要なのではないでしょうか。
テクノロジーが作るこれからの未来

令和2年度版科学技術白書https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202001/1421221.html
最後に紹介したいのは、これからの未来についてです。
これは、科学技術白書が令和2年度にまとめた、20年後の未来を予想した図です。的中率はなんと7割とも言われています。
よく「子どもが大人になった社会を予想して、教育することが大事」と言われますが、あらゆる生活や福祉の問題は今以上にテクノロジーで解決できる時代になります。
そうした未来を作っていく子どもたちに、これまでの福祉教育だけではなく、テクノロジーで解決できるという経験と発想を学ばせていくことが学校教育で大切だと思います。
200年前にルイブライユが聴覚障害者の暮らしをよくしようと、手話を発明したように、今のデジタル時代にテクノロジーを利用して、障害だけでなく、あらゆる問題の壁を乗り越えられる市民を育てていく、それがこれからの福祉教育なのではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
