
【かんたん解説】深夜も営業するBARなどを始めるときの手続きを、誰よりも分かりやすく解説します!
この記事では、BARを始めるにあたって必要となる「深夜酒類提供飲食店営業の届出」という手続きを、できるだけ簡単に分かりやすくお伝えしております。
最後までお読みいただくことで、飲食店の中でもBARを開業するときに必要となる手続きについてご理解いただけるかと思います。
どんなときに必要な手続き?かんたん解説します。
■バーやパブ、バールなど深夜の時間帯に主にお酒を提供する営業をする場合には「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出します。
ここで重要なのは太文字に大きくした部分、「深夜の時間帯」と「主にお酒を提供する営業をする場合」の2か所に該当する場合、この手続きを行う義務が発生します。
・「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。
・「主にお酒を提供する営業をする場合」とは、そのままの意味ですが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。

■注意点
深夜酒類提供飲食店営業では、「接待行為」と「深夜の時間帯に客に遊興をさせる」ことができません。また、「客室の照度は10ルクス以下」、「複数の客室がある場合、1つの客室面積を9.5㎡以下」にすることはできません。
・「接待行為」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。いわゆるキャバクラやホストクラブなどが該当します。
・「深夜の時間帯に客に遊興をさせる」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合を指します。いわゆるクラブ(DJが音楽を掛けてお客さんが踊っている方のクラブ)などがこれに当たります。
・「客室の照度は10ルクス以下」となるような照度(明るさ)では営業できません。例えば、深海バーのような暗い雰囲気が演出されたお店などの場合です。
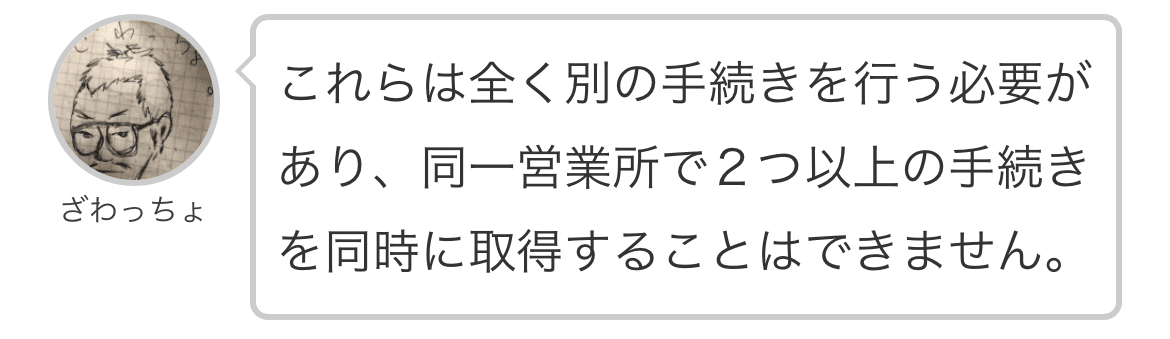
・「複数の客室がある場合、1つの客室面積を9.5㎡以下」となるような個室を設けることはできません。
図を用いて説明しますと、小さな店舗では営業店舗が狭く全体でも面積を満たすことが困難ですが、客室となる部分が1室であれば、9.5㎡未満であっても営業することが可能です。

しかし、下図のように客室を区切り個室となるような客席があると、1室につき9.5㎡以上の面積が必要となります。

費用はかかるの?
行政庁に対する届出のための手数料はありません。
行政機関から必要書類を取得するために、数千円ほど掛かります。
必要となる書類
【法定の書式があるもの】
(下記、警視庁のHPよりダウンロードしていただけます)
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
【作成しなければならないもの】
・メニュー表(概要)
・営業所の配置状況を記載した図面(座席、テーブルなど)
・照明、音響、防音設備を記載した図面
・営業所・客室の面積を求積した図面および求積表
・営業所の存在するフロアの平面図
・営業所付近の見取り図
・用途地域を証明するもの
【公的機関より取得するもの】
・本籍地の記載がありマイナンバーの記載がない住民票(法人の場合は役員の全員分、届出前3か月以内のもの)
・(法人の場合)履歴事項全部証明書
【その他用意しなければならないもの】
・飲食店営業許可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・建物使用承諾書
・(法人の場合)会社定款の写し
※行政書士に依頼した場合は、委任状が必要となります。
※その他、営業施設の概要や、自己所有物件の場合には建物の全部事項証明書、外国人の場合には在留カードのコピー、管轄によって誓約書などを求められる場合もございます。
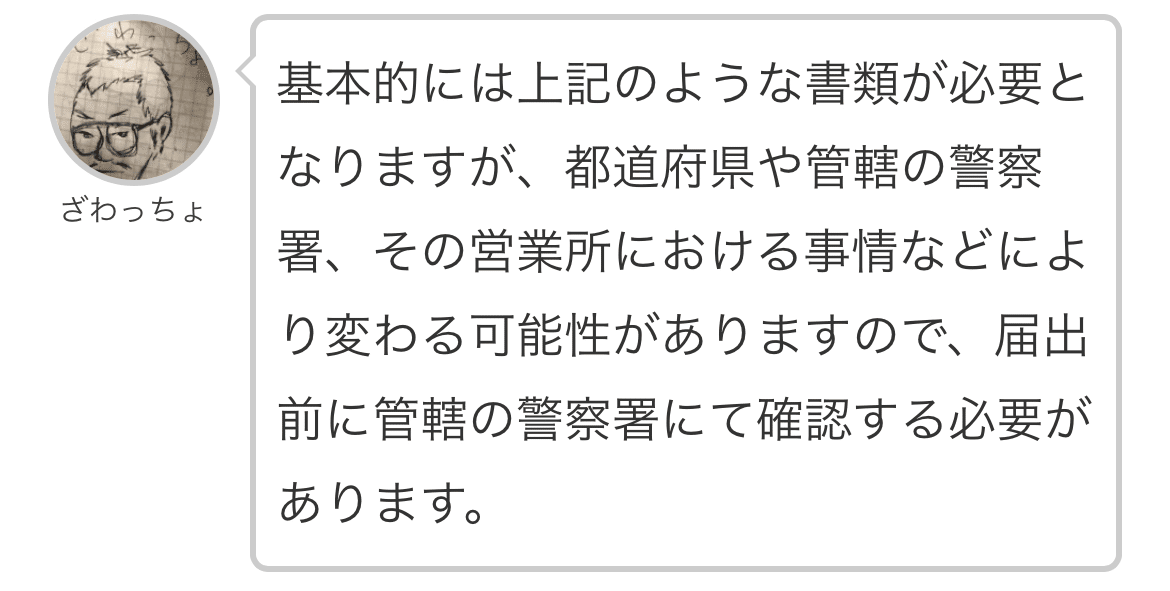
もしも、ご自身で手続きを行いたい場合、法定の書式があるものに関しましては、警察署のHPからダウンロードして記入すれば大丈夫です。
このときに、上部にある日付記入欄は届出する日を記入するところですが事前に記入せず、警察署で担当者から提出する届出書類に不備がないことの確認を受けて指示されてから、その場で日付を記入してください。
営業所の配置図や求積図など図面は、営業する店舗が法令に適合しているか確認できる情報が記載されている必要があるため、内装工事のために作成した図面とは全く異なる性質のものです。今ではCADを使用して作成した図面を提出することがほとんどの場合に求められます。
用途地域を証明するものは、市役所等で入手できる資料を基に作成することができます。深夜に酒類を提供する営業をする場所には制限がありますから、本来禁止されている場所において営業をしてしまった場合には罪に問われることになります。事前に用途地域について十分に確認する必要があります。
用途地域とは‥簡単に説明しますと、日本という土地を「ここは人が住むようの地域」や「こっちは工業地域」「商売をするならこのエリア」など、土地(場所)を目的に沿って区分しています。
BAR開業のQ&A
■資格について


「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格をお持ちでなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」がいなければなりません。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。
(営業店舗での収容人数が30人以上となる場合は、防火管理者を選任しなければなりません。)
■営業場所について


日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。
■設備などについて


深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、カウンターの高さが1メートル以上ある構造は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダック(調光器)は認められていません。
これらを修正するために余分に工事が必要となる可能性があるため、居抜き物件の場合には注意しなければなりません。どちらも以前の営業店舗が単なる飲食店だった場合によくあります。


デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制対象外となります。


大阪府の条例によって定められており、「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
・音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
■経営方法について
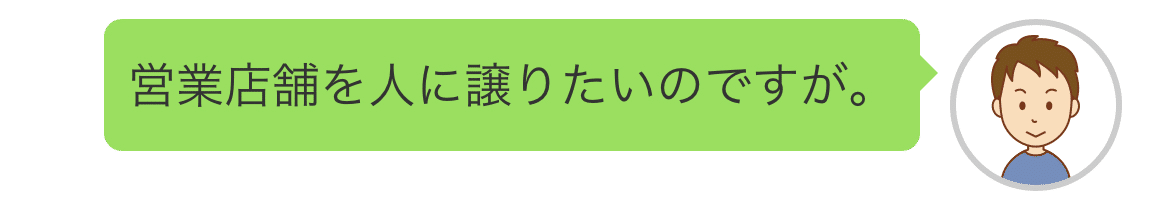

いわゆる名義変更はできません。
お問い合わせ

