
遠回りのススメ その2~「混ざって暮らす」って~
山を削り田んぼを埋めて、
私たちの都合に従ってまちがつくられてきた。
高度経済成長期という突っ走った時代。
自然破壊など目もくれず
高層ビルやコンクリートの建築物が立ち並び、人の暮らしも激変した。
しかし、この時代が生んださまざまなひずみは、
人々の暮らしや生命までもおびやかす深刻な社会現象となってあらわれた。
経済的な豊かさを求めた大量消費社会は
もうすでにその限界を迎えている。
また、自然の営みの前では、人が築いたものに「絶対」はないと、
未曾有の大災害から教わった。
自然という生命ある空間の中で、
助け合い支えあい与えられまた還すという
智慧と工夫に満ちた生命の循環を忘れてはならない。

豊かさを求め、幸せになるべく走ってきたはずなのに。
いったい、幸せな暮らしとはなんなのか。
子どもたちにどんな未来を残すのか。
仲間たちと目指したのはいろんな人が混ざって暮らすまち。
そこには、
つながり(一人ひとりに役割と居場所があるまち)と
あんしん(助けがなかったら生きていけない人は全力で守る)と
緑(ふるさと(命ある空間)の風景を子どもたちに)がある。
まちづくり・人づくりは
「遠回りすればするほどおおぜいが楽しめ
うまくいかないことあるほどいろんな人に役割がうまれる」
これが大前提。
そして、キーワードは
「ぼちぼち、だいたい、ほどほど、まぁまぁ、適当」

ところが、いざまちづくり・人づくりというと
どうしても作る側と作られる側に分けて、
共に生きることを「目的」にして仕事としてしまう。
すぐ組織をつくって、リーダーを決めて、
スケジュールはこのように、、、
そうすると、一気に「ぼちぼち、だいたい、
ほどほど、まぁまぁ、適当」ではなく
てきぱき、きっちり、手分け、仕分けがはじまる。
暮らしの話なのだから
「右に従ってやれる人はこちら、やれない人はこちらにどうぞ」
では何の話もできない。
行政であれ、高齢者の施設であれ、どこであれ、何であれ
まずは、そこに居る人の話をよく聞いて
そこの空気を一緒に吸ってみてほしいとお願いした。
暮らし(=時間に追われない国)の話を
仕事(=時間に追われる国)のやり方で
進めようとすると、
それは共生ではなく強制になってしまう。

ゆっくりやればいいんだ、
モタモタグダグダでいいんだ。
いろんな人が来たら、いろんな人と一緒に話す。
もし、まったく話が変わってしまっても、
今、その人が来たことを受け入れて、
おしゃべりの輪をつくっていけばいい。
その時の流れにのることも大事なこと。
邪魔ばっかりで話にならないと怒る人もいるが、それもそれでよし。
すぐ、結論を出さない方がいいことはたくさんある。
「わたしたちは、今日、この話をすることが目的だったので
その話をしたいので、ちょっとあちらに」と別室へ行き
きちんとした書類にきちんとした答えを書いて
その通りに進めていくというのでは
そもそもの「混ざって暮らす」が話せなくなってしまう。
1人で考えたことを誰かに伝えて命令するのではなく、
あるいはお金を出して他人任せにするのではなく、
ひとり、またひとりと仲間になってもらうことからはじめて、
ひとりひとりがその人らしく、
思ったことが言えるようになるとよい。
当然時間がかかる。
1年単位で予算を計上!にはそぐわないこともある。
そこをなんとか工夫して、みんなで迷ったり、智慧を出し合ったり、
一緒に苦労して作業をすれば、いわゆる「コミュニティ」が生まれる。
その場はきっと、
多額の経費をかけて、専門家が最短時間・最速の効率で作り上げ、
さて、だれも利用しなくて困ったなぁと言われる場所とは異なる
「地域の宝」となる。

あらゆるものが一緒にいるためには
「ゆっくりとおおらかな心持ち」が必要。
だから、
何事も時間をかけてよい、
失敗してもよい、遠回りしてもよい、
無駄がたくさんあってよい、
正解はなくてよい、あったとしてもひとつでなくてよい、
いつも迷っていてよい、未完成でよい。
「混ざって暮らす」ためのルールをきちんと作るなんて、
そんなややこしいことはない。
ルールをつくるための話し合いを延々と続けること、
「遠回り・・・」することをおススメする。

人が寄れば何かしらのルールは必要になるのだから、
そのルールはいるのかいらないのか、柔軟に意見をぶつけ合う。
そもそも、ルールとは一体何なのかを問うことを忘れない方がいい。
決めたルールに縛られ身動きができなくなるのはつまらない。
決められたルールの中に
すっぽりとはまる人しかいられない場所では混ざれない。
管理する側の都合にあわせるのではなく
常にそこにいる人の側が心地よくいられるようにできる道具として
とらえなおしてみてはどうか。
人の営みは、自然のごとく常に変化するものなのだから。
今までのやり様を変える勇気を持つことで、
実に様々な多くの人が活き活きと笑い、泣き、暮らせるきっかけとなる。
天気の話、昨日見たテレビの話、
旅行にいったときの話、さっき聞いた面白い話、、
そんなところから「そういえばねぇ」とはじめてみればいい。
お互いが声をかけあえる空気がただよっていると居心地が良い。
みんなでしゃべることが、新しい仕組みの第一歩。
時間がかかる。それがおもしろいんだ。
ふと、振り向くとほどよく混ざっている。
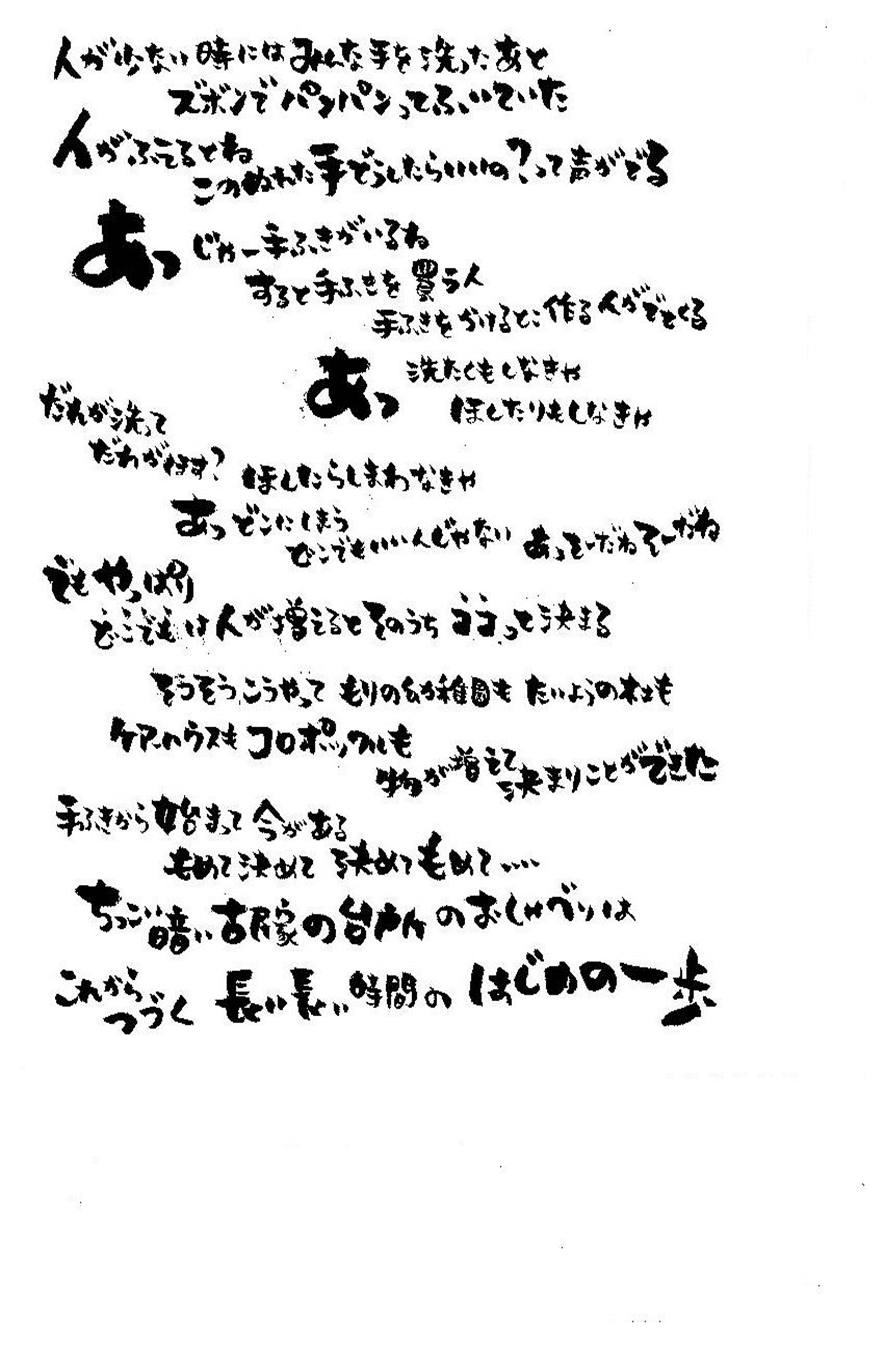

今日はこの辺で。
お付き合いいただきありがとうございました。
