
自然の仲間であること~本能の部分にたっぷりとしみこませてやりたい~
「自然の中で、自分も自然の仲間であることを知り、
四季を楽しみながらゆっくり暮らし、自然を相手に思いっきり遊び、
そのおもしろさや生きていることの楽しさを
本能の部分にたっぷりとしみこませてやりたい」
とようちえんを始めた。
40余年過ぎ、
そこで育った子どもたちが「ようちえんは楽しかった」と
目を輝かせてくれる。
が、学校に通うようになるとどうも様子がちがったらしい。
「前~ならえ!って何すればいいかわからなかったんだ~」と
子どもたちが笑う声を聴きながら考える。

自然を相手に田んぼや畑を耕し、
日々の暮らしを営んでいた多くの日本人に
「富国強兵」の名のもと「世界と戦うための教育」をはじめた明治の頃。
やがて始まった戦争に向かった大半は、
昨日まで武器ではなく鎌(かま)や鍬(くわ)を持っていた人々だった。
その頃の、隊列を組んで「右向け右!」と
一糸乱れぬ動きを身体にしみこませるための「教育」が
今も続いているのではないだろうか。
同じ動き、同じ思考、同じ反応を
機械的に効率的に無駄なくできるようになることが、
個々の意思に関係なく、
最速で最高の成果を上げるための同質の人を増やすことに重なる。
同質の人が良しとされるから、
自分らしさを消していくことを「頑張る」。
親たちも「みんなと同じ、またはみんなよりよくできる」ために
「頑張ること」を応援する。
「今」を生きる、楽しむことができる素晴らしい才能にあふれた子どもたちの個性や感性はどんどん切り取られていく。
自然が多様性の宝庫とするならば、
実に不自然な現実が子どもたちを取り巻いている。
自分がやりたいことではなく、誰かにやらされることをこなす。
同じことを同じスピードで同じ答えに向かってやり続けることで
成果をあげて評価を受ける。
誰かにやらされたことがうまくいかない時、
できない理由を人のせいにしてしまう。

遍路道をひとり、癒しと畏れを感じながら、
自然の中を歩きたどり着いたお宿。
人の声にホッとして、一杯のお茶にも思わず手をあわせる。
いつ来るか、もう来るかと気をもむそぶりも見せず
「お接待」をする地元の方々のふるまいは、さりげなくあたたかだった。
先祖代々きっとその場所で、
延々と迎え入れ、送り出す日々を続けているのだろう。
「稼ぐ」というのにはあてはまらない気がしてならない。
「人は得るもので生計をたて、与えるもので人生を築く」
そんなチャーチルの言葉が浮かぶ。
生計をたてるということは、競争に身を置き苦しむことか?
そんな呪縛にしばられた世の中に、もう付き合う必要はない。
自分と他者を比較して、競争の果てに優劣をつけることで得る暮らしと
自分と向き合い、自分自身と戦いながら望むものを得ていく暮らしは
たどり着く過程で身につくことや見える風景がまるで違うだろう。
ある人が、幸せとは
「必要とされる、ほめられる、愛される、役割がある」
ことだと言っていた。

田植えをしている母に苗をなげて渡すと
「猫よりましじゃなぁ」と喜んでくれた。
あの母の笑顔を今も思い出して、今でもうれしくなる。
必要とされていること、役割があること、
そしてそれを喜んでくれる人がいることは、
その先何があっても、自分を支える土台になる。
せっかく縁あって生まれてきたのだから、
自然の仲間であることを忘れず、
自分がワクワクドキドキすることを
思いっきり楽しめばよい。
だんだんと「自分らしく」なっていく。
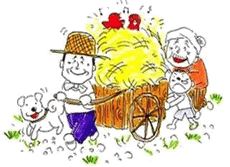
今日はこの辺で。
お付き合いいただきありがとうございました。
