
あり得ない日常#98
閑静な住宅街、それも夜で夕飯時もすっかり過ぎたようだ。
かつての関東の冬はじわじわ刺さるような乾いた寒さが特徴で、これがアスファルトとコンクリートで敷き詰められた結果なのかは定かではない。
たしか、親切な誰かに連れられて病院で診察を受けているはずだが、それはどうなったのだろう、最近記憶がどうも混濁するようで確定できないから困っている。
そもそも、それをお医者さまに診てもらっているはずだが、まあこうしてこうなっているということは、解決には至っていないということだろう。
やれやれ、世界がおかしくないのだとすれば、原因はわたし本体の問題であって、どうやらその問題と終ぞ共にしなければならないらしい。
とはいえ、人間の身体のメカニズムなんて現代医学でもほとんどが解っていないのだから仕方がない。
人間どころか、植物の光合成のメカニズムや構造すら完全に解明することは難しいとされている。
でなければ、とっくにそれを活用して世界中のエネルギーや食糧問題など解決の道筋はいくらでも出来ているはずだから。
さてそんな誰か権威のある科学者や研究者に任せておいていい壮大な問題より、わたしは目の前の問題をどうにかしなければならないらしい。
こんな寒空の中、一本の電柱につく街灯がもたらす狭い光の下で、若い女の子が一人小さくうずくまっている。
わたしも、見知らぬ人に気軽に自分から声をかけていけるようなそんな立派な人間ではないので内心困惑しているところだ。
すると、存在に気付いたのか彼女がふと目線を上げる。
「お姉さん何?」
しばし沈黙が流れる。
いや、何と言われましても。
むしろ、逆にこちらが聞きたいくらい。
「ほっといてくれない?」
ダメだ、これはすべての干渉を受けつけてもらえない。こんな人に必要なのは唯一、時間だけだろうが生憎わたしもどうしたらいいのかわからない。
どうにかこの人とコミュニケーションを成功させる必要がありそうだ。
そういえば紙コップに入った熱々のお茶を持っている。
一杯だけだがまだ口をつけていないからとこの子に飲みなよと手渡す。
「どこからもってきたの?」
まあそれはそう。
わかんないと答えると、クスクスと彼女が笑ってくれた。
「ありがと。」
うん、よかった。
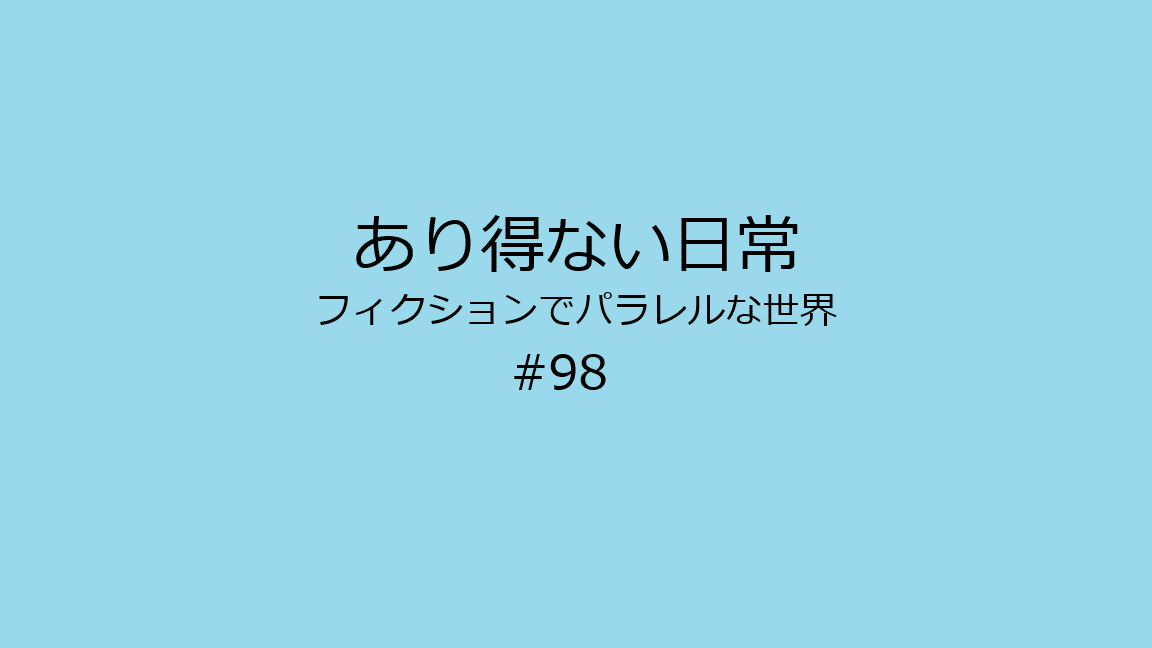
※この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在する人物や団体とは一切関係がありません。
