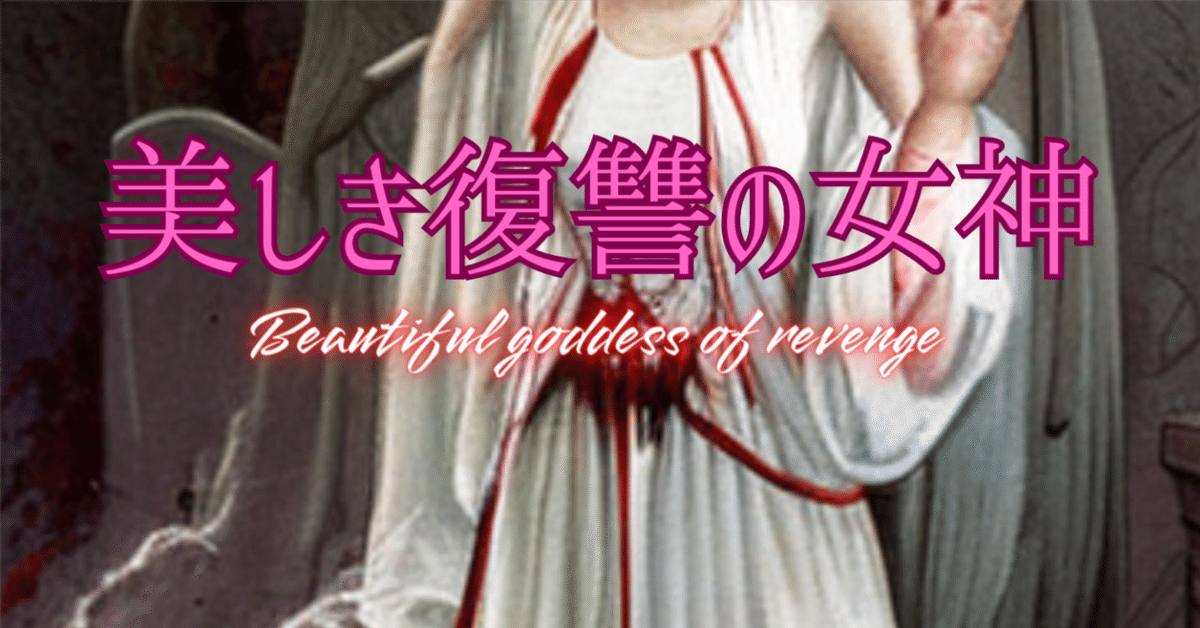
連載長編小説『美しき復讐の女神』3-3
「今日永岡さんが来たよ」
食卓の中央に山盛りされた唐揚げを箸で持ち上げながら隼人は言った。唐揚げは隼人の好物だった。現役の時は体作りも兼ねて食事制限などを行っていたが、唐揚げだけは制限しなかった。好物だから、という理由はもちろんあるが、高タンパクの鶏肉は疲労回復効果が期待できて、その上唐揚げはどれだけ食べても太らないという特別な料理だった。
歯に割かれる繊維と繊維の間から肉汁が染み出て、うまい。
「永岡さんって、二つ上の先輩の、あの永岡さん?」
母の美代子はサラダを取り分けながら訊いた。隼人が一年の時の大会に美代子は応援に来ていた。だから永岡のことを覚えているのだ。それに、凛と交際していたことも知っているはずだ。
「そう。永岡さん、今度全国大会に出るらしくて――」
「へえ、それはすごいわね」
「俺も来年からは今よりもハイレベルなところで剣道をやる。進路も決まったことだし、今から大学のトップレベルの試合を観ておくのもいいんじゃないかと思っててさ、永岡さんも団体戦には出るみたいだし、その応援も兼ねて、大会を観に行こうかなって思ってる」
「大会って、それどこであるの?」
「東京」
「いい機会だ」父の太一が言った。「もう隼人も大学生になるんだから、見聞を広げることも必要だ。仕事のせいにするつもりはないが、忙しくてあまり旅行にも行けてないから、馴染みのない場所を旅するというのは必ず良い経験になる」
「まあ、東京なら隣だし。でも……」
「俺も若い頃はな、散々遊んだもんだ。親父の事業がうまくいって、そのおかげでずいぶん楽しませてもらったよ。親が公務員で、贅沢させてやれないのは凛と隼人に申し訳ないが、俺が隼人ぐらいの頃はまだ景気も良かったからな。それこそ競馬に競艇、ギャンブルは大抵やったんじゃないか」
「競馬は今でもやってんじゃん」
過去を懐かしむ太一に隼人はちくりと言った。太一が話し始めてから、美代子は隣で顔を歪めている。
「時々だがな。若い頃は毎週競馬場に通ってた。他にもキャバクラだって行った。大学の頃と就職してすぐの頃は、どっぷり嵌ったな。母さんと出会ってからはめっきり行かなくなったけど、若い頃は毎晩夜通し飲み歩いてた」
こうして三人でゆっくり食事をするのは久しぶりだった。そのため太一は酒も入っていないのに饒舌だった。過去の、特に親や上司の武勇伝を聞かされるのは面倒の限りだが、武勇伝を語るほうは愉快でたまらないのだろう。凛が出て行って以来、父のこんなに楽しそうな姿を隼人は初めて見た。
「まあ隼人はまだ未成年だから、ギャンブルもキャバクラも時期尚早だが……。いいか隼人、人生は経験が物を言うんだ。次のステージを見据えて観戦するのもいいが、これをきっかけにもっといろんなものを見ておくんだ。それが今後の隼人の人生を豊かにしてくれる」
「ギャンブルもキャバクラもだめよ」
美代子は太一の皿にトマトを置いた。太一はトマトが苦手なのだ。
「未成年だからとかそんな理由じゃなくて、知らなくていい世界もあるの」
「まあ、それはもっと先にならないと……。でも競馬は確かに面白いよ。別にお金を賭けてなくても、第四コーナーを回ってからの会場の盛り上がりは鳥肌ものだよ」
美代子は目を細めて隼人を見た。母は姉には無頓着なくせに、息子にはひどく過保護なのだ。
「東京、一人で行ける? ついて行こうか」と訊いてきたように、凛と隼人でまるで態度が違う。一日か二日東京に行くだけなのに、美代子はついて来ようとする。だが凛が身一つで家を出た二年前は特に心配する様子も見せなかった。母娘と言っても女性同士、一定の距離感は保たなければならないということだろうか。男の隼人には二人の間にどういったものが存在するのかまるで想像もつかないが、女性同士だとあまり干渉し過ぎないことが必要なのかもしれない。
他にも怪我をした時や体調不良の時なども、隼人の場合は大袈裟なほど心配された。太一は「大したことない」と風邪や軽い擦り傷の時などは言っていたが、美代子は落ち着きがなくなり、忙しく息子を看病した。今でも、東京に出て音沙汰のない凛のことはまるで気にも掛けていないのに、毎日自宅から学校に通って、そして夜には帰宅する隼人の一日の様子を聞きたがる。
高校三年にもなると煩わしさを感じずにはいられないが、しかしそうして気に掛けてもらっている分、姉よりも愛されているのは間違いなかった。これは凛に対して、隼人が唯一優越感を抱けるものだった。
「もう子供じゃないんだから」隼人は唐揚げを頬張りながら言った。「一人で行けるよ」
「そう?」と美代子は不安を顔に出した。「お母さんには体が大きくなったようにしか見えないわ。唐揚げを食べてる顔なんか、小さい時から全然変わらないんだもの」
「心配してくれるのはありがたいよ。東京なんて、隣だけどすごく遠い感じがするもんね」
そういえば、と隼人は言った。
「凛は東京でどうしてるんだろう」
美代子は白米を口に運んでいたが、太一は味噌汁の入った漆器を持ち上げたまま、難しい表情になった。
「メールはしてるんだけど、なかなか返事がなくてな。電話で声を聞きたいと思うけど、凛の都合もあるだろうから、なかなかこっちからは電話できないんだ」
「親なんだから、気を遣わずに電話してみればいいのに」
「それはそうだが……。とにかく、度々メールを送ってるから気に掛けてることは伝わってるはずだ」
「お母さんは、何も連絡とかないの?」
「うん、知らない」
美代子が凛の現状を知るはずもなかった。母が自分に無頓着であることは、娘である凛自身が最もよく承知しているだろう。美代子が凛に連絡を取ることは考えにくいし、そんな母親に凛のほうからも連絡をするなど考えられない。
美代子とは対照的に、隼人よりも凛に思い入れがありそうな太一ですらメールの返事がなかなか来ないのだ。ちょっと気に掛かる。
俺からも連絡を取ってみようか。
そう考えて、すぐに頭を振った。わざわざ自分から姉に近づくべきではない。それに、メッセージを送ったところで無駄だ。隼人はそう思い、唇を掻いた。
4へと続く……
