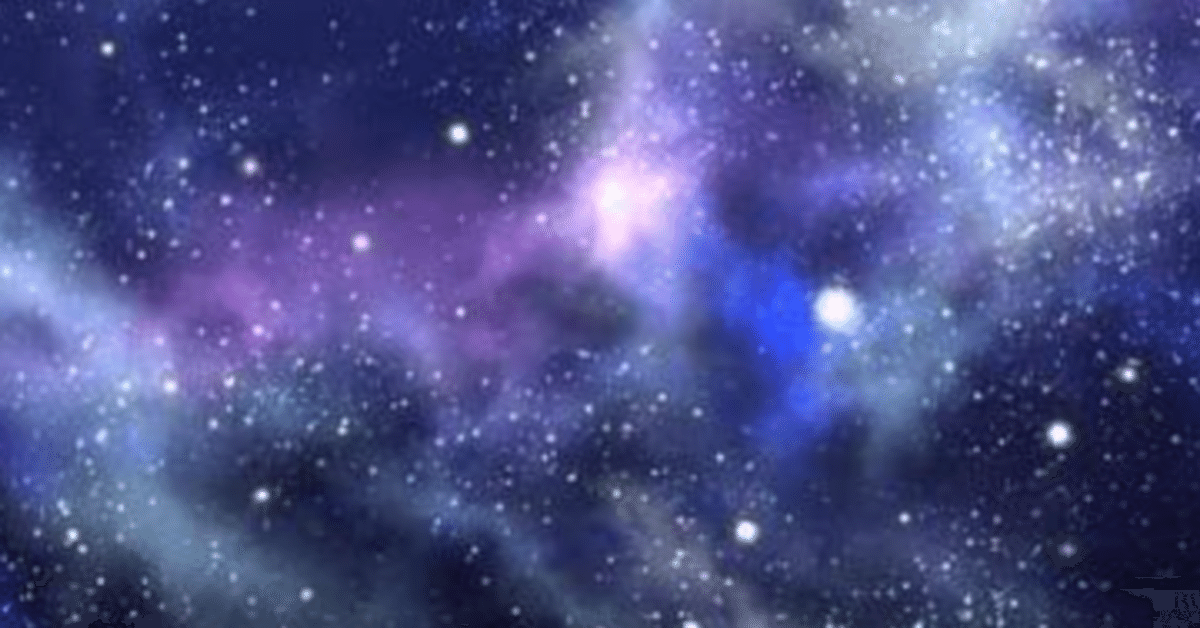
『春と私の小さな宇宙』 その15
※ジャンル別不能の不思議な物語です。少し暗め。
※一人称と神視点が交互に切り替わります。
以上が大丈夫な方だけ閲読ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二章
1
ハルが家に帰宅すると、玄関でアキが出迎えた。腰に掛けていたエプロンを外しているのを見て、ハルは料理が完成したことを知る。
廊下の奥からカレーのにおいがした。ある程度の予想はついていた。アキが料理当番の時は八十パーセントの確率でカレーになるからだ。
「おっそーい! 待ちくたびれたわ」
「よく言うわ。今できたところでしょう?」
「ばれたか。もっと早く作ってびっくりさせたかったんだけどな」
「せめてエプロンは外しておくべきだったわね」
靴を脱いでリビングに向かう。あの独特なにおいが歩くごとに強まっていく。嗅覚の鋭いハルからすれば正直、苦痛だった。
ただ、それをアキにそのまま伝えれば、ショックを受けていじけるに違いない。料理が苦手な彼女の数少ないレパートリーなのだ。
昔、子供の頃、ハルはアキが作った料理に口出ししたことがあった。ハルに悪気は無かったのだが、アキは泣き叫んでしまい大変だった。
その後しばらくの間、絶交状態であっ た。ハルからすれば一人の方が落ち着くため別に良かったのだが、最終的に耐えきれなく なった彼女は絶交中止を泣きながら宣言した。
一緒に暮らしている以上、面倒な事態は避けたかった。やはりここは、見慣れた茶色い流動食を胃に流し込むしかなさそうだった。
リビングに入る。室内は広く、二人で住むには十分な空間である。部屋の中央には背の低いテーブルが置かれており、向かい合うようにして座布団が敷かれている。
「持ってきたわよ! たんと召し上がれ!」
リビングから見える位置に台所はある。そのため、カレーが入っているであろう鍋から、 大量の湯気が立っているのが確認できた。
ハルは頭が痛くなった。アキは明日の朝と晩もカレーにする腹のようだった。それがいつものパターンだった。
ズボラ女子大生からカレーの入った皿を受け取る。真っ白な皿の上で均等に白米とルーが分かれていた。徐々に流動性を持った茶色が小粒の白を侵食していく。
「どう? 今度はきれいに分けて入れたよ」 「・・・悪くないわ」
ハルは満足した。前からアキのカレーの食べ方が汚いと思っていたのだ。白米の上にルーをかけていたからだ。食材にはそれぞれの味がある。いきなり混ぜ合わせるなど、素材 の味を台無しにしている。
味覚に鋭敏なハルの舌はそれがどうしても許せなかった。 その暴挙をアキに訴え、半々に分けてもらうように頼んだのだ。
本当は自分で盛り付けるのが安全で確実だが、残念なことにアキはハルの分まで用意したいときかなかった。ハ ルの体調を気遣っているようだった。
「・・・やっぱり、野菜を入れる必要ないと思うのだけれど」 茶色い流動物を胃に流し込みながらハルは言った。舌に熱といつもの味が広がる。
「何言ってるのよ! 何度も言うけど、野菜を食べないと健康になれないわよ!」
アキはカレーのこびりついたスプーンをハルに向ける。口周りにルーをくっついていて汚い。
「意味がわからない。私にはこれさえあれば十分よ」
白衣の左ポケットから栄養剤の入った小瓶を取り出す。錠剤には、野菜から摂取できるだけの栄養素が含まれている。
「だ、か、ら、それじゃダメなの! なんていうの、精神的にダメな感じがするでしょ!」
ますます意味がわからない。なぜ、ここで精神が出てくるのだろう。 ハルは意味不明な反論を無視し、錠剤を取り出して一飲みする。
別に野菜が嫌いなわけでない。肉類や魚類でも同じだ。だだ、栄養剤では摂れないタンパク質などの高エネルギー源を得ることができないのが、野菜だけだからだ。
ハルは一度食べたものを完全に記憶できるため、二度以上、同じ料理を食すのはうんざりであった。
脳で瞬時に味を再現できてしまう。つい先ほど、食事したように。 毎回、違う味の料理ならまだしも、栄養を摂る目的であれば、既に認知している料理を わざわざ食べるのはおかしい。
そう思うのが、ハルが料理に抱く嫌悪感の根源であり、栄養剤で食事を済まそうとする理由でもあった。
「健康に良いだけの成分が詰まった最高の食品よ。こっちの方が手っ取り早いし、無駄に味がしないわ」
小瓶をテーブルの上に置く。蛍光灯の光が瓶の透明なガラスに差し込み、中身の錠剤が白く光った。
「不服なら証明してみなさい。なぜ、栄養剤よりも野菜を食べる必要があるのか。・・・まだ、答えを聞いて無かったわね」
ハルは議題を提示した。以前にも似たようなことを言われたので、そう出題したことがあったのだ。
その時のアキは「なっ、なっ・・・」と完全に言葉を詰まらせていた。結局、「ハルの意地悪!」と半泣きしてこれ以上、追求してこなかった。
そう言えばまたアキは黙るだろうとハルは考え、議題を突きつけたのである。
しかし、今回は違うようだった。
続く…
前の小説↓
第1話↓
書いた人↓
