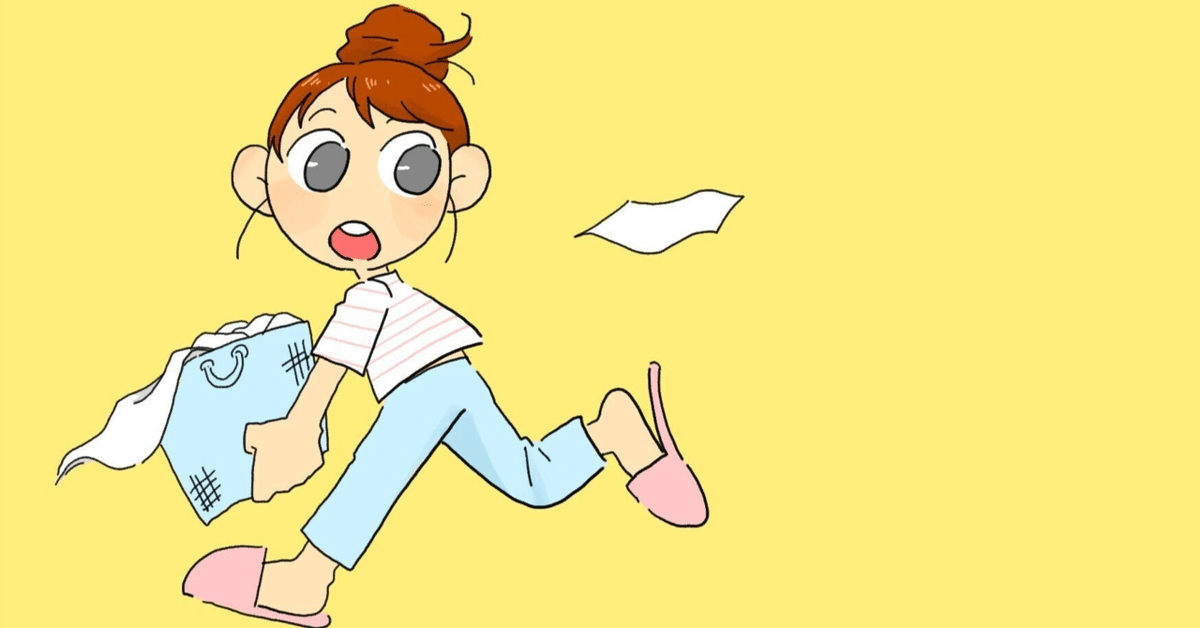
第二話⭐️ ドメスティックプロフェッショナルー専業主婦は経歴に書けますか?ー
1話からはこちら
「まじか、そんなこと」
寝室。息子二人は謙太と加奈子の間で寝ている。さっきまで騒いで喧嘩していた二人なのだが寝てしまえば静かになる。
「掃除当番一人抜かしたとかそんなことでさわーわー言ってるの、暇人だな。工藤……さんだっけ? その人みたいに気にせずそのまま回せばいいわけだよ」
謙太は鼻で笑った。加奈子は内心、家事も育児も町内会も全部妻である彼女に投げてるくせに何その口はと思っている。
「あとさ、やっぱあそこの百均ダメだった」
「あ、え? なんのこと」
やっぱ忘れてる、と加奈子は呆れる。
「ほら昨日言ったじゃない、あそこの百均で九時半から十三時までの時間帯募集ってあったから……平日で。そしたら平日以外も入れますかって」
「で、断ったら不採用ってか、また電話で」
せっかくの平日、子供たちが学校や幼稚園に行っている間の時間帯、短時間だが働けると思ったがやはり小売業。
土日も入れないとダメだったのだ。加奈子は司書資格をもっており、近くの図書館で司書の募集が役所から出ていたのだが毎年ため息をついてその募集を見ている。
そこももちろん土日勤務必須だったのだ。謙太も
「土日どうするんだよ、子供は誰が見るんだよ」
と言う始末。
「それにその司書の仕事は所詮パートだから土日くらい休めるだろ」
とも。
そんなことを言われたこともあって土日の仕事は完全に除外だ。土日は子供たちと遊んでくれるものの外食よりも加奈子の手作りの料理が一番だろといい結局は土日も加奈子は台所に気づけばずっといる。
「うちのおふくろも言ってたけどあせんなくていい、相馬が中学行くまでは働かずに家で待ってなさいって」
「でも……」
謙太の母親を思い出す。結婚してすぐ同じく専業主婦だった謙太の母、香純。家事を完璧にきようにこなせる加奈子には憧れであったが彼女を超えることはできないとおもっている。
趣味は家庭な香純、なぜそこまで従順でいられるのだろうか。
そして一度香純に言われた。
「うちの謙太、給料少ないっていうの? 稼いだ金をうまく回すのが主婦っていうものよ。うちの息子はt大にでて優秀な子なのよ、サポートしてあげてちょうだい。そして女は出しゃばらず後ろについて歩いていくのよ」
その言葉がとても重かった。
こんなことを言う人がいるものだと。加奈子の周りではそんなことを言う人はいなかった。
結婚前まで加奈子は新卒の大手デパートに勤めていたものの、寿退社して専業主婦になると言ったら周りから祝福よりも反対の声が多かった。
「やめなさい、そんな結婚」
とお世話になっていたお客さんにそう言われたり
「趣味が家族っていうのは危険よ」
って言われたり。加奈子は戸惑った。
「パートとして残ってもいいのよ」
と人事や先輩に説得されても謙太や謙太の両親がそれを反対し、結婚したら家に入れそうじゃないと結婚はしないということ言われ当時結婚ブームの第二波でこれで乗り遅れたら次はいつ結婚できるのだろう、という焦りもあった。
それに早めの結婚をして子供を産まないと20代で出産した友人でさえも体力がもたないと言っていた。
だから退職をした。
「今どき専業主婦だなんて」
専業主婦になって地元のスーパーで買い物をしていたら同級生の母親にそう冷たい声を掛けられたり
「子供がいないのに働いてないなんて」
と失笑する近所の人。
「それはただの僻みだ」
と謙太はそう言ったから加奈子はそうか……と思ったのだが次第におかしいと思い始めたのだ、だがその時には大我がお腹の中にできてこれでただの専業主婦でなくなる、とほっとしたものだった。
そしてすぐ3年後には相馬も生まれ二人の子を育ててきた加奈子だったが、ママ友サークルで異変を感じたのだ。
相馬が一歳になったころにメンバーが減っていたのだ。残ったメンバーも話す内容は仕事のことや保育園の話。
「相馬くんママは働かないの?」
「ええ、相馬が中学になるまでは……」
と言うとそこにいたママたちが声を合わせて
「中学ぅ???」
「それありえない……それまで専業主婦でいるつもり?」
と次々と。加奈子はもうそれ以降そのままともグループに行くのをやめた。
もともと行くのも億劫でただ喋るだけ、上っ面なつながりが苦痛だった、そんな時間あったら子供を連れて出かけていた方がマシって思っていた。
そして食費高騰したのに生活費は上がらない。毎月謙太からもらう生活費では賄えない、けどそれでやりくりをするのが主婦だと言われてなんとかしてきたがもう限界だった。
「なぁ、ひさしぶりにさぁ」
と謙太がいやらしいめで加奈子を見る。だが加奈子は相馬出産後から拒み続けている。
育児も家事も全て押し付ける、妻の自分よりも親を優先する謙太に嫌気を前から感じていた。
そして近づく顔が謙太の両親それぞれの特徴を合わせた顔が年を重ねて浮かび上がってくる。あんなに好きで結婚した謙太なのに結婚してからの彼の態度の転換にもう嫌気がさしてきた。
「疲れたから寝る」
そう言って加奈子は寝ると謙太は舌打ちをして部屋の照明は消された。
朝、 謙太は出勤し、子供たちもそれぞれ小学校に幼稚園に行き部屋の中は一気に静かになり家事をいつものようにこなしていく加奈子。もう同じようなルーティーンで慣れっこである。
しかし今日はいつも以上に早く進める。なぜなら友人とのランチがあるからだ、と言っても友達はそこまで多い方ではない加奈子だが高校からの友人の瑠美とは細々と付き合いは続けている。
他の友人たちは結婚して子供ができたり仕事をしていたりでスケジュールがなかなか都合つけられなくなったのもある。仕事はしているが結婚をしていない留美とは連絡が取れやすい、唯一加奈子の過去から近況を知っている一人である。
洗濯も終えて晩御飯も下ごしらえと焼き魚で済むものにして掃除も終えて身支度もして出かけた。
久しぶりの友達とのランチ。いつも子供連れでお座敷で個室、そこに友達だけでなく子供たちがたくさんいる。友達と話をしたいのに途中で子供たちが邪魔したり喧嘩をしたりしてランチを終えた後はぐったりと疲れたことも多かった。
お子様セットを注文したり一つのものを子供と分けたり。
今日はお座敷でも個室でもない、かといってカフェでもない。
だが加奈子は選びきれず留美がうどん屋にしようと決めてくれたのだ。
「かけうどんひとつ、あ、小さいので」
と一番安くてうどんの麺だけ。
それを見た留美が
「野菜のかき揚げとあとひとつ何か好きなの入れてあげるから」
「いいよ、素うどんがいいの」
「誕生日プレゼントちゃんとあげれてないから。健康は食からよ」
「……はぁい。じゃあとり天」
「まぁまぁバランスよし」
「ありがとう」
ジムトレーナーの留美。ガッチガチに栄養学をやっているわけでもないのだがせっかくの子供抜きのランチで流石に素うどんだけでは目も当てられないと思ったのだろう。
席に座った二人。
「こないだの高校の集まりいかなかったのって節約?」
留美が早速切り出した。先日誘われていたものの加奈子は行かなかった。その理由はいつもの高校のメンバーの集まりだがもうほとんどが子供達も幼稚園と小学校に行ったのにも関わらずに子供を連れて公園で遊ぶということでそこがいやで断った。
とにかく今は大人と話したい、遊びたい、なのに公園でってなると大人同士で喋ることもできるが子供が怪我しないよう行方不明にならないように見守っていなくてはいけないのだ。
だなんて説明するのはめんどくさいと留美には言わない加奈子。留美も深堀はしない。
「日曜だったし謙太さんに言うのもね、俺の昼ごはん用意してよぉー冷凍ピラフなんて食べないよって」
「そうそう、それもあるんだよ」
「ふはは、そうだと思った。でも手作りとか色々切り詰めて加奈子もやるよねー」
「今しかないでしょ、自分働かず夫からもらう生活費からコツコツやってきたんだけどね」
「食費高騰でさすがの加奈子も……」
「そう、無理ー私の今までの努力も無駄の泡!」
「そりゃ、素うどんにしたくなるわ。謙太さんはやっぱり生活費……上げるわけないかー」
「ないない。上げても素うどんよ」
「せっかく自立できる資金貯めてたのにね……」
「うん……」
自立、と言葉まろやかにしているのだが実際のところは「謙太との離婚」である。
離婚するとお金がかかる、お金がないと離婚ができないと言うのを高校の集まりのメンバーの一人が姑との不仲で夫とも喧嘩して離婚した時に年月とお金を消失したということを二人は知っていたのだ。
だが加奈子はその話を聞く前から貯金はしていた。結婚後、自分の父から聞いてたのと正反対の性格と義父母の態度だった。上司である加奈子の父には謙太は逆らえないがその代わり加奈子には横柄な態度をとる。
「結婚してからの貯金は夫婦間の財産だから離婚の時にその貯金は半分にしなきゃいけないからねぇ。自分の独身時代の貯金に手を出さないようにプールしておいたけど子供が大きくなって、時代の変化で大打撃……はぅ」
「でも離婚せず謙太さんから渡される生活費から少しずつ貯金してったのもすごいわ」
「生活費以外の光熱費や子供たちの学費や習い事とかはあっちもちだからさ。子供を大学卒業させて仕事につくまでは色々と出してもらわないとね。養育費とかでは賄えないわ」
養育費のこともメンバーの経験談から聞いたはいた。
「はー、私もそれ加奈子に聞いてから貯金はしっかりしようって思ったわ。結婚するつもりはないけどさ」
「また言うー」
「てかPTAとか回ってきたのに仕事探して大変よね。あー、結婚して子供できたら幸せも束の間めんどくさいことだらけで子供だけでなく結婚も嫌になるわ」
「生きづらいよね」
「ねー」
と二人はうどんを啜る。
「あ、いい男」
加奈子はまたか、と留美の男観察センサー察知にやれやれと思いながらも付き合う。
見た感じ背は180センチ余裕で超えていて黒髪のソース顔、白パーカーにジーンズ。一人で大盛り肉うどんに野菜のかき揚げ、とり天、稲荷を載せていた。
「若いのにはぶりよく、平日休み、一人で来店、大食い……性欲旺盛、公務員、独身、彼女なし……かな」
「加奈子の予想は半分くらい当たるよね」
「……素人だもん」
「そうよね、ちゃんと当たるなら謙太さんみたいなマザコンケチ男……おっと失礼」
留美は水を飲んだ。正解ではあるが紹介したのは加奈子の父である。
だが少し加奈子は彼をじっと見る。
「さては、タイプ?」
「……でもどうせ年下よ」
「付き合えば年齢は関係ないよ。まぁそれ以前に加奈子、早く清算しないと不倫になるよ」
「しないし……」
とか言いつつもそのよく多く食べる姿に惚れ惚れする加奈子であった。
お腹もいっぱい、気も使わないたわいもない話で心も満たされて二人はうどん屋を後にして別れた。これから留美は自宅からリモートプライベートレッスンらしい。
スタジオで働く時もあればリモートでも働く。加奈子は自分にもも少しスキルがあれば、体力があればと思った。
加奈子は運動音痴でコミュ障なことを知ってる留美はあえて自分の会社は勧めてこないし加奈子もするつもりはない。
街から離れて地元に戻ると本当に田舎だ、と思いながらも知り合いが多い地元のスーパーで働く気にもならないし時給も低い。
さっきのうどん屋でも自分くらいの世代の女性が働いていた。違う店舗では加奈子のママ友が働いており、長期休暇は休み取れる、子供が学校行っている間のみと好都合だと言っていたが知り合いのいるところには入りたくない、それに大手のチェーン店でもある。
「選んでる場合じゃないよな」
と加奈子はため息をつく。
「乾さーん!!!」
聞き覚えのある声に加奈子は振り向くとそこには工藤さんがいた。
「工藤さん、こんにちは」
「こんにちはー。昨日はどうも……おでかけ?」
たしかに昨日の服とは違ってワンピースにメイクもしている。そのためそう言われたのかと。
「友達と……ランチ」
と加奈子が小声で言ってしまうのも、過去に子供が生まれる前にランチに行くと言ったら謙太から夫が仕事で汗水流してる時に優雅に夫の金でランチか! と言われたり近所の人からも似たような言葉で揶揄されたことがあったからでもある。
「いいわねー! 子供いないうちに楽しまないと!」
と工藤さんは予想外の返答に加奈子は驚いた。かと言ってもあの時も他の友人からは別にランチくらいいいじゃん、て言う人もいたのだが夫が揶揄するから断った際にはそんなこと言ったら友達無くすよと言われたことも思い出した。
だがなぜ今ここに工藤さんが? と加奈子。普段は会うこともないのだが二日連続である。
「そーそー、ちょうどよかった。あなた今仕事してないわよね?」
「は、はい……」
図星な質問にすこし加奈子は身構えた。
「あ、今日は私は休みよ。普段介護職なんだけど……今ねー、友達が職員さん募集してるのよ」
「え、介護の?」
「ちがうー、介護は体力いるわよ? どう見てもなさそうだからっ! でも似たようなもんかしら」
少し失礼だなと思いつつも介護職でない似たような仕事とは? と加奈子は前のめりになる。
「地域のふれあいセンターの事務員さん募集してて、あなたみたいに人の世話焼き好きそうな子……いいと思うの!」
「世話、やき……」
「ほら! 昨日の阿澄さんとかさぁー。あと事務経験無くてもパソコン触れるなら大丈夫。他に先輩もいるしね。それに時間も10-16時だし土日祝休み! 週に一、二回出勤だから月に8日ってところかしら。時給も県の最低賃金よりプラス20円増し! シフト制だけど所長に聞いたらお子さんやご家庭優先で、早抜けもOK! って」
加奈子はそれを聞いてビビビッと来た。
土日祝休み、16時までだが早抜けもできる、そして家庭優先である。
返事をしようとしたら加奈子は思いとどまる。
こんな都合の良いものには何か裏がある、と。新卒で入った会社を辞めた後にハローワークで検索して出た受付は正社員採用と書きながらも辞めるまでパート扱いで低収入であったり、他にも理不尽な思いをしたり……。
「とりあえず今度お話だけでも聞きに来たら? 知ってるわよね、ふれあいセンター」
「はい……以前バザーとか子供の行事で行きました」
子供二人の通う幼稚園と小学校のちょうど間にある場所でこぢんまりとした施設であり、町内の老人たちの憩いの場であった。
「絶対いいと思うの! 考えてちょうだい! あ、一応履歴書……持ってきて」
と工藤さんに手をぎゅっと握られた加奈子であった。
「へーいいじゃん」
夜、相談するやいなやあっさりとそう言う謙太。
「月に数日だろ? 家事にも支障なさそうだし」
そこかい、と言いたくなる加奈子だが早く謙太からのOKがもらえてびっくりしている。
「多分ちゃんときっちり働いても扶養の……」
「あー、そんなの数えなくてもわかる。扶養の範囲余裕だろ」
ああ、またか。と加奈子は右から左に受け流し、即座に用意した履歴書を広げた。
実に10何年ぶりに先日から書いていた履歴書の残り。
大学の就職活動では何百枚も書き、次の転職2回ほども書いた。どの仕事も職種が違うし期間も短い。相変わらず書くのは大変だが……と加奈子は手をとめ、ため息をつく。ここ数日ら履歴書書いてる時は常にここで
「十年間の経歴が無い」
と手が止まってしまうのだ。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
