
ハイコンテクスト時代からローコンテクスト時代に
「これ見た?」「思ったよりケンジだった」超ハイコンテクストな会話の例です。今朝のタイムラインからです。こんにちは。野田です。
ハイコンテクストとローコンテクスト
今読んでる本で面白いところがあって、日本がハイコンテクスト社会からローコンテクスト社会へ移行しつつある、というところ。
コンテクストというのは、共通の言語・知識・体験・価値観・嗜好性のこと。
ハイコンテクスト社会とは、コンテクストの共有性が高い社会のこと。つまり、言わなくてもわかるでしょ。察することで、なんとなく通じる環境のこと。
ローコンテクスト社会では、共有するコンテクストがないため、前提や定義、都度確認が必要。共通言語による明確な意思の疎通が必要。
つまり、ケンジの定義を明確にしないと、上記の会話の「思ったよりケンジ」が通用しないのである。
料理上手で倹約家の弁護士・筧史朗(通称・シロさん)と、史朗の恋人で人当たりのいい美容師・矢吹賢二(通称・ケンジ)の暮らしを、日々の食を通して描くもの。
漫画、ぜひ買ってください。そしてドラマも楽しんでください。ニヤニヤします。
さて、ハイコンテクスト社会からローコンテクスト社会へという部分に戻ります。
つまり、あれやっといてよ!というのが通じなくなる。終身雇用が崩れつつある今の時代に、複業とかあるんだから、認識の相違が無いようにいっぱい喋っていっぱい聞いて。そうしないとリアルずれるし、ここ見誤ったら後々大きな認識の相違ができる。たどり着いた先が全然違うーー!的な。
ローコンテクスト社会のことを考えてたら、2014年から特定非営利活動法人チルドリン徳島で養成したICTママのことに行き着いた。
とんでもないことだと思う。まだなんの実績もないけど、育成やります!来てね!って新聞に載せてもらったって話、しましたっけ?
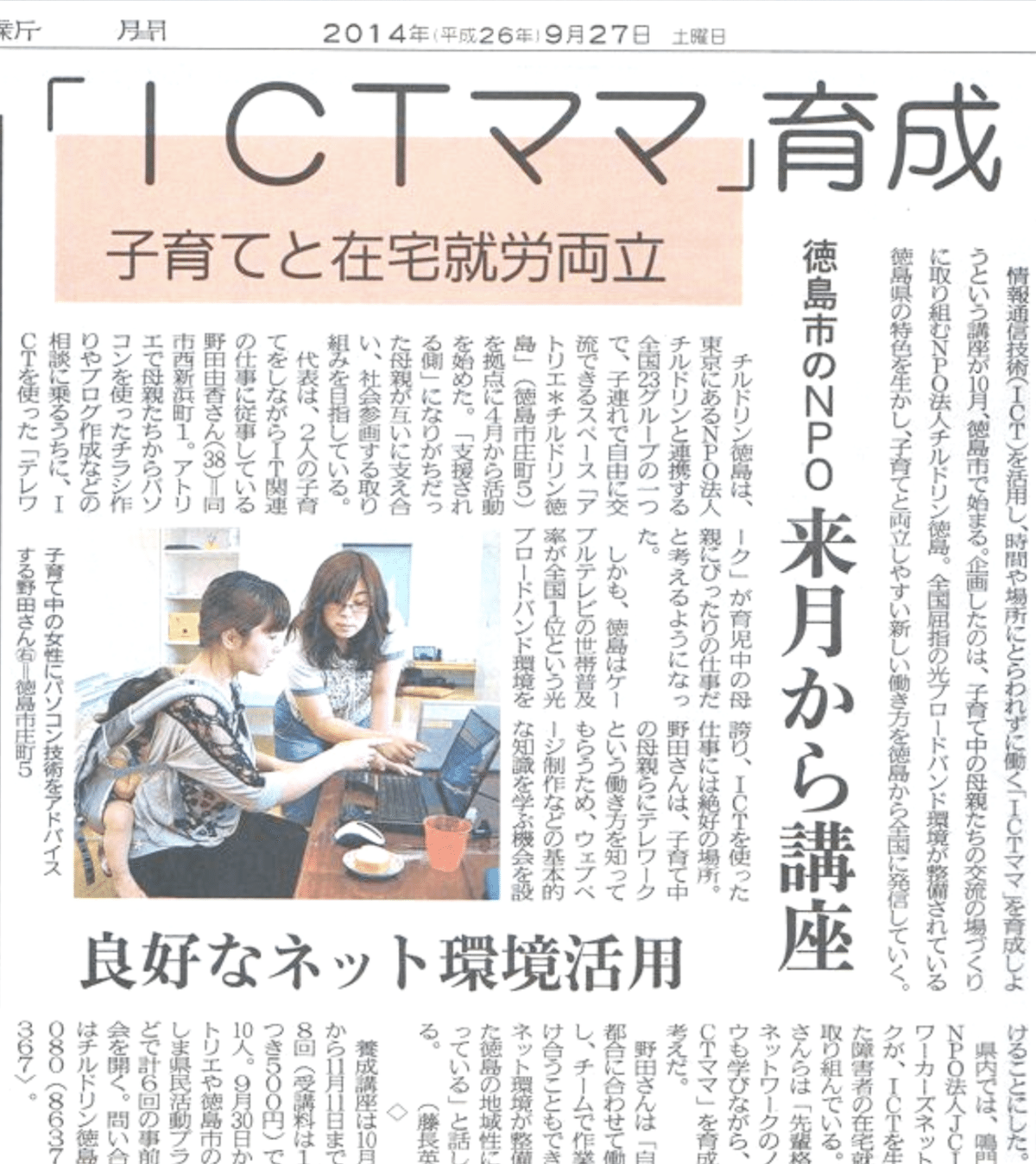
私たち、2人で作ったんですね。NPOを。何時間もワクワクする話をしてずーっと話して、これもやろう、あれはどうかな、それとこれって繋がらないか?とか。涙でちゃう。
話がずれました。戻ります。
ICTママは究極のローコンテクスト社会の先端じゃないか
著書ではグローバル環境や様々な人種や国籍の人々が集まることを「究極のローコンテクスト社会」と解説いている。
ICTママとは?
女性の働き方が多様化する現代において、出産により退職する女性が6割を占めるなど、結婚や出産などのライフステージの変化に伴い、女性の就業に関する課題は多く存在します。また、NPO法人チルドリン徳島では、子育て世代のママたちへのICTを活用した就労機会の創出を目的とした「ICTママ」(ママたちがチームを組みテレワークやクラウドソーシングを行うこと)に対して、子育て世代のママたちに適した仕事の継続的な創出が課題となっています。(チルドリン徳島サイトより抜粋)
よく、ITの得意な女性の集まりじゃないか?徳島だからほら、元J社とか、サテライトとか!と、勘違いをされがちなのだが、普通の普通のお母さんたちがソースの話とかコードの話とかし始めたらおもろい感じになったんです。徳島。このエピソードが大好きなんですが、ブランクが10年あった人が、ご主人のパソコンを持ってきて、電源のボタンも分からなかったんですが、1年後、本当に頼りになる事務局の中心になってくれたことや、クラウドで経理の処理をするのですが、チャットで質問してるのに先方から電話していいですかって聞かれて、チャットでお願いしますっていうのとか。
大切にしたいものごとができたときに、私たちは働きかたを変える必要があったのから
私は子育てが大切にしたいものでした。なんせ初めての経験でしたから、野にはなられた!と言う言葉で表現することがピッタリなほど、全てがよく分からなかった。が、働かなくてはならなかった。しかしだ。シングルマザーの6ヶ月の子どもを抱えた30過ぎた女に仕事などない。面接でいいところまでは行くんですよ。私。
でも、最後の面談で、子どもが熱出したらどうするんですか?とか、子どもが3歳になったらもう一回、面接に来てくださいね!って落とされる。悔しかったな。あの時は。
でもおかげさまで団体作りましたよ。ありがとうございます!
落としてくれた人ー!
そう。ハイコンテクストからローコンテクストの話。
ICTママ養成講座は8日間の講座が終わると、グループウェアを使って家でもしくは、コワーキングスペースで遠隔指示で業務を行います(業務委託)

テレワークコーディネータの存在
ローコンテクスト社会に通じるものがあるなと言ったのは、業務をお願いするときに、誤解が生まれないように細かく細かく言葉を選んで指示を出しているところや、打ち返しのところ。企業や事業体から仕事をいただくときのヒアリングのところもそうですが、一つ一つを明確な意思の疎通を確かめることが、品質の担保には必要。
これから、もっともっと働き方は変わります。在宅勤務、リモートワーク、ワーケーション、副業、複業。
労働人口不足の時代に、一蓮托生と思っていただき、業務を切り出すときにもまた、新しく業種業界を飛び超えるような案件も。これまで以上に、聞く力が大事になっている。この人と仕事がしたい、この団体に出したい、と思われるようにこれまで以上に聞く力をつけて、コンテクストを埋めていきたいと思う。
