
<書評>『ゲルマン、ケルトの神話』
『ゲルマン、ケルトの神話 Mythologie Germanique, Mythologie Celtique』トンヌラ E. Tonnelat ロートG. Roth ギラン F.Guirand著 清水茂訳 みすず書房1960年第1刷、読んだのは1979年第5刷。原著は1935年パリ。
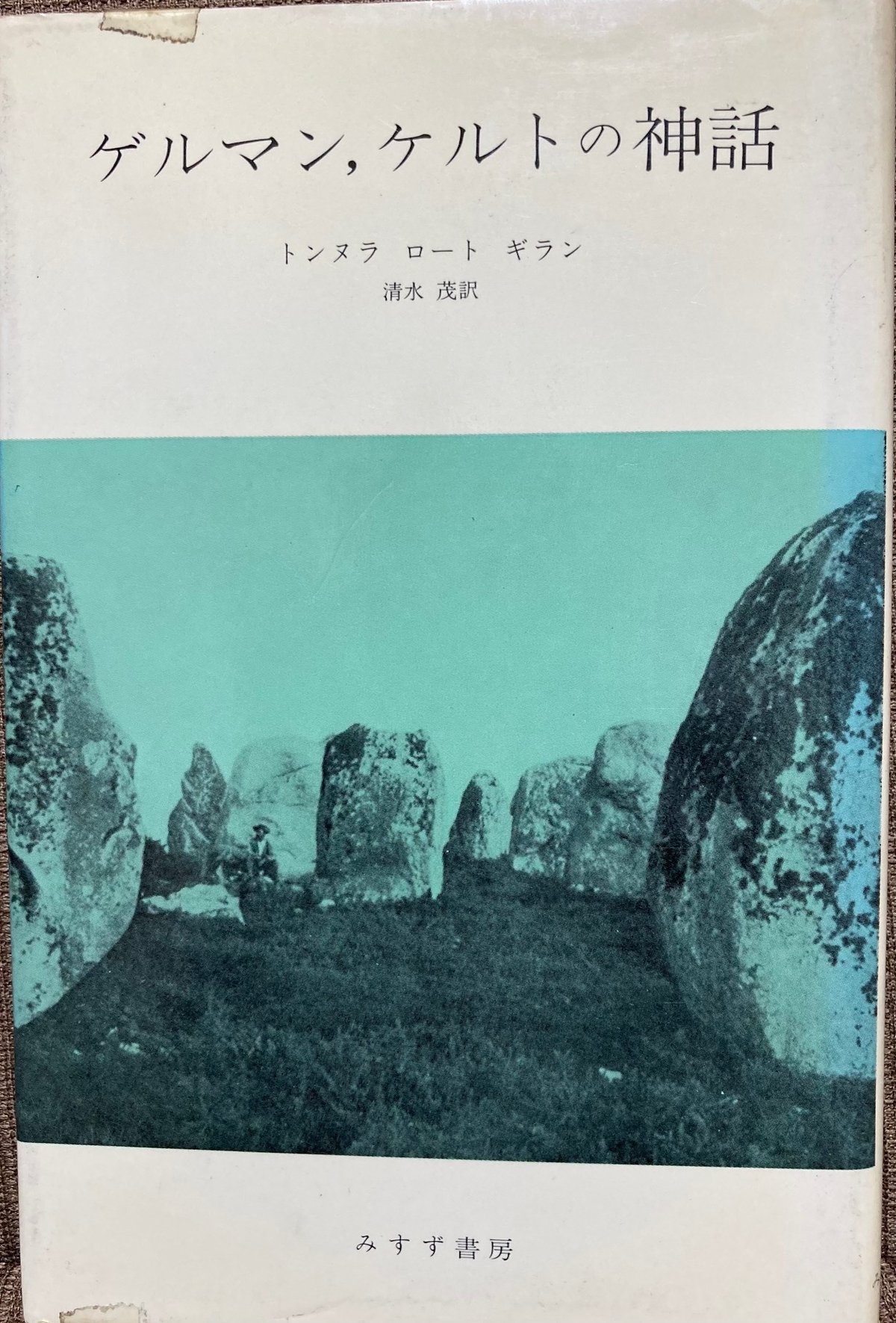
今日では、ハリウッド映画、日本のアニメ、そしてゲームの世界に、ゲルマン及びケルトの神々・英雄・精霊・魔術師の名(例えば、トール=ソーン、ロキー、ヴァルキューレ、トロール、マーリンなど)が多数利用されている。しかし、それは二十世紀以降に始まったことではない。中世の騎士道文学や十九世紀のロマン主義文学、リヒャルト・ワーグナーの楽劇として、様々な芸術の分野で多数の作品となって残されている。そして、人々はこうした芸術作品を通じて、ゲルマン・ケルトの神話に触れてきた長い歴史がある。
また、ゲルマン・ケルトの神話は、後発のキリスト教の強圧的な布教によって、古来の神々たちを「(キリスト教の)悪魔」と称されて弾圧されてきた。しかし、そうした歴史を乗り越えて人々の間に生き残り、また芸術・文芸・娯楽の世界では根強い力を持ち続けてきた。このように人々の心情に訴える大きな力がある理由は、神話が誕生した経緯――古代人が苛酷な自然と生活する中で長い時間をかけて創造した――のもつ大きな力によるものであり、そのため後発の思想であるキリスト教に一掃されることはなかったのだ。また、とりわけ非人間的及び反自然的な社会に生きる現代人にとっては、このゲルマン・ケルトの神話が持つ根源的なイメージは、人類が帰るべき故郷を体現していると言える。
本書は、今日ほど日本でゲルマン・ケルト神話がポピュラーになる以前に発行されているものであり、そうした観点からは妙な先入観等を持たずに書かれているので、基礎的資料として参考になるものである。しかし、その後神話学及び考古学の世界は急速な発展を遂げているため、ここに記された著者の見解は、もはや歴史的遺産の一部になっているのは致し方ない。
そうした中で、私としては、ゲルマン・ケルト神話を解釈する原点を把握するという目的で本書を読み進めることにした。そうした目的はほぼ果たせたと思うが、著者が述べているように、現在でもゲルマン・ケルト神話の全貌については、『エッダ』以外のまとまった文献が残されていないため、結論として「ゲルマン・ケルト神話の全貌は不明」という状況は変わっていない。
それでも、私が感心を持っている「古代の宇宙人論」という観点から、気になった部分があったので、それを抜粋して紹介したい。なお、( )内は、抜粋部分が該当する箇所の小題である。また、<参考>として、私の視点(解説)を付けた。
<ゲルマンの神話>
P.21(ウォーダン=オーディン)
ウォーダンはゲルマン人たちの主神とみなされているが、ドイツ人たちの先祖の間では数世紀にもわたってそのように考えられてきたことは真実である。(中略)そして、この神(アングロ=サクソン語では、ウォーデン)は彼らには自分たちの王の先祖だと考えられていた。<水曜日>という名は、こんにちでもなお、英語ではこの神の名を伝えている。というのは、Wednesdayとは<メルキュール神の日>(Mercurii dies)というラテン語名のそのままの置換えにすぎないからである。
<参考>
曜日の名称として、このようにゲルマン神話の神々から付けられたものは、ヨーロッパではほぼ共通に使用されている。また、フランス語では(日=太陽を除き)そのまま月や惑星の名を付けているが、そもそも惑星の名は神々の名である。なお、木曜はフランス語ではユピテル=ジュピターだが、英語ではゲルマンのトール=ソーンから由来する名称である。同様に、火曜のマルス=アレスに対して、英語では、ゲルマンの(アレス同様の)戦争の神であるティウス=ティールに由来するものとなっている。
P.90(精霊)
その起源においては守護の霊とみなされていたフィールギュール(fylgjur.fylgiaの複数)は、キリスト教が導入される時期になると、危害を及ぼすデーモンたちとして怖れられるようにさえなった。
<参考>
こうしたゲルマンの自然の精霊たちは、キリスト教によって悪魔にされたが、それでも民衆の間に、悪魔崇拝や魔女崇拝として生き残った。それは、民衆が自然の中で生きるために必要なものだったのだ。キリスト教には、乙女たちの恋愛相談はなかった。
P.104-105(巨人)
矮人や巨人やあらゆる種類のデーモンに対する信仰は、キリスト教が導入された後、幾世紀ものあいだ、ゲルマン諸国ではながく続いたのである。(中略)一つならずのゲルマンの士族がキリスト教を受け容れながらも、そのために伝統的な信仰を放棄しなかった。
九世紀に大ブリテンやアイルランドに拠っていたヴァイキングのあいだにも、彼らが植民地とした地方の宗教を自主的に採用したものが多かったが、しかし、ゲルマンの神々を信じることをやめなければならないとはいささかも考えなかったのである。彼らのあいだでは二つの宗教が重なり合っていた。きっと彼らは、二つのうちのどちらにもそれほど強く結びついてはいなかったのである。
<参考>
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は皆一神教であるため、自分たちとは異なる宗教は、異教・異端として排除する。しかし、仏教などの多神教は、異教や異端をも自分たちの理念世界に引き込んでしまう包容力と寛容さを持っている。そして、後者の方が人と自然に対して無理のない合理的な対応であると考えるのは、邪道だろうか。無限の宇宙に星々が多数あることからは、神が一人である理由は見つけられない。
<ケルトの神話>
P.126(ケルヌーノス)
その額が長い鹿の角を生やしているために、ケルヌーノス(角のある者)と言う名称をあたえられているようなかなり異様な神・・・この神は通常、脚を組んで坐した姿で描かれている。一般に、他の二神といっしょに同一のグループをなしているが、ときには、またただこの神だけのこともある。しかし、その場合、この神は三つの頭をもっており、その一つの頭だけが正面の顔を見せ、他の二つが近く向き合っている横顔であるか、または、両耳の上で冠にくっついている二つの小さな頭をもっているかのどちらかである。(中略)一般にこの神が傍に角の生えた蛇、または牡羊の頭をもった蛇を置いていることから、人はこの神のうちに一種の冥府の神を見ようとしている。
<参考>
ケルトの神の中で、この鹿の化身のようなケルヌーノスは、非常に興味深い。また、まるで瞑想の正座をしているような姿は、仏像の姿と似ている。そして、ヒンズー由来の神には、多面体・多頭身のものがある。これはケルヌーノスと同じである。では、ケルヌーノスがヒンズー由来かと言えばそれは違うだろう。
おそらく、ヒンズーの神々が誕生した頃と同時期に、ヨーロッパ大陸の西の外れ(今日のフランスのゴール地方からブリテン島のドルイド信仰の場所)に、同じ姿をした「神」が降臨したのだと思う。そして、その神は地球外生命体である。その証拠として、蛇に象徴される爬虫類を伴っている。おそらくは、ケルヌーノスは地球外生命体が持ち込んだロボットであり、ケルヌーノスに伴う蛇たちこそ、地球外生命体であった。しかし、古代人にとっては驚異的な力を発揮するロボット=ケルヌーノスが、より「神」として印象付けられたのではないか。
P.136-137(島の神々)
大ブリテンのブラーン・アブ・リーアのほうは恐るべき英雄である。これはとてつもない巨人で、あまりに大きいためにどんな宮殿も船もその身をかばうことができないほどである。(中略)アイルランドでのこの神の姿、つまりマナナン・マク・リーアは、恐ろしい魔術師である。燃えるかぶとを着け、そのよろいは破損することがなく、また身につけるマントのためにその姿は見えなくなるのである。
(中略)伝説によれば、彼はたしかにマン島の王だった。――そこでは、いまもなお、ビールの城に彼の巨大な墓が見られる。彼は三本の足をもっていたようである。島の武具がそれを証拠だてている。三本の足がそこにひとつの車輪の輻(や)のように放射されて描かれているのである。
<参考>
このマナナン神は、前述のケルヌーノスと同様に、地球外生命体が持ち込んだロボットだったのではないか。その証拠が、三本の脚であり、その脚がまるで車輪のように見えたのである。
フランスのカルナック(本の表紙に使用されている画像)、イギリスのストーンヘンジなど、とりわけケルト神話が生まれた場所には、古代の巨石遺跡が多く残されている。それらは、ケルト人が作ったのではないことは既に判明している。ケルト以前の人類とは、通常後期新石器時代の人類とされているが、当時の文明が持つ能力では、こうした巨石建造物を作ることは明らかに不可能であった。
そして、「誰が作ったのか?」という問いには、「地球外生命体が作った」という答えしかない。こうした巨石建造物を作った地球外生命体は、ケルト人が出現した頃まで一部が地球に滞在していたと思う。そうした最後の滞在者が、ケルト人には「神」として認識された。その「神」は、ケルト人をブリテン島に追い出したゲルマン人たちにも引き継がれた。
こうしたことが、ケルト・ゲルマンの神話がキリスト教の支配によっても消滅しなかった理由の一つであると思う。それはまた、人類共通の記憶、すなわちユングの述べる集合的無意識として、現代人の心に深く浸透している。
<私がアマゾンで、キンドル及び紙バージョンで販売している、書評やエッセイなどをまとめたものです。宜しくお願いします。>
