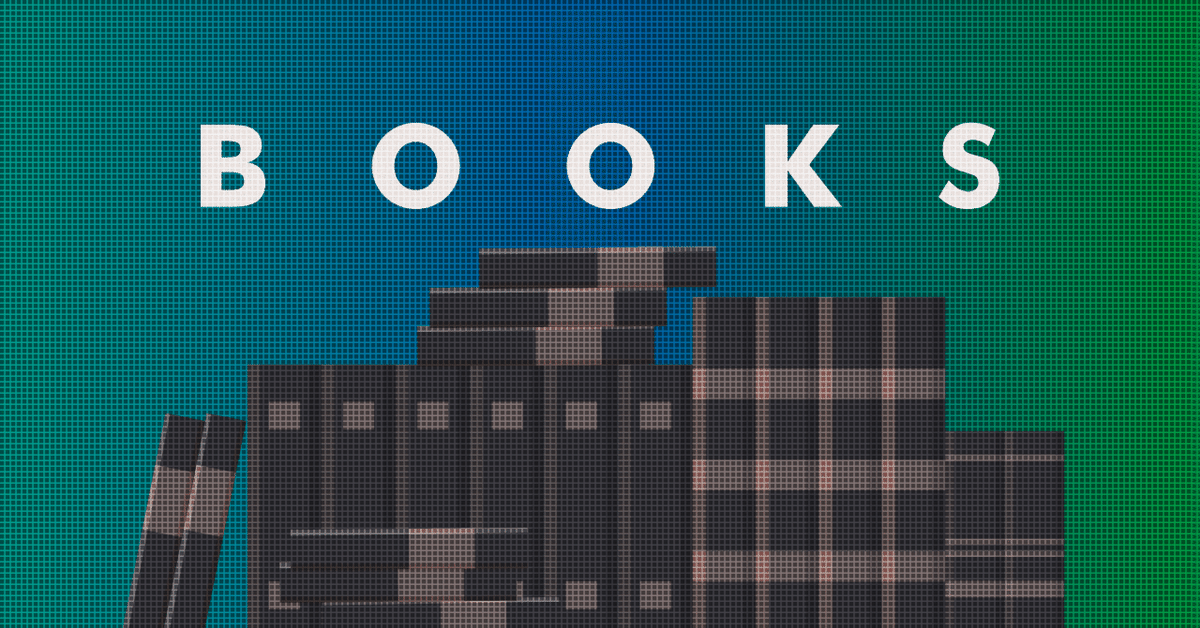
【読書記録】USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門 - 森岡毅
はじめに:マーケティングの本質を理解する
マーケティングは、ビジネスの成功に不可欠な要素です。しかし、その本質を正しく理解している人は意外に少ないのが現状です。本記事では、USJを劇的に変革させた森岡毅氏の著書を基に、マーケティングの真髄に迫ります。
マーケティングとは「売れる仕組みを創ること」
マーケティングの定義は様々ありますが、森岡氏は端的に「売れる仕組みを創ること」と表現しています。この定義は、マーケティングの本質を鋭く捉えています。
多くの企業が「良い商品を作れば売れる」という考えに陥りがちですが、現代の競争激化市場ではそれだけでは不十分です。消費者の心理を深く理解し、自然と商品やサービスを選んでもらえる環境を整えることが重要なのです。
マーケティングは、単なる宣伝活動や販売促進ではありません。消費者のニーズや欲求を的確に把握し、それに応える価値を提供することで、持続的な成長を実現する戦略的なアプローチなのです。
営業とマーケティングの違いを理解する
マーケティングと混同されやすいのが営業活動です。両者は密接に関連していますが、その本質は大きく異なります。
営業は「商品を売ること」が主な目的です。直接顧客と接触し、商品やサービスの魅力を伝え、成約に結びつける活動です。一方、マーケティングは「商品を売れるようにすること」が目的です。
具体的には、以下のような違いがあります。
視点の違い
営業:個別顧客に焦点を当てる
マーケティング:市場全体を俯瞰的に見る
時間軸の違い
営業:短期的な成果(売上)を重視
マーケティング:中長期的な顧客関係構築を目指す
アプローチの違い
営業:直接的な説得や交渉
マーケティング:環境整備や仕組み作り
マーケティングは、顧客が自然と商品やサービスを選択したくなるような環境を整えることで、営業活動をより効果的にサポートします。両者が適切に連携することで、企業の持続的な成長が実現できるのです。
このように、マーケティングは企業活動全体を見据えた戦略的な取り組みであり、その本質を理解することが、ビジネスの成功への第一歩となるのです。
日本企業におけるマーケティングの課題
日本は高品質な製品やサービスを生み出す技術力で知られていますが、マーケティングにおいては課題が多いのが現状です。森岡毅氏は、日本を「マーケティング後進国」と評しています。なぜそのような状況に陥ったのか、そしてどのような転換が必要なのかを探ります。
マーケティング後進国としての日本
日本企業の多くは、マーケティングの重要性を十分に理解していない、あるいは効果的に実践できていないのが現状です。この状況には、以下のような要因が考えられます。
規制によるバリア: 長年、政府の規制や保護によって競争が制限されてきた産業が多く、積極的なマーケティング活動の必要性が薄かったこと。
終身雇用によるバリア: 日本の伝統的な雇用システムにより、専門的なマーケターの育成や登用が難しかったこと。
技術志向によるバリア: 優れた技術や製品があれば自然に売れるという思い込みが強かったこと。
これらの要因により、日本企業の多くがマーケティングを単なる販売促進活動や広告宣伝と捉え、その戦略的重要性を見逃してきました。
技術志向から消費者志向への転換の必要性
日本企業が国際競争力を維持・向上させるためには、技術志向から消費者志向へのパラダイムシフトが不可欠です。この転換には以下のような取り組みが必要です。
消費者インサイトの重視: 技術や製品の機能だけでなく、消費者の潜在的なニーズや欲求を深く理解し、それに応える価値を提供すること。
全社的なマーケティング思考の導入: マーケティングを特定部署の役割ではなく、全社的な戦略として位置づけ、組織全体で消費者志向の文化を醸成すること。
データ駆動型の意思決定: 感覚や経験則だけでなく、市場データや消費者行動の分析に基づいた戦略立案と意思決定を行うこと。
グローバル視点の強化: 国内市場だけでなく、グローバル市場を見据えたマーケティング戦略を構築すること。
イノベーションとマーケティングの融合: 技術革新と消費者ニーズを有機的に結びつけ、新たな市場創造につなげること。
このような転換を図ることで、日本企業は優れた技術力を活かしつつ、より効果的に消費者の心を掴み、持続的な成長を実現することができるでしょう。
USJの改革事例:コンシューマー・ドリブンの実践
USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)の劇的な改革は、マーケティングの力を如実に示す事例です。森岡毅氏が主導したこの改革は、「コンシューマー・ドリブン」という考え方を中心に据えたものでした。
USJの課題と森岡毅氏の参画
USJは2001年のオープン以降、初期こそ好調だったものの、2004年頃から集客数が伸び悩み、経営危機に直面していました。その主な要因は以下の通りです。
限定的な顧客層: 主に映画好きの大人をターゲットとしており、ファミリー層や若者の支持を十分に得られていなかった。
競合との差別化不足: 東京ディズニーランドとの差別化を図るため映画に特化していたが、それが逆に顧客層を狭めていた。
新鮮さの欠如: 新しいアトラクションの導入が少なく、リピーター獲得に苦戦していた。
このような状況下で、2010年にマーケティングの責任者として森岡氏が就任。彼が掲げたのが「コンシューマー・ドリブン」という考え方でした。
ブランディングの転換:映画専門からエンターテインメントのセレクトショップへ
森岡氏が実施した改革の核心は、USJのブランディングの大転換でした。具体的には以下のような変更を行いました。
コンセプトの拡大: 「映画だけのテーマパーク」から「世界最高のエンターテインメントを集めたセレクトショップ」へとコンセプトを拡大。
コンテンツの多様化: 映画だけでなく、アニメ、ゲーム、コンサートなど、多様なエンターテインメントを導入。
ターゲットの拡大: 大人の映画ファンだけでなく、ファミリー層や若者など、幅広い層に訴求。
体験価値の向上: 「いつ来ても予想を上回る驚きを体験できる」という価値提供を重視。
この転換により、USJは以下のような成果を上げることができました。
集客数の大幅増加:低迷期から V字回復を遂げ、東京ディズニーランドを超える月間来場者数を記録。
顧客層の拡大:ファミリー層や若者の来場が増加し、幅広い支持を獲得。
ブランド価値の向上:「驚きと感動を提供するテーマパーク」としてのイメージ確立。
効果的なマーケティング戦略:3つの顧客接点
森岡毅氏のマーケティング戦略の核心は、「3つの顧客接点」を制することです。これらの接点を効果的にコントロールすることで、顧客との強力な関係を構築し、持続的な成功を実現します。
頭の中を制す(ブランディング)
「頭の中を制す」とは、顧客の認知と好感度を高め、ブランドの価値を確立することです。USJの改革では、以下の点に注力しました。
ブランドイメージの刷新
「映画だけ」から「世界最高のエンターテインメント」へとイメージを転換。
「ハッピーサプライズ」をキーワードに、予想を超える体験を提供するブランドとして再定義。
認知度の向上
効果的な広告キャンペーンの展開。
有名人(例:ベッキー)を起用したイメージ戦略。
差別化要素の強調
ディズニーランドにはない、ユニークなアトラクションやイベントの強調。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」など、独自のコンテンツの前面展開。
これらの取り組みにより、USJは顧客の頭の中で「驚きと感動を提供するテーマパーク」としての地位を確立しました。
店頭を制す(流通・販売戦略)
「店頭を制す」とは、顧客が実際に商品やサービスに接する機会を最大化し、購買を促進することです。テーマパークであるUSJの場合、以下の点が重要でした。
アクセシビリティの向上
交通機関との連携強化。
オンラインチケット販売の拡充。
視覚的インパクトの強化
パーク入口やアトラクション周辺の装飾の大幅改善。
目を引くディスプレイやサイネージの活用。
価格戦略の最適化
季節や曜日に応じた柔軟な価格設定。
顧客セグメントに応じた多様なチケットプランの導入。
これらの施策により、USJは来場のハードルを下げつつ、パーク内での顧客体験を最大化することに成功しました。
使用体験を制す(製品開発・顧客満足)
「使用体験を制す」とは、顧客が実際にサービスを利用した際の満足度を高め、リピート率を向上させることです。USJでは以下の点に注力しました。
体験価値の向上
「ハッピーサプライズ」コンセプトに基づく、予想外の体験の提供。
フラッシュモブやサプライズイベントの実施。
アトラクションの継続的刷新
定期的な新アトラクションの導入。
既存アトラクションの改良とリニューアル。
カスタマーサービスの強化
スタッフの接客品質向上。
待ち時間短縮やファストパスなどの利便性向上策。
シーズンイベントの充実
ハロウィン、クリスマスなど、季節に応じた特別イベントの強化。
これらの取り組みにより、USJは顧客満足度を大幅に向上させ、リピーター率の増加に成功しました。
森岡氏の戦略は、これら3つの顧客接点を総合的にマネジメントすることで、顧客との強固な関係を構築し、持続的な成長を実現するものでした。
マーケティングのフレームワーク
森岡毅氏が USJ の改革で用いたマーケティングのフレームワークは、理論と実践を効果的に結びつけるものでした。このフレームワークは、体系的なアプローチにより、戦略の立案から実行までを一貫して管理することを可能にします。
目的・戦略・戦術の順序
マーケティング活動を成功に導くためには、適切な順序で計画を立てることが重要です。森岡氏は以下の順序を強調しています。
目的(Goal)の設定
具体的で測定可能な目標を定める。
例:「年間来場者数1000万人達成」
戦略(Strategy)の策定
目的達成のための大局的な方向性を決める。
例:「ファミリー層をメインターゲットとし、驚きと感動を提供する」
戦術(Tactics)の立案
戦略を実現するための具体的な施策を考える。
例:「ハリーポッターエリアの新設」「季節イベントの強化」
この順序を守ることで、場当たり的な施策を避け、一貫性のある効果的なマーケティング活動を展開することができます。
5Cによる環境分析
戦略立案の基礎となるのが、綿密な環境分析です。森岡氏は5Cという枠組みを用いて、包括的な分析を行いました。
Customer(顧客)
ターゲット顧客の特性、ニーズ、行動パターンの理解。
Company(自社)
自社の強み、弱み、リソースの把握。
Competitor(競合)
競合他社の戦略、強み、弱みの分析。
Collaborator(協力者)
サプライヤー、パートナー企業との関係性の検討。
Context(環境)
社会、経済、技術など、外部環境の動向把握。
この5Cの分析により、市場の全体像を把握し、効果的な戦略立案の基盤を作ります。
4Pマーケティングミックス
戦略を具体的な施策に落とし込む際に有用なのが、4Pマーケティングミックスです。USJの改革では以下のように活用されました。
Product(製品)
アトラクションの多様化と品質向上。
「ハッピーサプライズ」体験の提供。
Price(価格)
柔軟な価格戦略(季節別、時間帯別料金など)。
価値に見合った適切な価格設定。
Place(流通)
オンラインチケット販売の強化。
旅行会社との連携拡大。
Promotion(プロモーション)
効果的な広告キャンペーンの展開。
SNSを活用した口コミ戦略。
これら4つの要素を最適に組み合わせることで、ターゲット顧客に対して最大の効果を発揮する戦略を実現しました。
森岡氏のアプローチの特徴は、これらのフレームワークを柔軟に組み合わせ、常に顧客視点を中心に据えて戦略を立案・実行したことにあります。
USJの具体的な成功事例
森岡毅氏が導入したマーケティングフレームワークは、USJの様々なキャンペーンや施策で実践され、大きな成功を収めました。ここでは、特に印象的な4つの事例を詳しく見ていきます。
10周年イベント:予算ゼロからの奇跡
2011年、USJは開園10周年を迎えましたが、当時は厳しい経営状況で、イベント予算はほぼゼロでした。
目的
前年比108%の集客増(数十万人の増加)
戦略
「ハッピーサプライズ」をコンセプトに、予想を上回る驚きと感動を提供
戦術
フラッシュモブの実施(スタッフが突然歌や踊りを披露)
トリックアートの設置(リアルな落とし穴など)
人気コンテンツ「ワンピース」の大々的展開
有名タレント(ベッキー)を起用したイメージキャンペーン
結果:目標を大きく上回る集客を達成し、パーク全体に活気を取り戻しました。
震災後の夏の戦略:関西から日本を元気に
2011年3月の東日本大震災後、観光業界全体が自粛ムードに包まれる中、USJは大胆な戦略を展開しました。
目的
震災後の落ち込んだ集客を回復させる
戦略
「関西から日本を元気に」というビジョンを掲げる
戦術
「大人1名につき子供1名無料」キャンペーンの実施
大阪府知事と連携した「関西から日本を元気に」キャンペーン
「スマイルキッズパス」のCM展開
結果:自粛ムードを打破し、パークに活気を取り戻すとともに、社会貢献企業としてのイメージも向上させました。
ハロウィンキャンペーン:恐怖の中の歓喜
2011年10月、USJは従来のハロウィンイベントを大幅に刷新しました。
目的
10月の集客14万人増
戦略
若い女性をターゲットに、「怖いけど楽しい」体験を提供
戦術
リアルなホラーメイクを施したキャラクターの導入
パーク内に「ゾンビ」を自由に徘徊させる
有名タレントを起用した「怖いけど楽しい」イメージの訴求
結果:目標を大きく上回る40万人以上の集客増を達成。ハロウィンイベントが USJ の名物に成長しました。
クリスマスキャンペーン:感動のファミリー体験
2011年12月、USJはクリスマスシーズンに向けて、従来とは異なるアプローチを取りました。
目的
クリスマス期間の集客増加
戦略
小さな子供を持つ父親をターゲットに、家族との貴重な時間の価値を訴求
戦術
感動的なTVCMの制作(「娘と過ごせるクリスマスはあと何回?」)
世界一の光のツリー(ギネス記録)の設置
サンタクロースとの特別な体験の提供
結果:ファミリー層の集客が大幅に増加。感動的な体験を提供するパークとしてのイメージを強化しました。
マーケティング思考の重要性
USJの成功事例から学べることは、単なるテクニックやツールの活用だけでなく、根本的な「マーケティング思考」の重要性です。森岡毅氏が実践したマーケティング思考は、あらゆるビジネスシーンで応用可能な、普遍的な価値を持っています。
戦略的思考と資源の集中
マーケティング思考の核心は、限られた資源を最も効果的に活用することです。
選択と集中
全てを均等に行うのではなく、最も効果的な施策に資源を集中させる。
例:USJがハリーポッターエリアに大規模投資を行った決断。
長期的視点
短期的な売上だけでなく、ブランド価値の向上や顧客との長期的関係構築を重視。
例:「ハッピーサプライズ」コンセプトの一貫した展開。
データに基づく意思決定
直感や経験だけでなく、市場データや顧客インサイトを基に戦略を立案。
例:ターゲット顧客の綿密な分析に基づくキャンペーン設計。
顧客中心主義の徹底
マーケティング思考の根幹にあるのは、顧客を中心に据えた発想です。
顧客インサイトの深掘り
表面的なニーズだけでなく、潜在的な欲求や感情を理解する。
例:クリスマスキャンペーンでの「家族との貴重な時間」という価値訴求。
顧客体験の設計
商品やサービスそのものだけでなく、顧客の全体的な体験を設計する。
例:パーク全体での「ハッピーサプライズ」体験の創出。
継続的な価値提供
一度の購買で終わらせず、継続的に新しい価値を提供し続ける。
例:季節ごとの特別イベントの企画・実施。
全社的なマーケティング視点の必要性
マーケティングは特定部署の仕事ではなく、組織全体で取り組むべき課題です。
部門横断的な協力
マーケティング部門だけでなく、全部門が顧客視点を持って協働する。
例:USJでのスタッフ全員参加型のフラッシュモブ実施。
トップマネジメントの関与
マーケティングを経営戦略の中核に位置づけ、トップが率先して推進する。
例:森岡氏自身が CMO(最高マーケティング責任者)として全体を指揮。
組織文化の醸成
顧客中心主義を組織の価値観として浸透させる。
例:「お客様の期待を超える」ことを全スタッフの行動指針に。
イノベーションとの融合
マーケティング思考は、イノベーションを促進する触媒としても機能します。
市場創造
既存市場の奪い合いではなく、新たな市場を創造する視点。
例:「ホラーナイト」による新しいエンターテインメント体験の提供。
技術とニーズの橋渡し
技術シーズと顧客ニーズを結びつけ、新たな価値を創出する。
例:最新技術を活用した没入型アトラクションの開発。
継続的な挑戦
成功に甘んじることなく、常に新しい挑戦を続ける姿勢。
例:毎年進化し続けるシーズンイベントの企画。
このようなマーケティング思考を組織に根付かせることで、環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現することが可能となります。USJの成功は、このマーケティング思考の力を如実に示す好例と言えるでしょう。
まとめ:マーケティングの本質と実践
森岡毅氏が USJ で実践したマーケティング戦略は、「売れる仕組みを創ること」という本質に忠実なものでした。顧客の潜在的なニーズを深く理解し、「頭の中」「店頭」「使用体験」という3つの接点を制することで、持続的な成功を実現しました。
重要なのは、単なるテクニックではなく、顧客中心主義に基づいたマーケティング思考です。目的・戦略・戦術を明確に定め、限られた資源を効果的に活用する戦略的思考が不可欠です。また、マーケティングは特定部署の仕事ではなく、組織全体で取り組むべき課題であり、トップマネジメントの関与も重要です。
日本企業が国際競争力を高めるためには、技術志向から顧客志向への転換が必要です。USJの成功事例は、マーケティングの力が企業を劇的に変革させ得ることを示しています。
