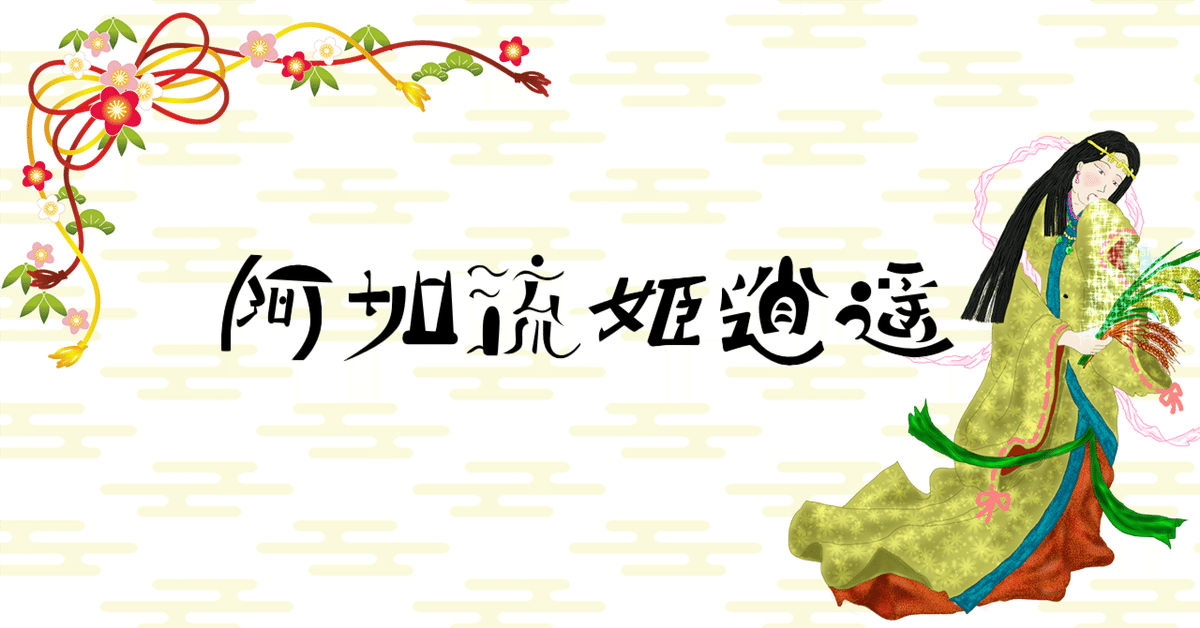
木花開耶姫と石長姫
瓊瓊杵尊が天降りして、笠沙の岬に来たときに、美しき乙女に出会い、恋に落ちる。
そこで乙女の父である大山祇に結婚の許しを請うと、大山祇は姉の石長姫も添えて寄越した。
しかし石長姫は醜く、瓊瓊杵尊の意に沿わなかった。そこで大山祇の元に返されたが、大山祇曰く、石長姫を娶ればその子孫の寿命は岩のように長くなったであろうに……。
そうして神の子である瓊瓊杵尊の末裔は人の子とように短い寿命となったのだった。
日向の高千穂のくしふる岳
天忍穂耳と鸕鶿草葺不合が同一人物で卑弥呼と神武が祖母と孫の関係だとすれば、瓊瓊杵尊とその子の彦火火出見(山幸)は存在しないことになるが、無から物語は生まれないので何かモデルがあったのだろうとは思う。
瓊瓊杵尊は日向の高千穂のくしふる岳に降臨するが、くしふるの意味がわからなかった。
そこに、金官伽耶国、首露王が出て来る。
後漢の世祖、光武帝の建武18日壬寅(42年)三月、禊浴の日に、彼らが住んでいた村の北側にある亀旨に、みんなを呼ぶ怪しげな声がした。
村の衆二、三百人がそこへ集って行くと、人の声は聞こえるが、姿は見えない。
その声は、
「ここに人がいるか?」
と聞く。九干らが
「われわれがおりまする」
というと、また
「ここはどこなのか?」
と聞く。
「亀旨であります」
と答えると、声はまたこういった。
「皇天が、私にいいつけてここにこさせ、国を新しく建てて、私をここの君主になれといわれたので、いまここに降りてきた。お前たちは、峰の頂上の土を掘りながら、つぎのように歌いなさい。亀よ亀よ 頭出せ ださずんば やいてたべるぞ。このように歌いながら舞い踊れば、それで大王を迎えて、喜び踊ることになるのだ」
九干どもは、いわれたとおりに、みんなが楽しげに歌いながら舞った。
しばらくたってから空を仰いでみると、紫色の紐が天から垂れてきて地面についた。
紐の端をみると、紅いふろしきがあり、その中に、金色の合子(盆)が包まれていた。
それをひらいてみると、なかに黄金の卵が六つはいっていて、太陽のように丸い。みなのものがそれをみて驚きながら喜び、百拝した。
しばらくしてふたたびそれを包み、かかえて我刀干の家に持ち帰り、床のうえに安置してから、みな解散した。
首露王は亀旨峯(くしほう/クジポン)に降臨する。金の卵から生まれたため金姓を名乗る。
瓊瓊杵がくしふる岳に天降る時、真床追衾に包まれて降るのだが、これを胞衣と呼ぶ者もいる。
卵で亀旨峯に降りた首露王とよく似ているということで、天皇家は朝鮮から来た説によく採用される類似神話だ。
2つの系譜
卑弥呼の後継者は台与である。
男王を討った立役者が神武天皇で、もしも二人が異父兄妹であれば、男女のきょうだいで家督を継いだ古墳時代の家制度にならって、二人で統治したとしておかしくはない。
国際的――と言っても中国と朝鮮だが――には男系である。
記紀が作られたのは国際情勢にあわせて男系に変えようとしていた奈良時代だ。
神武天皇の系譜と、台与の夫の系譜を繋げたのではないか、と言う説が1つ。
もう1つは、天照大神、天忍穂耳、彦火火出見のエピソードを間の系譜に持ってきたのではないかという説が1つ。
2つともを採用したような気がする。
特に、瓊瓊杵尊と石長姫、木花開耶姫のエピソードは、須佐之男の妻訪いに重なる。
神大市姫と政略結婚をしたエピソードだ。
神大市姫は、石長姫と同じく大山祇の娘だ。
稲田姫は大山祇の孫だ。
稚日女
若い娘の方が好きなのは古今東西変わらないだろう。
稚日女と天照大神は親子ほど年が離れていたのではないだろうか。
また大山祇のもとに居たことから、古代の家族制度を考えると大山祇もまた女王だ。
夫の候補は、狗奴国、紀氏の王だ。
同母同父姉妹ではないかと思う。
女性が妊娠できる期間を考えて最大で30歳差くらいか。
娘ほども若い妹を夫が陵辱したとき、怒りはどちらに向かうだろうか。
また、天忍穂耳だ。彼も稚日女を陵辱し子をなさせたならば、天忍穂耳の人望がないのはそのせいかもしれない。
二人の近親者を狂わせた妹を遠く離れた丹後の王に嫁がせたのが、脱解の物語に続くのかもしれない。
稚日女の伝説がある安楽島の伊射波神社は、かぶらこさんと呼ばれる。
日本書紀の神功皇后紀に、「尾田吾田節之淡郡所居神」と名乗っている。木花咲耶姫の別名は、神吾田津姫だ。
須佐之男の別名は、「伊邪那伎日真名子加夫呂伎熊野大神櫛御気野命」だ。
木花咲耶姫と石長姫の物語が稚日女と天照大神の神話であることは、そう外れていないと思う。
伊和大神
もう一つ、木花咲耶姫が稚日女ではないかと言う根拠がある。
播磨国風土記の伊和大神だ。
彼の妻の名が、許乃波奈佐久夜比命と言う。伊和大神は大国主の別名と言う。なお播磨国風土記では大国主の別名を持つ神同士が相対している。大国主が何人も居ることになっている。
ところで播磨国風土記には粟鹿神社の神も出て来る。阿和加比売と言ってこの姫は伊和大神の妹だ。
