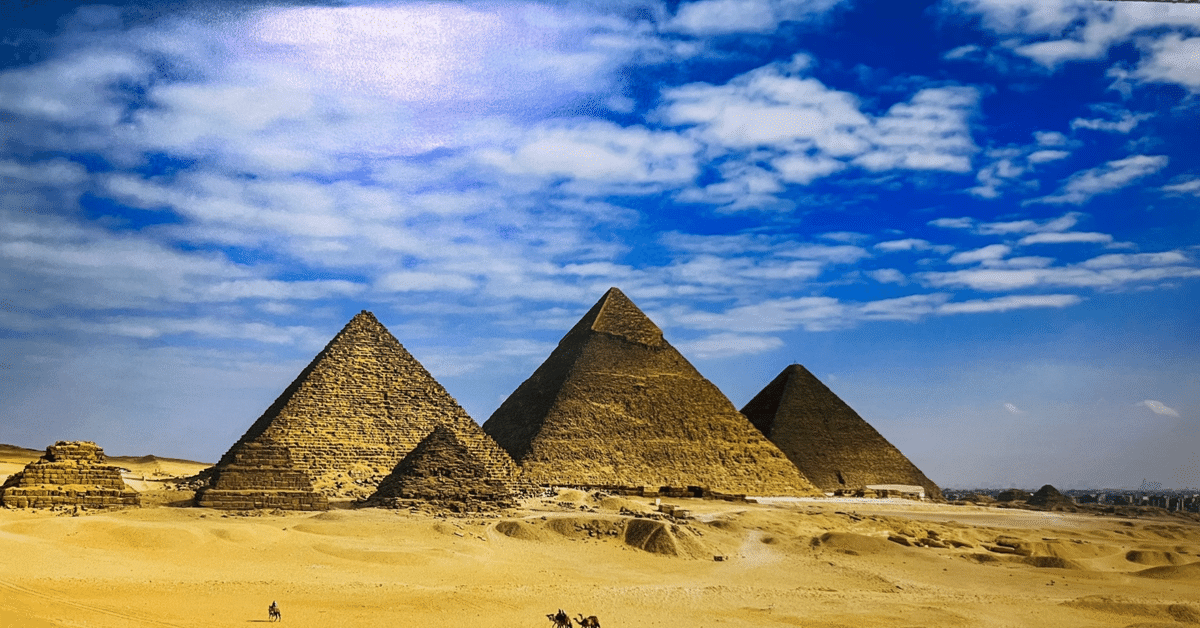
ボトムアップの説明はやめてくれという話
学生の時、社会人になってからも説明を受ける機会は多くあるだろう。私が説明する立場になることもあるが、基本的には説明をしてもらう立場の方が多い。長年説明を聞いていると「この人はいったい何を言いたいんだろう?」と思う場面も多々あるのではなかろうか?私なりに分析してみたところ、「私が理解に苦しむのはこういう説明方法を取られたとき」という法則性に気づいたので共有する。
京都を外国人にどう説明する?
説明の例題から入ろう。シチュエーションとしては、日本のことをまるで知らない外国人の友人に対して、京都を説明してあげる場面だ。さあ、あなたならどう説明する?

私なりに説明するならこんな感じだろうか。
「京都は日本の大都市のひとつであり、世界有数の観光都市です。かつては日本の首都であり政治や文化の中心地でした。寺院や神社が数多く存在しているためご利益を求めて参拝する方も多いですがそれだけではありません。寺社仏閣は建築物としても見ごたえがあるほか、風光明媚な景色が楽しめます。また京料理と呼ばれる工夫を凝らした伝統的でヘルシーな料理も楽しめます。城や庭園、食事処に至るまで、数日では巡り切れないような観光名所に溢れた雅な都市として京都は知られています。」
それでは模範解答…というか、海外向けのwebサイトで京都はどのように説明されているか見てみよう。以下はJNTO(国際観光振興機構)からの引用である。
Kyoto is the former capital city of Japan and world-famous for its refined culture, dining, and charm of rural Japan
Kyoto City attracts millions of local and international visitors each year looking for traditional Japanese culture. Temples and shrines such as Kiyomizudera Temple and Kinkakuji draw lots off attention from visitors, as do the bamboo groves of nearby Arashiyama. Stay in a traditional ryokan, take a dip in a rejuvenating onsen, and enjoy the seasonal changes of cherry blossoms and brilliant autumn foliage. Kyoto's magic is only a short bullet train ride from Tokyo. Beyond the city lie Kyoto Prefecture's many attractive rural areas. In the north, Amanohashidate has long been considered one of Japan's three most scenic places. Nestled in the mountains, Miyama is one of the last towns with thatched-roof farmhouses, many of which are still inhabited. Enjoy delicious local vegetables and the famous green tea grown in Uji.
この説明ではまず題名にて京都が日本の以前の首都であるとともに文化、食事、日本の田舎の魅力で世界的に有名と表現したうえで、日本の伝統的文化を求めて国内外から人が訪れるという一文から始めている。寺社仏閣、温泉、四季折々の景色をアピールしつつも交通の便についても説いている。
二つの説明文は近いと私は感じる。私の説明はいい線いっているのではないだろうか。
それではどういった説明文を私は受け付けないか。例えば以下のような説明である。
「京都は有数の観光名所です。寺社仏閣が数多く存在しているのが特徴で、観光に訪れるならば金閣寺が良いでしょう。なにせ建物の表面に金箔が使用されており、外から見ると金色の建物ゆえに金閣寺という俗称で呼ばれているのです。室町幕府三代将軍の足利義満が建立したという意味でも日本史を学ぶ上での印象深い建築物に間違いありません。」

この文章は前述の二つの文章よりも具体的記述に力を割いている。京都が観光名所だとは言い切っているし、歴史という観点でも、建物としての珍しさも触れているという点では私の書いた文章と同じである。人によってはこっちの方が好ましいというかもしれない。しかし私はこの説明を受け付けない。説明がマクロからミクロへと遷移していないためである。私はこの類の説明方法をボトムアップの説明と呼んでいる。
ボトムアップの説明を定義する
個別事項について詳細に説明する一方で全体を俯瞰するような説明をしない種の説明を私はボトムアップの説明と呼んでいる。先ほどの例であれば、金閣寺という個別事項について説明したうえで、京都の特徴や魅力について包括的にそして概念的に説明していないのが私が拒絶反応を示す理由である。説明をただ聞いただけでは、京都ではなく金閣寺について詳しくなったかのように思ってしまうためである。
パズルのピースを組み合わせて全体像を作る説明になっていると言い換えてもいい。聞き手である私からすれば、パズルのピース単体の理解はできるのだが、そのピースがどこに嵌ってどういった絵を描くのかが全くイメージできない。そのような全体像が見えにくい説明をやめてほしいというのが本項の趣旨だ。

逆に私が書いた説明やJNTOの文章は全体を俯瞰する文章を必ず入れるようにしている(JNTOの方は具体例を織り交ぜているのが特徴)。京都は日本国内ではどういった立場の都市で、世界にとってはどういった場所なのか?京都の魅力を観念的に説明するならば一般化してどう描くべきなのか?そういったことを意識して私は説明文を書いたし、おそらくJNTOの担当者もそういった書き方をしているだろう。
ボトムアップの説明はパワーポイントのスライドで顕著
京都を説明するならばまず日本にとって京都がどういった都市かを書くといったように、大局的に物事を捉えてから徐々に記述の範囲を狭めていくという手法を多くの人は頭では理解している。だが、パワーポイントで説明する際にそれを完全に実践できている人は少ない。
研修資料のタイトルを「○○向けの研修」にする人がいるがそれはよろしくない。研修を通して何を学んでほしいのかが不明瞭だからだ。自部署の説明をする際にいきなり専門知識を必要とする説明から入るのも良くない。聴衆は話が横道にそれたように感じて「その部署はどういった部署か?」という一番理解すべき項目が頭から抜け落ちてしまう。試しに自分が作ったスライドの12ページ目を見てみてほしい。そのスライドはプレゼンテーション全体の中でどういった役割を持つスライドかを説明できるだろうか?私のようなボトムアップ志向を苦手とする人間はそのスライド1枚の意味は理解できたとしても、そのスライドがプレゼンテーションの中でどういった役割を果たしているのかに頭を悩ませる羽目になる。

論文では概要、導入、従来の課題、実験、結果と考察、結論といった具合に話の流れが決まっている。実験の章で書かれている文章は必ず実験の内容を説明しているから私は頭を悩ませることはない。だが、プレゼンテーションでは何を言うためにそのスライドを作ったんですか?と言いたくなるようなスライドが挟まれている場合がある。何かを詳しく説明したいと思うあまり、プレゼンテーションという全体の中での立ち位置があいまいなスライドが生まれている。
ボトムアップの説明の方がいい場合もある
ここまではボトムアップの説明はやめてくれと繰り返し伝えてきたが、私だってボトムアップの説明をする場合もある。例えばΣの公式の証明方法を覚えているだろうか?$${\Sigma k^2}$$を証明するときには以下の恒等式を利用するだろう。
$${(k+1)^3-k^3 =3k^2+3k+1}$$
$${k=1,2,…,n}$$をこの恒等式に代入して辺々足し合わせると公式が導かれる。初めに宣言した恒等式が狙いをもっていると最後に分かる形になっているわけだが、この程度の小規模の証明であれば理解可能である。
小定理を組み合わせて大定理を示す場合ではもっと思考が追いかけづらい。その小定理から大定理に辿り着くまでの道を一度理解してから読み返さないと理解できない。だが、これはこのままでいいのである。証明者の意図をあらかじめ説明しなくとも良い。逆にトップダウンの説明ではなくボトムアップの説明しか数学では認められていない。
ピラミッドを立てるのと同様に、個々の地盤をしっかり固めてから一段階上へと進むような説明が望まれる場面ではボトムアップの説明をした方が良い。そちらの方が説得力は増す。一方で全体像が見えにくくなるリスクには自覚的であるべきだと私は考えている。
スライドではなく文章で説明してくれ
ボトムアップの説明をやめる方法は簡単である。文章で説明すればよい。ある程度の訓練を積んでいるのならば、論理的な文章を書くのは可能であるだろう。論理に飛躍があれば自分で気づいて修正ができる自信があるならばぜひ文章で説明文を作ってそれを周囲に配布してほしい。周りの人が説明不足だと感じる箇所があれば突っ込みを入れてくれるはずだ。
なお文章に対応するようにスライドを作れば論理的でわかりやすいプレゼンテーションになるかと言えばそうでもない。特に一枚一枚はわかりやすいスライドを作成できてしまう人ほど私は信用していない。一枚の完成度は高くても前後のスライドとの関係性を意識しないまま作成すると、聴衆は前後のスライドとの関係性がandなのかbutなのかfor exampleなのかを理解しないまま、一枚一枚のスライドの完成度の高さにごまかされてしまう。AがBであることはわかったんだけれども、プレゼンテーション全体を通してこの人は何を言いたかったんだ?と聴衆に思われてしまったら、それはスライドの出来は良くてもプレゼンテーションの質は低いということになってしまう。
私の苦悩
共感できるか否かはともかくとして、以上が私の不平不満を文章に変換したものである。文章を読むのが苦ではない私にとっては論理に欠陥があるかを確認したいので会社ではプレゼンテーションではなく文章で説明してほしいと常日頃から思っている。この思いはたぶん届かないのだが、せめてインターネットに残しておこうと思い筆を執った。言いたいことは書ききったので筆を置くことにする。
P.S.
本ブログは収益化を目指しているので、心ある方がいたら何か買っていってほしい。
