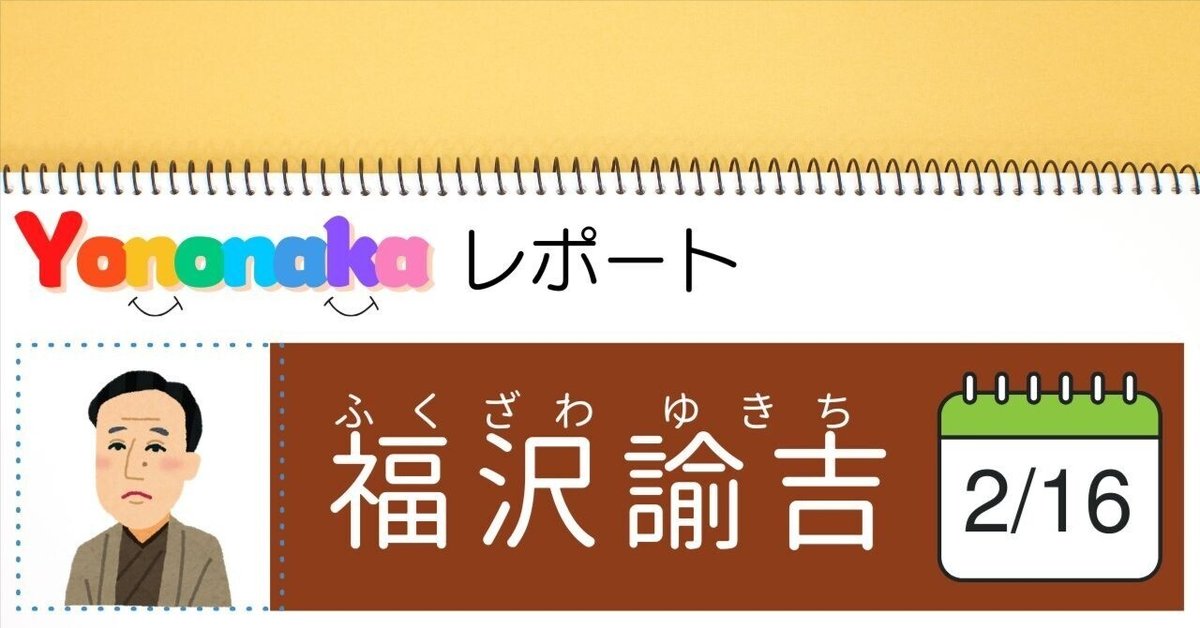
Yononakaレポート㊲「福沢諭吉」
「福沢諭吉」がテーマだった2月16日のYononaka。
授業内容を動画でも振り返っていますので、ぜひご覧ください。
今回は9名(小学生2名、高校生3名、大学生1名、社会人3名)の参加者とともに〝元〟一万円札の顔である「福沢諭吉」について学びました。これまで、Yononakaではいろいろなテーマを取り扱ってきましたが、歴史上の「人物」に焦点を当てた回は、今回が初めてでした。
まず「福沢諭吉って知ってますか?」と質問すると、「一万円札の人!」という声があがりました。やっぱり「諭吉=一万円札(お金)」のイメージが強かったですね。続けて「じゃあ何をした人?」と聞くと「わからん」という声がほとんどでした。参加者だけでなく、こういう人が多いのではないでしょうか?
「慶應大学をつくった人やろ」
「学問のすすめを書いた人」
「なんか明治時代に勉強にかかわってた人」
学校で学ぶ諭吉の知識はこれくらいかなぁと思います。いつも財布に潜んでいた人なのに、興味を持たないと調べる気にはなりませんよね。諭吉に限らず、歴史上の人物とか偉人と呼ばれる人の多くも同じような状態だと思います。Yononakaでは、参加者同士が自分の意見を話し合いながら、考え方や世の中の見方(視野)を広げていきます。この目的を前提としたら、歴史上の人物について知り、「①何をした人か?②どんな考え方をしたのか?③いまの自分にどう活かせるか?」という3点を意識すれば良い学びになるのではないか。そう思い、その一番手として諭吉を選んだわけです。
ざっくりまとめると、
①何をした?→身分・性別・仕事に関係なく皆が学べるようにして、日本の教育の基礎を築いた。
②どんな考え方→「実学」という「実際の生活に役立つ学び」こそ、するべき学問(勉強)であり、学ぶことによってのみ、人は賢くなれると考えた。
③いまに活かす?→受験の形式が変化している現代、テストのための勉強だけでいいのか、勉強(実学)は学生だけがするものなのかを考える。
学問を通して、三本柱を持った人、国になることを目指した
諭吉は「実学」という考え方を大切にしたとともに、学問をすることで、三つの柱を持った人、国になってほしいという思いも持っていました。「国とは一人ひとりの人が集まってできるものである」と考えていた諭吉は、人がそれぞれ立派になれば、国(日本)も立派になると信じていました。
三つの柱とは、
①自由平等→身分や仕事に関係なく、みんなが自由に学び合える。だれもが、話し合うこと、教えること、意見することができるようになること。
②独立自尊→自分で責任を持ち、人の役に立てるような仕事をし、一人の人間として力をつけること。
③国民皆学→みんなが勉強することで、みんなが幸せになれる。①,②を達成するためにも必要なこと。
諭吉は1835年生まれ、いまから約200年前の人物ですが、学問(勉強)や人の生き方についての考え方は、全く古くささを感じることなく、むしろ、いまの社会を生きる人々に必要な考え方であると感じます。SNSでの誹謗中傷や、自分だけがよければいいという考え方、形だけの勉強(学び)などを身近に感じたことはないでしょうか?便利でありながら、複雑な時代でもある現代だからこそ、こうした考え方、生き方を一度振り返ってみることが大切なのかもしれません。

参加者の感想の一部を以下に記します。
・自由平等、独立自尊、国民皆学は必要だなと思いました。
・福沢さんがみんなの人生を豊かにするために教育の重要性を説いたことや
お札になるぐらいの偉大な人物であることがよく分かりました。
・実学の考え方だと、お散歩や料理、YouTubeを見ることだって、
やり方、使い方次第で学びになると思う。
授業レポートは以上になります。
3月のテーマは「スマホ」です。これからの子どもたちにとって、必要不可欠になるであろうスマホ。その使い方や危険性について、学校ではまだまだ教わらないとのこと(生徒たち談)だったので、Yononakaでいっしょに考えていこうと思います。さらに!オンラインではなく「現地開催」となっておりますので、次回レポートもお楽しみに!
