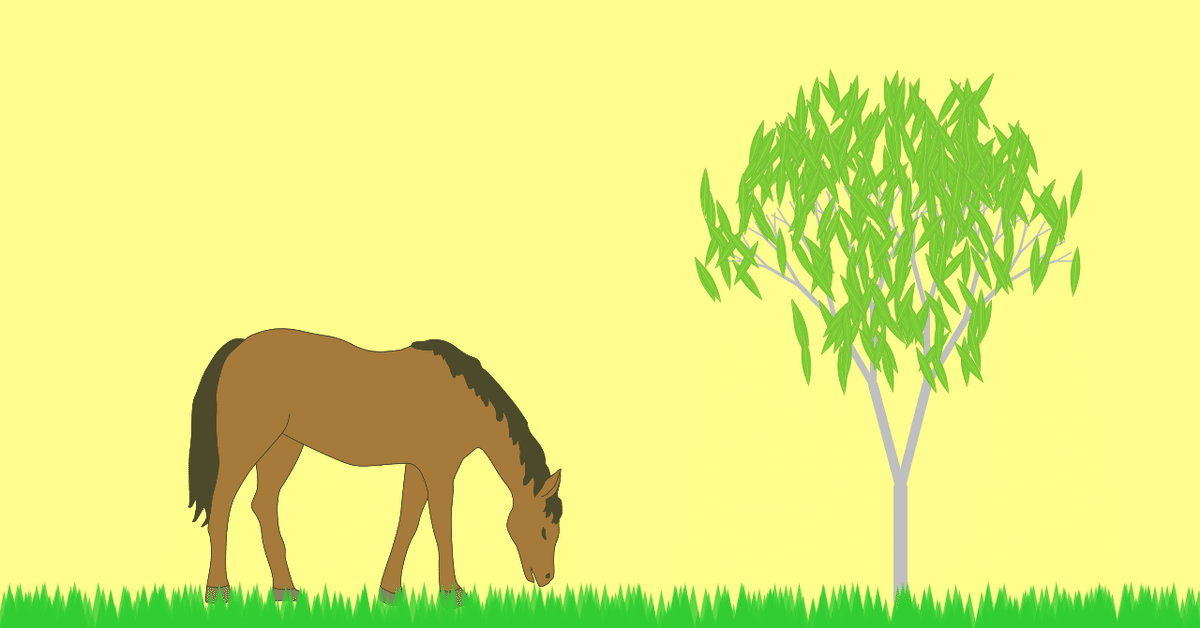
シュペルヴィエルの詩「動き」―ふりかえった馬は何を見たのか?
ジュール・シュペルヴィエル(1884-1960)はウルグアイ生まれのフランス詩人だ。「動き」は、1925年刊行の詩集『万有引力』(『引力』『重力』とも訳される)に収められている。有名な詩のようで、日本の中学校や高校の国語教科書にも掲載されてきた。
教科書では、中村真一郎訳、堀口大学訳、安藤元雄訳などが使われている。中村真一郎は「運動」と訳し、堀口大学と安藤元雄は「動作」と訳している。また、教科書には使われていないが、飯島耕一の訳もあって、やはり「動作」と訳している。
でも僕が出会ったのは、『海に住む少女』(光文社古典新訳文庫)の「訳者あとがき」に掲載されていた永田千奈訳だ。
永田は「動作」ではなく、「動き」と訳している。なんとなくこっちのほうがいいように思う。
一読して心を惹かれた。
■シュペルヴィエル「動き」(永田千奈訳)
ふりかえった馬は これまで
誰も見たことのないものを見た
そして、再び草を食べ始めた
ユーカリの木のしたで
それは人でも樹木でもなく
牝馬でもない
木の葉をゆらしていた風の
なごりでもない
それは 二万世紀も前に
別の馬がみたもの
今日と同じこの時刻に
とつぜん振り向いて目にしたもの
人も馬も 魚も虫も このさき誰も
この大地がいつの日か
腕もない 足もない 頭もない
彫像の残骸に成り果てるそのときまで
もう二度と見ることのないもの
■語句
これまで/誰も見たことのないもの――わかりにくいところ。第1連で「これまで誰も見たことのないもの」とされているのに、第3連では「二万世紀も前に別の馬がみたもの」と言われる。原詩のフランス語は"nul ne"となっており、これは「誰も~ない」(英語のno one、nobodyに相当)という意味だ。「人間は誰も見たことがない」という意味かと考えてみるが、第4連では「人も馬も 魚も虫も このさき誰も……見ることのない(nul ne)」と言われていて、この「誰」には人間以外の生き物も含まれている。とりあえず、第1連の「誰も」を「人間は誰も」と解し、第4連の「誰も」は別の使い方をしていると見なしておくことにしよう。(無理?)
ユーカリ――主にオーストリアに分布する常緑高木。コアラが食べるものとして知られる。
それは人でも樹木でもなく/牝馬でもない/木の葉をゆらしていた風の/なごりでもない――「~ではない」とたたみかけるように否定するが、読者の脳裡には否定されたものの残像が残る。外山滋比古が「修辞的残像」と呼ぶものだ。同じ技法は島崎藤村の「千曲川旅情の歌」でも使われている。(川崎寿彦『分析批評入門』65頁以下参照)
二万世紀――200万年。
■解釈
◆馬は何を見たのか?
この詩を読むと、どうしても、「いったい馬は何を見たんだろう?」という疑問が湧いてくる。
第一連では、「誰も見たことのないもの」とされ、第二連では、「人でも樹木でも牝馬でもない」「風のなごりでもない」と言われる。この世界で普通に見えるものではないということだろうか。
第三連に至ると、それは「二万世紀の前に別の馬がみたもの」と言われる。ここでいきなり、現在から果てしない過去に戻る。
そして第四連では、一気に果てしない未来に飛び、それは「人も馬も 魚も虫も このさき誰も(……)もう二度と見ることのないもの」と言われる。
この未来では世界はどうなっているか。大地は、「腕もない 足もない 頭もない 彫像の残骸に成り果て」ている。これは世界の終末の光景だ。そしてこの光景を見る者は誰もいない。見る者がいたとしたら、そのときに見るものとは何か。
それは虚無ではないか。
◆世界の二重性
二万世紀前にある馬が虚無を見る。二万世紀後の現在、またある馬が虚無を見る。そしてそれ以降、二度とそれを見る者はいない。
「どうして?」って思う。だが、詩人はそれを事実としている。詩的事実だ。だから、「どうして?」って思っても、そうなのだと認めるしかない。問題はそれによって何が表現されているかだ。
二万世紀前にある馬が見たものが虚無であり、二万世紀後の馬が見たものも虚無であるとすると、虚無は世界が終わるときに見えてくるものであるだけでなく、世界の始まりのときからずっと存在し続けているものとされていることになる。
世界はつまり、二重性を帯びている。
ユーカリの木が生え、その下で馬が草を食べている。向こうには牝馬もいて、同じように草を食べている。風が木の葉を揺らしている。そういう明るい世界が一方にある。
他方には、もはやいっさいの生き物が存在しない暗い世界がある。あるのは彫像の残骸に喩えられる荒涼とした大地のみ。ぞっとする沈黙の世界だ。
明と暗、平穏と戦慄、動きと静寂、生と死、日常と終末の世界の対立だ。平和な明るい日常の世界と、暗鬱で虚無的な終末の世界が、一枚の紙の表と裏のように、二重になったまま、世界の始まりから、ずっと存在し続けている。二万世紀前にもあり、現在もあり、はるかな未来にもある。それらは並行して存続する。虚無は僕らの日常の裏側に貼りついているということだ。
二つの世界は互いに交わることがない。いや、二頭の馬だけが虚無の世界を垣間見る。だが、馬はまた何ごともなかったかのように「再び草を食べ初め」る。人間ではないので、見たもののことが語られることはない。
明るい世界と暗い世界の二重性が解消されるのは、世界の終わりにおいてだ。そしてそれは、前者が消え、後者だけが残るという形でだ。
◆この詩が語るもの
この詩は日常の背後に潜む虚無について語っている。それは怖いものだ。
地球の最後は必ず来るだろう。自身の死も必ず訪れるだろう。でも、人間は通常、そういうことは意識せず、日々を生きている。馬が坦々と草を食むように。私たちの目には世界は穏やかに見える。でも一瞬暗転することがある。馬だけでなく、僕たちだって虚無の世界を見ることはある。そして絶望する。
しかし、慰めがある。この詩の「ふりかえった馬」は、虚無を見たにもかかわらず、何事もなかったように、ユーカリの木のしたで再び草を食べ始める。それでいいのだ。見たものを忘れて、静かに日常を続けていくだけで。
虚無があるにしても、そしてそれが常に僕たちを脅かし続けるにしても、馬、草、ユーカリの木、樹木、牝馬、風などによって表現される今ある世界は、美しい世界だ。
■おわりに
馬が長い首をめぐらせて、大きく後ろを振り返るさまはとても印象的だ。詩人はこのゆったりした動きを見て、馬が人間には見えない何かを見ているのではないかと思ったのかもしれない。
年譜を見ると、シュペルヴィエルは1884年にウルグアイの首都モンテビデオで生まれている。富裕なフランス移民の子だそうだ。
生後6カ月で、突然両親を失う(中毒かコレラ)。その後、おじとおばの家で、二人を両親と思って育つ。おじ、おばの子供たちとともに。
ところが9歳のとき、偶然、実の両親のことを知り、大きな衝撃を受ける。
世界ががらがらと崩れるような気がしたのではないか。両親も、一緒に遊んでいたきょうだいも実は本当の両親ではなく、本当のきょうだいではなかったのだから。
この詩には、シュペルヴィエルのこのような生い立ちも関係しているのだろう。
■参考文献
『シュペルヴィエル詩集』堀口大学訳、新潮文庫、1955
『アポリネール コクトー シュペルヴィエル詩集』世界詩人全集17、渡辺一民・堀口大学・飯島耕一訳、新潮社、1968(シュペルヴィエルの詩は飯島耕一訳)
『シュペルヴィエル詩集』安藤元雄訳、ほるぷ出版、1983
『フランス名詩選』安藤元雄・入沢康夫・渋沢孝輔編、岩波文庫、1998(シュペルヴィエルの「動作」は安藤元雄訳)
シュペルヴィエル『海に住む少女』永田千奈訳、光文社古典新訳文庫、2006
川崎寿彦『分析批評入門』至文堂、1967
外山滋比古『修辞的残像』みすず書房、1968
北鎌フランス語講座 - 読解編:「動作」
http://lecture1.kitakama-france.com/index.php?詩a
