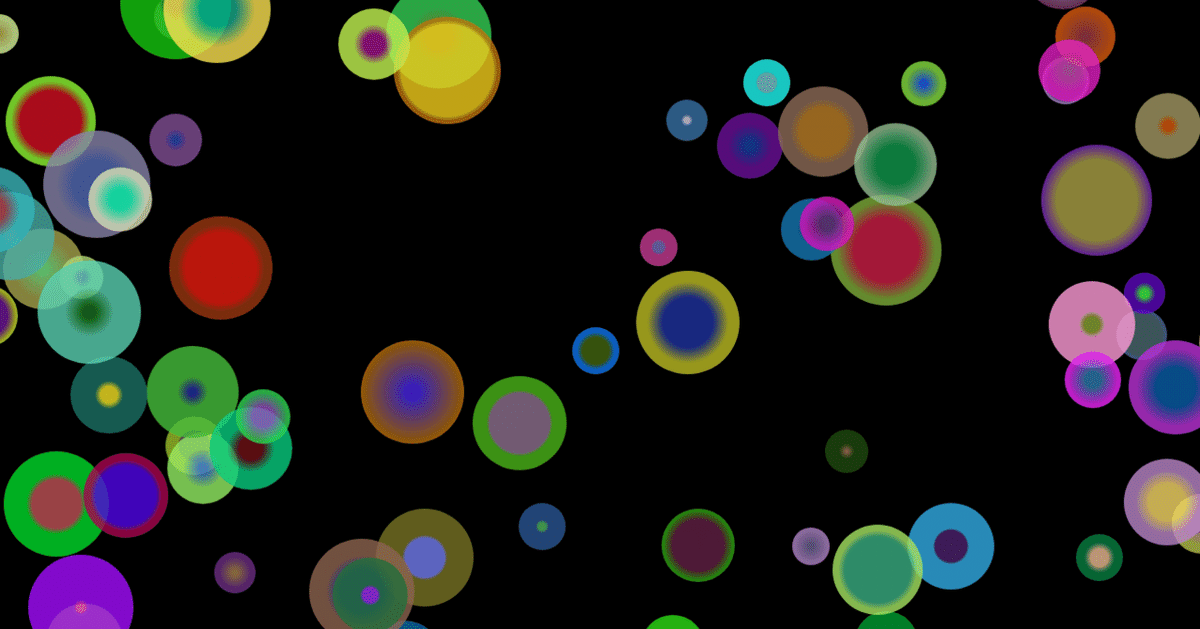
ロマンチックなカフカ
主人公がおどろおどろしい虫に変身する奇妙な小説『変身』を書いたカフカに、普通の作家が描くようなロマンチックな恋愛場面はあるのだろうか。
性描写はある。主人公によって行われる性行為だけでなく、脇役のそれまで含めれば、かなりあると言えよう。だが、恋愛描写はどうか。
僕が、カフカが書いた唯一のロマンチックな恋愛場面だと思うのは、未完の短編『ある犬の探究』末尾の一シーンだ。そこでは、犬同士の出会いが描かれる。
『ある犬の探究』はカフカの未完の自伝的短編で、犬族の話だ。人間は登場しない。
主人公の探究犬は、犬族は何を食べて生きているのかを探究する。犬族はとりあえずは大地から得られるものを食べているのだが、探究犬は、大地の食物は実は天から来るのではないかと思う。そして自らの考えを証明するために断食実験を行う。しかし、何の成果も得られず、絶望する。
探究犬とは、人間にとっての生きる糧、精神的な糧とは何なのかを探究する作家カフカ自身のことだ。カフカは生の世界の享楽を断って、文学にひたすら打ち込む。生きる糧を求めて。しかし、すべては徒労に終わる。探究犬は過度の断食のために血を吐き、気を失ってしまう。
探究犬が再び意識を取り戻すと、目の前に一匹の「美しい犬」がいる。犬は自分を「狩人」(猟犬ではない)であると言い、これから狩りをするので探究犬にその場を離れるように求める。しかし、探究犬は、体が弱っているので歩けないと抗う。こうして探究犬と狩人犬との間に、立ち退きをめぐる長い議論が始まる。
探究犬は「狩りをやめにしてください」と頼むが、狩人犬は「私は狩りをしなければなりません」と譲らない。探究犬が、どうして「しなければならない」のかわかっているのかと狩人犬に問うと、狩人犬は「それは自明で、自然な事柄です」と答える。探究犬はなおも追及するが、逆に、「この自明なことがわからないのですか」と問い返される。
狩人犬は探究犬とは正反対の生き方をしている。探究犬は食べることを拒否してまで、犬族は何によって生きているのかを追究している。それに対して狩人犬は、単純に他の生き物を狩り、その肉を食べて生きている。
狩人犬とは自然な生を生きている一人の女性である。
狩人犬が「この自明なことがわからないのですか」と問い返したとき、探究犬は黙る。狩人犬が「歌を歌い始めている」ことに気づいたからである。
――私は(……)その犬が胸の奥から一つの歌を歌い始めていることに気づいた。「あなたは歌を歌うのですね」と私は言った。「ええ」と犬はまじめに言った、「歌を歌います。すぐに。でもまだ歌ってはいません。」「もう始めていますよ」と私は言った。「いいえ」と犬は言った、「まだです。でも用意をしてください。」「あなたが否定しようと、もう聞こえていますよ」と私はふるえながら言った。犬は黙った。私は当時、これまで私以前にいかなる犬も経験したことのない何かを認識したと思った。少なくとも、伝承にはそのかすかなほのめかしさえ見られない。そして私は急いで果てしない不安と恥ずかしさの中で、血だまりの中に顔を伏せた。私が認識したと思ったのはつまり、その犬が気づかないうちにもう歌っているということ、いやそればかりか、犬を離れた旋律が、それ自身の法則に従って、空中に浮かび、犬の上方を離れ、その犬とはまるで関係ないものであるかのように、私の方を、ただ私の方をめざしているということであった。(……)私は抵抗できなかった。それはどんどん強まってきた。それはとどまるところを知らず、もう今はほとんど私の耳を破裂させんばかりであった。しかし最悪なことは、それがただ私のために存在しているように思われることだった。この声、その気高さの前では森も沈黙したこの声が、ただ私のためだけに。(ヨジロー訳)
このあと探究犬は、「旋律に駆り立てられて」、いつのまにか「なんともすばらしい跳躍をしながら、飛ぶように走って」いる。
カフカの手にかかると、恋愛も犬と犬の間の事柄として表現される。犬同士の間に響く<沈黙の歌>となる。だが、これまでさまざまな作家によって描かれた人間同士のどの恋愛シーンにも劣らず、美しい。
断食の末についに血を吐いてしまう探究犬は、結核のために喀血したカフカであり、探究犬の目の前に現れた「美しい犬」はカフカの恋人ミレナ・イェセンスカーである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
