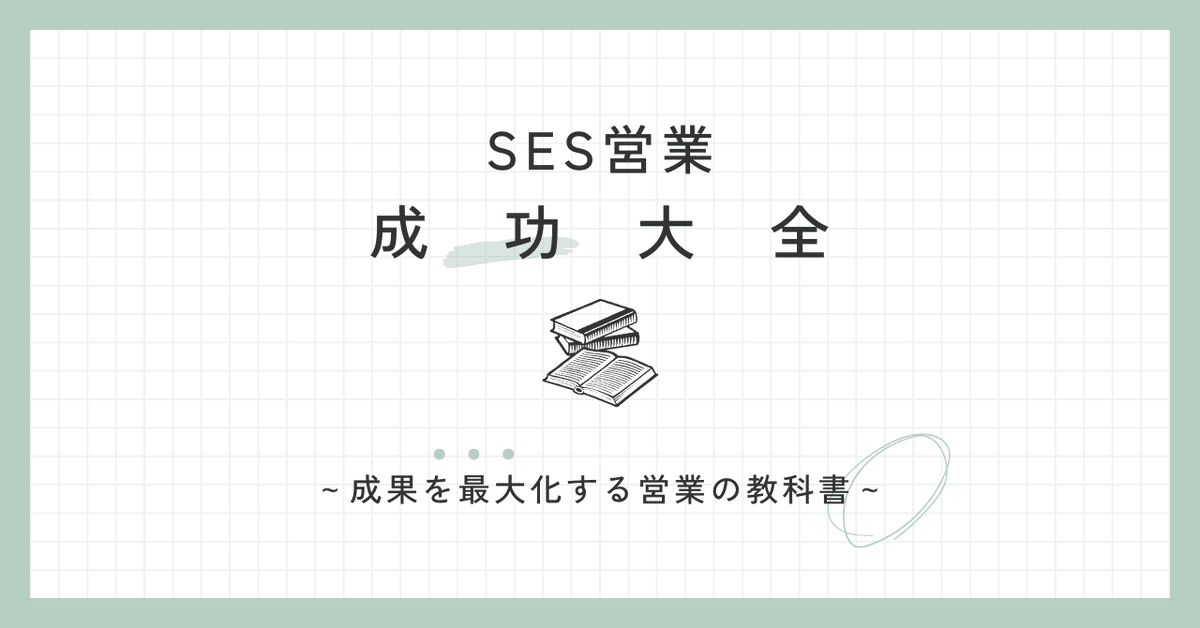
SES営業 成功大全 ~成果を最大化する営業の教科書~
本書の狙いと概要
「SES営業で成果を出すには何が必要か?」――本書は、そんな疑問にこたえるために生まれました。単にビジネスモデルの概論や基本スキルを解説するだけでなく、SES営業の現場で頻発する悩みを解決し、成果を最大化するためのノウハウを体系的にまとめています。
特に、SES業界で離職が多い背景として、以下の4点をよく耳にします。
成果が見えづらく、モチベーションを保ちにくい
SES営業はエンジニアをアサインして終わりではありません。実際の開発進捗が自分の成果にどう結びついているか把握しづらく、やりがいを感じにくいという課題があります。
→ 本書では、「業務プロセスの可視化」「定期的なフィードバックシステム」などを活用し、やりがいと達成感を高める仕組みを解説します。キャリアパスが曖昧
営業としての成長機会やスキルアップの道筋が見えづらいせいで、長期的なビジョンを描きにくいのが実情です。
→ 本書では、SES営業だからこそ描けるキャリアの可能性を示し、自分なりの目標設定や年収アップへのロードマップを提示します。仲介役として板挟みになりやすく、ストレスが溜まりやすい
顧客からの要望とエンジニアの事情が噛み合わず、気づけば「お互いの不満を背負う」立場に。
→ 本書では、コミュニケーション・ファシリテーション術やトラブルシューティングのシナリオ集を通じて、「板挟み状態」を回避し、最適解を導く方法を紹介します。利益率の圧迫とノルマの厳しさ
単価交渉のプレッシャーや高いノルマに追われると、利益確保が難しくなりがちです。
→ 本書では、提案設計の工夫や価格交渉での“値引きしない説得術”などを実践的に解説し、適正利益を確保しながら営業成果を伸ばす方法を具体的に示します。
本書で取り上げる内容
第1章:SES営業の基本構造を理解する
SESビジネスの仕組み・法規制を知り、リスクを最小化する。第2章~第3章:必要スキルの実践マスター術
技術理解力・ビジネス翻訳力・データ分析力・共創力・倫理観など、今日から使えるヒントを解説。第4章:業界別攻略マニュアル
製造・金融・医療など主要業界ごとの押さえるべきポイントを整理。第5章:契約獲得までの7ステップ
リード発掘~初回アプローチ~ヒアリング~提案~価格交渉~契約締結~アフターフォローまでを体系的に学ぶ。
なお、本書は全7章・32セクションを予定しており、第5章までを先に記載しています。
現在は 第6章・第7章を準備中 で、以下のような内容を取り上げる予定です。
第6章(仮)モチベーションとトラブルシューティング
成果の“見える化”とチームのモチベーション管理
スキル不足やコミュニケーション摩擦など、現場で起こりがちなトラブルへの対処法
板挟み状態を解消するためのノウハウとハラスメント対策
第7章(仮)キャリアパスと利益最大化の戦略
SES営業としてのキャリアデザイン:専門性の深め方、マネジメントスキルの習得
利益率を高める営業戦術:単価交渉、付加価値の創出、チームマネジメント
今後の業界トレンド予測や独立・起業・海外展開の可能性
本書の特徴は、「営業の勘」に頼らず、具体的なテンプレートやデータ分析を活用する方法を提示している点です。
生成AIやデジタルツールの有効活用
業界別攻略の要点整理
契約形態・法務面のリスクマネジメント
トラブルシューティングでの実践的シナリオ集
これらを通じて、SES営業として収益を安定化し、さらに大きく伸ばすための総合戦略を習得していただくことが本書の狙いです。ぜひ目次を俯瞰しながら、気になる章からでも読み進めていただき、日々の営業活動に活かしてください。
✳︎本書は全7章・32セクションを予定しています。
✳︎随時更新中。第5章まで記載済み。約70,000文字。
✳︎第1章途中まで無料公開中です。
第1章:SES営業の基本構造を理解する
1. SESビジネスの全体像
1-1:3分で分かる「SES」と「派遣」「請負」の違い
「SESと派遣と請負の区別が曖昧なまま営業をするのは、プロ失格です。
それくらい、この3つの契約形態を正確に理解することは重要です。
派遣
労働者派遣法に基づき、派遣先企業が労務管理を行う形態。
営業としては、契約書の「労働者派遣契約」上の条件(期間制限、派遣可能業務など)を把握しなければならない。
“法令違反すると即アウト” という厳しさがある。
請負
請負企業が仕事の完成責任を負い、成果物を納品する契約。
一般的には「業務委託(請負契約)」と呼ばれることも多い。
SESと比較すると、指揮命令権は請負側(受託企業)にあり、発注先企業が直接エンジニアに業務指示を出すことはNG。
営業側は、プロジェクトの進捗・成果物品質の責任を大きく負うため、プロマネ力が問われる。
SES(準委任)
Software Engineering Serviceの略称ではなく、「System Engineering Service」の意味で使われることが多い。
準委任契約がベースで、エンジニアが派遣先の指揮命令を受けながら業務を行う形。
営業がやるべきことは、「スキルマッチを精度高く行い、適正な単価交渉と稼働管理を徹底すること」。
派遣と似て非なる点が多いため、法的リスクを把握しつつビジネスチャンスを逃さないことがカギ。
ポイントは、誰に指揮命令権があり、誰が成果物に対して責任を負うか。
SESは成果物の完成責任を負わないが、派遣並みにエンジニアが現場で業務指示を受ける。
だからこそ「偽装請負」や「実質派遣」と疑われるリスクがあり、契約形態をあいまいにしていると行政指導や取引停止を食らう危険もある。
1-2:市場規模3.2兆円の内訳(業界別シェア・主要プレイヤー)
日本のIT人材不足が深刻化する中、SES市場は右肩上がりに成長しています。
国内のIT関連市場の中で、いわゆる「技術支援・開発支援」分野の規模は約3.2兆円とも言われます。ただし、この数字を鵜呑みにして「ブルーオーシャンだ!」と盲信してはいけません。なぜなら、派遣・請負・SESなどが複雑に混在した数字だからです。
業界別シェア
製造業系:IoT需要の拡大により、現場の技術支援ニーズが加速中。
金融系:DXやFinTechブームで、大量のシステム刷新案件が絶えない。
通信系:クラウド・5G関連のインフラ構築や保守が常に発生。
その他(官公庁、医療、物流など):公共案件や医療データ関連など、潜在的に拡大余地が大きい。
この中で特に成長が期待されているのは、製造業のIoT分野と金融のDX関連。営業としては、既存の主要プレイヤーをよく知り、どの企業がどんなソリューションを打ち出しているのかを常に追いかけることが必須です。
主要プレイヤー
大手ITベンダー系:大企業向けに包括的なITサービスを提供する中でSESを活用。
専業SES企業:技術者数や専門特化分野で勝負する。
人材派遣グループ:派遣とSESの両方を展開しているケースも多い。
コンサル企業:DXコンサルの一環としてIT人材をSES的に提供する動きが増えている。
大事なのは、「なんとなくSESをやっている企業」と区別する視点です。SESと銘打っていても、実質は派遣会社や下請け構造で利益を取っているだけの企業が山ほどあるのが実情。どこにビジネスモデルの強みやリスクがあるのかを掴まなければ、取引先の選定やエンジニアのアサインで致命的なミスを犯します。
1-3:SES企業の収益モデル図解(単価×人数-コストの計算式)
SES営業が理解すべき最重要ポイントは、「自社の利益がどこから生まれるか」 です。単純化すると、収益モデルは下記の式で表されます。
営業利益 = (契約単価 × 稼働人数 × 稼働期間)-(エンジニアへの給与・諸経費)契約単価:
エンジニアのスキルレベルや経験年数、対応できる技術領域で上下する。
ハイレベルスキルを持つ技術者ほど単価が高くなるが、その分、給与や福利厚生も高くなりがち。
営業がいかに“相場より高い単価”を引き出すかが勝負。
稼働人数:
会社全体の稼働技術者数 × 稼働率(実際に稼働している割合)
SES企業では「 bench(ベンチ)=待機」状態が長いと、その分コストが出続ける。
「稼働率をどこまで上げられるか」は営業の腕次第。的外れなマッチングを連発すれば、エンジニアは空きが増え、利益が下がる。
稼働期間:
一般的に3ヶ月、6ヶ月、1年などで区切る。延長が繰り返されるケースも多い。
長期稼働ほど収益が安定しやすいが、その分、客先やエンジニアの不満が顕在化しやすいリスクも。
ちゃんと定期フォローをして延長につなげるのが優秀な営業。
コスト:
エンジニアへの人件費・教育費・採用費など。
オフィスなどの間接費も含まれるため、規模拡大とともにコスト構造は複雑化。
コストを見誤ると、いくら単価が高くても儲からない事態に陥る。
ここで見落としがちなのは、“エンジニアの定着率”です。
いくら受注が増えても、エンジニアがすぐ辞めてしまえば採用コストだけが膨れ上がり、利益がどんどん目減りする。SES営業は、「エンジニア確保」と「顧客へのアサイン」の両輪を回せなければ、真の稼ぎを得られません。
まとめ:この章のキーポイント
SESと派遣・請負の違いを曖昧にしない。法的リスクがある以上、言い訳は通用しない。
市場規模3.2兆円の正体を見極め、主要プレイヤーの動向を常に把握する。
SES企業の収益モデルは、契約単価×人数×稼働期間 - コスト。営業はマッチング精度と単価交渉力、エンジニアフォローで差をつける。
ここまでが、「SESビジネスの全体像」です。SESは“なんとなく”やって利益を上げられるほど甘いビジネスではありません。逆にここを正しく理解し、リスク管理と利益構造を分かった上で動ける営業ならば、成功する可能性が大きくなります。
次は「主要顧客企業の購買プロセス」を学び、どういうプロセスで案件が決まるのかを見ていきましょう。
2. 主要顧客企業の購買プロセス
2-1:IT部門 vs 事業部門の意思決定構造
営業が心得るべき最初のステップは、「誰が最終的に決定権を持っているか」を正確に把握すること。
SESの商談では、IT部門(情報システム部や開発部門など)と事業部門(現場部隊、経営企画、マーケティング部門など)が絡む場合が多く、両者でニーズやゴールが異なるのが普通です。
IT部門の優先事項
技術要件の適合度:システム要件定義やインフラ要件とのマッチング。
リスク管理:スキル不足や進捗遅延、セキュリティ事故に対する懸念。
運用保守性:継続的なサポート体制や、技術者が長期稼働できるか。
事業部門の優先事項
業務効率化・売上向上:SESによる開発スピードアップや運用コスト削減が見込めるか。
予算との兼ね合い:最小コストで最大効果を狙いたい。ROIの説明が必要。
納期厳守:新サービスやプロモーションのリリース時期が死活問題になる。
多くの案件では、事業部門がゴーサインを出すかどうかが鍵になると同時に、最終的な技術適合判断はIT部門が担うことが多い。つまり、IT部門と事業部門、両方を納得させられる提案が必要です。
2-2:調達担当者が重視する5つの評価基準
大企業や官公庁クラスでは、独立した調達・購買部門が存在します。ここでは、調達担当者が「どんな項目で評価しているのか」を押さえておきましょう。
ここから先は
¥ 980
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
