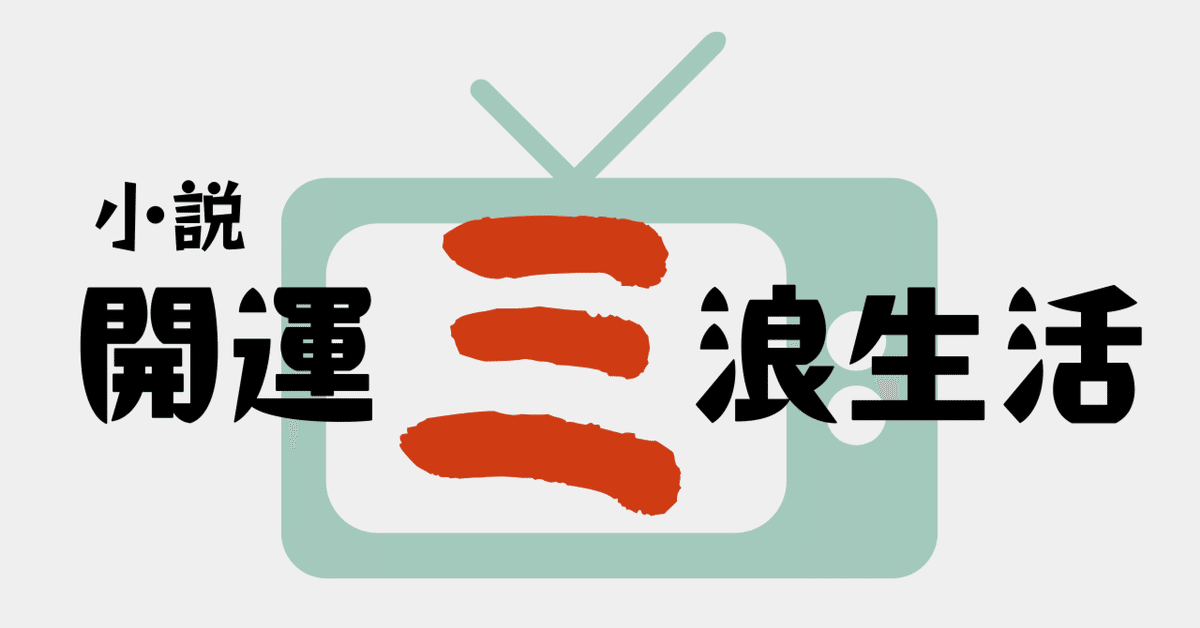
小説 開運三浪生活 28/88「滑り止め滑り込み」
半年後、文生は予定どおり熊本大を受験し、そして大方の予想どおり余裕で落ちた。
例年より難しいと言われたセンター試験の英語で154点というまぐれの点数を叩き出した文生は(模試でもせいぜい6割しか取れていなかった)、得意の国語ではしっかり八割を得点し、苦手の理系科目はもちろん低かったものの、それでも合計点で七割に肉薄した。同じく劣等生の野田が「予想屋フミオ」と命名し、普段安定して好成績を残してきた木戸が「最後の最後に本気出してきたな」と感嘆するほど、文生にしてはかなりの上出来だった。二次試験の結果によっては、逆転合格の可能性もなくはなかった。
「……厳しいと思うぞ」
担任はいちおう出願を止めてくれたが、文生は諾かなかった。
実際、さすがに記述式の試験で実力以上のものを発揮できるはずもなく、熊本大の二次試験はほぼ白紙で答案を提出した。
そんな意固地の文生でも、後期受験は担任の忠告を容れ、理系学科の受験を諦めた。西日本へのこだわりも捨てざるを得なかった。文生のセンター試験の点数でも合格の可能性が高く、環境問題の勉強もできそうな文系の学部に出願した。世間体を気にする母親から「うちは浪人させられないかんね」としつこく言われていたこともあり、さすがに現実を見たのである。
結果、滑り込んだのが、前年に岩手に新設されたばかりの県大の公共政策学部だった。二次試験は面接と小論文で可もなく不可もない手応えだったが、配点の高かったセンター試験の国語と英語が効いた。
県大の存在は文生もよく知らなかったし、近所の住民たちにもほとんど知られていなかった。にもかかわらず、口々に文生を褒めそやす現象が起きた。
「国公立だっぱい? 難しいんだわぁ」
「フミオちゃん、いいとこ受かったわ。親孝行だっぱい」
「さすが理数科だぁ」
不本意ではあったが、元・優等生としてのつじつまはなんとか合わせることができた。
級友たちの進路も大方決まった。同じ理数科で三年間学びながら文生とほとんど交流のなかった超優等生たちは東北大や医大や早稲田慶應に進み、センター試験がいまひとつだった木戸は東北大を回避して受験した中部地方の国立の総合大学に、野田は都内にある私立の工業大学に進学することになった。
「岩手行ったら、テレビ、買う」
実家を発つ日、助手席に座った文生は窓越しに宣言した。あからさまにがっかりした顔を見せた母親が口を開く前に、文生は主張を押しかぶせた。
「テレビ観なっきゃ、世の中のことわがんない」
「……うん、必要だよ、テレビ」
横から弟の武登が加勢してきた。母親はしぶしぶ了承した。
「いいんだぁ。ゲームとか、いやらしい番組にうつつ抜かさないんなら」
父親は苦笑し、無言でアクセルペダルを踏んだ。
