
「こんな音にしたい」という意志をどうやって持つか?(12)
ある日、全身を使いたいと思った。
伴奏がなくても身体でリズムを刻めなくてはならない
ミリヤム・バーンズ(Mirjam Berns, 1944-)のダンスクラスは楽しかった。長らくフランスの振付家ジャン‐クロード・ガロッタ(Jean-Claude Gallotta, 1950-)のダンサーたちにレッスンを付けてきた人だ。
彼女は鏡を使わない。音楽も使わない。1,2,3,4....というカウントもしない。その代わり適当な口三味線でリズムを取る。

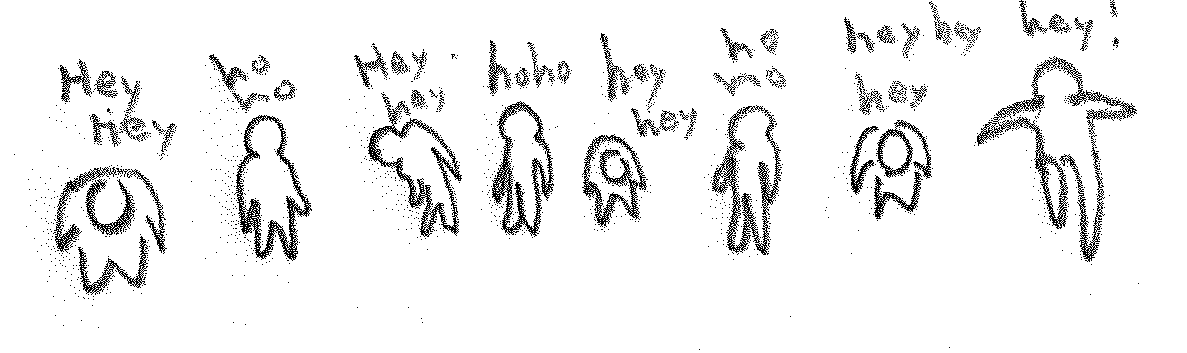
ヨーロッパでは夏になると、シアターも学校も休み。フランス人がバカンスを田舎で過ごすのはよく知られているけれど、ダンスでも音楽でも多くのワークショップが開かれるのもこの季節で、多くのダンサーやミュージシャンたちがいろいろなワークショップをはしごする。また、若いアーティストを支援する小さなプロダクションでは、それぞれのレジデンスアーティストにスタジオや泊まる場所を提供して創作を助ける。ブリュッセルのP.A.R.T.Sのように、学校がスタジオを開放してダンサーたちの創作や研究を助け、毎朝希望する参加者にダンスレッスンを付けたりする場合もある。
音楽や美術や演劇、あるいは芸術学や芸術史などの研究をやっていて、ダンスのレッスンを受けるという人はわりといる。ミリヤムのクラスは子供から老人まで年齢にかかわらず、またいろいろな職業をしている人たちが参加しやすいところがあった。もちろんダンスを職業にしている人たちも参加していた。またいろいろな地域から参加者がいて、ミリヤム自身もいろいろなところで過ごしてきた人なので(確かオランダ生まれのベネズエラ人で、ニューヨークにいたこともある)、フランス語、英語、スペイン語がレッスン中は入り混じった。彼女の息子と娘にも会ったけれど、彼女らは親子で話していてもいろいろな言語を使う。
2000年の夏、彼女は、ガロッタが作品を創っていたグルノーブル(ガロッタのダンサーと一緒に朝のクラスをほかのダンサーも受けられる)、マルセイユの先にあるイストル(Istres、実際の発音では「ル」はほとんど聞こえない)という海辺の町、フランス中部の山の中のオベナ(Aubenas)という小さな町で教えていて、私はどれにも参加した。このうちイストルとオベナではテクニックのクラスのほかに創作のクラスもあった。オベナの最終日はお城のような村役場の建物のあちこちの部屋に参加者が散らばってワークショップで創ったダンスを披露した。観客はそれを美術館を巡るように見て回った。
創作ワークショップでは集団即興もよくやった。皆が何をやっているか見ながら自分はどうそこに関わるかを決め、何かをやる。そのとき参加者のうち一人が「伴奏者」になった。何かを喋り続けて、それを「伴奏」として聴いて踊る。よく日本語やギリシア語など、他の大半の参加者が理解できない言葉を話す人が「伴奏者」になった。
各クラスの終わりごろには汗をかいた体を静めることをよくやる。たいていはヨガのポーズのひとつでもある、正座して上体を前に伏せる姿勢になるけれど、そうして皆が静まり返ったとき、たいてい彼女はハミングを始めた。すると皆もハミングを始める。声の柔らかなクラスターが部屋いっぱいに広がってゆく。他人の声を聴きながら、それに対して自分の声の音高を変えて何かハーモニーを創ろうとする参加者もたくさんいる。歌う人もいる。今度はそれを「伴奏」にして、皆そろそろと踊り出す。数分間、皆が動き出してちょっと目が覚めたようになったら、Hasta mañana—明日またお会いしましょう。
このように、伴奏のためにCDやピアノ演奏も使わないことで、ダンスクラスの間に音楽的な瞬間を体験することができる。マース・カニングハム以降のコンテンポラリーダンスではよくあることだけれど、ダンサーはよくアンビエント・ノイズや無音の中で自分の体でリズムを刻むことを要求される。伴奏音楽のリズムを自分の運動の推進力として使えないような作品が多い。そこではあなたの運動がリズムであり、メロディだ。
"Be there!" "Into space!"
ミリヤムのシークエンスは複雑なものはあまりなかった。ただ緩急の変化があった。立ち尽くしたと思えばパッと次のポジションに進む。そんなとき、彼女がよく英語で言ったのは「Be there!」そして「Into space!」。そこにいるときはそこにしっかりといなければならない。そしてある場所から次の場所に移動するときは、自分の体を次の空間に運ぶということをしっかり意識すること。ステップするというより、あなたの存在それごとその空間に持っていく。私は「あなたはときどきそこに居なくなるね」と、よく注意された。パフォーマーとして人前で何かをするのに必要なものが欠けていた。もともと十代後半ぐらいから極度のあがり症になってしまっていたこともある。
それでもダンスや演技なども学んでいた理由のその一つとは、もともとは作曲を学んでいたころ、シアターピースに興味があったということがある。といっても伝統的なオペラを書く気はなくて、何かよくわからないけれど、身体を使ったもの、もしかしたら映像や言葉も使うもの、というように、漠然と、何かできないかな、と考えていた。結局何者にもなれなかったけれど、実際に劇場で舞台に立つ機会もあった。
同世代の作曲科の学生で、実際に自分で踊ったりする人たちもいた。普通の「現代音楽」を書いて、その作品の中に演劇的要素、パフォーマンス・アート的要素を取り込む人たちもいた。そんな人たちを横目で見ながら、「これは演出や演技をちょっと勉強した方がいいかな?」と考えるようになっていた。
今思うに、当時は「あれとこれを足したらこうなります」みたいなのにちょっと疑問を感じていたのだろうと思う。結局は「どういうテーマでどんなことができるのか?」という問題にたどり着く。それまで学んでいた作曲の技術を使えるかどうかは二の次になった。
実際パフォーマンス・アートの側から見れば、「良い音楽」なんて必要のないことが多い。たとえば、「名曲」が使われる多くの場合では一種の引用のようなやり方で、観客がその曲を知っている可能性が高いということが、その曲が有用かどうかということを決める。映画で言えば、タランティーノがそうだ。劇場のパフォーマンス・アートの分野では、フランスの振付家ジェローム・ベル( Jérôme Bel, 1964-)がよくやる。
私が昔参加したプロジェクトでは、作品の途中でF.R. Davidの『Words (don't come easy)』という80年代のダサいヒット曲の一節;
Words don't come easy to me/How can I find a way to make you feel I love you/Words don't come easy
をパフォーマーたちが観客たちが諦めて皆出て行ってしまうまで繰り返し歌い続ける、というのがあった。音はあくまで演出の一要素であって、全てはテーマに奉仕する。そのテーマというのがまた、考えるといろいろ難しいのだけれど、それについてはまたの機会に書く。
ダンスや演技、特にダンスを学ぶことにしたもう一つの理由はセラピー的(therapeutic)なものだ。全身を動かすと気持ちいい。それだけならスポーツでもいいのだけれど、ダンスや演技には表現やコミュニケーションが含まれている。それに体ごと飛び込んでみることにした。Into Space!
モダンダンス史について少し
イサドラ・ダンカン
これを書くためにジェローム・ベルの動画を探していたら、彼の最新作のトレーラーが上がっていた。なんと、最新作はイサドラ・ダンカン(Isadora Duncan, 1877-1927)についてのものらしい(ベルは最近気候変動を考慮して飛行機に乗ることをやめてしまったらしいから、たぶん日本に—かつてはときどき来日していたが—この作品が来ることはないだろう)。
トレーラーだけではどういう作品なのか本当にはわからないけれど、舞台下手で一人がダンカンについてレクチャーし、そのダンスが実際どんなものだったか、実際に長年ダンカンを研究してきたダンサー、エリザベス・シュヴァルツ(Elisabeth Schwartz)が踊ってみせる、おそらくそれを繰り返しながら作品が進んでいくのだろう。ちなみにトレーラーで踊られているダンスは下の70年代に撮られた映像を参考にしたものと思われる。
ダンカン本人の映像として残っているものは下の通り。踊り終えて客に挨拶する様子しか残っていない。
イサドラ・ダンカンはモダンダンスのパイオニアの一人とされている。カリフォルニアで生まれ育ち、22歳のときにヨーロッパに渡り、パリを中心に活動していた。一般的に彼女のダンスについての説明はだいたいこんな感じになる—「バレエの伝統と袂を分かち(そもそもバレエはほとんど学ばなかった)、フォークダンスやソーシャルダンスの要素も取り入れながら、スキップ、ジャンプ、ランニングなどの自然な動きを使った。ハイアートとしての(エンターテインメントでない)、精神、感情を表現するダンスを目指し、動きと感情を結びつけることに努力した。即興的、自然発生的である一方、フォームをギリシアの彫刻や絵に求めた。また、ダンスを通じて女性の教育に努めた。」
イサドラ・ダンカンについては、その名を知る人々にとってはロマンティックな印象が付いてまわる。彼女の芸術がある「解放」を目指していたこと(コルセットを脱ぎなさい、靴を脱ぎなさい)。多くの芸術家のミューズであったこと。恋愛遍歴。事故で子供を失ったこと。また自らもショッキングな事故死を遂げたこと。
彼女のスタイルを今に伝えることを目的にしたダンスの映像はYouTubeにもたくさん上がっている。古代ギリシアに想を得たチュニックという衣装。音楽はクラシカルの小品を使うことが多いこと。今の視点から見ると、なんだか古いなという身振り。見る人によっては失笑するかもしれない。また、彼女について解説しようとする動画も多い。その多くは彼女に対するロマンティックな憧憬を秘めている。
「身体の解放」という諸刃の剣
近現代において、「身体の解放」というひとつのプロジェクトがあったとすれば、そのプロジェクトの源泉の一つとして、19世紀ロマン派の自然礼賛という別のプロジェクトがあった。また、キリスト教は身体を抑圧してきたから、そういった宗教に囚われず、自由に考えようとするプロジェクトも19世紀には広がっていた。
近代オリンピックは1896年に始まった。国民国家を創設することの当初の目的のひとつは国民を兵隊にすることであったから、健康な国民を育てることも国家にとって重要な課題だった。
「身体の解放」は諸刃の剣だったと言える。ナチスは自然、身体、ギリシア礼賛の思想を吸収していた。ヒトラーはワンダーフォーゲルの隊長のような人だった。その隊員は親衛隊になった。モダンダンスのパイオニアの幾人かはナチスと微妙な関係だった。たとえば、ダンス理論家で振付家のルドルフ・フォン・ラバン(Rudolf von Laban, 1879-1958)はゲッペルスの下で働く契約をしていた。1936年のベルリンオリンピックの開会式のための群舞を委嘱されて制作したが、ゲッペルスはその作品を気に入らなかった(ゲッペルスの日記には「あまりに知的過ぎる」と書きつけられてあるらしい)。ラバンはお役御免になってドイツを去った。ラバンがこの時どのような気持ちで去ったかは諸説ある。私が持っているヘルムート・プルブスト(というカナ表記でよいのかわからない。Helmut Ploebstという、ヨーロッパのコンテンポラリーダンスのサークルではよく知られたライター)の『no wind no word』という、2001年に出版された、当時のヨーロッパのコンテンポラリーダンスの代表的な振付家(ただしあまりにも大御所的な人たちは除く)を紹介し、またダンスの歴史についても説明している本(ヨーロッパのいくつかの劇場で購入できた)では、ラバンはしぶしぶ去ったことになっている。

ラバンを擁護する人はそもそもラバンはナチスの思想に反対していたのだと言う。ラバン、そして後で述べるマリー・ヴィグマン(Mary Wigman, 1886-1973)の、直接の弟子だった邦正美(1908-2007)は、ラバンはパルッカ(Gret Palucca, 1902-93)というユダヤ人の血を引いた人をソリストとして使ったからクビになったと言っていた。ラバンはその後イギリスに移ってダンスを教え、死ぬまでイギリスにいた。彼の仕事を引き継いだ学校、ラバンセンターは2005年に音楽学校と合併している。
ナチスと当時ドイツにいた芸術家たち、その戦後の評判についてはいろいろ検証が難しい(日本でも有名な名前を出せば、フルトヴェングラーとカラヤン、どちらが悪かったか?)。2003年、フランクフルトのゲーテ大学でパフォーマンスアートなどを学ぶ学生や教授と話す機会があったのだけれど、ドイツ表現主義ダンスの研究はあまりやっていないと聞いた。
ゲッベルスがラバンを雇った理由は分かる気がする。群舞の振り付けのスペシャリストだったからだ。「動きの合唱」である。パリで建築を学んだ彼は、空間を身体で構成することに興味があった。
ダルクローズと「動きの合唱」
ラバン以前に、音楽教育の分野から「動きの合唱」を考えたのが、エミール・ジャック‐ダルクローズ(Émile Jaques-Dalcroze, 1865-1950)で、今でも幼児教育でよく使われる「リトミック(eurhythmics)」の創始者だ。もともと和声とソルフェージュの教師で、もっと若い時にはガブリエル・フォーレ(Gabriel Fauré, 1845-1924)やアントン・ブルックナー(Anton Bruckner, 1824-96)に作曲を学んでいたこともある。
もともとはテンポ感の悪い学生に、試しにテンポに合わせて歩いてごらん、と言ったら、テンポを保って歩くことはすぐできた、その観察から、楽器を手にする前に歩くなどの日常的な動作でリズムを学ぶことができるのではないか、と考えたことが始まりだったらしい。これは楽器を学んでいる人は知っていると思う。実際にあるメロディを楽器で鳴らす前に、そのリズムを手拍子で打つと効果的だったりする。
和声の理論書通りに宿題を書いてくる学生が、実際には音を聴き取っていない。聴いて感じることと読むことと書くこと、どう繋げるか?音高は身体の動きとは直接結びつかないとしても、リズムやダイナミクスはすぐに結びつけることができる。音のエネルギーの動きを動きで表現することはできる。ゆるやかに動いたり、素早く動いたり、大きく動いたり、小さく動いたり。
たとえば、譜面を読んでそのダイナミクスやアクセントを(指揮者のように)身振りで表してみる。それは心の中に鳴らされるべき音を思い浮かべてみる助けになるだろう。でも、それができるようになるためには、逆に、音楽を聴いてそれに反応するように即興的に動いてみることも役に立つだろう。
動作を使うことは単に教育の場だけにとどまらなかった。ダルクローズは「動きの合唱」作品を1912年のオリンピックで披露している。彼自身作品を創ることには興味があったし、音楽の概念をちょっと拡張するような(ほかの人たちは、色彩を音楽にするとか、香りを音楽にするとか、やっている)ことを結果的にはしている。客観的にはダンスだけど。
彼のもとにはモダンダンスのパイオニアたちが通っていた。ラバン、ヴィグマン、クルト・ヨース(Kurt Jooss, 1901-79。『緑のテーブル』が有名だけど、最近日本ではスターダンサーズバレエがやっている)などなど。また、スタニスラフスキー(Konstantin Stanislavski, 1863-1938)の俳優訓練法にも影響を与えたようだ。
さて、前回までの投稿で触れたフリッツ・ラングが、ダルクローズやラバンをどれだけ知っていたのかは知らない。『メトロポリス』の機械のような労働者たちの動きなど、群舞である。『M』の市井の人々の動き、『マブゼ博士』の車の動き、どれも空間構成が非常に計算されているし、リズムもある。ナチスは『メトロポリス』を好んでいた。『マブゼ博士』は上映禁止にしたけれど。ラングに依れば、ゲッベルスが直々に彼を呼びつけたそうだ—『マブゼ博士』は申し訳ないが、上映禁止にした。しかし我々はあなたの映画作家としての手腕を非常に買っているのでUFA(第一次大戦のころからほぼドイツでの映画事業を独占してきた映画制作会社。ドイツでは映画は以前から国によって管理されてきていた)のヘッドとして迎えたい—そのミーティングのあとすぐに、ラングは妻の指輪を売って後は着の身着のままで単身ドイツを出国した(妻は脚本を担当して二人で作品を創ってきたが、彼女の方はナチス支持だった)。1933年、ナチスが政権に就いた年だ。ラングのパスポートの記録だとこの年彼は何度か出入国を繰り返しているので、話をどこまで信用していいのかはわからない。彼がこの年結局出国してパリに一度滞在したのは事実だ(その翌年からラバンがゲッベルスの下で働くことになる。ドイツ中のダンスフェスティバルを監督する仕事だ)。
ダンサーと観客の間の炎(マリー・ヴィグマン)
『Mary Wigman, When The Fire Dances Between The Two Poles』と題されたマリー・ヴィグマンのダンスやインタビューの映像にヴィグマン自身の著作からの言葉が英語に訳されてボイスオーバーされている40分ほどのドキュメンタリービデオがある。アレグラ・フュラー・スナイダー(Allegra Fuller Snyder)という人によって構成、編集されたらしい。1990年にVHSとして出版されていたようだが、今では出版元のDANCE HORIZONSが自らインターネット・アーカイヴに上げているようだ。YouTubeでも見られる。
ヴィグマンはラバンのアシスタントをしていた。4分55秒目辺りからラバンの生徒たちの小人数の群舞(またはその復元か)の映像を、ごく短い時間だけど、垣間見ることができる。次回の投稿はいつになるかわからないけれど、このヴィグマンのヴィデオの話から始めてみたいと思う。また、「テーマ」ということについても考えてみたい。
