
はなのいろはで始まる和歌で知られる歌人といえば
勧修寺に広がる風景を楽しんだ後は
また自転車にまたがって、山科の寺院をたどる。次は、
はなのいろはから始まる和歌で知られる歌人ゆかりの
寺院へと。時は移り、時代は変わり、形あるものは、姿を
変え、美しきものもいたづらに。限られた時の中で目
の前のものにしっかりとふれて感じる旅を楽しもう。

























はなのいろは うつりにけりな いたづらに
わがみよにふる ながめせしまに




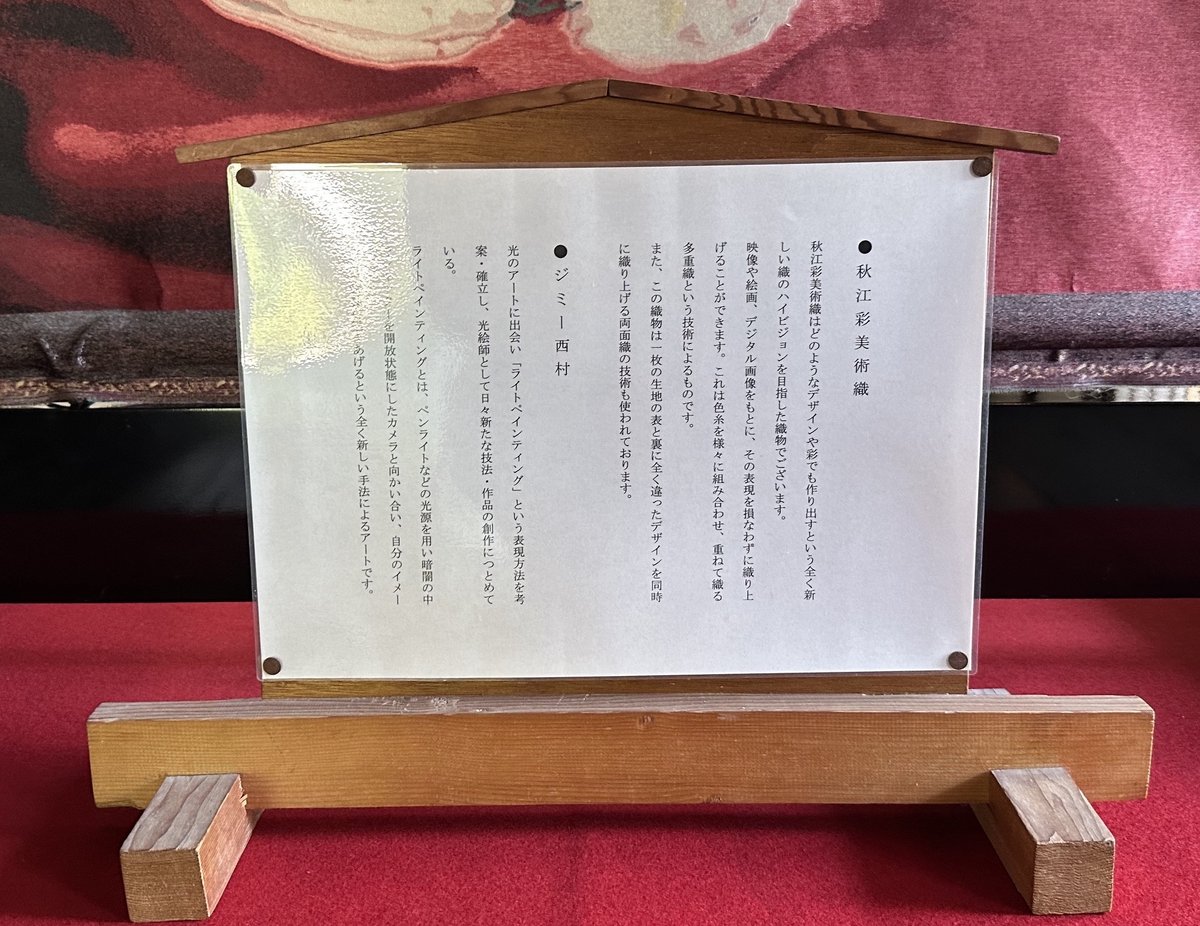



















動画で仏像の様子も楽しんで






隨心院は小野小町ゆかりのお寺

動画でも寺院の様子を楽しんで
991年に仁海僧正によって創建された随心院。ここも
真言宗十八本山の一つで、代々、摂関家が住職を務めた
門跡寺院。その随心院が建つ小野は、かつて小野郷と
いい、遣隋使の小野妹子を排出した小野一族が栄えた
場所だという。その小野一族の中で、広く知られている
小野小町。随心院は小野小町のゆかりの寺院でもあり、
この地は小野小町が余生を過ごした地とされている。
随心院に広がる風景を楽しんで、また次の寺院へ進む。
