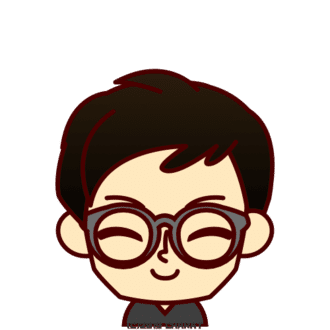個人向け国債の販売手数料原資を有効に使うには?
個人向け国債は、通常の国債と異なり元本割れすることがなく、利率も定期預金と比べて高めなど、個人にはメリットがある金融商品です。
この個人向け国債の販売が減速しています。証券各社が「現金還元」の販売促進キャンペーンを相次ぎ中止していることが理由のようです。個人向け国債は1年経つと換金が可能です。この「現金還元」の恩恵を受け、1年後には別の金融機関のキャンペーンに乗り換える「渡り鳥」の存在を記事では指摘しています。
この現金還元の原資は、財務省からの販売委託手数料です。この手数料は100円につき40銭。つまり0.4%です。最近の個人向け国債の金利が0.05%なので、この手数料を加えると、実質の金利は「0.45%」にのぼります。この状況の打開に向けて、手数料制度の変更を財務省が決めています。詳細は記事をご覧ください。
この記事を読んで思ったのは、この販売委託手数料を原資とするキャンペーンの存在自体に違和感があること。販売促進が目的であれば、個人向け国債を買う「個人」と、国債を通してお金を借りる「国」の関係にもとづいた販売促進方法があってよいと思います。
もちろん、個人向け国債自体にある「利子」の恩恵はあります。ただ、お金の貸し借りの対象が「個人」と「国」である以上、販売委託手数料の原資を有効に使うならば、それは、この2者間の関係で考える必要があると思います。
例えば、個人向け国債残高が1,000万円ある場合、その残高までは金融譲渡所得における税率が、この販売委託手数料の原資である0.4%まで減税されるなどの仕組みがあれば、この違和感はなくなります。もしくは、1,000万円の0.4%、つまり4万円がNISA投資枠に上乗せされるなどです。
そもそもこれぐらいの恩恵であれば、現金受取の方がよいかもしれませんが、その場合であっても、個人と国の関係に基づいたキャッシュバックの仕組みの方が違和感はなくなります。マイナンバーカードを利用したマイナポイント制度を応用してこのキャッシュバックも構築できそうな気がします。
いいなと思ったら応援しよう!