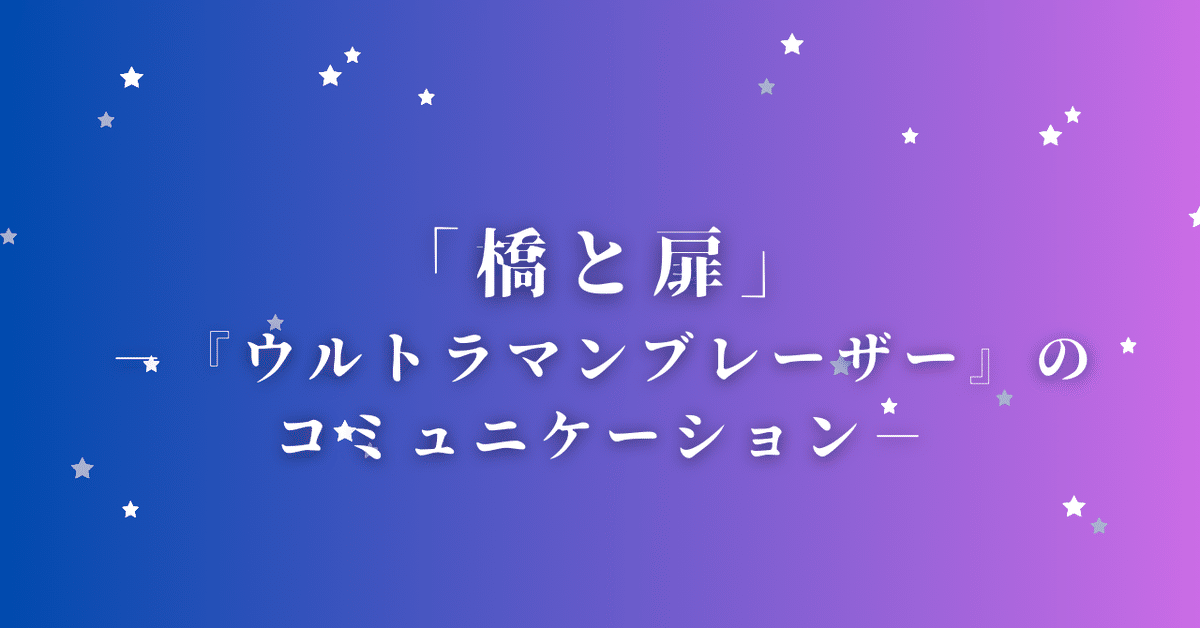
「橋と扉」ー『ウルトラマンブレーザー』のコミュニケーション
1.『ブレーザー』とコミュニケーション
『ウルトラマンブレーザー』第1話の衝撃を、私ははっきり思い出すことができる。全編にわたって続く防衛隊と怪獣の攻防、そして突如として現われ、大暴れするウルトラマンブレーザーの闘い。そのリアリズムと荒々しいエネルギーに、私は痺れ、すっかり虜になってしまった。
一方で、続く第2話からは隊員同士の細やかな人間関係が描写され、その丁寧さも『ブレーザー』の魅力だった。時に互いの距離を探り合い、時に本音を見せ合いながら、1つのチームとして成長していくSKaRDの面々が、ドラマとしての『ブレーザー』に深みを持たせていた。
そしてそれは、『ブレーザー』という作品のテーマの現れでもあった。『ブレーザー』でテーマとされたのは”コミュニケーション”であり、それだけに登場人物たちの関係性の構築が丁寧に描かれた。SKaRDの面々どうしだけでなく、ゲントとブレーザーや家族、SKaRDと上層部、そして人類と来訪者––––コミュニケーションの形も、結果もそれぞれ違った。しかしその根本には、私たちのコミュニケーションにも通じる、ある可能性が見えてくる。今回は『ブレーザー』という作品を、”コミュニケーション”という観点から振り返ってみたい。
2.仲間は秘密とともに
『ブレーザー』の登場人物たちの関係性のポイントを一言で言うなら、「秘密を抱えながらわかり合っていく」ことだろう。ブレーザーと一体化しているゲント、父の因縁やトラウマを抱えたエミ、機密を抱えた地球防衛隊上層部、そして出身地も目的も不明で、意思疎通もままならないブレーザー––––皆、他人には明かせぬ事情を抱えながら関わり合っていく。
普通、こういう登場人物たちの秘密というのは、それが明かされる瞬間にドラマの盛り上がりを生み出す。ウルトラシリーズでは定番の「正体バレ」は正にその典型例だ。しかし『ブレーザー』では、結局”バレ”なかった秘密も多い。
例えばゲントは、自身がブレーザーであることを最後の最後まで隠し通した(つまり『ブレーザー』は、定番だった「正体バレ」のない作品だったわけだ)。エミの過去も、ゲント以外のSKaRDの面々にはほとんど明かされていない。そもそもエミがV99という重大機密を追っていることも、ゲント以外のSKaRDの面々は終盤に至るまで知らなかった。
そしてブレーザーについては、依然そのほとんどが謎のままである。設定では出身地はM421とされているが、物語内では一切語られない(ゆえにおそらくゲントたちは知らない)。彼が地球に来た目的や理由、なぜゲントと一体化したのか––––そうした情報もまた、ほとんど語られることはなかった。
だが、それぞれが秘密を抱えていてなお、SKaRDも、ブレーザーも、互いを信じ合っている。エミが不在にしがちでも咎める者はおらず、第19話「光と炎」では、ハルノ参謀長に対して、SKaRDの面々は真っ向からブレーザーへの信頼を語り、第25話では傷つき倒れたブレーザーを、SKaRDは”仲間”として地球に連れて帰る。彼らは互いに秘密を抱えながら、それでも”仲間”として互いに信頼しあっている。
そして最終盤、V99の船団が姿を現わしたとき、SKaRDの面々は彼らとの対話を試み、そして彼らの追撃を止めることができた。攻撃しようとするドバシら防衛隊をエミが制し、成り行きを聞いていたSKaRDの面々はアースガロンにV99との交信を頼む。断片的な交信が続き、ギリギリのところでエミの発した「未来」というメッセージがV99に届いたことで、彼らは去っていった。
V99もまた、依然謎多き存在だ。新天地を求めてワームホールで旅をしていること、最初に地球を訪れた際は無防備だったが、以降は宇宙怪獣を次々送り込んできたこと。その理由は「恐怖」であること––––それ以外はほとんど言及されぬまま、物語は幕を閉じた。
ゲントやSKaRD、ブレーザー、V99––––彼らは互いに、全てを見せ合っているわけではない。特にブレーザーやV99は、コミュニケーションそのものがかなり断片的なものしか成り立たなかった。つまり彼らは、互いに互いの断片しか見ることができていない。しかし、それでも彼らは互いにわかりあうことができた。ここにこそ、『ブレーザー』のコミュニケーションの重要なポイントがあるのだ。
3.断片しか見えなくても
そもそも、私たちは仲間や友人、家族といった親密な間柄では、包み隠さぬ”本音”を話すことを良しとしている。それ以外の関係性では言えないからこそ、”本音”で話せる関係性を、私たちは仲間や友人、家族といったものに求めている。そして相手も”本音”で話すことも、同時に求めている。包み隠さず、全てを打ち明けられる存在として––––そして相手にも、全てを打ち明けてもらえる存在として––––私たちは親密な間柄の人と接しているはずだ。
反対に、そこに”秘密”があるとき、親密な間柄には疎外感が生まれる。たとえ理性で、それが踏み込むべきでないことだとわかっていても、私たちは感情ではそこに寂しさを感じ、場合によっては不信感すら覚えるはずだ。それだけ、私たちは親密な間柄に”秘密”のない関係を求めているということだ。”秘密”とは、言わば他人との距離の証なのであり、時として信頼を崩しうるものだ。
だがそもそも、私たちはどんなに親しい間柄でも、相手の全てを知ることはできない。私たちは、他人の内面について、自分から見えるその人の断片からその人の内面を想像している。哲学者・社会学者のゲオルグ・ジンメルは、次のように述べている。
人びとはけっして他者を絶対的に知る––––そのことが、それぞれの個々の思考や気分についての意識を意味するとなれば––––ことはできないが、しかし、他者が彼の断片においてのみわれわれにとって近づきうるものとなるからには、人びとはそれでもこの彼の断片から、ある人格的な統一体を形成する。したがってこの統一体は、彼にたいするわれわれの立場が見ることを許した彼の部分に依拠している
ジンメルが言うように、私たちは他人の断片にしか接することはできない。相手の思っていること、考えていることの全てを知ることはできない。しかも、私たちが接することができる他人の断片とは、その人が私たちに見せていいと判断した、その人の一面にすぎないのだ。そして私たちは、その一面に基づいて、相手の総合的な”人物像”や”人となり”を、私たちの中で作り上げる。
そしてこれは、どんな関係性だろうと、どんな間柄だとしても同じことだ。どんなに親しい相手にも、私たちは全てをさらけ出しているわけではないし、全てを伝えることもできない。そこにはどうしても”距離”が生まれる。全てをさらけ出して、”秘密”のない関係性を望んだとして、それは叶わない。なぜならそもそも、人間は他者を絶対的に知ることができないからだ。他人の心の内は、誰にもわからない。
先に書いたように、『ブレーザー』ではゲントもエミも、ブレーザーも、仲間や家族に秘密を隠している。ゲントも周囲にブレーザーという一面を見せず、エミも自分の過去をほとんど他人に明かさない。ブレーザーもところどころでしか自分の感情を表すことはない。また最終盤で登場したV99も、その意思を表明する場面はほとんどなかった。彼らは”秘密”を抱え続けているわけだ。
しかしそれでも、ゲントたちSKaRDは互いに信頼しあい、ゲントも他のSKaRDの面々もブレーザーに信頼を寄せている。V99も、断片的なコミュニケーションしか取れなかったが、それでも地球人を信頼し、撤退した。
この”信頼”こそ、『ブレーザー』を読み解くうえでのキーワードだ。ジンメルは、先に引いた文章の続きで、こうも述べている。
信頼は、十分に実際の行動の基礎となりうるほどに確実な将来の行動の仮説として、まさに仮説として人間についての知識と無知のあいだの中間状態なのである。完全に知っている者は信頼する必要はないであろうし、完全に知らない者は合理的にはけっして信頼することができないのである
ジンメルの言うように、完全に知っている––––相手の内面の何もかもまで知っている者を、わざわざ”信頼”する必要はないであろう。ジンメルによれば、信頼とは他人の行動についてのほぼ確実な”仮説”である。相手を”完全に知ってい”れば、相手がどう考え、どう行動するかまで全てわかっているのだから、”仮説”に頼る必要はない。反対に、何もかもがわからない相手に対しては”仮説”の立てようがないから、信頼などできない。
先に引いた部分でジンメル自身が述べているように、私たちは相手の全てを知ることはできない。だから、私たちは”仮説”に頼るほかない––––相手を”信頼”するしかないのだ。言い換えれば、相手の全ては知ることができないからこそ、私たちは”信頼”することができる。
『ブレーザー』で示された”信頼”の形は、まさにこの”仮説”に他ならない。例えばゲントとブレーザーの”信頼”が問われた第10話「親と子」~第12話「いくぞブレーザー!」は、”仮説”が崩れ、そしてそれを建て直す物語だった。
第10話「親と子」では、幼体のデマーガ・ベビーデマーガと、それを助けようとした親のデマーガが出現する。防衛隊は2匹の撃滅のために出動し、ゲントもブレーザーに変身して交戦。そしてブレーザーがとどめのスパイラルバレードを放とうとした瞬間、ブレーザーのもう一方の手がそれを食い止めた。その後ブレーザーは、まるで2つの意思が争うかのように悶絶した後、防衛隊のミサイルを撃破、デマーガ親子を再び眠りに就かせる。
続く第11話「エスケープ」では、スパイラルバレードも効かない宇宙電磁怪獣・ゲバルガの猛攻の前に、再びブレーザーの中のもう一つの意思が現われ、そのまま戦線を離脱してしまう。そして第12話「いくぞブレーザー!」では、ゲントは自分の意思に反してデマーガ親子を助け、ゲバルガの前から逃亡したブレーザーの意思に不信感を抱き、ブレーザーストーンを基地に置いて出動する。
しかし、ゲントが危機に陥ったとき、ブレーザーは自身の記憶を見せてゲントに語りかける。自分は常に命を救おうとしてきたこと、そしてゲントにも同じ想いを感じていること。それを知ったゲントは「俺と同じじゃないか」と、再びブレーザーと共に戦う決意を固める。
何度も言うように、ブレーザーは言葉を話さない。しかも自分の意思を示すことがほとんどない。だからゲントは、突如として自分に力を貸すようになったブレーザーを、その行動”だけ”に基づいていざというときに怪獣と戦ってくれる存在として信頼していた。つまり彼は、”怪獣と戦う存在”としての、ブレーザーの断片しか見ていなかったのだ。だからこそ、何もわからないままデマーガ親子を助け、ゲバルガから逃亡したブレーザーを、ゲントは信じられなくなった。それまでの自分の信頼と反する行動をブレーザーが取った––––それまでにゲントが作り上げた、ブレーザーの”人物像”と反するような”断片”を彼が見せてきたのだから、当然のことだ。
”怪獣と戦う存在”という断片と、”怪獣を守る”あるいは”怪獣から逃げる”という断片––––相反するようなその2つの面を繋ぎ合わせる答えを、ブレーザーは示した。それこそ”命を守る”という、彼の根幹となる(であろう)意志である。それを知ったゲントは、「俺と同じじゃないか」とブレーザーへの信頼を取り戻す。
そしてV99と人類が築いた信頼も、”断片”に基づいた”仮説”である。アンリの発案でV99の船団と交信したアーくんは、彼らの言葉を翻訳して、こう伝えた。
断片的ですね……「仲間」「武器」「光の星」「新天地」「旅」「青い星」「危険」「恐怖」「恐怖」「恐怖」「恐怖」……
彼らが伝えてきた言葉は断片的で、そこから読み取れる情報は少ない。しかしエミが突き止めた情報と合わせ、ある程度の事情が推察された。彼らは新天地を求め、何も武装せずに旅をしていた。しかしドバシの命で防衛隊はその宇宙船を撃墜。彼らは危険な星への恐怖から、バザンガ・ゲバルガ・ヴァラロンといった怪獣を送り込み、そしてついに自ら船団でやってきたのだ。
船団でやってきた目的が攻撃なのか否か、それすらも明言されていない。しかし彼らが繰り返す”断片”––––「恐怖」には、地球人への強い恐れが示されている。
エミたちはV99に「私たちは戦いを望んでいない」と繰り返し、全世界の防衛隊も説得して警戒態勢を解かせる。それでも迫りくるV99に、エミはこの”断片”を伝える––––「未来」と。それを聞いたV99の船団は、ワームホールを通って去って行く。
結局、彼らが直接地球にやってきた目的も、そして去って行った理由も語られてはいない。そもそもコミュニケーションも断片的なやり取りしかできていない。しかもV99の船団は去っても、ヴァラロンは残されたままだった。しかしそれでも、V99と地球人の間には信頼が生まれたはずだ。それが”仮説”と呼ぶにふさわしい、微かなものだったとしても。そしてそれは、”断片”しか見えなくても、互いを信じることができる可能性を、私たちに見せてくれている。
4.「橋と扉」ー僕らは 信じあえる
私たちは、自分の断片しか相手に見せることができず、また他人の断片しか見ることはできない。だから相手を”信頼”するしかないし、だからこそ”信頼”することができるとも言える。言い換えれば、人間どうし、他者との間には必ず”秘密”があり、それゆえに必ず”距離”がある。しかしその”距離”があるからこそ、人間はその距離を超えてつながろうとすることができる。
そもそも、なぜ人はつながろうとするのだろうか。ジンメルの最も有名なエッセイ「橋と扉」は、次のような書き出しで始まる。
外界の事物の形象は、私たちには両義性を帯びて見える。つまり自然界では、すべてのものがたがいに結合しているとも、また分離しているとも見なしうるということだ。……
しかし、自然と違って人間にだけは、結びつけたり切り離したりする能力が与えられている。しかも一方がつねに他方の前提をなしているという独特の方法で、私たちはそれを行う。自然の事物があるがままに存在しているなかから、私たちがある二つのものを取り出し、それらを「たがいに分離した」ものと見なすとしよう。じつはそのとき、すでに私たちは両者を意識のなかで結びつけ、両者のあいだいに介在しているものから両者をともに浮き立たせる、という操作を行っているのだ。
そして逆もまた真なり。私たちが結びついていると感じられるものは、まずは私たちが何らかの仕方でたがいに分離したものだけだ。事物は、一緒になるためにはまず離れ離れにならなければならない。そもそもかつて別れていなかったようなもの、いや、なんらかの意味でいまもなお分かたれた状態にないようなものを結びつけるなどということは、実際上も論理上も無意味だろう。
さて、人間が行動するさい、この二つの作用はいずれのパターンで出会うことになるか、つまり、結合と分離のいずれが自然な所与と感じられ、いずれが私たちに課せられた仕事と感じられるか、それによって私たちのあらゆる行動が分類される。直接的な意味でも象徴的な意味でも、また身体的な意味でも精神的な意味でも、私たちはどの瞬間をとっても、結合したものを分離するか、あるいは分離したものを結合する存在なのだ。
私たちは、人間どうしが“結びついている”ことを無意識に理想としている。だからこそ、他人との間の”距離”が、まるで”分離している”ように感じる。ジンメルの言うように、そもそも”結びついた”と感じられるものでなければ、”分離している”とは感じないからだ。反対に、そもそも”分離している”と感じられるものでなければ、私たちは”結びつける”ことはできない。私たちはそもそも人間どうしが”分離している”からこそ、人間どうしを”結びつける”ことを求めるのではないか。
私たち人間は、お互い結びつきながら分離している。だからこそ、私たちはそれを超えて離れていくことも、結びつくこともできる。そして人間の行為とは、そのどちらかに分類できる。コミュニケーションもまた同じだ。相手との距離を超えて結びつこうとするか、あるいは結びつかなければならない相手を引き離そうとするか––––そのどちらかだ。
この結合と分離の関係において、ジンメルは橋と扉にそれぞれ象徴的な意味を見出す。
川の両岸がたんに離れているだけではなく、「分離されている」と感じるのは私たちに特有のことだ。もし私たちが、私たちの目的思考や必要性や空想力のなかで両岸をあらかじめ結びつけていなかったとしたら、この分離概念はそもそも意味をもたないだろう。ところがここで自然の形態は、さながら積極的な意図をもっているように、この概念に立ち向かってくる。……
橋がひとつの審美的な価値を帯びるのは、分離したものをたんに現実の実用目的のために結合するばかりではなく、そうした結合を直接視覚化しているからだ。……
橋の「目的」は、たんなる運動力学のそのときどきの現実のなかに汲みつくされている。しかし、そのたんなる力学にすぎないものが視覚的=恒常的ななにものかになったのだ。
分離と結合の相関関係において、橋は結合にアクセントをおき、同時に、橋によって視覚化され、また測定できるようになった両岸の距離を克服しているとすれば、扉はより明確な形で、分離と結合が同じ行為の両側面にすぎないことを表現している。最初に道を作った人と同様に、最初に小屋を建てた人もまた、自然に対する独特に人間的な能力を発揮したと言える。すなわち彼は連続する無限の空間のなかから一区画を切りとり、この区画をひとつの意味にしたがって特殊な統一体へと構成したのだ。こうして、ひとつの空間部分が内的なまとまりを得ると同時に、他のすべての世界から切り離された。扉は、人間の空間とその外部にあるいっさいのもののあいだに、いわば関節をとりつけることによって、この内部と外部の分断を廃棄する。
扉はまさに開かれうるものでもあるがゆえに、それがいったん閉じられると、この空間のかなたにあるものすべてにたいして、たんなるのっぺりとした壁よりもいっそう強い遮断感を与える。壁は沈黙しているが、扉は語っている。人間が自分で自分に境界を設定しているということ、しかしあくまで、その境界をふたたび廃棄し、その外側に立つことができるという自由を確保しながらこれを行っているということ、これこそ人間の深層にとって本質的なことなのだ。
『ブレーザー』の世界において、人類とブレーザー、人類とV99とは、それまで見えていなかった”向こう岸”だ。偶然か運命か、人類はその存在すら知らなかった”向こう岸”と遭遇することとなった。そしてそれを繋いだワームホールとは、正に”橋”であり”扉”でもあった。ワームホールは、離れているとも感じられないほど遠くの星々をも結びつける。その意味で、ワームホールは”橋”である。だがワームホールという一点のみで繋がり、それによって初めて人類は”向こう岸”を知る。そこに私たちは、”橋”という繋がりだけでなく、異星との果てしない距離を見る。そしてそこに境界線を見出す––––ワームホールという”扉”が、それを超えて繋いでくれる可能性を残しながら。
しかし”扉”を開けた先でなお、”結びつく”ことが叶うとは限らない。V99がかつての旅で開けた”扉”の先で、彼らは防衛隊の先制攻撃に道を閉ざされてしまった。
一方でゲントとブレーザー、彼らは偶然出会って結びつき、怪獣と戦ってきた。しかし先に書いたデマーガ、ゲバルガとの戦いで、ゲントはブレーザーとの”距離”を感じ、彼を遠ざけた。
しかし二度目のゲバルガとの戦いで窮地に陥ったとき、ゲントはブレーザーとの出会いを思い出す。3年前に巻き込まれた爆発事故の際、逃げ遅れた人を探していたゲントは、突如発生したワームホールに躊躇なく飛び込む。逃げ遅れた人がそこにいるのではないかと直感しての行動だったが、そのとき彼が掴んだ手こそ、他ならぬブレーザーだった。
少なくともゲントにとっては、おそらく偶然彼の前にワームホールという”扉”が開いたのだろう。そして彼はその”扉”の向こうに、自身が守るべき生命を感じ取った。だから彼は躊躇わず手を伸ばし、その生命の––––ブレーザーの手を掴んだ。まるで2つの星の間に”橋”を架けるかのように。ウルトラマンシリーズで初めて、人間とウルトラマンとが手を取り合った瞬間だ。
無論、彼らが架けた”橋”とは、それきり簡単に保てるものではない。2人の関係性が揺らいだデマーガ、ゲバルガ戦や、生命の危機から2人が分離したヴァラロン戦など、彼らの繋がりが途切れそうになる瞬間はいくつもあった。しかしその度に彼らは相手に手を伸ばし、再び繋がってきた。そしてゲントが伸ばした腕には、その度に、その繋がりを証すかのように、ブレーザーブレスが現われている。
そしてそれはSKaRDも同じだ。V99の船団との争いを避けるべく、彼らは必死に呼びかけた。一度は人類が突き放し、ほとんどコミュニケーションが取れない相手だとしても、彼らは諦めなかった。断片的だとしてもコミュニケーションを試みることで、彼らはV99と心を通じ合わせることができた。もちろん、その繋がりは不安定だ。彼らの船団は撤退したが、ヴァラロンを引き下げることはしなかった。彼らの意図が描かれていない以上、ヴァラロンが暴れ続けたことに彼らの敵意を見ることもできる。だが反対に、彼らの船団が撤退したことに彼らの善意を見ることもできるはずだ。彼らと繋がる可能性は、まだ残されているはずだ。
『ブレーザー』の物語とは、”扉”が開き、”向こう岸”が見えた後の物語だったのだろう。ワームホールを越えてやってきた、コミュニケーションもほとんど取れない相手。人類とはかけ離れたような相手と、どう接していくか。ジンメルの言うように、”扉”とは人間が自ら設定する境界線であり、それを超えていく可能性を残すものでもある。エミの父は、何とかその”扉”を開こうと研究していた。彼は、”扉”を開いた先でV99との対話を望んでいた––––ワームホールを開く実験の事故で彼は命を落としてしまうのだが。
その”扉”を超えて、未知なるもの––––ブレーザーやV99が現われた。彼らとのコミュニケーションは断片的で、場合によっては通じ合えないことすらあり得る。しかしゲントとブレーザーのように、手を伸ばすことでその間に”橋”をかけることもできる。SKaRDが試みたように、”扉”を開いて繋がろうと試みることもできる。断片的にしか繋がれないからこそ、相手を信じることができるのだから。
そしてそれは、人間のコミュニケーションの本質でもある。そもそも私たちは、自分の断片しか相手に伝えることができない。だがそれでも私たちは繋がることができるし、断片的だからこそ、私たちは相手を信じることができる。相手と”離れている”ことを受け入れること、そしてそれゆえに見えてくる可能性に目を向けること。それこそが私たちのコミュニケーションを豊かにしてくれるはずだ。その可能性をこそ、『ウルトラマンブレーザー』は描いていたのだ。
