
「まんが おやさま」を読み直す 14/48 「立教」その3 神の歴史と人間の歴史






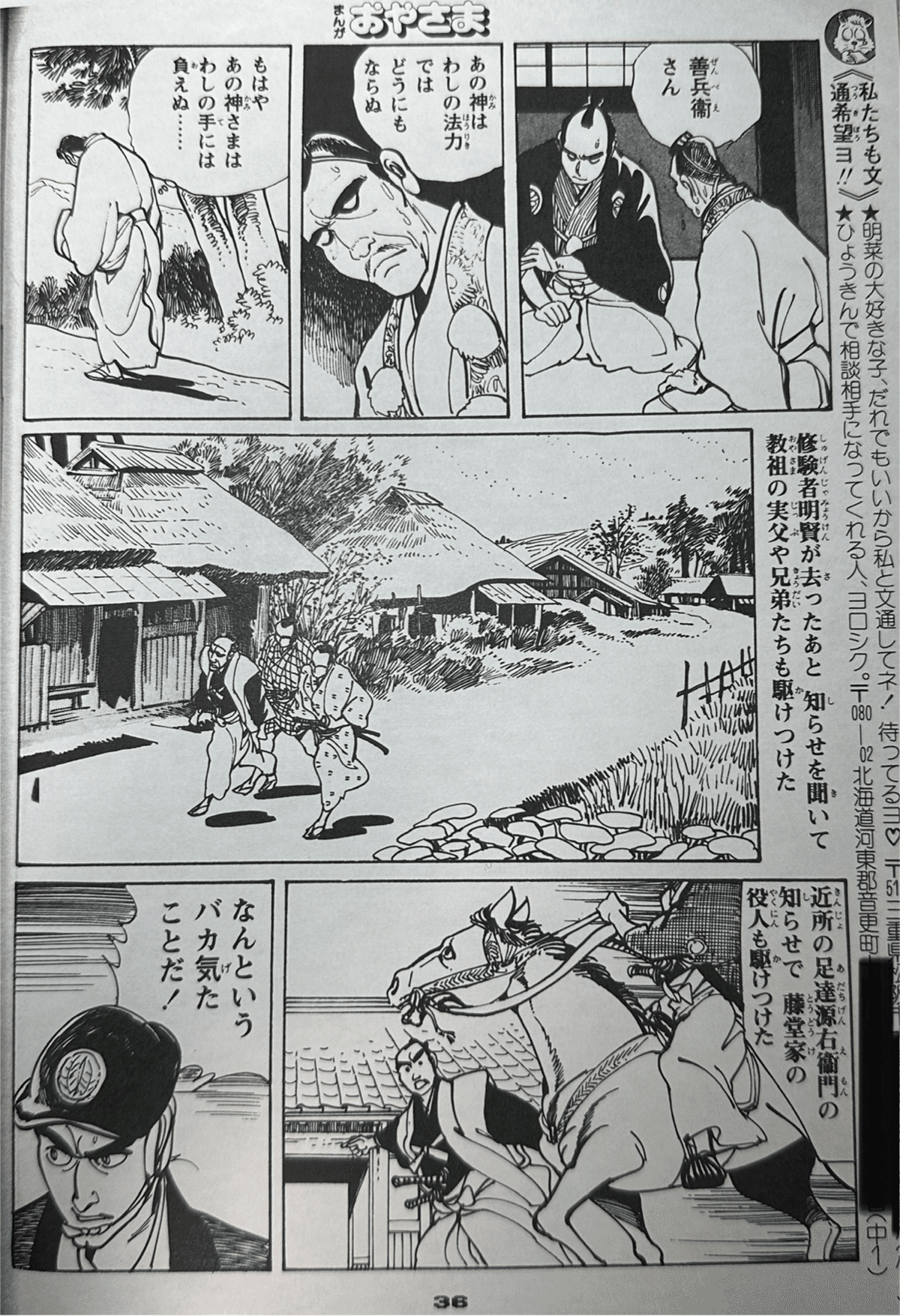

「われは元の神 実の神である」と、「顔のなくなったみきさん」が「神の言葉」を語り始めるシーン、子どもの頃に読んだ時は、とにかくひたすら怖かった。人間に「神」が入り込むと顔がなくなる、という絵画表現の手法は、誰が考えたのか知らないけれど、異様な説得力があると今でも感じる。1970年代から現在に至るまでずっと続いている「ガラスの仮面」という演劇マンガがあって、私はこれが大好きなのだけど、このマンガでは登場人物の演技やそれに向けた努力が神がかってくると「白目」になるという演出が繰り返し使われており、子どもの頃から私はそれに出くわすたびに、あ、また「おやさま化」してはる!と、一人で盛り上がったりしていたものだったのだが、そんなことはまあ、余談である。

あるいはそういった表現技法の歴史は、旧約聖書の時代にモーゼの前に姿をあらわしたという「神」が、「十戒」のひとつとして「偶像を作ってはならない」ということを人間に命じた、とされているようなところにまで、遡りうることなのかもしれない。キリスト教やイスラム教といった一神教の宗教が、それぞれ「偶像崇拝を禁止する」という教えを打ち出してきたことは、「生きた人間を崇拝の対象とすることを禁じた」という点において、人類史上、積極的な意味を持つことだったと私は思っている。この教えがあったからこそ、それが守られてきた地域においては、自らを「神」であると称する絶対権力者が民衆の生殺与奪をほしいままにするといったような事態は基本的に起こって来なかったのだし、また「すべての人間は神の前に平等である」という、差別を否定する思想の萌芽もそこから育まれてきたわけなのである。
一方で、この「偶像崇拝の禁止」という教えは、そうした宗教において「神」が持たされてきた神秘的権威というものを、絶対的に高める方向に作用してきたとも言いうると思う。人間という存在が自分を「人間」であると意識しはじめた原初の時代、「人間」という概念と「神」という概念との間にそれほどハッキリした区別はつけられていなかったはずだろうと私は思っているのだけれど、「偶像崇拝の禁止」をひとつの結節点として、「人間」と「神」との間には明確な「線」が引かれることになった。それまで人々にとって「身近なもの」として感じられてきたであろう「神」は、「わからないもの」「わかろうとすること自体が罪に値するぐらいにオソれ多いもの」であるとして、決定的な「畏怖」の対象となると同時に永続的な「恐怖」の対象とも、なることになったわけである。
「よく見届けよ!神殺しがいかなるものか!」という台詞が、宮崎駿監督の「もののけ姫」という映画が公開された際、テレビのCMでしきりと流れていたのを私はよく覚えているのだけれど、この映画に限らず、「神殺し」というキーワードをひとつの重要なテーマとしている神話や伝説は、世界中の様々な民族のあいだで普遍的にと言ってもいいくらい、広範に存在してきた。このことは、古代の人々にとっても「神」というものはやはり「おそるべき存在」ではあったのだろうが、同時にそれは「倒す」ことも可能な存在であり、そしてそれを「倒す」ことに成功した人間には「神」と同格の「力」が宿ることになる、という「信仰」と言うか「発想」が、存在していたということを示しているように思われる。そこに表現されているのは、人間という存在が「自然」という「他者」とどのように向き合ってきたかをめぐる歴史、あるいは、人間という存在が「母なる自然」からどのように「自立」を果たそうとしてきたかをめぐる歴史の物語であると、言って間違いにはならないだろうと思う。
人間が自分自身に対して関係するその関係の結び方は、人間が他者に対して関係するその関係の結び方と、相互規定的な関係にある。 「人間と人間」がどのように社会的な関係を結び合うかは、「人間と自然」がどのような関係を取り結ぶかに規定されて決まってくることなのであり、その逆も然りである。「人間と神との関係」に象徴されているイメージは、つまるところ「人間と自然との関係」のあり方に他ならない。そしてそこに示されているのは結局のところ、「人間と人間との関係」と同義のことでもあるのである。
人間と自然との関係が「倒し倒される戦いの関係」でしかありえなかった時代、人間と人間との関係もまた「倒し倒される戦いの関係」以外のものでは、ありえなかった。「自然の脅威」も「自然の恵み」も、太古にあっては人間にとって、もっと生々しく直接的な形で身の回りに存在していたものだったろうと思う。物陰から突然襲いかかってくる猛獣の姿も、迷い込んだ森の中に突然現れる果実をみのらせた樹木の姿も、太古の人々にとってはひとつひとつが「運命」であり「奇跡」であり、「神の顕現」と同じくらいの重さと深みをたたえた「事件」であったことだろう。けれどもそれにいちいち「感動」していられるような余裕もまた、太古の人々には存在していなかったはずである。猛獣は撃退できなければ自分が死ぬことになるのだし、果実はその場で収穫しなければ他の人間や動物に奪われるか、さもなくば腐ってしまう。「戦って、奪って、自分のものにする」という一連の過程が「生きる」ということの大部分を占めていた時代が、人間の歴史においては気が遠くなるほど長い期間にわたって存在していたのだということを、我々は自分たち自身がそれを繰り返すことをしないためにも、銘記しておかねばならないと思う。
人間が「自然の脅威」に立ち向かうには、「力を合わせる」こと、言い換えるなら「たすけあう」以外にないのだということを、当時から人々は、経験的には「知って」いたことだろうと思われる。けれどもその「力を合わせる」という行為は、これもまた人間の歴史の非常に長い期間にわたって、「最も強い力を持った人間の意思に従う」という形をとってしか、実現されてこなかった。人間が子どもをつくって自分たち自身を再生産するという営み自体、「男」と「女」が「たすけあう」ことからしか決して始まりはしないのだということは、中山みきという人の思想の原点に位置する重要な「発見」だったと私は思っているのだが、「同じ人間」であるはずの「女性」の存在それ自体が、「男性」にとっては「戦って、奪って、自分のものにする」対象に他ならなかった時代が余りに長く続いたため、その「あたりまえの事実」は彼女の時代に至るまで、「自覚」されることも「発見」されることもなく、「埋蔵」され続けている他になかったのだと言わねばならないだろう。
このように、「最も強い力を持った人間」が「神」と同格の存在として人々の上に君臨する一時期を人類史は経験してきたわけだが、人間というのはそもそも年をとるものであり、衰えて弱って死んで行くことを運命づけられている存在である。だから、と言っていいことなのだろうか、「神殺し」の神話や伝説と同じ発想にもとづいて、「王位」の交替は「王殺し」によってのみなされるという慣習が、大昔には相当広範に存在していたらしく、民俗学という学問の創始者と見なされることの多いイギリスのフレイザーという学者は、「金枝篇」という全13巻のその主著のほとんど全てを、「殺される王」という神話的モチーフはどこからどのようにして生まれてきたものなのかという問題の考察に充てているほどである。
「神」が人間をつくったのは「人間同士がたすけあって陽気に暮らすのを見て神も楽しみたいと思ったから」だと中山みきは説いたわけだが、それが本当ならどうして「神」は、こんなにも残酷な時代をこんなにも長きにわたって人間に味合わせるようなことを、したのだろう。このことは、誰の心にも浮かぶ疑問であると思う。そもそも、動物であれ植物であれ、生き物が命をつなぐためには他の生き物の命を奪うしかないようにつくられているその「仕組み」自体、どうなのだろう。もっと他の「つくり方」とかは、なかったものなのだろうか。
けれども、中山みきに言わせるならば、「神」だってその気が遠くなるほどの長いあいだ、ただ人間が殺し合うのを手をこまねいて眺めていたわけではなく、何とかその人間たちを「たすけあわせる」ために「努力」し続けていたのだ、ということになるのだろう。「ない人間」「ない世界」を泥海の中から「はじめかけた」その時から、「世界いちれつたすけたい」という「神」の思いは、変わらないのだという。しかしながら「神」が思った通りになかなか世界が運ばないのは、中山みきという人の教えの中に言葉として明記されているわけではないけれど、「神」が人間を「自由な存在」として形づくったからなのである。そしてその「自由な存在」である人間たちが、他から強制されるのでなく「自由な意思にもとづいて」たすけあう姿が生まれなければ、「神」だって「楽しめない」わけなのである。そのことに人間たちが「自分の力で」気づくことができるようにするために、「神」は何度となく失敗と挫折を繰り返し、そのたびに涙を流しながら、「努力」を重ねてきた。中山みきという人が説いた「神」とは、そんな風に「失敗」を「失敗」と認めて「自己批判」できる回路を持ち合わせている「神」なのであり、かつその「神」の「願い」は、「人間の協力」なしには決して実現できないものとして把握されているわけなのである。
そしてこの考え方には、確かに「救い」があると思う。「宗教」であれ「科学」であれ、弱肉強食の競争原理に「合理的な説明」を与えてみせるような立場からは、それに乗っかって他者の命を奪うことを正当化するような言説しか、決して生まれてこない。けれどもそれは「拒否していいこと」なのだということを、中山みきという人は「神」の名のもとに、宣言している。それが本当に「神の意思」なのか、そもそも「神」というのは本当に「ある」ものなのか、たぶん私に「わかる」ことは死ぬまでないかもしれない。けれどもそこには間違いなく「希望」があるし、そこにしか「希望」はないように、私には思われる。
ヨーロッパ世界における「信仰」のあり方は、多神教から一神教へという形で「発展」を遂げてきた。このことを「進化の法則」みたいな形で捉えることは間違いだと思うし、同じような「発展」のありようを世界の他の場所にまで当てはめたり押しつけたりすることが、正しいことだとは全く思わない。けれどもこうした「変化」が、「万人の万人に対する闘争」の時代から「群雄割拠」の時代を経て、一人の権力者の意思に全体が服従することを強いられる時代へと「発展」を遂げてきた人間社会のありように対応して起こった「変化」であるということは、見ておかねばならないことだと言えるだろう。人間が神に成り代わろうとすることが「畏れ多いこと」だと見なされるようになったのは、人間が人間社会の中に自ら作りあげた権力者の意思に逆らうことが「畏れ多いこと」だと見なされるようになったことの結果に他ならないわけであり、少なくともその逆ではありえないように思う。
一方で、「多神教から一神教へ」というこの信仰形態の変化に反映されているのは、人間の「共同体」から「個人」が産出され、その概念が成長を遂げてきた歴史の歩みであるとも言いうるかもしれない。「神」というものが人間にとって「鏡」のような存在であり続けている以上、その人間が自らのことを「集団あっての存在」であると感じている限りにおいては、「神」というものもまた「集団」的な存在として想定されることになることだろうが、ひとりひとりの人間が自らのことを「唯一のかけがえのない存在」であると感じ始めたなら、「神」というものも必然的に「唯一のかけがえのない存在」として意識されるようになる。そして「自分のかけがえのなさ」を「わかる」ことができなければ、「他人のかけがえのなさ」というものも、「わかる」ことのできる回路は永遠に開けてこないはずなのである。
天理教という宗教は一神教なのか多神教なのかという「古くて新しい議論」が存在しており、このことについてはいずれ改めて詳しく触れたいと思っているのだが、それを検証する一番「正確」な方法は、ひとりひとりの信仰者の方々が「自分の胸に聞いてみる」ということに尽きているのではないだろうか。真面目な信仰者の方なら、自分や他人の悩みについて「神」はどう考えているのか、ということに思いを巡らさない日はないことだろうと思われるのだけど、その場合に心の中に描かれている「神さん」のイメージは、自分という存在がそうであるように、あるいは中山みきという人がそうであったように、「ひとりの人格」のイメージを必ずまとっているはずなのであり、「をもたりのみこと」はああ言うだろうけど「たいしょくてんのみこと」はこう言うかもしれない、みたいなことは普通考えないと言うか、考えようとしても無理な相談であると思う。だとしたらそれはやはり一神教「的」な信仰のあり方なのであり、少なくとも多神教のそれではない。
同様に中山みきという人自身、「神さん」の教えを人々に取りつぐにあたっては、「をふとのべさんはこう言うてはるけど、かしこねさんはああ言うてはるで」みたいな玉虫色の説き方など間違ってもしていなかったはずだし、そもそもそうした「神名」は本当に彼女が教えたものだったのかということ自体、極めて疑わしい話だと私は思っている。けれども彼女は「そういうことも言っていた」という伝承も、一方ではまことしやかに語られ続けており、それが話をややこしくしているわけなのだが、このことは結局「事実としてはどうだったのか」ということをひとつひとつ正確に検証してゆくことを通してしか、「答え」の出しようがない問題であるのだと思う。それについては回を改めて詳しくやって行くつもりでいるので、今の段階ではまあ余談である。
余談ついでに、「仏教」という宗教は「多神教」で「偶像崇拝」の宗教なのだろうかという問題にも触れておきたいのだが、仏教というのはそういう「定義」が当てはまる宗教ではないと私は思っている。確かに仏教では「仏像を拝む」わけだし、その仏像の種類からして、如来、菩薩、明王、天部等々、無数に存在している。しかしながら仏教という宗教は、「仏像に服従すること」を人々に強制するようなことは、決してしていない。仏教において仏像というものが「必要」になるのは、自らも仏のような存在たらんとしている修行者がその「仏のイメージ」を具体的に心に描くための材料としてなのであって、その意味では仏像というものは「道具」であるにすぎない。それに、怒った顔から優しい顔まで、多種多様な名前と形を持っている仏像の姿というものは、真言宗の教義を踏まえるならば、大日如来という擬人化された存在に象徴されている「ひとつの真理」が様々な姿をとって表現されたものに他ならないという説明が、あらかじめ与えられている。仏教においては、「対象に服従すること」ではなく、「対象と同格の存在になろうとすること」が「信仰」なのである。
この点、天理教、と言うより中山みきという人の説いた教えは、他のどんな宗教よりも仏教によく似た教えであるという印象を私は持っている。同時にそうした「信仰のありよう」を、人々に「神への服従」を強制することしかしてこなかった西洋の一神教や日本の国家神道と同じ「宗教」という言葉で一緒くたにしてしまって本当にいいものなのだろうかという疑問を、ずっと昔から感じている。
「宗教」、「信仰」、「崇拝」、そして「多神教」に「一神教」、どれもこれも「明治」期のインテリが外国の思想を翻訳して日本に移入するために発明した「新しい日本語」であるにすぎず、中山みきという人が自らの思想を築きあげた頃には、そういった言葉はまだひとつも存在していなかったのだということを、我々は覚えておかねばならないと思う。こうした言葉が「独り歩き」を始めて久しくなった現代においては、上に見たような「全く異なった人間の心のありよう」が、「宗教」や「信仰」といった「同じ言葉」で「説明」されてしまいがちであることを、おかしいと感じることのできる回路自体が封鎖されてしまっているように感じることもしばしばだ。「神」という言葉にしてからが、「明治」以降の日本においては天皇制軍国主義の独占物となり、それにキリスト教や他の諸宗教が掲げる互いに全く無関係な「神」のイメージが入り混じって、この言葉に「ひとつの定義」を与えようとしたら「終わらない戦争」が始まってしまう以外にないような状況が、長きにわたって続いている。
中山みきという人自身は、こうした時代の動きに対応して「誤解」を避けるための配慮だったと思うのだが、「明治」の8年以降は「おふでさき」の中で明らかに意識して「神」という言葉を使うことをやめており、「月日」や「をや」といった言葉を、それに代わる表現として採用している。「神」という言葉に対するこの「執着のなさ」は、学ぶべきものであると思う。「神は神」「宗教は宗教」といったような言い方は、何かを説明しているようでいて実のところ何も説明していないにも関わらず、それで何かが「わかった」ような気持ちになっている人々というのは、結局のところこうした言葉が持っている「呪術的性格」に深々と支配されているにすぎない、ということが言えるのではないだろうか。その点、彼女という人は、そうした「呪縛」から全く「自由」になった立ち位置から、自分が「神」と呼んだその対象と向き合い続けていたのだということを、見ておかなければならないだろうと思う。
ここまで思いつくままにとりとめなく話してきたことを、現実世界での実際の歴史の歩みに合わせて、改めて整理することにしてみよう。
人間は太古の時代から長きにわたって、「倒すか倒されるかの戦いの世界」に生きることを余儀なくされてきた。「自由」は「最も強い力を持った存在」にだけ与えられた「特権」としてあり続け、人々が元初から持っていたであろう「たすけあって生きたい」という「欲求」は、「最も強い力を持った人間の意思に服従する」という形を通してしか、基本的には「実現」されることがなかった。人間と人間との間に形成された「支配と服従の関係」が変化するに従って、観念の世界における「人間と神との関係」もまた、様々な形で変化を繰り返してきた。
「偶像崇拝の禁止」に象徴される「神と人間の分離」という出来事を通して、「最も強い力を持った存在」は人間社会から「疎外」され、感性でとらえることのできる具体的な姿かたちを備えた対象であることをやめて、理性でしかとらえることのできない抽象的な対象へと変化した。このことは一面においては、「倒しあいをやめて万人がたすけあいのために生きること」の可能性を人間社会に切り開いたとも言いうるが、そのことは人間が「自由」を放棄すること、人々が自らを「服従主体」として形成してゆくことを、条件としていた。個々の人間が現実社会において「最も強い力を持った存在」と取り結んできた関係は、各人の心の中における「神という絶対者」との「一対一の直接的な関係」へと転化された。このことは人間社会における「個人」の覚醒と成長を促したと言いうるが、本質においてそれは「抽象的な恐怖への服従」以外のものではなく、そうした「服従精神」は諸個人の心の中に、深々と内面化されることになっていった。
地上の権力者は「神の代理人」を名乗るようになり、人々はその意思や掟にもとづいて「たすけあう」ことを求められるようになったわけだが、「強要されるたすけあい」などというものは、どこまで行っても「疎外されたたすけあい」でしかありえない。この「疎外」は究極的には、「神の敵」との「殺し合い」を意味する「戦争」において、最も高度なレベルの「たすけあい」が人々に要求されるという点にあらわれてくる。人間というものが「倒しあう」ためにしか「たすけあう」ことのできない生き物であるのだとしたら、こんなに絶望的な話はないと思うが、おそらくそんなはずは、絶対にないのである。なぜならそうした戦争や殺し合いは、往々にして「誰ひとり望んでいないにも関わらず」発生するものであるからだ。
こうした「不条理」が起こってしまうのは、「人間と人間との関係」のあり方を根本において規定している「人間と自然との関係」のあり方が、いまだ「倒し倒される戦いの関係」でしかありえておらず、「たすけあう関係」になりえていないことに由来しているのだと思われる。「神」という抽象的権威のもとに「力を合わせる」ことを覚えた人間は、それから猛烈な勢いで「生産力」を発達させてきたわけだが、その活動の内容というものは、こと「自然との関係」において見る限り、一方的な「征服」事業以外の何ものでもありえなかった。中山みきという人が「傍楽」という字を当ててその意味を人々に説明した「働く」という活動の内実は、この「戦争」的な関係に規定されて、「人間と人間との関係」の内側においても、「競争」による「疎外」をこうむることになっていった、ということを見ておく必要があるだろう。この「競争」は、「自然に対する征服事業」がエスカレートするに従い、ますます耐えがたいものとして個々の人間の上にのしかかるようになって、現在ではほとんど全ての人間がそれを望まないと感じるまでに至っている。それにも関わらず、「競争」は「人間の外部」から押しつけられる「強制的な力」として、人々の生き方を深々と「支配」し続けており、人間は「人間として」生きたいと願うならば、そこから抜けることも降りることもできないような状況に陥っている。中山みきという人が生きた時代は、まさにそうした人類史の一時期の「入口」にあたる時代であり、そして我々が生きる現代は、そうした状況が決定的に煮詰まって、もはやどこにも「出口」が見いだせないところにまで立ち入ってしまった時代なのだということを、確認しておく必要があるだろう。
「人々の絶対的服従」を条件に「三百年にわたる平和」を可能にしてきた徳川幕府という体制が、中山みきという人の時代に至って「倒される」日を迎えたのは、人々が「万世一系の天皇」という「新しい服従の対象」を求めたからでは決してなく、人々が「自由」を求めたからに他ならないのである。中山みきという人はそうした「時代のエネルギー」を最も鋭敏に感じ取っていた人だと私は思っているし、また本人も…東アジアの片隅の「ほん何でもない百姓家の女」としての立場から…切実に「自由」を希求していた人だと思っている。人々を直接に抑圧していた徳川幕府というものをたとえ「力」によって倒しても、それによって人間の生き方に「自由」がもたらされることにはならないことを、彼女はおそらく当時を生きた他の誰よりも、深いレベルにおいて「わかって」いた。だから当時において大和一円をも席巻していた尊皇攘夷運動というものに、彼女は一貫して距離を置く姿勢をつらぬいていたのだと思う。人間を「倒しあい」へと駆り立てる「見えない力」の正体が、彼女には確実に「わかって」いたし、その「力」は「倒しあい」に勝利した人間たちにさえ決して「自由」をもたらさないということを、彼女は間違いなく「わかって」いたのである。
人間にとっての「自由」とは、「その人が望んだ通りに生きること」でなくて、何だろう。その「望み」の形は、人によって様々であるに違いない。けれどもあらゆる人々の「望み」の根底には、「たすけあって生きたい」という「欲求」が必ず横たわっているはずだという確信が、中山みきという人には、あったのである。ともすれば「永遠に続く倒しあいの歴史」だったとしか思えないような人間の営みの底流に、一貫して存在し続けていた「たすけあって生きたい」という人々の渇望が、彼女の心の眼には確実に映っていた。それは彼女という人自身が誰よりも「たすけあって生きること」を渇望していた人だったからこそ、「見えた真実」だったのだろうと私は思っている。
その「真実」を、おそらく中山みきという人は、「神」と呼んだのである。そしてその「真実」の立場に立ちきるという「決意」を込めて、一切の「人間心」を捨てさり、「神」そのものとして人々の前に立つことを、おそらくは天保9年旧暦10月23日の日が暮れたその後に、決断したのである。
人々を「倒しあい」に駆り立てる「見えない力」の正体は何なのか。それは人々の心をその内側から蝕んでいる「服従精神」に他ならない。他人を支配したいと思う「欲」や「高慢」は、「服従を強いられて生きること」の辛さや苦しさを人間なら誰でもわかっているからこそ、そこから逃れたいという「あがき」として、生まれてくるものだ。けれどもよしんば「倒しあい」に勝ちぬいて人間の最高位にまで登りつめた人間であっても、その恐怖から逃れることはできない。そこまでは人間は、「自力で」気づくことができた。だから「目に見えない神」というものをつくりあげ、それに服従を誓うことと引き換えに、「自分だけはたすかりたい」と願いをかけるタイプの「信仰」が生まれることになった。しかしながら、「それでは誰もたすからない」のである。「目に見えない力」に対する「恐怖」から人々を解き放つには、「神がおもてにあらわれる」以外にない時が来た。というのが中山みきの下した結論だったのだと思われる。それが「人として」の考えだったのか、「神として」の考えだったのかは、私にはわからない。けれども最終的には「どちらであっても同じこと」と言っていい問題なのだと思う。その人の出した答えが「真実」であるならば、そこには必ず「神が働く」はずだからである。
天保9年(1838年)10月に「神がおもてにあらわれた」ことの趣旨は、それから32年後の明治2年(1869年)に初めて書かれた「おふでさき」の冒頭の八首の歌の中に、あますところなく言い尽くされている。のちに歌の文句を五七五七五に調整して、催馬楽の節回しで「よろづよ八首」として「おつとめ」の冒頭に歌われるようになった歌…という説明が天理教本部からはなされているわけだが、本当のところは「声に出して歌われる歌」の方が先にできていて、「おふでさき」の冒頭八首の方は後になってからそれを整理したものではなかったのか、という印象を私は感じている。けれどもそれについての検証は別の回に回そう。まずは、その全文を紹介したい。
よろつよのせかい一れつみはらせど
むねのハかりたものハないから
万代の世界一列見晴らせど
胸の分かりた者はないから
そのはづやといてきかした事ハない
なにもしらんがむりでないそや
そのはずや 説いて聞かした事はない
何も知らんが無理でないぞや
このたびハ神がをもていあらハれて
なにかいさいをといてきかする
この度は神が表へあらわれて
何か委細を説いて聞かする
このところやまとのしバのかみがたと
ゆうていれども元ハしろまい
このところ大和の地場の神方と
言うていれども元は知ろうまい
このもとをくハしくきいた事ならバ
いかなものでもみなこいしなる
この元を詳しく聞いた事ならば
いかな者でも皆恋しなる
きゝたくバたつねくるならゆてきかそ
よろづいさいのもとのいんねん
聞きたくば尋ね来るなら言うて聞かそ
万委細の元の因縁
かみがでてなにかいさいをとくならバ
せかい一れつ心いさむる
神が出て何か委細を説くならば
世界一列 心勇むる
いちれつにはやくたすけをいそぐから
せかいの心いさめかゝりて
一列に早く助けを急ぐから
世界の心 勇めかかりて
…なんという、自信に満ちた宣言なのだろうと思う。一言一句に注釈や感想を付け加えたい誘惑にかられてしまうのだが、それもまた別の機会に回そう。中山みきという人が説いた「神」は、人々に対して「服従」を求めるのではなく、「心を勇ませて助けを急ぐ」ことを求めている。「世界の真実」は、それを知ろうとしたらバチが当たったり目が潰れたりするようなものではなく、それを知っただけですべての存在が愛おしく思えてくるようなものなのだということを、教えている。彼女の説いた「神」のイメージは、それまでにあった「神」のイメージからの「断絶」の上に形成されており、そのことは
いまゝでにない事ばかりゆいかけて
よろづたすけのつとめをしへる
今までにない事ばかり言いかけて
万助けの勤め教える
という歌の中にもハッキリと示されている。「言わん言えんの理」というものがあるから、「他者を否定する言葉」を基本的に彼女は使わないのだけど、事実上、今までに説かれてきた「神」というものは全部まやかしだ、と言いきっているに等しい姿勢である。逆らう者を皆殺しにする記紀神話のような「神」としてではなく、「死後の救済」しか約束してくれない抽象的な存在としての「神(-仏)」としてでもなく、「ここ」を「この世の極楽」にするために、現実の歴史の流れを踏まえるならば「再び」具体的な姿かたちを備えた感性の対象として、すなわち「生きた人間」の姿をとって、「神はおもてにあらわれた」のだと言うことができるだろう。
ちなみに、中山みきという人が説いた「たすけあい」とは、「人間と人間との関係」の内側にとどまるものではなく、「人間と自然との関係」にまで踏み込んだものとしてある「たすけあい」であり、後に彼女が説いた「貸し物·借り物の理」には、そのことが示されていると私は思っている。だから彼女の説いた思想は、人々を「倒しあい」へと駆り立てるこの世界の矛盾の根本=「よろづ委細の元の因縁」を対象化し、それを「止揚」する道筋を示したものとなり得ているというのが私の理解である。しかしながら「人間と人間との関係」の内側においてさえ「たすけあい」が実現できていない状態において、「人間と自然との関係」に「たすけあい」を求めるのは、順序を無視した暴論と言うべきだろう。だから彼女はとりあえず、人間と人間とがたすけあって生きること「だけ」を人々に教えたのだろうと私は受け止めている。そこから先のことは「言わん言えんの理」の領域の世界なのだろうと拝察させて頂く次第である。
ここまで延々1万2千字以上を連ねて私が今回結局何を言いたかったのかというと、中山みきという人には間違いなく「顔があった」、ということなのだ。こんな「当たり前」のことを言うのに、どうしてこれほど長大な文章を書かねばならなかったのだろうと自分でも思う。けれども何しろ中山みきという人は、「誰よりも人間らしい人間の顔」をして「神の言葉」を語っていたに違いないわけで、だからこそ彼女の時代に彼女の周りにいた人たちには、「神がわかった」わけなのである。それなのにどうして彼女の教えを人に取りつぐ立場にある人たち、すなわち天理教の先生方は、せっかく「おもてにあらわれた神」の姿を再び「隠して」しまうようなことを、続けているのだろうか。
彼女の死後に形成された天理教団は、それからほどなく起こった日清戦争を皮切りに、太平洋戦争における日本帝国主義の敗戦に至るまで、「倒しあい」のための「たすけあい」に人々を動員することを通して教勢の拡大を図るという、中山みきの教えからは最もかけ離れた行為に手を染めてきた。そのためには教祖の本当の教えを「隠す」必要があったわけだし、教祖の姿を「いかなものでも恋しなる」気持ちの対象から「服従精神」の対象へと、「再構築」する必要があった。このために、言うなれば「神と人間との分離」の時代に「逆戻り」するような形で、いったんは写真にまでおさめられた彼女の「顔」は、「隠される」ことになったわけなのである。
扉開いてろっくの地にしてくれ、
と言うたやないか。
という「教祖臨終のおさしづ」の言葉が、それを思うと実に悲痛なものとして響いてくるのを感じるが、それについて詳述できるのは当分先のことになると思う。「当時はそれで仕方なかった」とか、「そうしなければ生き残れなかった」とか、いつまでも服従精神を丸出しにして人のせいにすることを続けていたいというのであれば、それもそれでいいだろう。中山みきという人の教えた「神さん」は、そういう人々にも「不自由はさせたくない」という気持ちで向き合ってくれるはずだし、そういう人々もそういう部分だけは「信じて」いるはずだからである。けれどもそれなら、「高山の支配」に「恐怖」する必要がなくなった戦後になってからなされた「復元」と呼ばれる事業は、いったい何だったのだろうか。そして弾圧の中にあっても中山みきという人の教えを曲げることなく説き続けようとしたために、他ならぬ天理教本部の手によって「抹殺」されていった先駆者の人たちの名誉は、いつになったら回復されることになるのだろうか。「応法の理」が説かれていた時代を「間違い」だったと認めるのであれば、それに対する真摯な反省と自己批判が表明されることのない限り、天理教という宗教の手はいつまでも血に染まり続けていると言わねばならないと私は思っている。
「顔のなくなったみきさん」の顔を見て反射的に「恐怖」を感じてしまった子どもの頃の私を、そんなわけで今の私は、恥じている。「何やこれは」と思わねばならなかったはずなのである。思うことだってできたはずなのである。そのためには、子どもの頃に見たあの絵に感じた「異様な説得力」は一体どこから生まれてきたものだったのだろうということを自分自身で解明し、その「恐怖」と改めて向き合い直す必要があった。それで今回の記事は、こんなにも抽象的な内容になってしまった次第なのだが、皆さんにもしんどい思いをしてつきあってもらったおかげで、「顔のないみきさん」は「本当のみきさん」ではなかったのだという「当たり前の事実」に、今では自分自身でもようやく「納得」がついたような気がしている。そして、他の誰かが勝手につくりあげた「顔のないみきさん」のイメージに幻惑されて、「本当のみきさん」の姿は今まで自分自身にも「見えない」ままになっていたのだということに、気付かされつつある。「わかりきったこと」でもそれを敢えて「言葉にする」ことには、やはりそれなりの意味があるものだと思う。もっともそういう体験は、人生で一回あればそれで充分だとも思うのだけど。
今回あらためて整理してみた「中山みきという人のイメージ」に照らしてみるならば、「立教」に際して彼女が発したとされている「神の言葉」の数々はあまりに「高圧的な印象」を人に与えるものであり、本当に彼女はこんな言葉を口にしたのだろうかという疑問が湧いてくる。「寄加持」という「場の設定」自体がフィクションにしか思えないということは前回つぶさに検証したのだし、本当はどういう人々の前でどういう形でどういう言葉を口にする形で「それ」は為されたのだろうかということが、やはり気になってくる。本当ならば今回の記事ではそのことを具体的に考察するつもりでいたのだったが、それをこの文章の続きでやれる余力は、当然ながら私にはない。
…とうとう1万4千字を越えてしまった。というわけで次回に続きます。
いいなと思ったら応援しよう!

