
企業行動論講義note[06]「誰がために企業はある:派生的経営としての企業&価値循環という事象」
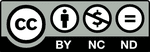
この内容は、第2講の〈その1〉もしくは第2講〈その3〉に当たります。講義の進み具合で変動します。
なお、このnoteはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示-非営利-改変禁止」です。
みなさん、おはこんばんちわ。やまがたです。
いよいよ、2nd Phase「企業ってどんなしくみで動いているのか」の話に入っていきます。1st Phaseが「そもそも、企業ってなんで存在するのか」というところに力点を置いていたので、すこし具体的な内容に進んでいくかたちになります。
[今回のキーワード]
経 営(Betrieb):人間が何かのために活動するコトの連鎖と、それをモノと結びつける何らかの方法やしくみ。
家政 / 家計:一般的には、消費を通じて欲望充足しようとする経営。なので、〈本源的経営〉とも呼ばれる。個人でも複数でもOK。
企 業:家政 / 家計が抱く欲望を充たすようなモノやコトを創出・提供しようとする経営。なので、〈派生的経営〉とも称される。
価値循環:さまざまな経営内部や経営間で、価値をもたらすものやことがつくられたり、つたえられたり、つかわれたり、さらにやり取りされたりする流れや動きのこと。経営内部での流れや動きを内部価値循環、経営間での流れや動き(やりとり=交換)を外部価値交換という。
前回の講義note[05]の最後で、企業行動論において企業という存在を〈価値創造を共有目的とする協働体系〉として捉えるとお話ししました。
ビジネスとは、他者を充たすことで、自らをも充たしていくことだ:価値創造という考え方(復習)
これは、講義note[03]で説明したことなので、さらっと復習しておきます。
「価値を創造する」という表現は、いろんなところで用いられています。そして、いろんな意味合いで用いられています。ただ、この講義では、以下のような意味で〈価値創造〉という言葉を使っています。
[ここでのキーワード]
価 値:欲望充足の主観的強度。ある主体が抱いている欲望が、何らかの効用給付(財)からもたらされる効用によって、どれだけ充たされたのか。
価値創造:他者に〈価値〉をもたらすことで、自らも何らかの〈価値〉を得ることができている状態。
この定義でいえば、「価値を創造する」とは、自分ではない他の誰かにとっての欲望や期待を充たすようなモノやコトを創出し、提供することで、他者に価値をもたらし、それによって相手から対価(反対給付 / 見返り)を獲得し、自らの欲望や期待を充たす(=自らも何らかの価値を得る)営み、ということになります。
ビジネスという営みは、まさにここです。ビジネスを担っていく活動主体としての企業の存在意義 / 目的が価値創造にあるというのは、ここまでの講義noteでもわかってもらえるんじゃないかと思います。
ここをわかっておいてもらったうえで、今回の本題です。
アクター(登場人物)としての〈経営〉:ニックリッシュという人の慧眼①
いきなりわけのわからないタイトルで、面喰った人も多いかと思います。まず先に、ここで当然のように使ってしまった〈経営〉という言葉について説明しておきます。
【言葉の解説】「マネジメント」ではない〈経営(Betrieb)〉
「経営」というと、一般的には「マネジメント」という意味合いで理解されるのではないかと思います。いわゆる「経営する」という感覚ですね。ところが、ここで用いている〈経営〉というのは、その意味ではなくドイツ語でいうBetriebという言葉の訳語です。Betriebというのは、ひじょうに多様な意味合いを持っているのですが、一般的には「職場」「工場」といった意味合いで理解されています。ヴェーバー(Weber, M.)は、〈経営〉という概念を「一定の労働サービス相互間およびこれと物的生産手段とを継続的に結びつける、そのしかた」(富永健一訳「経済行為の社会学的基礎範疇」尾高邦雄責任編集『ウェーバー』〈中公バックス世界の名著〉第61巻、372頁)と定義しています。ややこしい説明ですが、人間が何かのために活動するコトの連鎖と、それをモノと結びつける何らかの方法やしくみを〈経営〉とよんでいるわけです。
そして、そこからも影響をうけて、ここで採りあげるニックリッシュは〈経営〉という概念を、「道具、原料を備えていて」「自己ないし自分たちの目的を実現するために働いている」「個人ないし複数の人間」、あるいは「欲望充足のための価値を生産するために装備された一つの共同体」(Nicklisch, H.[1922]S. 36 f.)と定義しています。
ドイツ語の直訳なのでわかりにくいかもですが、何らかの欲望を抱いていて、それを充たそうとして何らかのモノを備えている個人や共同体をBetriebと呼んでいると考えていただければ、さしあたって大丈夫です。
↓ ここに、私の論文のリンク(近畿大学学術情報リポジトリ)を貼っておきます。ほんとに興味があるかたは、どうぞご覧ください。
ちょっと長々と〈経営〉という概念について述べてきましたが、最近はこれと同じ意味合いで〈アクター〉という言葉もしばしば用いられます。活動主体とか、より限定的には俳優や登場人物という意味合いもあります。「登場人物」というのは、この講義での流れだとイメージしやすいかもですね。そのビジネスにおいて生じる価値の流れに参画する主体ということですので。
さて、今、説明してきた〈経営〉という概念、これちょっと落ち着いて考えてみると、企業に限られないことは想像してもらえるかなと思います。
ここでの主人公であるニックリッシュ(Nicklisch, H.:1876-1946)という人は、ドイツ人の経営学者です。彼は、ちょっとかわった考え方を打ち出した人で、「すごい人」という評価はなされてるのですが、ドイツですらあまりちゃんと理解されてないっぽい人です(笑)
ニックリッシュという人は〈規範学派〉に属するという文言が、あちらこちらでみられます。これは、1933年にシェーンプルーク(Schönpflug, F.)という人が著した『個別経済学の方法問題』(邦訳は『シェーンプルーク 経営経済学』古林喜楽監修、大橋昭一 / 奥田幸助訳、有斐閣)による分類に依拠しています。ニックリッシュ自身は自らを規範学派だと称したことはほとんどないのですが、これがニックリッシュの位置づけを決めてしまったのはまちがいありません。山縣自身は、ニックリッシュには確かに規範的な側面もあるけれども、それは多かれ少なかれ、どの学者にもあるもので、それだけをもって規範学派としてしまうのは早計にすぎると考えています。というのも、ニックリッシュもまた当時の社会経済や企業、さらに働く人たちの現実を見ていたからです。その点は、彼の著書や論文からも十分に窺われます。
ニックリッシュの評価にとって致命的なのは、晩年にナチスにすり寄ったとみなされ、第二次世界大戦後にはものすごく評価が下がってしまったことでした。現実には、そこまですり寄ったわけでもないのですが、ナチスから迫害されたシュマーレンバッハやリーガーという人たちに比べて、まともに論究されなくなってしまったのも事実です。
ニックリッシュの学説に問題がないというのではありません。いろいろと克服すべき問題は含まれています。それらをしっかりみきわめたうえで、現代にニックリッシュの学説を活かすというのが、山縣の考え方です。
本源的経営としての家政 / 家計:ニックリッシュの慧眼②
そのなかでも理解されなかったのが、〈本源的経営〉〈派生的経営〉という概念です。
ふつう、経営学だったら企業がメインの対象になるってのが常識だと思います。ところが、ニックリッシュは欲望を充たそうとする活動主体=経営としての家政 / 家計(Haushalt)こそが出発点だというのです。なので、ニックリッシュは家政 / 家計を〈本源的経営〉と呼びます。ちなみに、ここにいう家政 / 家計は個人の場合も複数の場合もあります。家政 / 家計というと「家族」というイメージが強いかもですが、例えば下宿している学生さんだったら、ひとまずその人ひとりで家政 / 家計と呼ぶことができます。また、経済的に裕福であるか、そうでないかも特に関係ありません。一般的に「消費を通じて、欲望を充足しようとする」*というところにポイントがあります。
* ただし、ニックリッシュは家政 / 家計も単なる消費だけではなくて、「価値を創造する」経営であるとみています。これは100年前当時の状況を背景にしていますが、家政 / 家計は後で論じる企業に対して、労働をはじめとする企業にとっての効用給付を創出しているからです。これは、今回だけでなくこれまでの講義noteで名前を挙げている〈サービスドミナント・ロジック〉を考えるうえでも、ひじょうに重要な点です。
さらに、〈消費〉という言葉をどう捉えるかも、今この状況においてあらためて考えてみる必要があります。最近、「捨てないデザイン」という考え方が注目されつつあります。〈消費=使って、捨てる〉という発想だけでは片付かない新しい動きが出てきています。このあたりも、ぜひみなさん一度考えてみると、おもしろいと思います。
派生的経営としての企業:ニックリッシュという人の慧眼③
このように、ニックリッシュは欲望充足しようとする活動主体(経営)としての家政 / 家計を〈本源的経営〉として、まず最初に位置づけました。そのうえで、この〈本源的経営〉の欲望を充たそうとして生まれてくる活動主体(経営)として企業を位置づけようとしたのです。なので、ニックリッシュは企業を〈派生的経営〉と呼んだわけです。
このような考え方は、経営学のなかでは少数派といっていいでしょう。なぜなら、経営学のメインターゲットは〈企業〉だからです。もちろん、ニックリッシュの考察のターゲットも企業が中心です。けれども、あくまでも欲望を充たしたいと考え、行動している人としての家政 / 家計を軸にして、企業という存在を位置づけようとしているところに、彼の考え方のユニークさがあります。
この点こそが、ニックリッシュとサービスドミナント・ロジックやサービスデザインとの距離を近いものにしている大きなポイントです。
企業それぞれが、どの家政 / 家計(←欲望を抱いている人。マーケティング的観点から言えば〈顧客〉とみることができます)のどんな欲望を充たそうとして、そのためにどう資金を調達し、どんな効用給付を創出しようと企画構想し、それをどう生産し、どう流通させ、どう販売し、相手に届けようとするのか、そしてそれにともなう収入や支出の流れ、内部での原価の計算などをどのようにおこなっているのかを明らかにすること、これがニックリッシュの経営学の根幹にあります。
価値循環という考え方:ニックリッシュの慧眼④
ニックリッシュは、この本源的経営と派生的経営という考え方を基礎にして、〈価値の流れ / 価値運動 / 価値循環〉という概念を打ち出します。最もシンプルなのが、下の本源的経営1つと派生的経営1つの関係性を描いた下の図です。

これは、経済学などの教科書でも昔からよく示されているものとほぼ同じなので、それほど珍しくはないかもしれません。経済学が財の交換という事象に焦点を当ててきたことを考えれば、こういった基本図式が似てくるのは当然ともいえます。ニックリッシュは、これを〈価値の流れ / 価値運動 / 価値循環〉という言葉で説明します。
ちなみに、ドイツ語圏における経営学はBetriebswirtschaftslehre=経営経済学と呼ばれてきました。ただ、ここでいう経済学というのは、今、一般的に理解されている経済学と完全に合致しているわけではありません。むしろ、講義note[01]でお話しした〈欲望充足〉や原価などの収支の流れに即して企業活動を捉えるという意味合いだと考えてください。
ただ、ニックリッシュ(というか、経営学)の場合に大事なことは、それぞれの経営間での価値のやり取り(交換)だけではありません。経営内での価値の流れ / 価値の運動も、当然ながら重要です。経営内での価値の流れとは、先ほども少し触れましたが、資金調達や企画・開発、生産、流通、販売などの効用給付を創出&提供していく流れや、それにともなう情報の流れ、そして貨幣の流れをさします。
ニックリッシュは、この経営内部での価値の流れを〈内部価値循環〉、経営間での価値の流れ(交換)を〈外部価値循環〉と呼びました。そして、経営学が対象とするのは、これらの全体としての〈価値循環〉と称される事象であると捉えたわけです。これが複合的になると、以下の図のようになります(Nicklisch, H.[1922]S. 大橋昭一編著、渡辺朗監訳[1996]『』)ニックリッシュは、より具体的に、価値循環には企業と労働者だけでなく、出資者(自己資本提供者)、債権者(他人資本提供者)、調達業者、流通業者、そして何より顧客などのさまざまな経営が存在することを想定した議論を展開しています。当時は、まだステイクホルダーという言葉もありませんでしたが、ステイクホルダーとのあいだでの価値の流れを捉えうる理論枠組を提示しようとしていた点で、きわめて先駆的であったと言えます。この考え方は、講義note[05]で言及したバーナードにもおそらく影響を与え、またこの講義で登場するシュミット(Schmidt, R.-B.)の〈企業用具説〉へと展開されることになります。そして、直接的なつながりはないにもかかわらず、サービスデザインにおいてもきわめてよく似た図式が登場します。その図式が提示されている文献をここではご紹介しておきます。
また、近年『ビジネスモデル2.0図鑑』でよく知られている近藤哲朗(チャーリー)さんと沖山誠さんの新著『ビジネスの仕組みがわかる図解のつくり方』(スマート新書)でも〈価値循環〉という言葉が出てきます。ちなみに、近藤哲朗さんや沖山誠さんが立ち上げられた図解総研というシンクタンクは、ひじょうに興味深いです。
【加筆:2020年6月2日】
価値循環に関して、山縣がこしらえた図も併せて掲載しておきます。こちらのほうが、1対1の価値循環のようすをイメージしやすいかなと。

本源的経営にも、派生的経営にも、それぞれ内部価値循環があり、そしてそれらの経営のあいだのモノやコトやお金などのやり取り、つまり価値交換関係が外部価値循環としてあらわれるわけです。ちなみに、BtoBの場合でも、この図式は当然成り立ちます。つまり、本源的経営と派生的経営の関係はどちらがどんな欲望を抱き、それをどちらが充たすのかによって決まってくるということなのです。
今回の〆。
今回は、ニックリッシュの考え方に依拠しながら、企業という存在をどうとらえるのかについて説明してきました。一般的な経営学の教科書に載っている説明とは、かなり色合いが違っていたかもしれません。なので、面食らった方もおられることでしょう。
ただ、新型コロナウィルスの蔓延や、じつはそれに先立ってすでに生じ始めていた〈アフターデジタル〉への動きは、ニックリッシュが提示した企業観と整合性があります。ニックリッシュ自身がどこまで意識していたかはわかりませんが、彼が生きていたほぼ100年前は第一次世界体制船が勃発し、スペイン風邪が流行し、社会主義運動が激化し、彼がいたドイツでもワイマール体制が成立するなど、ひじょうに激動の時期でした。そのようななかで、企業は何のために存在しているのかということが問われたとしても、それはひじょうに自然なことであったといえるでしょう。技術や衛生状況、また教育水準、経済状況など、100年前と今を並べて考えてもあまり意味はありません。しかし、激動する時代においては「そもそも」を問い返すことが求められます。
ニックリッシュが提示した枠組は、その点で今の私たちが「企業は、いったい何のために存在しているのか」を考える重要な手がかりとなっているのです。
次回は、この考え方に立って、企業がどう動いているのか、企業をどう動かすのかという点について考えていこうと思います。
んじゃ、また次回に。
ばいちゃ!
