
企業行動論講義note[11]「価値ある(価値をもたらしうる)何かをやり取りする:価値交換関係の基礎」
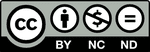
この内容は、第8講に当たります。講義の進み具合で変動します。
なお、このnoteはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示-非営利-改変禁止」です。
みなさん、おはこんばんにちは。
やまがたです。
前々回と前回、価値創造過程をめぐる話をしてきました。前々回は、価値創造過程の基本的な理解について、そして前回は新しい考え方としてのサービスドミナント・ロジックについて採りあげました。
じつは、前回のサービスドミナント・ロジックにおいても、今回からの価値交換の問題はすでに含まれていました。その点も含めて、今回と次回、価値交換関係について考えてみたいと思います。
〈関係の束〉としての企業。
企業にとって、いちばんコアになるのが他者の欲望充足(と、それを通じた成果獲得)=価値創造であることは、この講義で何度もお伝えしてきました。
ただ、ここでもう一つ思い出していただきたいことがあります。それは、企業という存在が「実在ではあるが、実体ではない」という点です。この点、以前にもお伝えしましたが、もう忘れられてるかもしれません(笑)
(1)自然人と法人
この「実在ではあるが、実体ではない」とはどういうことか。
たとえば、企業は多くの場合、会社というかたちをとります。株式会社であったり、合同会社であったり、特定有限会社(新規設立はできません)であったり、合資会社であったり、合名会社であったり。この会社を含めて、人為的存在としての団体を、さながら意思を持つ存在であるかのように社会に位置づけるための法律的な概念が〈法人〉です。
ちなみに、サイボウズの青野慶久さんのこの本は、会社という存在を捉え返すうえで、ものすごく学びの多い一冊です。ぜひお読みになることをお薦めします。
ちなみに、法人に対する概念が〈自然人〉です。これは、生きている人間のことです。
ということは、「法律上、自然人と同じような権利や義務をもつとみなされる存在」が法人であるわけです。この点、まず押さえておいてください。
(2)関係性の総体としての〈人〉
さて、少し話が変わります。大きくは変わりませんが。
ここで「人」という存在をどう捉えるのか、という問題が出てきます。別に、ポエムみたいな話をする気はありません(笑)
この講義で登場したこともあるバーナードは、個人という存在を物的側面、生物的側面、心理的・社会的側面の3つから捉えました。物的側面とは「肉体を有している」ということ、生物的側面とは「肉体が、生命維持機能によって活動している=生きている」ということ、そして心理的・社会的側面とは「人間は他者との関係性のなかで生きており(=社会的)、その際にはさまざまな感情などを抱いている(=心理的)」ということです。
自然人の場合は、この3側面が備わっています。
ただ、法人の場合は、少なくとも最初から物的側面が備わっているわけではありません。誰かによって、おカネやモノなどが提供されて初めて物的側面が備わります。自然人の場合は、基本的に生命が息づいた瞬間から、徐々に物的側面が生きていくのに必要であるように形成されていきます(もちろん、そのプロセスでさまざまな事態が発生します)。ところが、法人の場合は意図的に「誰かが」何かを提供しなければ、生まれえないわけです。
なぜこんなことを言い出したのかというと、この企業や事業というのは人間が意図的に生み出した営み、存在であるからです。ということは、すでに企業や事業というのは、「誰か」との関係性を前提にしているからです。もちろん、自然人の場合も誰かとの関係性抜きにはありえません。
たとえば2020年度の前期に近畿大学経営学部で開講されている企業行動論の講義を受講してくれている人と山縣とは、受講生と担当教員という関係性で向き合っているわけですが、それを離れると関係性が解消されるか、あるいは別の関係性において向き合うことになるわけです。
もっというと、ある人が何がしかの繊維の織り成された布を裁断し、縫い合わせた物体を身につけている、あるいは身につけられる可能性があるとき、その物体は「服」と呼ばれるわけです。
このように、生命を持つ存在は自らの周りにある物質や生命的存在などを自らとの関係性において認識しています。そして、その存在自身も関係性の総体として捉え返されるわけです。新しい人や物との出会いによって、その人の人生が変わるってのは、まさに人が関係性の総体、関係性が織りなされていくことによってできあがっていくという事態の一場面であるといえるでしょう。
(3)〈関係の束〉としての企業
そう考えると、前々回の価値創造過程の講義において、価値創造過程は財(資源)によって構成されるとお伝えしたわけですが、この点の見え方も変わってくるのではないでしょうか。

この図に出てくるさまざまな財は、最初から企業に備わっているわけではありません。というか、そもそも、企業というのは、その企業自体が何らかの財を持ち合わせて生まれてくるのではなく、誰かによって財を関係づけられたところに生まれてきます。より具体的には、誰かが名目財や物的な実質財、自然人に由来する実質財や知識財を企業に提供することで、企業という存在が成り立つわけです。
さらに、この図でいうと「成果の獲得」と一言で終わっていますが、これは企業が創出・提供した効用給付を、誰かが(その効用からもたらされるであろう価値を期待して)購入した対価に由来します。つまり、名目財の還流もまた関係性において生じるのです。
このように、企業というのは価値創造過程を基軸としながら、そこには数多くの多様な関係性が存在しているのです。この関係性は、より具体的には価値交換関係なのです。
企業をめぐる価値交換関係:価値創造過程とステイクホルダー
今述べたように、価値創造過程はさまざまな財 / 資源からなっています。これを誰から獲得 / 入手するのか、また価値創造過程によって生み出された効用給付を誰にどう提供するのかということが問題となります。
それを一般的な図式として描き出したのが、図[11]1です。
図[11]1 企業をめぐる価値交換関係とステイクホルダー

この図は、あくまでも一般的に想定される株式会社企業をもとに描き出したものです。当然、誰がステイクホルダーになるのか、どんなやり取りがあるのかは企業によって異なります。
ただ、どんな場合でも企業、より具体的には価値創造という営みをめぐって、必ず財や資源などのやりとり、前回のサービスドミナント・ロジックに立脚していえば〈サービス〉*の交換が存在しています。
* 繰り返しになりますが、ここでの〈サービス〉は、この企業行動論での概念でいうと〈効用〉となります。なので、有形商品としての製品 / グッズ(Goods)や無形商品としてのサービスたち(サービシィーズ)と、交換媒体たる名目財 / 貨幣との交換という現象も、有形や無形の媒体(=製品やサービシィーズ)によってもたらされる効用と、貨幣という場板によってもたらされる「何らかの別の効用 / サービスを入手できる」という効用との交換として捉え直されるわけです。
ステイクホルダーという言葉は、今やビジネスのみならず社会において広く用いられるようになったものの一つです。ステイクホルダーという概念の歴史について関心のある方は、こちらの文献にぜひ触れていただければと思います。
この講義では、ステイクホルダーを「価値創造過程に必要な財を提供する個人や集団」と定義しておきます。学問的には、「資源の提供」という言葉で説明するか、あるいは「影響を与える」という点も含めるかといった議論があります。ただ、価値創造に必要なさまざまな資源 / 財というのは、明示的な契約によって獲得する場合もあれば、交換とみなして獲得する場合もあります(たとえば、天然資源などの場合)。また、資源といっても、もちろん物的資源にとどまりません。法規制なども、価値創造にとって(制約となる場合もありますが)資源の一種であると位置づけることができます。どの場合にも、価値創造をおこなおうとするアクターにとって必要な資源を提供してくれている他のアクターのことを〈ステイクホルダー〉と呼んでおくことにします。
価値創造過程と価値交換関係:ミクロにみてみる。
企業にとって、どんな財 / 資源が必要になるのかは、状況によって変わってきます。ただ、そこに価値交換関係があることは共通しています。その価値交換関係をミクロに図式化すると、以下のようになります。
図[11]2 価値創造過程と価値交換関係の基本モデル

ここで、横向きの矢印が、相手に価値をもたらす効用のやり取りです。ステイクホルダー→企業が先になるか、企業→ステイクホルダーが先になるかは状況によって変わります。例えば、B to Bの場合、納品した後になってから代金が支払われるケースは珍しくありません。いわゆる正社員、常時雇用の従業員とのあいだのやり取りなどは、ある時間や日、月、年の労働と、それに対する報酬というのが基本的な価値交換関係ではありますが、厳密にどの時期のどの労働と報酬が対応しているというのは、ひじょうに見定めるのが困難です。それに、福利厚生などを含めていくと、時間的な前後も複雑化します。
ただ、ここではいったん単純化して考えてみましょう。
まず、ステイクホルダーから企業にとっての効用給付が提供されるというのが第一段階で、その提供された効用給付が価値創造過程に財ないし資源として摂り込まれ、別の効用給付へと転態されるのが第二段階です。そして、その価値創造過程を通じて得られた成果が原資となって、ステイクホルダーにとっての効用給付が企業からステイクホルダーへと提供されるというのが、第三段階です。
先ほども言いましたように、第一段階と第三段階は順序が逆になることは、何ら珍しくありません。
順序が逆になることは、ここでさほどの問題ではありません。むしろ問題になるのは、この双方向の矢印が、じつはほとんどの場合「同時ではない」という点です。別の言い方をすると、「価値交換関係には、タイムラグが生じる」ということです。
なぜ、世の中で詐欺行為が発生するのかというと、まさにこのタイムラグがあるからなわけです。もう少し厳密に言うと、タイムラグだけではありません。知識や情報の差も詐欺行為をもたらします。現実に即していうと、知識や情報の差とタイムラグを“活用して”、合意によらない、あるいは納得のない不等価交換としての詐欺や搾取といった現象が生じるわけです。
残念ながら、この手のリスクをゼロにすることは不可能です。今述べたような意図的な詐欺や搾取でなくても、時間差によって状況が変わってしまうことや、知識や情報の差、あるいは解釈の相違によって価値交換を成り立たせる〈等価感〉が損なわれてしまうことも、しばしばあります。
価値交換関係は、価値創造過程を動かしていくうえで絶対的に必要です。仮に、価値創造過程を体内のメカニズムだとすると、価値交換関係は呼吸や栄養補給、排泄などの外部とのやり取りとしてみることができます。この外部とのやり取りなしに、体内メカニズムが機能することなどありえません。
そう考えると、リスクは避けられないけれども、価値創造をやっていくうえで必須の価値交換関係をいかにして成り立たせるかということが、きわめて重要な課題となってきます。そこで浮上してくるのが〈意思疎通ポテンシャル〉です。

意思疎通ポテンシャルについては、後で説明します。
価値交換関係のあらわれ方:取引から贈与まで
さて、価値交換それ自体は、言葉としてはマーケティングなどで用いられているものの、よく見かけるようになったのは最近です。ただ、この交換という事象自体は、社会学や経済学などによって古くから議論されてきました。
そもそも、価値交換が成り立つとはどういうときなのでしょうか。
図[11]3 価値交換関係が成り立っている状態

基本的に、交換においては、双方に欲望充足を通じて価値が感じられなければなりません。この点を念頭に置いてもらったうえで、価値交換の様相として取引と贈与という2つについて、みてみることにしましょう。
(1)経済的な価値交換としての取引
そのなかでも、かなり普遍的に用いられているのが〈取引;Transaction〉という概念です。簡単に言うと、「財のやり取り」です。ちなみに、もともとの語であるTransactionは、trans-とactionからなっています。actionというのは行為です。trans-とは、translation(latは、ラテン語のlatus「運ばれる」からきた語で「運ぶ」という意味合いから「向こうへ運ぶ」=翻訳する)やtransnational(nationは国、国を超える→多国籍)など、「向こうへ」とか「超える」とかいった意味合いを持っています。そう考えると、Transactionとは「相手に向けての行為」という意味合いで捉えることができます。
その点で、取引という概念も単なる財のやり取りとだけ捉えるのは狭いと言えるかもしれません。このあたりは、これ以上やると議論がややこしくなるので、いったんは「財のやり取り」として取引を捉えておきます。
ちなみに、取引においてやり取りされるのは、厳密には権利です(←ここはS-Dロジックと近い考え方です)。具体的には、以下の4つがあげられます。
①財を利用する権利
②財を変化させる権利
③財の利用によって収益を獲得する権利ならびに損失を負担する義務
④財を売却する権利
これらのうち、どこまでを相手から受け取るかが取引における一つのポイントになります。これらの権利を総称して〈所有権〉あるいは〈裁量権〉と呼びます。
このように財そのものとしてではなく〈権利〉として捉える発想は、サービスドミナント・ロジック(S-Dロジック)での〈サービス〉概念と軌を一にしています。
図[11]4 経済的交換としての取引

ちなみに、取引という価値交換関係が締結されるときに結ばれるのが〈契約 contract〉です。みなさんも、スマートフォンの新規契約のときに、ものっすごく細かい文字で書かれた契約書を持って帰っているはずです。ちゃんと読んでるかどうかは別にして(笑)
ただ、どれだけ詳細に契約書を作っても、将来の状況を完全に予測することなどできません。そもそも、人間の知識は不完全かつ非完結だからです。なので、すべてを契約書に記載してしまうことは不可能なわけです。そこで出てくる考え方が〈不完備契約〉というもので、場合によっては取引に参加する主体が状況によって行動を変えるという機会主義が発生します。
このあたりは、2020年に逝去したノーベル経済学賞受賞者であるウィリアムソンなどによって明らかにされました。
この点は組織の経済学という領域において展開されています。もし関心のある方は、ちょっとレベルは高めですが、ぜひ以下の文献に接してみてください。
(2)贈与という事象:交換なのか?交換ではないのか?
最近になって、再び〈贈与 Gift〉という概念が注目されるようになっています。この概念が最初に注目されるようになったのは、モースの『贈与論』という本とみていいと思います。
今、モースの贈与論に深入りする余裕はありませんが、贈与というのは単に片方がもう片方にただ与えるだけということではありません。むしろ、贈られたら、何らかのかたちでお返しをするというのが義務のように求められるという点に、モースは贈与の特徴をみました。その際、贈り(贈られ)、返礼を受ける(返礼をする)ということそれ自体がとりわけ重要になります。そういった贈り、贈られるという営みによってもたらされる内容の総体を、モースは全体的給付の体系と呼びました。
実は、前にも言及した〈意味のイノベーション〉という考え方においてもギフトという概念に光が当てられています。この贈与という事象を図式化すると、以下のように描くことができます。
図[11]5 贈与という事象

ここでのポイントは、贈り、贈られる内容も重要ではありますが、「贈る」「贈られる」という行為それ自体が価値をもたらすという点です。
この贈与というやり取りは、何がしかの共同体の結びつきであったり、共同体どうしの結びつきであったりを強めるためになされていたとも考えられます。
現代のビジネス事象をみるとき、こういった贈与概念をそのまま直ちに適用できないことは疑いをいれません。しかし、まったく当てはまらないのかというと、それも違います。たとえば、いつも事例に出している木村石鹸のシャンプー&コンディショナー「12/JU-NI」について、先日(6月30日)に木村祥一郎さんがnoteとしてまとめてらっしゃいました。
驚くべきことに、「12/JU-NI」をめぐって起こった一連のいろんな出来事は、直接的な取引でもなければ、ぱっと見、交換ですらありません。しかも、木村石鹸側から何か仕掛けたというのでもありません。もちろん、SNSを通じたコミュニケーション(←ちなみに、木村石鹸さんのレスポンスの速さは尋常ではないと思います)はあります。そのなかで「12/JU-NI」についての説明などは、もちろんありました。
もちろん、当初のクラウドファンディング(もっというと、それが始まる前)の段階から、すでに「12/JU-NI」への期待がめちゃくちゃ高かったのは事実です。とりわけ、「12/JU-NI」という価値提案が癖毛に悩んでいた人たちにとって機能的にも大きな価値をもたらすわけで、決して安価ではない「12/JU-NI」に対して、その価格に見合うだけの価値を見いだしていた点で、(1)の経済的な交換としての取引という側面はもちろん含まれています。
ただ、その取引のなかで、相手が想定以上の効用を提供してくれたり、あるいは誠実な態度で接してくれたり、意味や価値観という点で共鳴できたりした場合には、経済的な交換を超えて社会的な交換という側面が比重を増してくることもあります。
というより、もともとは社会的交換としての贈与のほうが先にあったとみるべきかもしれません。ただ、この講義では贈与と交換を対立的な概念と捉えていません。むしろ、交換の様相として贈与と取引を2つの極として位置づけ、そのあいだにおいて価値交換が現象として生じるという立場です。
以下の文献は、贈与と交換を峻別するという点で考え方を異にしますが、交易(Verkehr)という概念を上位においている点は興味深いです。この講義で「やり取り」という言葉を用いていますが、これはVerkehrの訳語として使っています。
今回の新型コロナウィルスの蔓延によって、多くの企業が厳しい状況に追い込まれたわけですが、そのなかで〈応援〉〈支援〉という概念が浮上したのも、実態としては経済的な交換でありながら、その根底に社会的な交換という側面が色濃く織り込まれていることを示していると言えます。
(3)1対1じゃない交換?:循環という姿をとる〈やり取り〉
さらに、贈与の場合は贈ってくれた相手に対する返礼というケースだけでなく、別のアクターに贈るというケースも見られます。このような場合は、本来の意味での交換とはかなり離れてくるようにも思われるでしょう。
しかし、前回お話ししたサービス・エコシステムの考え方を基礎にすると、必ずしも1対1の交換になっているわけではないってのが、すぐにイメージしてもらえるのではないかと思います。たとえば、近畿大学生協の近くに無料コピー機がありますが(撤去されてたら「ありましたが」です)、これの場合、コピーする学生の皆さんはおカネを払わなくて済みます。じゃあ、誰がそのコストを負担しているのか、コピー紙に広告があるのをみなさんご覧になったことあると思うのですが、まさに広告代によって賄われているわけです。もちろん、ここには応援や支援、贈与といった側面は皆無なので、ほぼ純粋な経済的交換ですが、ここから交換が1対1だけではないことは、簡単にイメージしてもらえると思います。そう考えると、いわゆる「恩送り」のような贈与行為も“交換”の一種と位置づけてよいでしょう。
図[11]6 玉突き循環式価値交換 / 恩送り

このように、交換は多様な姿をとってあらわれます。前節で説明した1対1の価値交換だけでなく、「玉突き循環式」価値交換も存在します。価値交換がどのような様態でおこなわれているのかを捉えることは、その企業のありようを考えるうえで、かなり重要です。なぜなら、企業と従業員の間にも価値交換関係があり、その実態は多様だからです。さらに、その企業と取引先との間の価値交換関係がどういう様態であるのかもまた重要ですし、お客さんと企業との価値交換関係もまた同様です。
つまり、〈関係の束〉としての企業を捉えるためには、価値創造過程だけでなく、企業をめぐる価値交換関係も併せて理解する必要があるわけです。そこで、続いて価値交換関係を視野に入れた企業の理論として、これまでにも採りあげてきたR.-B. シュミットの企業用具説について説明することにしましょう。
価値交換関係を視野に入れた企業の理論:企業用具説
企業や協働体系を捉える際に、いわゆるステイクホルダーとの関係性を意識的に摂り込もうとしたのは、ニックリッシュが最初です*。
* 体系的にではないですが、いわゆるステイクホルダーとの関係性が重要であることに触れた1915年の「利己主義と義務感」という論文は、その時代的特質を差し引いても興味深い内容です。
翻訳が収められている↓の文献、えらく高値になってしまってますので、図書館などで探してみてください。
ニックリッシュは、このあたりを共同体計算という枠組を提示したりもしたのですが、必ずしもその提案は十分に活かされずに終わりました**。
** ニックリッシュと似た問題意識を持ちながら、異なるアプローチを提示したのが、レーマン(Lehmann, M. R.)です。レーマンは生産性計算など、付加価値(Wertschöpfung / Value Added)概念を活用する議論を展開しました。レーマンのアプローチについては日本でも研究が数多く見られます。付加価値会計というキーワードで検索してみていただければと思います。
(1)シュミットの企業用具説の基本的な特徴
ニックリッシュのアイデアをベースにしつつ、バーナード(Barnard, C. I.)の組織経済論や、サイモン(Simon, H. A.)やサイアート(Cyert, R. M.)、マーチ(March, J. G.)の連合体理論(Coalition theory)などを包摂して、多様なステイクホルダーとの関係性において企業という存在を捉えようとしたのがシュミットなのです。
シュミットの主著は1969年から1978年にかけて刊行された『企業経済学』全3巻です。企業経済学とありますが、いわゆる企業の経済学や組織の経済学といった領域とはちょっと異なり、これはドイツにおける経営学の名称であるBetriebswirtschaftslehre(経営経済学)のことであり、Betriebのなかでも企業(Untenhemenung)に焦点を当てるという意味です。ちなみに、4冊目に掲げているのは、『企業経済学』を翻訳された海道ノブチカ先生の第1著書です。シュミットの企業用具説についての研究書であり、全3巻を1冊でみわたすことができます。
(2)企業用具説の基軸としての〈成果使用〉
シュミットは、もともとコジオール***のゼミナールで学んだ研究者で、もともとは収支計算にもとづく資金運動についての研究から出発しています。そこから、企業の自己金融をめぐる議論へと進み、成果使用(もともと利益使用 Gewinnverwendungという表現から、成果使用 Erfolgsverwendungへと変わっていますが、内容は大きく変わりません)に関心を抱きます。
*** 価値創造過程の説明の際に、3つの財ということをお話ししましたが、その考え方を提唱したのがコジオールです。
その際、成果使用として以下の3つの方法があると提唱します。
(1)分 配
(2)留 保
(3)投 資
このうち、(1)はステイクホルダーへの成果分配、(2)は流動性維持のための短期的留保、(3)は企業の維持や発展のための投資への活用をさしています。シュミットにおいて、他の研究者と少し異なっているのが、(1)だけでなく、(3)においても従業員からの貢献としての労働給付の獲得や労働給付の質の向上のための育成投資など、ステイクホルダーを意識した議論を展開している点です。この考え方は、『企業経済学』が公刊される以前の1963年には打ち出されていました。
それが、『企業経済学』というかたちで1968年以降に体系化されていったわけです。
なお、この成果使用方法を図式化すると、以下のように示すことができます。これは、コジオール学派でシュミットの企業用具説の影響を濃厚に受けているシュミーレヴィッチによって描き出されたものに、若干の加筆をしたものです。
図[11]7 シュミーレヴィッチによる価値創造モデル

(3)企業用具説における企業の捉え方
では、企業用具説とはどういう考え方なのか。
端的に言うと、「企業は、ステイクホルダーが自らの欲望や期待、利害を充たそうとするための用具である」という考え方です。
この講義で何度もお伝えしてきましたが、企業は〈関係の束〉であり、その〈関係〉によって提供されたさまざまな財 / 資源が、人間の活動(労働給付)を通じて、他者の欲望や期待を充たす可能性のある効用給付(製品や無形商品としてのサービス / サービシィーズ、コンテンツ、それらが提供する効用の総体としてのS-Dロジックの意味におけるサービス)へと転態されていくという現象が生じているわけです。この現象を、この講義では価値創造過程と呼んでいるわけです。
この価値創造過程を支えるのが、価値交換関係です。図[11]1で示した図は、その基本的なモデルです。
このモデルに即して考えれば、企業、より厳密には価値創造過程を維持・発展させていくためには、ステイクホルダーから貢献を獲得しなければなりません。当然、ステイクホルダーもそれぞれに欲望や期待、利害を抱いています。それが充たされないのに、好きこのんで貢献するなんてことは、まず考えられません。
となると、企業とステイクホルダーの両者の欲望や期待が充たされて初めて、企業の維持や発展も可能になるといえます****。
**** ニックリッシュが「経済性」という概念で、バーナードが「協働の能率」「組織経済」という概念で説明しようとしたのは、まさにこの点でした。サイモンは組織均衡という概念を提唱しましたが、これはバーナードの能率や組織経済の概念をより抽象化したものです。
ちなみに、シュミットの頃にはまだステイクホルダーという表現はほとんど使われていません。使われるとしても「利害集団」、あるいは従業員(労働者)や出資者(株主、自己資本出資者)、債権者(他人資本提供者)、顧客(消費者)などの個別の名称で呼ばれていました。このなかでも、企業の維持にとって重要な影響を及ぼす利害集団を〈企業の担い手〉と呼びました。つまり、企業の将来的な方向性を決める目標や方針=企業政策に影響を及ぼすステイクホルダーを〈企業の担い手〉と呼んだわけです。
そうなると、それぞれの企業の担い手が、企業とどのような関係性にあるのかが重要になります。これをシュミットは〈用具的関係〉と呼びました。この用具的関係こそが、ここでいう価値交換関係であるわけです。
用具的関係の具体的内容は企業によって異なりますし、同じ企業であっても時間の経過によって変化してきます。図[11]8は、コジオール門下でシュミットの影響も強く受けているドゥルーゴス(Dlugos, G.)という研究者が提示したモデルです。1980年代前半の状況を反映しているので、現時点から考えると、かなり古さを感じるのは否めません。ただ、企業の価値の流れをめぐる価値交換関係を描き出すためのフォーマットとしてみれば、十分に参考になります。
図[11]8 価値創造過程×価値交換関係(Dlugos, G.[1981])

(4)企業理念と成果活用意思決定:企業の存在意義を考える
私も時々お話をさせてもらっている(2019年度は、比較経営論の講義にもゲストでおいでくださりました)マザーハウスの副社長である山崎大祐さんが、2016年にFacebookで以下のような投稿をしてらっしゃいました。
会社の哲学は、分配にこそ宿る。
分配の視点は2つ。
今、ある資源をどう分配するか。
そして、今と未来、どちらに分配するか。
組織に関して言えば、給与テーブルと評価。
そしてスタッフの成長に対する投資。
ここに理想と哲学が現れる。
理想と哲学は明確にあるんだけどなぁ。
やっぱり先立つものがないと実現できん。
皆で理想を達成するために、もっと体力をつけなければ・・・。
2016年9月1日木曜日
これ、山崎さんが企業用具説を踏まえておっしゃられたわけではないです。ただ、考え方としては鮮やかに重なり合います。
シュミットは『企業経済学』第3巻で、企業理念や企業政策(←これらについては、ビジネス・リーダーシップについての回で説明します)は成果使用意思決定に他ならないというようなことを述べています。
企業をめぐる価値交換関係は、もちろん名目財(=おカネ)だけではありません。おカネを使わなくても、ステイクホルダーが求めている欲望や期待を充たせる場合もあります。しかし、名目財が企業にとっては血液のような資源であることも事実です。ステイクホルダーがその企業に対して抱いている欲望や期待を充たそうとする際、名目財をどのように獲得&活用していくのかという意思決定は、企業の維持や発展にとって致命的に重要(=critical)なのです。
ただ、その際にも留意したいことがあります。
それは、企業用具説に立脚するならば、その企業の存在が維持されうるのは、あくまでもステイクホルダーがその企業と用具的関係を取り結びたい、つまりステイクホルダーにとってはその企業が自らの欲望を充たしてくれるはずだという期待があるからなのです。
この考え方に依拠すれば、収益というのはあくまでも企業を維持・発展させるための手段にすぎず、さらに言えば、企業を維持・発展させるのもステイクホルダーの欲望や期待を充たすためなのです。見方を変えれば、ステイクホルダーが欲望や期待を抱かない企業は、その存在意義が問われるということなわけです。
先日(7月3日)のテレビ東京系の『カンブリア宮殿』でサイボウズが採りあげられていました。
この講義noteの最初のほうでも挙げたので再掲になりますが、サイボウズの社長である青野慶久さんが2018年に出された『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない』(PHP研究所)という本は、企業用具説に立脚して企業、会社という存在を考える手がかりになります。その本を読んだときに取り急ぎ書いたnoteがあるので、以下にリンクをはっておきます。ぜひ、本そのものを読んでみてください。
今日の〆。
今回も長文になってしまいました。ごめんなさい。
ただ、企業を〈関係の束〉として捉えるという視座は、じつは前回のサービスドミナント・ロジックをベースにして価値創造を考えることにもつながってきますし、サービスデザインにもとづいて企業を(再)構築する際にも欠かせません。
次回は、今回お話ししてきた価値交換関係をデザインする際に欠かせない〈意思疎通ポテンシャル〉とは何か、それをどうやれば構築できるのか、そして価値交換関係が価値循環としてあらわれてくるという現象をどう描き出すのかについて、顧客価値連鎖分析 / 価値循環マップ(CVCA)という考え方を紹介しつつ説明したいと思います。
ということで、ではまた次回に。
ばいちゃ!
