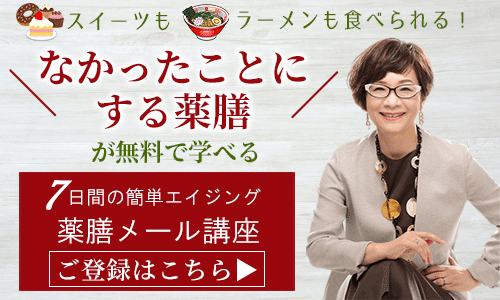冷え症の人は冷やして飲むアルコールを避けた方が良いのか?
「冷え性でお腹を壊しやすい娘さんが氷抜きや温めて飲めるお酒を選んでいるのですが、これでよいのですか?」
とご質問をいただきました。
これだけでは、娘さんの体調や体質が分からないのでハッキリ言えませんが・・・
お腹を壊しやすいのであれば、アルコールを控えた方が良いのです。
ただ、昔から酒は百薬の長と言われますよね。
アルコールを健康的に飲むための知識を薬膳の視点から解説します。
なぜ冷たいものを避けた方が良いのかと、食材の温熱性(飲食すると体を温める性質)と寒涼性(飲食すると体にこもった熱を冷ます)を混同しがちなので、まずそこから説明しますね。
冷たいものを避けると良い理由
〇〇サワーや〇〇ハイ、冷えたビールなどは暑い時期には喉越し良くて美味しいアルコールですよね。

空腹で飲むとアルコールの吸収が良くなってしまうだけでなく、消化器系に当たる「脾」や「胃」を冷やしてしまうため、これから食べる食事の消化吸収力が落ちるのです。
胃の消化液も薄まるので、アルコールを飲んだ翌日はお腹を下す人もいます。
アルコールに限らず、かき氷、アイス、冷たい飲み物は「脾」と「胃」の働きを弱らせ、要らない水分(どぶの水)を溜め込むようになります。
本来なら、尿や便として排泄されるべきものが、飲んでいる最中は利尿されて出ているとしても、その後には弱った「脾」や「胃」が残されているのです。
「脾」も「胃」も食事を続ける限り休むことなく動き続けますから、弱った状態で消化活動をすることになります。
そのため、必要な栄養は吸収されにくく要らない水分を溜めやすくなるのです。
お腹を壊しやすい人は、アルコールに限らず冷たいものは控えた方が良いですね。
お腹を下さない人でも要らない水分は溜まるので、むくみや肥満の原因になる恐れがあります。
もともとお腹の弱い人がアルコールを飲むとどうなるか
キンキンに冷えたビールなどでも、徐々に体温で温められます。
これは物理的な温度の問題です。
これとは別で、体を温める性質の話をすると、アルコールは温熱性です。
ウオッカなどのアルコール度数の高いものになると大熱性と言われ、強く体を温めます。
冬が極寒の地で飲まれるウオッカ、雪山で遭難者に飲ませるブランデーなどはこの温める性質を利用したものですね。
胃腸が弱い人は、強いアルコールにより胃腸の粘膜を刺激して、びらんのようになることもあるので控えめにした方がよいです。
胃腸が弱くなくても、アルコールをよく飲む人は要らない水分が溜まりやすく、それがアルコールの温める性質で熱化されるのため、どぶの水からヘドロになりやすいのです。
粘度が増すため、体から出しにくくなります。
これが血管の内側にこびりつけば、コレステロールですし、血管の太さを様くするため高血圧の原因にもなります。
アルコールはやっぱり悪なのか?
ここまで書くと、アルコールを楽しんでいる方を全部敵にしてしまいそうなので、アルコールの良い点を薬膳の視点から書きますね。
冷やして飲まないことを前提にしています。
〇冷えた胃を温める
〇体を温め寒気を飛ばす
〇血行を促す
〇焼酎には沈痛作用がある
〇精神の安定
〇リラックス効果
このようなメリットがあります。
これらは適量を冷やさずに飲んだ時のものです。
酒には発散効果や気持ちの落ち込みなどを上に上げる効果もあります。
ストレスが溜まっているからと量を越えて飲みすぎることがなければ、緊張を緩める効果もあると言うことですね。

血行が良くない人や冷え性の人は、アミノ酸の多い紹興酒や薬酒を毎日少し飲むと、気を巡らせ血流の改善にもなるのでおすすめです。
イメージで言うと養〇酒やお正月のお屠蘇のような感じですね。
娘さんは冷え性とのことなので、今までやって来られたことは良かったと思います。
できればサワーや〇〇ハイのようなものより、冷やさず飲む日本酒や赤ワインなどをほどほどに飲むと良いですね。
しかも、食事をしながら飲むようにすると飲み過ぎも防げるかと思いますj。
アルコールは冷やして飲んでも結果的に体を温める熱源となります。
そのため、火照り感のある高血圧気味の人、肝臓や心臓の疾患や糖尿病、甲状腺機能亢進症のある場合は悪化させる可能性があるため止めておいた方が良いでしょう。
アルコールの中でもビールは、低アルコールで原料のホップは利尿作用があります。少量なら食欲を増し脳に刺激を与える効果も言われています。
いずれにしても、適量なら百薬の長、度を越せば「毒」になると考えて上手にアルコールを楽しみましょう。
「スイーツもラーメンも食べられる!なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座」では、アルコール飲む時の「なかったことにする薬膳」も説明しています。
【関連記事】
なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。