
目的に到達する議論の進め方
事前準備が議論の質と議論時間を短縮する
議論課題の棚卸と優先順位を決めておきましょう
会議に参加する前に、自分の課題を棚卸して3つに分類して下さい。
1.拘りたいこと、譲れないこと
2.拘らなくていいこと、譲れること
3.どちらでもいいこと
そしてその課題に優先順位を付けて分類しておくことで議論すべき課題の順序と論点が明確になります。

課題が多い場合は4つ程度のフェーズに分けましょう
優先度の高い課題をクリアしながら次の課題へ進むようにしてください。
会議を進めるうえで、優先度の高い課題の議論から始めることです。時には、それが議論開始する前提条件だったりします。書面で明確に回答を得てから先に進めてください。
大きな議題では、4つ程度のフェーズ(課題の集まり)に分けて進めてください。もしクリアできない課題が1つでもあるとその時点で議論打ち切りすることができ、その見通しも予想できることから、参加者が多い会議などでは大変有効です。

会議開催の目的を大枠で合意しておきましょう
開催目的が、説明なのか、アイディア出し(相談|提案)、決める(決議|方向性)なのか、参加者全員が理解することが大切です。もし1つの会議の中に、説明と相談、決定の要素が含まれる場合は、説明、相談|提案、決定|決議|方向性の各フェーズで整理をしながら進めてください。但しこれは難易度が高い進行方法で、一人ひとりの理解度を一定に保つのが難しく、最悪は誤解して終えてしまうことあります。できれば一つの目的で一つの会議を開催するのが良いと思います。

要求していること、できることを整理して説明できるように
最近の会議時間は、30分や45分が多くなってきています。この時間内に必須参加者招集して議論できる議題は1つです。大事なのは双方の相手が「要求していること」と「できること」を整理して説明できるようになっていなければならないことです。この「要求していること」と「できること」の整理は、会議を開催する必要はなく各自で準備できます。
この準備ができていると、論点が明確で資料も簡素化されるようになり短い会議時間で済んでしまいます。
必須の情報はテンプレートを基に要求しよう
優先順位の高い課題への回答は、「必要な情報はこれで、こう書いて下さい」とテンプレートを渡して要求すると意図した質と量で返ってくることが多いです。悪い例は、回答になる頁が数十ページになったり、頁が飛んでいたり、結局のところ回答頁はどこなのか分からなかったりします。このようなことを避けるためにもテンプレートを用意して回答を得るようにしてください。
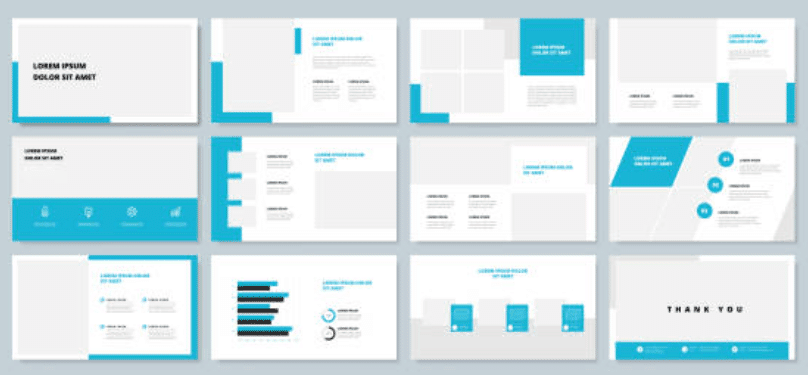
次の会議までの期間は、理解のゆがみを補正する期間です
正確に理解してくれていると思ってても、電話一本して確認するぐらいの不安感を持っていた方がいいかもしれません。その本人も会議中は理解したつもりでも、次の日には不安になっていたりします。重要な議論や行き違いが多い相手とは、短い時間でいいのでコミュニケーションをとることが本番の会議に活きてきます。

会議資料は3日前までに入手し関係者で議論した上で会議に臨みましょう
その資料作成の目的を前提にして、その目的が達成できている資料なのか、こちらの意図が正確に通じているのか、事前確認が必要です。そしてその確認をしている際に出されたアイディアや論点、議事の方向性などを整理して関係者と共有しておくことです。もし時間が許せばそのメモして先方へ伝えると会議の論点が共有され必要な情報を得られ易くなります。
一方、読む資料になっている場合や、1つのことを数頁にわたって説明されている場合は要注意です。恐らく解釈なしでは読み続けることができないと思います。このような場合は、会議用にサマリー版を要求し、テンプレートを渡して転記してもらうなど工夫が必要です。
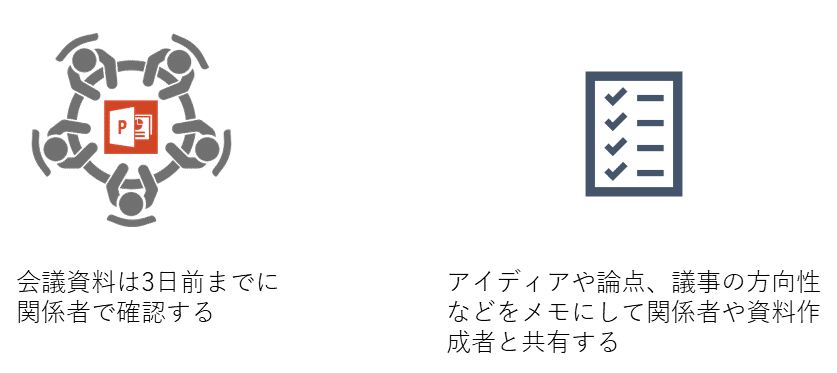
資料は事前に配布する
事前に作成した資料を配布し、参加者全員に目を通しておいてもらうことです。会議の時に情報共有するために「説明」も同時進行させてしまうと理解するのが目的になり、更に時間を費やすことになり、結論を出す時間が足りなくなります。前提知識や議題を前もって共有してからスタートすることです。
事前共有とすり合わせ 根回しをする
事前にキーパーソン同士が目的、資料の理解などを共有した上で議論に入ることで、目的達成に近づき会議時間を削減することができます。 これは社内に限ったことではなく、社外の方が参加する場合などはたいへん有効です。
例えば、お互いよく使う言葉の意味が違う場合や、聞きたい求めていることなどが正確に伝わっていないことがあります。少し違和感ある時は、必ず「私はこの様な意味で話していますが理解していますか」などと聞き正すことです。
また常に反論を好む人や、会議の方向性を壊してしまうタイプの人には、事前に話をしておきます。 ここで重要となるのは戦うのではなく、助けてほしいとの姿勢を見せることです。

会議開始
質問は YES NO クエスチョンで
質問する際に誤解なく伝えようとして丁寧に話そうとしますが、議論中はそれが逆効果になることがあります。質問の意図がぼやけた表現だと返事もぼけてしまうということです。丁寧に質問しようとするあまり枝葉の情報を混在させてしまい、それを受けた回答者も枝葉の情報で加工して答えようとします。質問は「〇〇ですか」これぐらいシンプルで発しましょう。もし分からなければ質問があるのでその時に枝葉の情報を加えて丁寧に解説してあげるぐらいで良いです。

会議中に発した「やります」「検討します」「QA」は共有する
議論中によくある会話。「やります」「検討します」「なぜ〇〇なんですか|それは〇〇だからです」などの場面は、意外に重要な話題だったりしています。次回会議時の宿題だったり、この後に続く説明の前提だったりします。このやり取りは、正確にメモ(Excelなどへベタ打ち)を興して共有して下さい。戻り議論が少なくなる効果があります。

会議の終了前に、本日の理解と宿題を参加者全員で共有する
会議終了後に、決定や合意、課題などの取りまとめ、会議参加者へ共有して下さい。その書式を読んでいると言葉や表現の違いからの温度感が感じられるようになり、先方の理解度が分かるようになります。こうすることで次回会議の必要性や論点整理に活用でき、会議冒頭に振り返りを繰り返すことで戻り議論が少なくなります。
司会進行を自分でやることも考えてみては
他社参加者に委ねると予定通りの議題をクリアできないことがあります。議題に応じて時間の強弱をつけられる立場になった方がいいです。特に議論してもらう時間、意見をまとめていく時間、決議する時間などの配分を気にしながら、合意を取りながら進めていくとスムーズに進められます。
また時間通りにアジェンダを進めていくのは重要ですが、きちんと1つずつ結論が出てから次のアジェンダに移るようにしてください。関係性の強い議題が他にあると順番を飛び越えて議論してしまったりしますが、会議参加者同士で「結論はどっちだったか?」という話になってしまうようではいけません。必ず議題が終わるごとに結論を伝えてからアジェンダを変えるようにしましょう。

なかなか結論に到達しない理由
「想像」を「事実」と思い込み議論する
不確かな情報や、断片的な情報を元に話しだしてしまう会議のことです。決裁者や本人に確かめていない想像話しや、確認が取れていない情報を前提として、会議を進行することがないようにしましょう。特に、ネガティブな内容は参加者の士気を下げ、議論が低迷する要因になりやすいです。

「できないこと」と「したくないこと」を混合してしまう
議論中の「難しいです」がそのどちらであるか、常に注意する必要があります。
「できないこと」は、その力量、技術的課題やその解決にかける工数、予算といった客観的な制約のもとに説明が必要です。
「したくないこと」は、その担当者なのか、上司なのか、組織なのか、その判断を下す人物や組織を特定しておくことです。今後の議論を進める中で進捗予想をする時に役立ちます。

その場で決められないことを延々と話しこんでしまう
その議題はこの参加者で決めることなのか、この視点も必要です。
まとまらない議論については、「上席者参加できめられるべき内容」なのか、それとも「追加で情報や意見が必要」のどちらかが該当します。

ある電算機生産会社の規則の例
会議時間は45分を基本に。短時間会議は25分で。
会議参加者には事前に「会議の目的」「時間配分」「必要な成果」を示す
会議出席者は必須の者のみに厳選
会議の主催者は冒頭に2を再確認
資料は1議題1枚。事前に配布
会議終了時には結論、宿題を確認。決定事項の担当も明確に。
議事録は会議中に作成。遅くとも翌日まで
矢印株式会社は好きなことを仕事にしています
矢印株式会社のサービス一覧です。
Executive Knowledge
経営財務マーケティングに関する記事を書いています。
5G Yajirushi Video Crew Service
ライブ配信や映像制作、写真撮影の記事を書いています。
補助金申請TIPS
小規模事業者向けの補助金申請にまつわる記事を書いています。
--- yajirushi owned media ---
note Twitter
Instagram Facebook YouTube
矢印株式会社のご説明
経営者の職務経歴 LinkedIn
矢印株式会社 Contact|お問い合わせ
LINEから気軽に Contact|LINE WORKS
