
【塾生インタビュー企画 私たちの軸足#11】~鋭い議論のための「捉え方」
このnoteは、薮中塾生の普段の活動や専門性を発信する企画の第11弾です。
この記事では、編集部の柴田紗良が担当します!🌸
今回私がインタビューさせていただいたのは、薮中塾6期で鋭い視点から議論にスパイスを加えてくれていた、佐田宗太郎(さだそうたろう)さん。
佐田さんは現在京都大学大学院の博士課程(5年一貫の博士課程プログラムの4年目)で、ネットワーク科学などを用いて国際的な問題を解析しています。
薮中塾での活動のほかに、NPO法人Mielkaのラボ事業部の事業部長を勤めたり、株式会社talikiにて社会起業家育成プログラムに参画したり、高校で高校生に研究指導を行ったりなど、とても精力的に活動されています。
今回佐田さんの軸足である、「議論の仕方」、そして物事の「捉え方」についてお聞きしました。
抽象的にも聞こえる二つの概念―佐田さんはどのような考えを持ってらっしゃるのでしょうか。

(1年ほど前、佐田さんが企画した「社会問題」を語るBarで男性の性被害について扱っている写真。立っているのが佐田さん)
議論の仕方
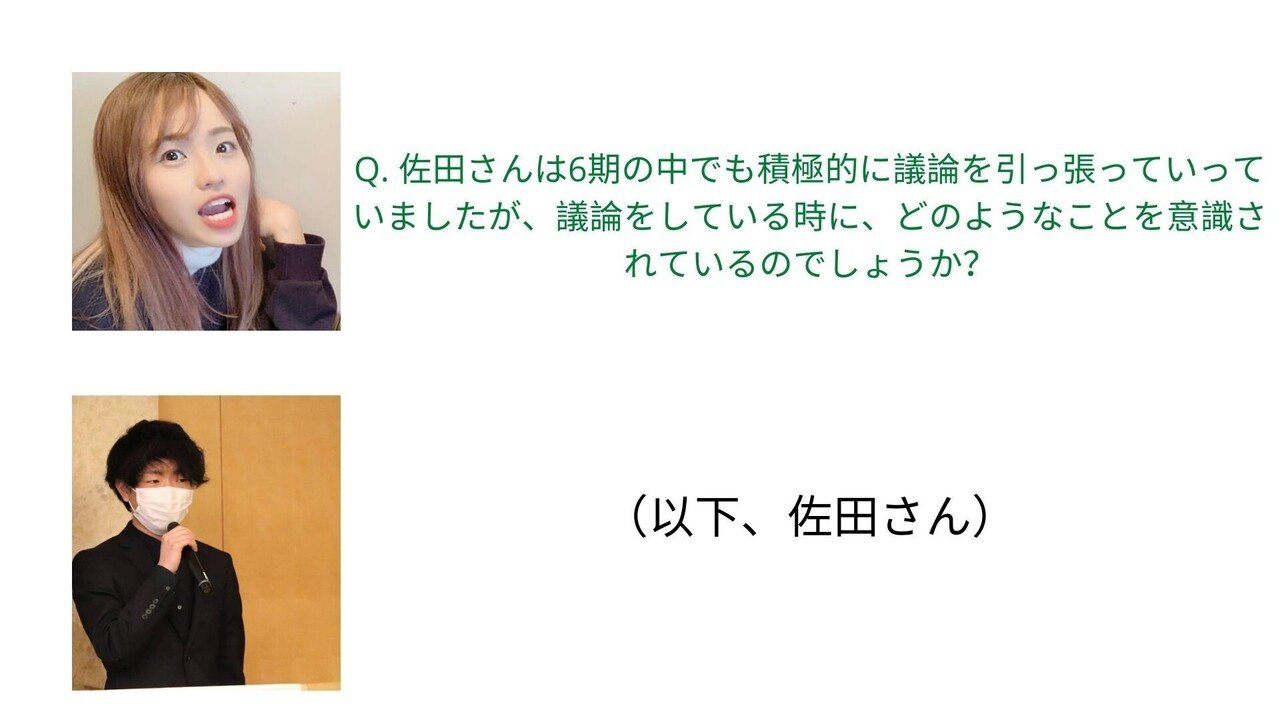
まずは「話す必要があるか?」、「自分が話すことによってこの議論に貢献しているのか?」などの視点から俯瞰的に議論をみて、自分が議論に加わるタイミングを図ります。
自分が話す行為は他人の時間を奪う行為でもあるので、自分が議論に参加する必要はまったくないな、改めて言う必要がないな、という時は発言しません。
自分が議論に加わる時は一度話題に上がったのに、忘れ去れてしまっているポイント、またまだ議論に出ていないポイントがある時などです。また、ある程度成熟している議論だったら早めに議論に参加します。(薮中塾では私より若いメンバー、特に学部生が多かったので、早めに議論に入ると喋らなくなる人が多くなることもあり、このようなタイミング設定になっていました。)
その一方で、議論が全然進まないな、と思ったら結局今までの議論はどういう意味でやっていたのか?というメタな質問で介入することもありました。
議論において、話すタイミング、そして発言する内容はとても重要です。「自分が発言したい」という気持ちが先行して行われる議論は「喋って消費する」だけの時間になってしまい、得られることはあまりありません。
あくまでも、「議論が終わった時に、議論参加者に何か新しい気付きがある」ことが最も大切なので、事前に設定された場の目的や参加者の目的に沿って進めることを意識します。
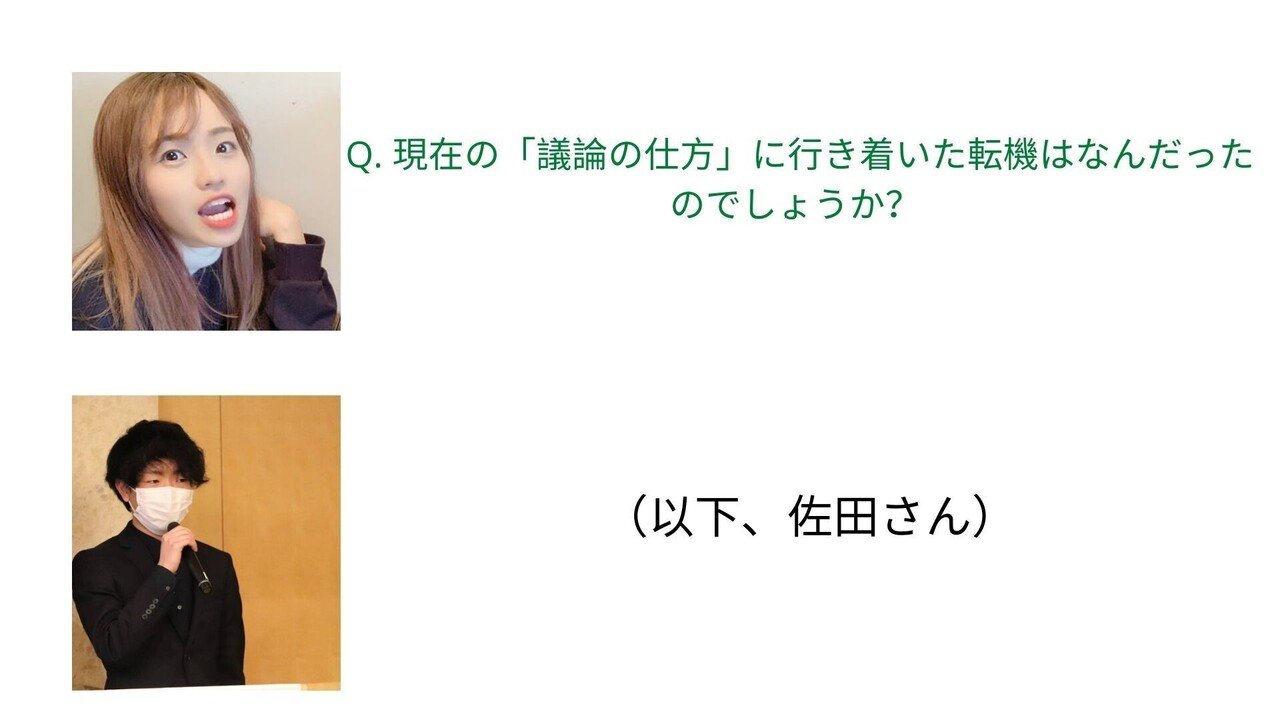
そもそも高校生までは議論することに興味すらありませんでした。
しかし、自分の中で「この世界とは何か?」、「生まれた意味とは?」、「死ぬまでに何をするべきなのか?」などの答えのない自問を小さい頃から続けていました。逆に言ってしまえば、そういった生の意味に関係のないように感じられる、現実的(問題として設定された)議論に関心がなかったのだと思います。ですが、その自問自答の延長線上に、社会問題などに対する議論の必要性があることを理解することができ、今に至ります。といっても最近のこと(学部4年頃)なのですが。
元々、おかしい、意味がわからない、と思うところは放っておかない性格で、すぐ疑問に思ったことは相手に質問したり、自分で調べたりしています。その時すぐに答えが見つからずとも、一度躓いたことは忘れません。すぐに見つかった答えが正しいとは限らないことも、念頭に置いています。
また、普段の会話でも、理解できないことが出てきたら、自分の理解不足なのか、それとも相手の伝達不足なのか?ということを意識しています。相手が理解できていないことについてその人に訊いても自分の理解には繋がりませんから、訊く相手を選ぶことは重要です(訊くことによって相手に気づきを与えられるという意味では訊く行為自体が重要ですが)。聞く相手を間違って、誤った理解に固着してしまう場合もあります。その最たる例が、不適切な専門家への取材に基づいた情報を信じてしまうことになると思います。
質問への回答に戻ると、私が簡単な論理でしか物事を理解できないこともあり、自分でも理解できるように論理を組み立てた結果、自然とそのような議論の方法に落ち着きました。誰かから教わったとか勉強したとかはないです。
謙虚さと自信の両立
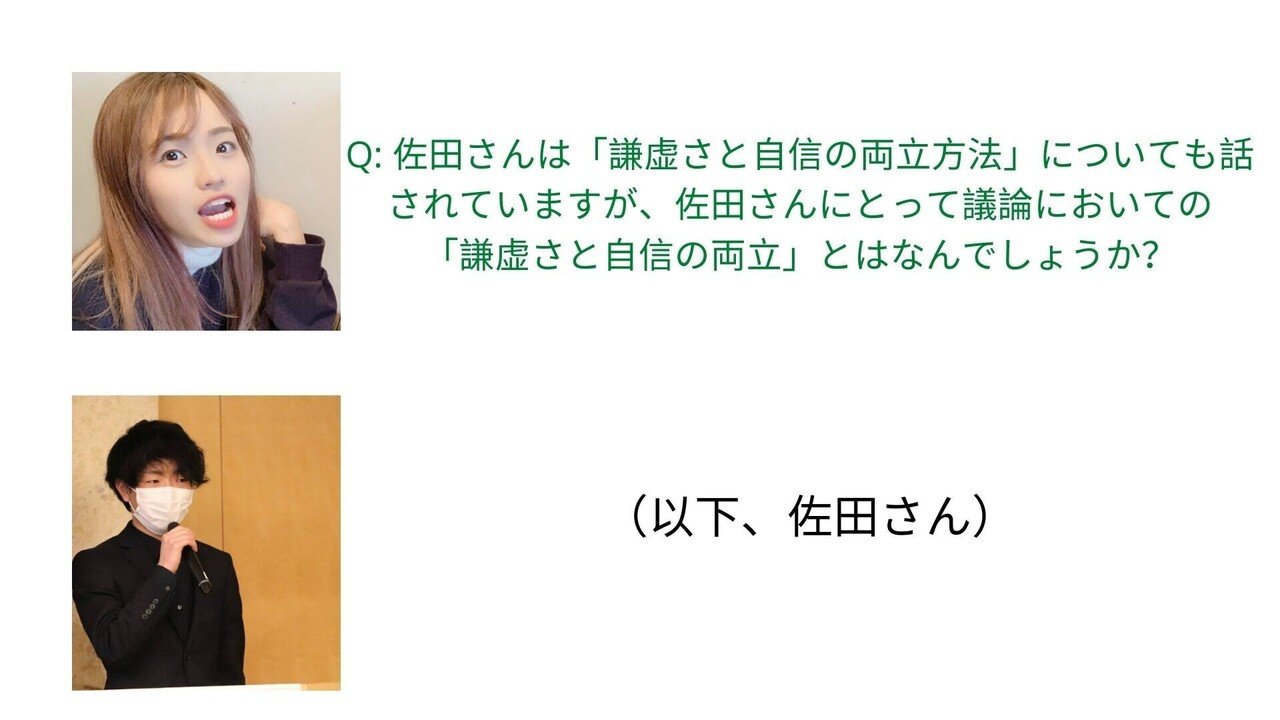
これは、多くの場で見かけますが、良い発言をしているのに自信無さそうな人、全く場に貢献していない発言をしているのに自信満々な人、という極端な人が議論で発生しやすい問題についての問いですね。
私は、そもそも自分自身の存在に価値はない(少なくとも他者にとっての私の価値は非常に小さい)、という前提で議論を行います。
すると、自分が発言している内容にどれだけの論拠があるか、だけが大切になります。これが議論において自信に繋がる部分です。
自信持って議論している割に、根拠がてんでないというのは最悪です。自分に自信を持ってるだけの薄い議論はよくないです。そういう意味では謙虚さが必要ということになります。
また、どの人の意見をきくにしても、「間違っている」という前提で聞いています。それがあるからこそ、自身が発言する時に証拠を提示しますし、相手の論拠を大切にします。
自分を盲信せず、それどころか自分にそれほど価値はないと思い込んで議論することが、謙虚でありつつ、自信も持てる確かな議論に繋がると思います。これが私が考える「議論における謙虚さと自信の両立方法」です。
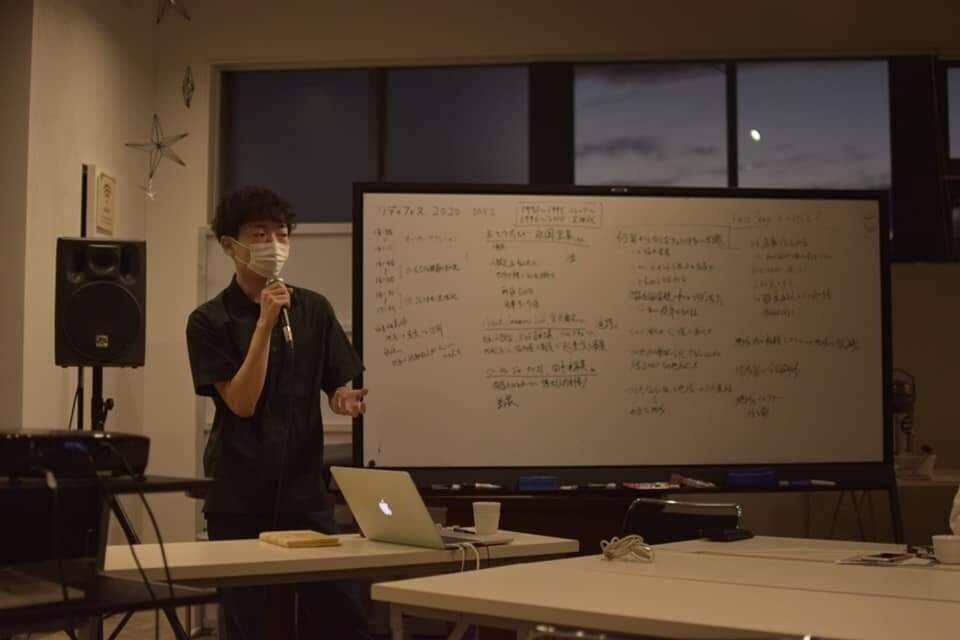
(リディフェス2020のパブリックビューイングにて)
あえて決定しない「捉え方」
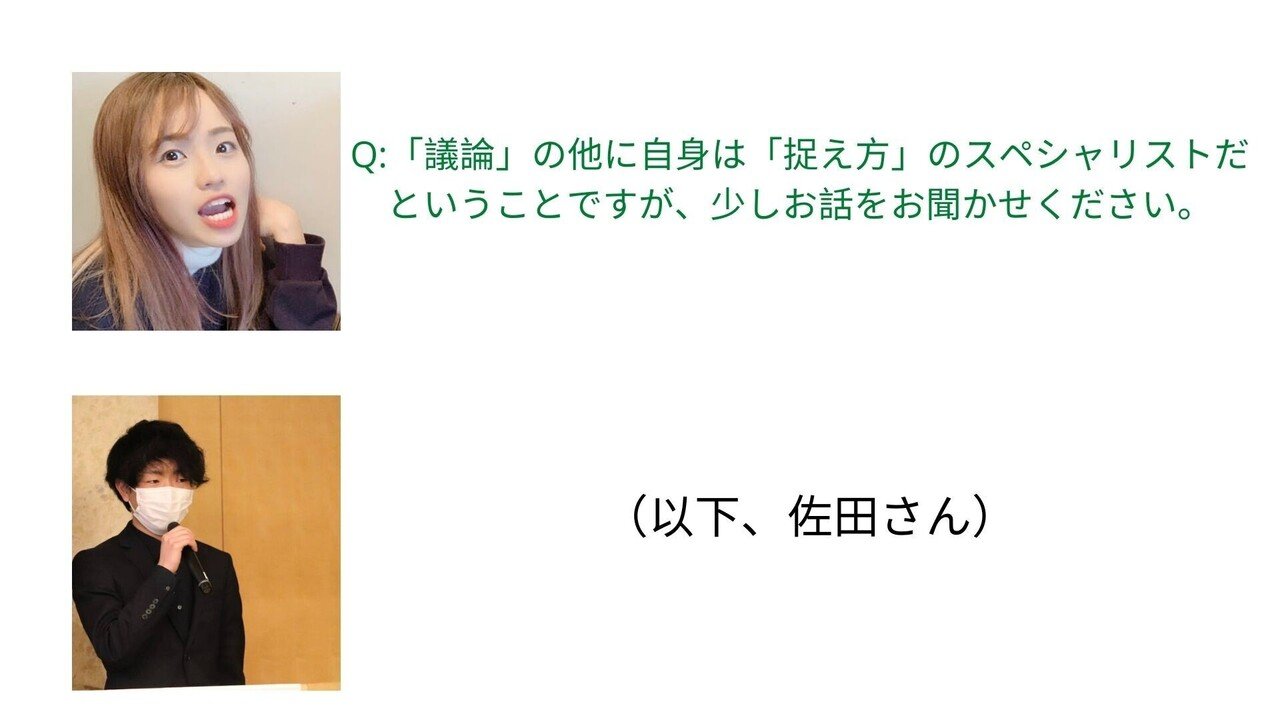
誘導尋問に近いですが。笑 敢えて言うなら捉え方には自信があるということでした。
大切なのは、「決定しない」ことだと思っています。要するに、一つの発言、物事、行動に対して、色んな解釈がある、ということを忘れずに「捉える」ことです。
言葉を「絶対」だとは思っていなくて、言葉は伝えるための手段でしかないと思っています。そのため、非言語の部分(例えば表情や仕草など)やそれまでの共有された文脈から、「どのような思い・意見を伝えようとその言葉を選んだのか」を汲み取ることが、聞き手に求められるコミュニケーションだと思っています。
実際、脳内で考えてることを言葉にしてみると、どんなに慎重に言葉を紡いでも、相手の反応から「あれ、違うな?」って思うこともありますよね。その結果、家族や友達から自分の発言が誤解されることもあると思います。
日常のコミュニケーションでは、自分の気持ちと言葉を合わせる「チューニング」、相手の認識と自分の言葉をあわせる「チューニング」がうまくされていないことがよくあります。これは自分も、相手もです。
相手が発した言葉で傷つく人も多いと思うのですが、相手がその言葉を使おう、と思った理由は実際私たちにはわかりません。それを自分が「解釈して」受け取っていることに自覚する必要があります。
議論においても、「捉え方に囚われない」ということが大切な「捉え方」ではないでしょうか。
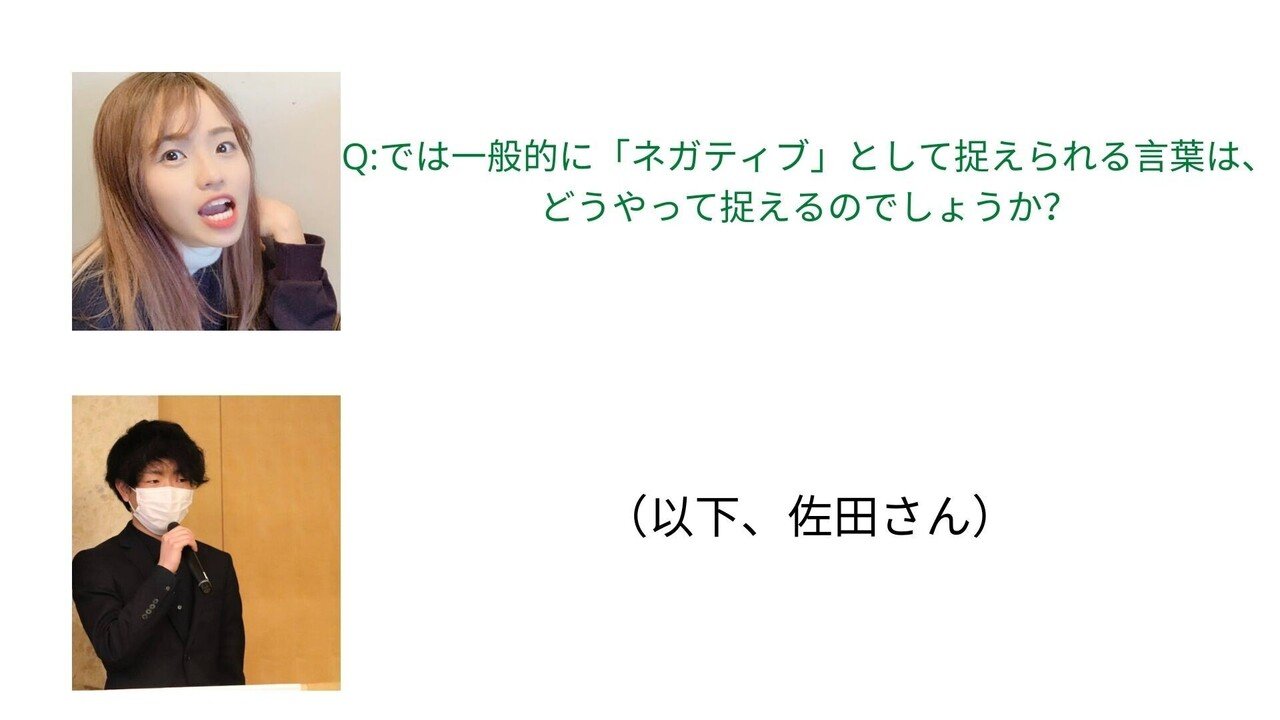
私は実はとてもネガティブな思考をしていて、誰よりもネガティブな事を想定しているので、ネガティブとされる言葉にもそこまで深くは傷つきません。
自分の中のネガティブよりは、大抵の言葉は相対的にポジティブだからです。
それよりも、相手はなぜ自分にそういった「ネガティブ」な言葉を発しようと思ったのか、について考えます。その人は何かに追い込まれているのか?相手はその言葉を通して、自分に何を伝えようとしたのか?何がその人にその発言をさせたのか?など、考えを巡らせます。
相手の言葉を自分なりに考えることで得られることはそんなにないのではないでしょうか。言葉が相手から発せられた以上、相手の文脈において考える必要があるので、相手の立場にたって考えるのが良いと思います。
そうは言っても、言われた瞬間はその「言葉」しか捉えられず、傷つくこともあるわけですが、意識的に「言葉」と「思い」は切り分けて考えるようにしています。
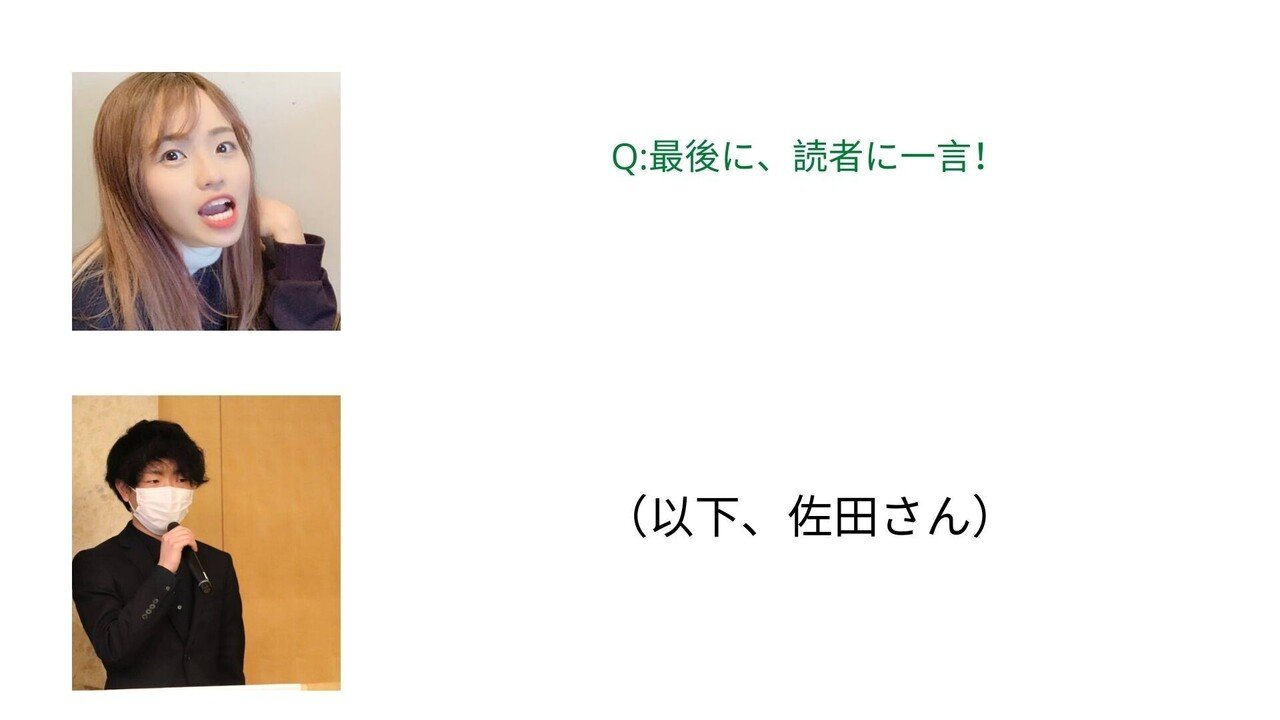
最近考えている事は、資本主義社会にいると、「周りが合わせてくれる」環境や、「趣味を持つ」などの行為が、自身のステータスにつながっていくことの不気味さです。
「コミュニティに属する」こともそうであって、「好きなものが一致する」から「コミュニティ」が成り立ったり、逆に嫌いなものが一致するという事も、コミュニケーションに繋がる共通事項となります。
なので「好き」「嫌い」が増えるということが社会的価値に繋がります。そして資本主義社会においては、好き嫌いの増加が新たなマーケットや差別化の余地を与え、資本を増やすことにつながるために歓迎されます。
このインセンティブによって、逆にコミュニティをコントロールされているとも言えるのではないでしょうか。
私たちはいつの間にか、様々な事柄を好き嫌いで判断することに依存していて、その好き嫌いに合う/合わせられる人がコミュニティを築き、合わない/合わせない人とは距離を置きます。これでは好き嫌いという表面的に誘発された性向によって間接的に交遊範囲が限定され、現在の自分が(予測不可能に)成長する範囲が狭められているようにも感じます。
薮中塾もコミュニティの一つですよね。
自分が今持っている「趣味」、「コミュニティ」を仮に全て失った時に、生きていけるのか?そのときどのような生活になるか?それらに依存しすぎていないか?コミュニティに属している安心に自惚れ、怠けていないか?ということ少しでも問い直し、自分が自分自身で悩み抜いた一歩をどれだけ歩めているか、振り返ることが大切だと思っています。私が変に考えすぎてるだけかもしれませんが、思考実験だと思って、習慣的に振り返ってみてください。
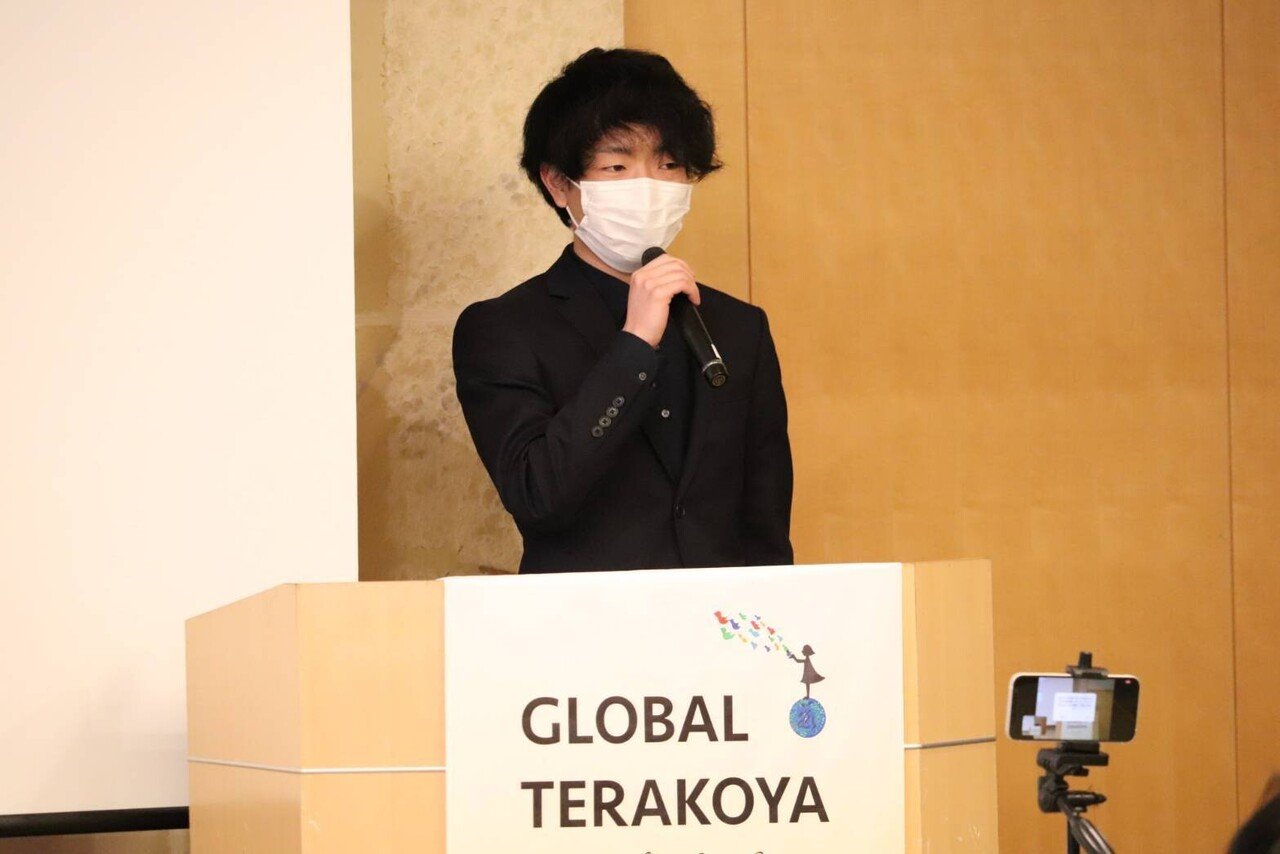
(6期卒塾式での佐田さん)
【インタビュイー】佐田宗太郎(さだそうたろう)
Twitter: https://twitter.com/sadasium
【聞き手・ライター】柴田紗良(しばたさら)
第11回インタビュー企画では、「捉え方」や「議論の仕方」を深く熟知してらっしゃる、佐田さんにお話を聞きました。
私自身佐田さんとインタビューを通して「対話」することによって、考えさせられること、腑に落ちることが沢山あり、とても勉強になりました。早く佐田さんのインタビューを公開したくて、この記事を書いてる最中もワクワクしました☺️
それでは次回もお楽しみに!
