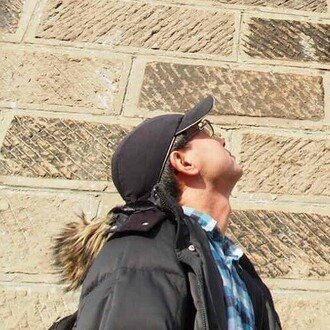沖縄県北大東島の見所紹介①
前回は北大東空港を紹介しました。今回から沖縄県北大東島の名所です。前回でも少し触れた沖縄県最東端の碑など、海岸沿いの名所から始めます。
1.沖縄海と沖縄県最東端の碑

北大東島も南大東島と同様、海岸線は崖ばかりです。崖ばかりの島東部に建設した海水浴場が「沖縄海」。写真は干潮から満潮に向かう時ですが、干潮時に潮だまりで海水浴が出来る場所です。

沖縄海前トイレそばにあるのが「沖縄県最東端の碑」。海側を向いて撮影。

北大東島に到着した日の夕方はこんな姿に。

碑の北側から撮影。でも碑が建つ場所は本当の最東端ではありません。

沖縄海・沖縄県最東端の碑から真黒岬までの海岸は崖が険しく、島の内側の良い場所はギリギリまで北大東空港の滑走路に使ったため、本当の最東端は北大東空港関係者しか行けないです。しかも沖縄海・沖縄県最東端の碑へは滑走路の南側にある道路(舗装されています)から行くしかありません。
2.台風岩

島の南、海が見える道路沿いにあるのが「台風岩」。2009年10月に大東島地方を襲った台風18号は北大東島で最大瞬間風速58.9m/sにもなりました。暴風により横幅約4.6m高さ約3.3mもの巨大な岩が吹き飛ばされて現在地にあります。

台風岩と向こうに見える南大東島をセットに撮影。

台風岩から南大東島を撮影。遠くからみると平べったく見えるのは北大東島も南大東島も同じですが、近づくと荒々しい崖ばかりです。
3.江崎港

沖縄海から島の南へ向かって、海岸線沿いを進むと現れるのが島南部の江崎港。台風岩から近いです。ここからの南大東島もおすすめ。

到着した日の夕方はゲートが開いていたので、岸壁に近寄って撮影しました。
4.北大東漁港

正確には南大東漁港(北大東地区)といいますが、港入口にある碑は「北大東漁港」。江崎港から少し西に進んだ島の南西部にあります。南大東島にある漁港と同様、大規模な岩盤掘り込み工事を行って完成しました。平成20年(2008年)に着工し、平成31年(2019年)2月に開港したばかりです。開港式典には宮腰沖縄担当大臣、玉城デニー知事も参加しました。

漁港が見渡せる高台から見ると、とんでもない大工事だった事がうかがえます。完成により、これまで島民の小型漁船を毎回クレーンで降ろしたり上げたりしなければならなかった手間が大幅に省け、漁業振興が期待されます。
5.上陸公園

島西部にある上陸公園は、島を開拓した玉置半右衛門率いる玉置商会の開拓団が明治36年(1903年)、最初に上陸した場所。公園内には開拓百周年記念碑があります。

海岸へ降りる事も出来ます。行った日は晴れ、航空会社・琉球エアーコミューター(RAC)で配られる写真はがきと同じ青い海の景色がありました。開拓当時は、サトウキビの出荷港としても使われ、海へ下る坂道には、線路が敷かれていたとの事です。

上陸公園からも南大東島が見えました。
6.西港公園

島西部にある西港には公園があります。

緑地が整備されているので、旅行時の休憩に最適でしょう。

西港公園には正式に日本の領土とされた明治18年(1885年)に初めて建てられた国標があります。現在の国標は3代目で平成28年(2016年)に建立。

陸側より撮影。

夕日がきれいな場所でもあります。

西港公園からは西港の不定期船が主に使う岸壁が見えます。岸壁付近から公園まで階段もありますが、それなりの坂で意外と疲れました。

西港公園から廃墟となった燐鉱石貯蔵庫跡が見えます。
7.燐鉱石貯蔵庫跡と西港

戦前北大東島ではリンが取れました。リン鉱石を貯蔵していた跡です。国指定史跡ですが、老朽化が進んで修復工事の足場がありました。

反対側から撮影。立入禁止柵はなく、中に入ろうと思えば入れますが、危険だったので止めました。

西港への入口。この下に燐鉱石貯蔵庫があります。

こちらのレンガ建物は、リン鉱石を乾かす施設でした。

煙突の跡と思われます。

近くの高台には戦前リン鉱石を採掘時に造られた石積みの壁があります。
8.魚市場

西港そばには魚市場があります。コンクリートの建物奥にある石造りの建物は、りんこう館といい、燐鉱事業の拠点となった施設の跡です。

近くには燐鉱事業の拠点となった、屋根が全く無くなった建物跡も。
9.北港

北大東島に到着する不定期船「だいとう」は主に西港岸壁を使用しますが、海況によっては南部の江崎港や北部の北港を使用する場合があります。

北港にはピラミッドが3か所もあります。実はこれ、先程触れた北大東漁港工事で発生した岩石を積み上げたもの。今回は往復飛行機で行ったので見えませんが、北港付近の海から眺めるときれいだと思います。
ここまでご覧くださり、ありがとうございました。次回は北大東島内陸部の名所を紹介します。
いいなと思ったら応援しよう!