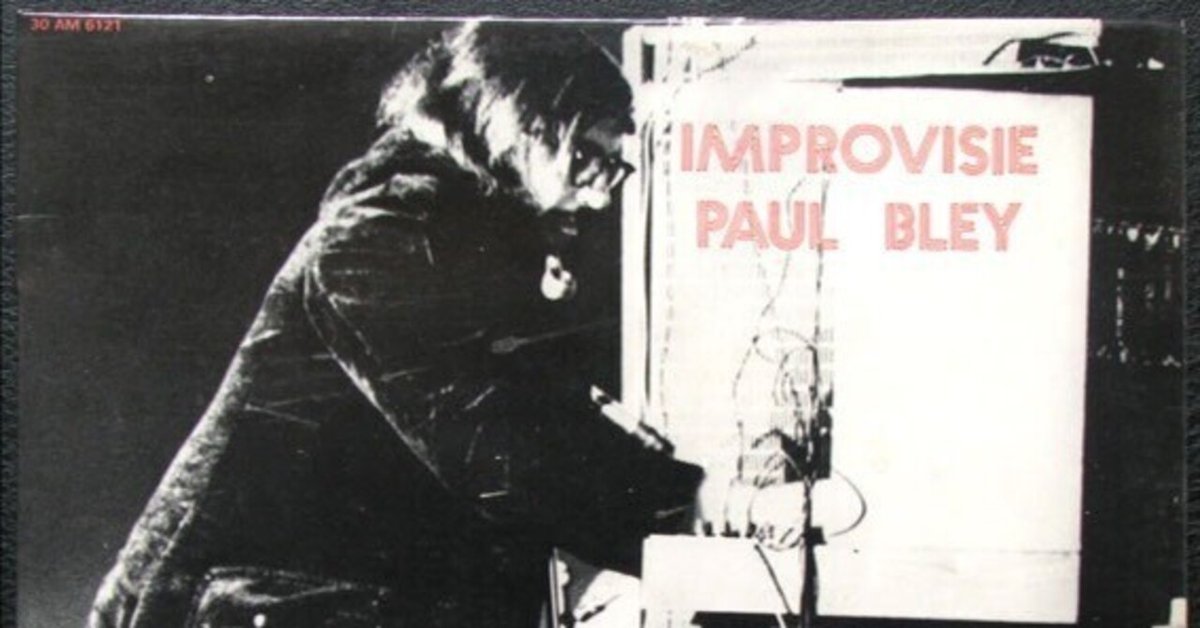
ポール・ブレイ 「インプロバイズィ」 Paul Bley – Improvisie
Tracklist
A Improvisie 16:05 Written-By – Annette Peacock, Han Bennink, Paul Bley
B Touching 23:45 Written-By – Annette Peacock
Credit
Percussion – Han Bennink
Synthesizer – Paul Bley
Voice, Piano, Electric Piano – Annette Peacock
年末にたまたま手に入ったので覚書程度。
ポール・ブレイのリーダー作となっているが、これが誰のリーダー・アルバムなのか?というと少なくとも"the Bley-Peacock Synthesizer Show"が妥当なところだ。またこのパフォーマンスに関してはハン・ベニンクの参加がとても大きい。であるからシンセサイザー・ショー+ベニンクという組み合わせでどのようなセッションになっているのか?が期待される聴きどころと思う。
モーグ・シンセサイザーに関してはもともとアネット・ピーコックが熱心で、例にもれず最初「スイッチ・オン・バッハ」を聴いて興味を持ったらしい。アネットが言うにはポール・ブレイはシンセに対してそれほどでもなかったようなのだが、彼女が説得してようやく乗り気になり、二人でモーグに会いに行き「シリアスな音楽をやるから」ということで、プロトタイプを会ったその日に貰い受けたとのこと。その時点でムーグの使われ方はCMのジングルだったり「スイッチ・オン・バッハ」だったり程度であったこともあって、モーグ博士も説得されたらしい。このあたりの経緯や初期のモーグに関しての苦労話などは以下のインタビューに詳しい。
ライナー・ノーツにあるブレイのコメントによると、彼はシンセサイザーと出会い「またアマチュアから始めることにした」とのこと。二人はシンセサイザーを譲り受けたものの、使い方が分かるわけでもなく、とにかく一から試し、学習していったらしい。
また上のインタビューでアネットがアルバート・アイラーに関して語るところがあり、「タイム(キープ)がアイラーの音楽で自由になり、そこから音楽の限界がなくなった」のだという主旨のことを言っている。若いアーティストとして、当時の彼女はそこを出発点とし、さらにモーグ・シンセサイザーとの出会いがあってキャリアが本格的に始まったわけだ。
冒頭にも書いたが、このパフォーマンスへのハン・ベニンクの参加はたいへん大きい、当時のドラムス、パーカッショニストとしてタイムキープしない代表のようなベニンクと、いわゆるメロディーだったりの楽音を奏でることを主眼としないこのシンセサイザー・ショーはベスト・マッチと思う。
普段ペーター・ブロッツマンとの共演ものなどICPやFMPものを聴きつけているが、とにかくベニンクがたたき出すと、何か不穏なことが起こっている現場に立ち会っているような気分になる。今回はそこにモーグの電子音というか振動、ヴァイブレーションが渦巻くわけで、当時のライブの参加者は音楽会というよりも、今で言うところのチルアウト系のセッションに参加するようなマインド・セットだったのではないだろうかと思う。
一応アルバム収録の2曲ともガイドとなるふわっとしたメロディーが存在し、それにリードされて、奥深くに分け入っていくような演出になっている。B面の"Touching"は構成感があり、生ピアノも聴け、アネットのヴォーカルもきちっと配置されている。であるから闇雲に電子音が渦巻いてパーカッションの乱打があると言うわけではない。また、アネットがティモシー・リアリーの助手だったことを思うと何かトリップ系のセッションを期待する向きもあると思う。まあ、そう言う聞き方も可能ではあるが、ベニンクのパーカッションはやはりフルクサス感というかダダイスト的な美学が色濃いこともあって、瞑想に役立ちそうな音楽ではあるのだが、聴き手を内面に没入させるというよりも、何か現場に参加させ目撃させるシアトリカルな感じがあり、そこが全体の魅力となっていると思う。
初期のシンセサイザーを使ったパフォーマンスとして「スイッチ・オン・バッハ」とはまったくの別世界であり、モーグ博士も納得ではないだろうか?
同年発売でthe Bley-Peacock Synthesizer Show名義の"Revenge: The Bigger The Love The Greater The Hate"がある。
