読んでみた(過去のレジメ集):クリストファー・プリースト The Affirmation (1981)
【現時点での注釈】未訳のプリースト長篇のなかで、たぶんこれがもっとも優れている作品であり、翻訳されないのが不思議でならない。何度か売り込んだものの、タイミングが合わないのか、良い結果が出ていない。死ぬまでに絶対に訳したい本なんだけど、そのまえに寿命が尽きるかもしれないかも。声をかけていただける出版社があるなら、是非! すぐとりかかります!(2022年5月5日記す)
The Affirmation (1981) by Christopher Priest レジメ
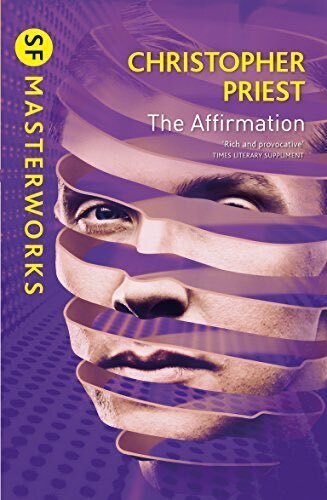
初版:Faber and Faber Limited, 1981
レジメ対象本:Touchstone, 1996 (pp.213)
(最新版は、Gollancz Masterworks, 2011)
(初版とTouchstone版の相違は、「著者前書き」がついたことと、「献辞」がなくなり、イエーツの詩"Sailing To Byzantium"をエピグラフにしていたものがなくなったこと。本文にはいっさい手を加えていない、と「著者前書き」で断っている)
プリーストがSF作家の範疇を越え、英国主流文学の一員として認められるきっかけになった記念碑的作品(1983年にジュリアン・バーンズ、イアン・マキューアン、カズオ・イシグロなどと共に「英国若手有望作家」に選ばれている)。また、それまで書きつづってきた〈ドリーム・アーキペラゴ〉物の集大成ともなっている。
作品内現実と入れ子構造になった作品内虚構が、おたがいに浸食しあい、文字通り、「虚実のあわいの妙」を堪能できる作品に仕上がっている。
【梗概】
主人公ピーター・シンクレアが確信を持って言えるのは、自分が英国人で、一九七六年の夏、二十九歳であったということだけであり、いま現在も二十九歳であるかどうかはわからない──という記述から、ピーターの回顧がはじまる。
二十九歳の夏は最悪だった。敬愛していた父が亡くなり、付き合っていた恋人グラシアにも振られ、あまつさえ失業の憂き目に遭い、とどめがロンドンの賃貸アパートからの退去勧告だった。失意に沈むぼくに、古くからのシンクレア家の友人エドウィン・ミラーから、願ってもない申し出を受ける。一夏、ウェールズとの国境近くにある、買ったばかりのミラー家の別荘(コテージ)に暮らし、修理改修をしてくれないかというのだ。
ミラーの話に乗ったぼくは、さっそく別荘へ移り住んだ。そこで、修繕作業のかたわら、来し方を振り返ることにした。過去を回想することで、自分のアイデンティティの確保をはかろうという目的で、回想録を書きはじめ、夢中になる。しかし、自分の記憶と事実との齟齬(たとえば、幼い子どものころ腕を骨折したのだが、記憶では左腕の骨折なのに、当時の写真を見ると、右腕を三角巾で吊っているなど)に気づく。自己の過去(=記憶)の曖昧さに違和感を覚えながらも、回想録執筆にいっそう埋没していくのだが、執筆に際して、現実をそのまま書くのではなく、多島海〈ドリーム・アーキペラゴ〉という仮想の舞台を設定し、一種の小説として、書こうとしたところが、この小説のポイントである(なぜ、小説仕立てにしたか、という説明にいささか説得力を欠くきらいがないではない)。
回想録小説執筆に夢中になっていると、二歳年上の姉フェリシティが突然別荘を訪ねてくる。電話にも出ず、まったく連絡が取れなくなっていたので、心配して見に来たのだと言いながら、ぼくの様子、部屋の有様を見て、絶句する。「ミラーさんに頼まれた改装にまったく手をつけず、ゴミの山に埋もれ、ろくに食事を取らず、風呂にも入っていないのが歴然の、このありさまはなに?!」そう言われて、はじめて姉の言うとおりの状態であることに気づく(それまでの記述では、改装作業をやっていたように書かれていたが、じっさいには(?)、まったく手つかずで、ひたすら回想録小説を書いていた)。見るにみかねた姉に強引に姉の家へ連れていかれるぼく……。
(ここからは、「現実の英国」と「仮想のドリーム・アーキペラゴ」のなかの主人公が交互に語られ、当然予想されるごとく、両者はたがいに侵食しあう……)
ドリーム・アーキペラゴのジェスラ(=ロンドン)で暮らしていたぼくは、いま、コラゴー島目指して、南行きの船旅に出ているところだった。宝くじに当選するという僥倖を得、コラゴー島でのみ可能な「不老不死」処置を受けにいくのである。この世界では、不老不死技術が確立していたのだが、あまりに高価な処置であり、一度に処置できる人数に限りがあるため、「平等」な機会を万人にあたえるべく、宝くじを買って当たった者にのみ、その機会が与えられるのだった。
対立する二大勢力のため、準戦時下にあるこの世界では、航空機が禁じられており、長距離の移動手段は、船旅しかなく、時間をかけ、いくつもの島を巡りながら、ぼくはようやくコラゴー島にたどりつく。途中、ミュリジー島の不死くじ事務所に立ち寄ったぼくは、そこの受付職員であるセリ・フルトン(=現実世界での恋人グラシア)と恋に落ち、いっしょに南への旅をすることになる。セリから、不死処置の恐るべき副作用を聞かされたぼくは、愕然となる。すなわち、その処置によって、それまでの記憶をいっさいなくしてしまい、あらたなアイデンティティを確立しなければならなくなるのだ。
シェフィールドの姉の家に引き取られたぼくは、徐々に現実への適応力を取り戻していき、そんなある日、別れた恋人のグラシアと出会い、よりをもどし、グラシアとふたたびいっしょに住むようになる(「捨てられた」と思っていたのは、じっさいには、ぼくがグラシアに癇癪を立てて別れ、もともと精神的に不安定なグラシアが自殺未遂を起こしたのであることが、のちに明らかにされる)。
コラゴー島に到着したぼくは、不死処置施設に出向くが、記憶を無くし、己を無くすことを懸念し、処置辞退を申し出る。しかし、処置を受けないと、あなたの余命が四年半だと言われる。精密検査を受けた結果、いつ破裂してもおかしくない動脈瘤を抱えていることが判明し、結局、不死処置を受けることに同意する。
処置前に、被験者は、その後のアイデンティティ確立に役立てるよう、詳細な質疑応答に答えることになっているのだが、ぼくは、自分の来し方についてはここに詳細に記しているので、これを参考にしてくれ、と紙の束を渡す(当然、それは、「現実世界」での、ぼくの来歴が記されている──つまり、「現実の英国」と「仮想のドリーム・アーキペラゴ」は、見方を変えれば、「仮想の英国」と「現実のドリーム・アーキペラゴ」という構造になっている)。そして、ぼくは、不老不死処置を受け、それまでの記憶をいっさいなくしてしまう……。
【注意 このあと、最後まで紹介していますので、ネタバレを読みたくない方は、ここで読むのを止めたほうがいいでしょう】
グラシアと暮らしながら、ふとぼくは仮想世界のセリの姿を想像し、セリと会話を交わすようになる。そんなぼくの様子を不信に思うグラシア。ついには、またしてもグラシアが自殺未遂を起こしてしまい、一命をとりとめたグラシアに、ぼくは自分の抱えている奇妙な物語を説明しようとし、その物語を書き留めた紙の束をグラシアに差しだす。が、グラシアは紙束を見て、恐怖に戦き、ぼくからあとじさる──「あなた、おかしいわよ、それはただの白紙じゃない!」
セリとともに、ジェスラの街を歩いているぼく。
「グラシアに会わなければ」
「彼女は二年前に自殺したんでしょ」
「そんな馬鹿な」
「ミュリジーで会ったとき、あなたはそう言ったわ、あなたが書いている小説のなかで、グラシアは自殺したんだ、と」
「そんなこと覚えていない」
ぼくは思い出さねば。そう、ここがロンドンであることを思い出し、グラシアに会わなければ。
「島にいればあなたは永遠に生きられる。島に属していれば」
「ぼくはもうなにも信じられない、ぼくはどこにも属していない」
ロンドンの舗装された通りが見えてきた。セリがぼくから後退していく。セリの姿を見失っていき、あわてて追いかけようとし、向こうの世界へたどりつこうとした瞬間、自分の居場所を思いだし、振り返ったところ──(突然、小説はここで終わる)
というわけで、後半の「ふたつの現実」がたがいに侵食しあいながら、怒濤のラスト(と突然の幕切れ)に向かうところは、まさに読書の醍醐味を満喫できる屈指の出来になっていると言って過言ではない。
以上
(レジメ作成日:2018年11月15日)
