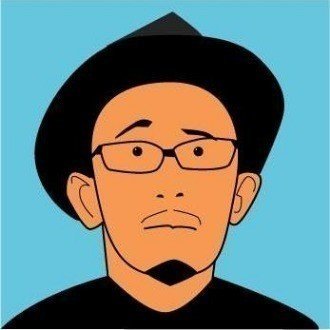お金のむこうに人がいる
おはようございます 渡邉です。一気に寒くなってきましたね。週末は、ralphというラッパーの無料ライブのチケットをゲットしに、横浜に買い物に行ってきました。途中在庫切れで、補充して回っているというインスタライブ情報を元に、待つこと2時間。少し気を抜いて、別のところをうろうろしている間に、本人が登場したということで、残念!本人には逢えず。ほんと、こういうのって一瞬のタイミングですね。でも無事チケットはゲット出来ました。
さて、今週は「お金のむこうに人がいる」- 田内学 を紹介します。
この本は、タイトルの通り、お金の向こうにいる「人」にフォーカスに当て、お金と労働という切り口で経済について語られたものになります。早速ですが、中身をみていきたいと思います。
すべてのモノは労働によって作られる
先ずは、この本の大前提とも言える、生産活動の大原則です。我々が、モノを手に入れたり、サービスを受けたりするには、誰かの労働が必要になります。その際に、お金が持っている「2つのコミュニケーション力」、「交渉力」と「伝達力」が生きてくる訳です。
言語の伝わらない外国にいても、相手が提示した価格を支払うことにより、他の人に働いてもらうことが出来る。
そして、欲しいものがあるときは
お金を流せば、自然に労働が集積され、どんな複雑なものも作り上げることが出来る。
そして、我々自身も労働の対価として、お金を受け取るわけですが、そのお金は、将来、誰かに働いてもらえるための予約券のようなものだと考えればよいということです。
そこで大事なのは、
働く人がいなければ、お金の力は消えるのだ。
よく映画で出てくる、荒廃した未来。世界に取り残されて1人ぼっち。みたいなシチュエーションだと、お金の力は発揮されない。自分で何かを作って、自分で消費するしかない。
現実世界でも僕が小さい頃、今から40年位前のお正月は、お店はどこも閉まっていた。セブンイレブンも文字通り、朝7時から夜11時までだったし、そもそも僕の地元には未だコンビニは無かった。お金を使おうにも使えるところは、神社位しかない。だから、年末の内に、おせち料理と呼ばれる保存食を作っておいて、それを家族で食べて過ごすしかなかったはず。それが時代が流れ、コンビニは24時間365日開いているし、スーパーだって開いている(ここ数年はまた変わりつつあるけど)。年末になれば、スーパー、コンビニ、ドラッグストア・・・ではおせちのチラシが置かれ、他の人に働いてもらうことになってきている。
つまり、第1部でのポイントは、以下の通りとなります。
「お金」に惑わされず、「誰が働いて、誰が幸せになるのか」を考えればいいだけだ。だいじなのは、みんなが生きている空間を意識して経済を捉えることだ。
「社会の財布」には外側がない
僕らが働いて稼いだり、投資して儲かれば、自分の財布のお金は増える。それは、「財布の外」の世界が存在していて、そこが減った分自分の財布に入ってくるからです。
しかしながら、視点を拡げて拡げて、社会全体としてみたとき、大きな大きな「社会の財布」には外側が存在しない。僕らが働いてもらった給料は、会社のお財布から出ていったお金だし、洋服屋さんで服を買ったときは、自分の財布からお金が出て行って、洋服屋さんの財布に入っていったということになる。
ミクロに家庭内に置き換えて見てみれば、息子がお手伝いをして、受け取ったお小遣いは、僕の財布が減り、息子の財布が増えただけで、我が家全体の財布の中身は変わっていないということです。
「預金大国」は「借金大国」
一方で、預金残高は増やすことが出来るということが書かれています。仮に自動車メーカーA社の預金残高をx円とする。とある車の購入者が銀行から貸付で300万円の車を一括で購入すると、300万円がA社に入ってきて、A社の預金残高は x+300万円 と増えている。実際には、銀行が貸し付けた額がA社に渡っただけなので、お金の量は変わらず、預金が増えたということになる。
つまり、「預金大国」ということは、言い換えると「借金大国」ということになる。
「経済効果」という言葉に潜む罠
「経済効果」という言葉をよく耳にすることがあるかと思いますが、僕自身もよく意味が分かっていませんでした。なんとなく、それ位新たな需要を生んでいるんだろうな?位に思っていました。
これを書いている2024年には、紙幣デザインが変わり、一万円が諭吉から栄一になりました。これにより、新紙幣を読み取るATM、自動販売機の機械の更新などこれらに使われる費用の合計が1.6兆円ということです。
1.6兆円の効果というとなんかすごくいいことがありそうなのですが、ここまで学んできたことを踏襲すると、お金が移動しただけということが分かります。ATMや自動販売機の機械を作るメーカーの売上は増えますが、一方でATMを買い替える銀行のお金は減ってしまいます。それによって、銀行員の給料が減るかもしれないし、僕らが保有する銀行口座の維持手数料が上がるかもしれない。結局のところ、昨日のポイントに戻るのだが、
「誰が働いて、誰が幸せになるのか」
という訳で、どこにお金を流すのか?というのがあらためて重要な論点になってくるわけです。
社会全体の問題はお金で解決できない。
貿易黒字とは「外国のために働くこと」
貿易黒字というと悪いことのようで、外国から叩かれこともありますが、このことについても人をベースに考えてみます。例えば、日本は長いあいだ貿易黒字を維持してきたのですが、これは、大量の商品を輸出しているということで、つまりは外国のために働いているということになります。何が問題かというと、例えばテレビを輸入していた場合、自国内で作っているテレビが売れなくなり、テレビを作っている人が失業してしまうかもしれないからです。一方で、将来への「労働の貸し」を作ったとも言えます。この「労働の貸し」があるから、例えば、東日本大震災など将来困ったときに外国に助けてもらえるわけです。
ではここで、この本の核心に触れる問題です。
Q:僕たちの抱える老後の不安を解消する方法は次のうちどれだろうか?
A:他の人よりも多くのお金を貯めておく
B:外国に頼れるように外貨を貯めておく
C:社会全体で子どもを育てる
ここまで本を読み進めてくれば、察しが付くのですが、
「僕たち」が自分や家族だけなら、Aが正解だ。他の人よりも多くのお金を貯めておけばイス取りゲームに勝つことができる。(中略)「僕たち」が国全体に広がるとAは正解にならない。(中略)
では、「僕たち」が「社会全に」になるとどうだろうか?
Bは正解から外れる。外貨を貯めることは、国内の問題を外国に押し付けているだけだと気づく。Cのこどもを育てることが唯一の正解になるのだ。
「おわりに」では、「僕たち」を輪を広げるための思考について書かれています。「僕たちの輪」とはつまりは、
目的を共有している範囲
ということになります。近年SDGsが何かと話題になりますが、なんとなく、SDGsという言葉が一人歩きしている感がつよいので、あらためてSDGsについて考えてみますと、
貧困、紛争、気候変動、感染症。人類は、これまでになかったような数多くの課題に直面しています。
このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなると心配されています。
そんな危機感から、世界中のさまざまな立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、
2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。
それが「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」です。
ということです、「僕たちの輪」を世界規模に広げて物事を捉えていくことが必要だと気づかされます。
そして、再び視点をミクロに戻してみましょう。この記事の画像は蕎麦を打っている人になるのですが、「目的を共有」ということを中心において、蕎麦を考えてみましょう。
そば屋さんは、「お客さんが美味しいそば食べる」ために働き、
お客さんは、「自分が美味しいそばを食べるために、そば屋さんが働いている」と考えるということです。
蕎麦を食べる為には、自分でスーパーで蕎麦を買ってきてゆでるか、蕎麦屋に行くしかない。いずれにせよ、自分でそばの実を育て、挽いてそばを打って、ゆでる。なんてことは大抵の人は出来ないので、誰かの労働が必要になってくれるという訳です。誰かのおかげで、蕎麦が食べられるということに感謝しながら、お金を払うということです。
余談ですが、僕は小諸そばが好きで、出社したタイミングでは必ずと言っても良いほど、小諸そばに行っていました。10月より転職をして、職場が変わったのですが、幸いにも会社の近くに小諸そばがあり、引き続き出社したタイミングでは小諸そばに行っています。次回、小諸そばに行った際にも感謝しながら、お蕎麦を頂きたいと思います。
という訳で、今週は「お金のむこうに人がいる」ということについて考えてきました。お金について考える際に、思い出したい1冊となりますね。
(2024.11.22)
いいなと思ったら応援しよう!