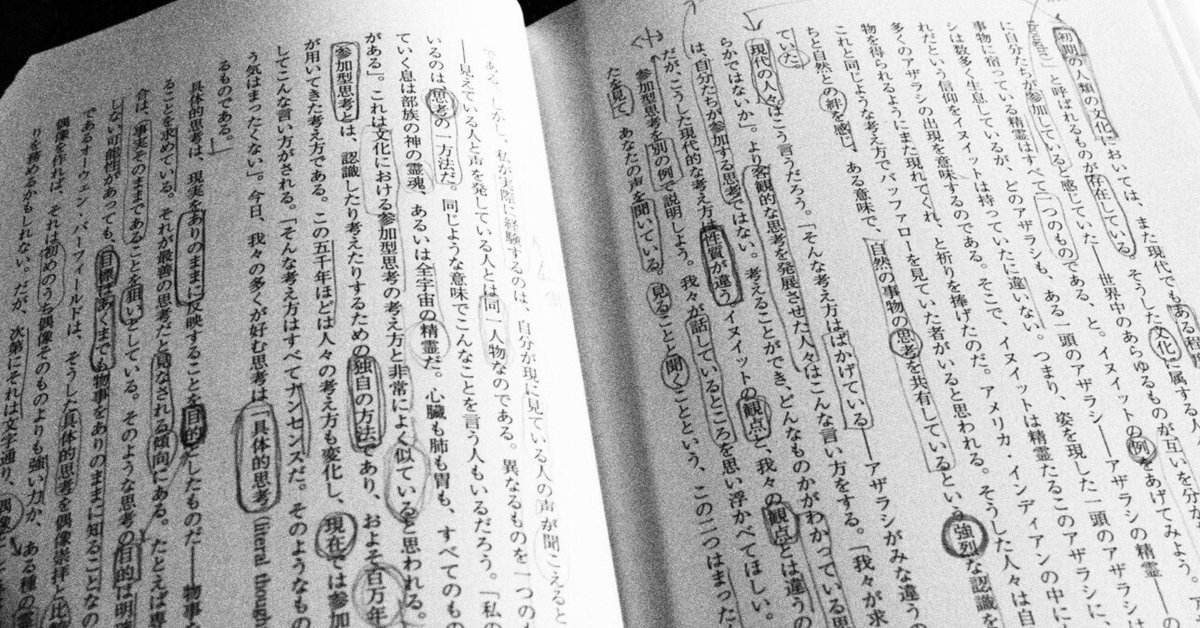
デビッド・ボーム Dialogue7章3-1
デヴィッド・ボーム「ダイアローグ」
対立から共生へ、議論から対話へ 唯識的解釈()内
7:PARTICIPATORY THOUGHT AND THE UNLIMITED
参加型思考(唯識の八識説と仮定)と無限
(PARTICIPATORY:語源から"全体の一部を取ること")
初期の人類(後述の現代の人々と対)の文化においては、また現代でもある程度(どの程度かは後述)までは、「参加型思考(PARTICIPATORY THOUGHT=唯識の八識説を仮定)と呼ばれるものが存在している。そうした文化(唯識的な理解)に属する人々は、目にするものの一部に自分たちが参加している(自分たちも属しているまたは宿している)と感じていた – 世界中のあらゆるものが互いを分かち合っており、事物に宿っている精霊はすべて一つのものである、と。(具体的な事は後述されます)
イヌイット(カナダ極北地域で生活を営む人々)の(参加型思考の)例をあげてみよう。アザラシは数多く生息しているが、どのアザラシも、ある一頭のアザラシ – アザラシの精霊 – の現れだという信仰をもっていたに違いない。つまり、姿を現した一頭のアザラシは、多くのアザラシの出現を意味するのである(全体=多くのアザラシは、個=一頭のアザラシの集まりである的な個と全体の関係)。そこで、イヌイットは精霊たるこのアザラシに、食物を得られるようにまた現れてくれ、と祈りを捧げたのだ。
アメリカン・インディアンの中にも、これと同じような考え方でバッファローを見ていた者がいると思われる。そうした人々は自分たちと自然との絆を感じ(全一性)、ある意味で、自然の事物の思考を共有(一体化)しているという強烈な(あいまいでない)認識を持っていた。
(このようなことに対して)現代の人々はこう言うだろう。「そんな考え方はばかげている – アザラシがみな違うのは明らかではないか(多様性のみ全一性の欠如)」。
より客観的な思考を発展させた人々は(主客を対立させ)こんな言い方をする。「我々が求めるのは、自分たちが参加する思考(主客合一)ではない。(客体として)考えることができ、(客体として)どんなものかがわかっている思考だ」。
だが、こうした現代的な考え方は性質が違う(的を射ていない?)。イヌイットの観点と、我々の観点とは違うのである。
(では現代でもある程度までは存在している)参加型思考を別の例で説明しよう。
我々が話しているところを思い浮かべてほしい。私はあなたを見て、あなたの声を聞いている。見ることと聞くことという、この二つはまったく違う経験である(個と全体の個々=見ると聞く)。しかし、実際に経験するのは、自分が現に見ている人の声が聞こえるということだ – 見えている人と声を発している人は同一人物(全一性)なのである。異なるもの(見る体験と聞く体験)を一つのもの(同一人物)にしているのは思考の一方法だ。(前述のバラバラにみながら全体を一つとしてみることをばかげているという現代の我々が実はバラバラの体験を一つのものとしてみているよ〜という無自覚への示唆か。7章書き出し部分の「また現代でもある程度までは、「参加型思考」と呼ばれるものが存在している」と呼応する。)
同じような意味でこんなことを言う人もいるだろう。「私の中に入っていく息は部族の神の霊魂、あるいは全宇宙の精霊(全一性)だ。心臓も肺も胃(多様性)も、すべての関わりがある」。これは文化における参加型思考の考え方と非常によく似ている(同等ではない?)と思われる。
参加型思考とは、認識したり考えたりするための独自の方法であり、およそ百万年の間、人類が用いてきた考え方である。(その百万年に対して)この五千年ほどは人々の考え方も変化し、現在では(我々は)参加型思考に対してこんな言い方がされる。「そんな考え方はナンセンスだ。そのようなものに注意を払う気はまったくない」。今日、我々の多くが好む思考は「具体的思考」と呼ばれるものである。
具体的思考は、現実をありのままに反映することを(あくまでも)目的としたものだ – 物事をそのまま伝えることを求めている(求めているということは出来ていないもしくは出来ない)。それが最善の思考だと見なされる傾向にある。たとえば専門的な思考の場合は、事実そのままであることを狙いとしている。(狙いとしているが果たして事実そのまま、ありのままを反映できるのか?)
そのような思考(具体的思考)の目的は明確さである。成功しない可能性があっても、目標はあくまでも物事をありのままに知ることなのだ。(ここで西田幾多郎の善の研究の冒頭、「経験するというのは事実其儘(そのまま)に知るの意である。全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純粋というのは、普通に経験といって居る者もその実は何らかの思想を交えて居るから、毫も思慮分別を加えない、真に経験其儘の状態をいうのである。」を想起)
英国の哲学者であるオーウェン・バーフィールドは、そうした具体的思考を偶像崇拝と比較した。もし、人が偶像を作れば、それは初めのうち偶像はそのもの(目に見えない偶像以前にあった何か)よりも強い力か、ある種の霊的エネルギー(認識することのできないエネルギー)の代わりを務めるかもしれない。(今まで具体的に認識することが出来なかった何かが偶像という目に見えるカタチを得たために)
だが、次第にそれは文字通り、偶像(カタチとしての価値、例えば美術的な価値)として受け取られるようになる。そして、偶像は(そのカタチに対して)最高の価値を与えられるという結果(と同時に目に見えない偶像以前にあったそのものはどこへ)になるのである。同様に我々は、自分たちの言葉や思考が(偶像のように)現実をありのままに表現したり、述べている(と思っている)限り、それら(言葉や思考)を(偶像のように)崇める。しかし、実を言えば、
そういった言葉や思考は現実をありのままに表現などしていないのだ – それらは(実は何らかの思想を交えて)過大評価されている(つまり既に常に誤謬を起こしている)。ある程度の現実は把握できるとしても、言葉や思考(一部分)が「すべて」を網羅するわけではない。(ここに個と全体の関係性がくずれてその結果、すべてが混乱状態に陥る。後述)
参加型思考(個と全体性の関係性)に大半を頼っていた文化も、実際的な活動にはおそらく具体的思考(個と全体性の非関係性)を用いていただろう。だが、自らの根本に関わる事柄には、ほとんど参加型思考を用いていた。
トーテム像 – 自分たちと同一視している動物をかたどったもの – を持つ部族はこんなふうに言う。「わが部族とこのトーテム像はまったく同じもの(全一性)だ」。これは、その部族とトーテム像が、ある種のエネルギーや精霊を共有しているという考え方だ。または、万物には宇宙的な精霊や事物との絆があるとさえ、言われるかもしれない。
ちょうど、声が聞こえている人物と見えている人物が同一(現代の我々でも実はバラバラの体験を一つのものとしてみているよ〜という無自覚への示唆)であると、私が言ったことのように。つまり、トーテム像が部族そのものというわけだ。人はトーテム像を通じてその部族に接するか、部族の一員、または全部族を通じてトーテム像に接するのである。
こうした考え方を試してみるのは非常に興味深い。いずれにせよ、人は絶えず参加型思考を(多様性と全一性を有して)行っており、それがなくなることはないと思われる。たとえば、自国が攻撃を受けたら、自分も攻撃を受けることになる。すると、我々はまさに参加型思考をするようになり、こう言うだろう。「おれとこの国とは同じものだ。その国境を越えたら、おまえはおれを殴ったことになる」。そのような考え方をしていることは多いが、人はそれを否定するだろう。参加型思考(自国と自分の同一視)などしていないと、具体的思考は断言する。したがって、具体的思考とはインコヒーレント(非干渉)なのである。人が具体的思考(五識と第六意識)に多大な価値を与えているのは明白だが、実をいえば、暗黙裡(第七末那識と第八阿頼耶識)に参加型思考にも大きな価値(影響=現行熏種子)を与えている。その結果、すべてが混乱状態に陥っているのだ。具体的思考は自覚している認識の中に見られ、テクノロジーを可能にし、さまざまな方式で膨大な利点をもたらす。同時に、参加型思考はなぜか日陰の存在となり、輝きを失った。だが、参加型思考はひそかに残っている。
この続きはp179「ところで参加という言葉はどんな意味だろうか?」へ
「ダイアローグ/デビッド・ボーム著/英治出版2007年刊
