
noteマガジンいまだ完成を見ず
〈SungerBook-キャッツアイ8〉
この春、noteのマガジンに着目し、ぜひともマガジン化をやってみようと思い立ちました。デジタルコンテンツによる自分全集のようなものが作れるイメージは、おおいに惹かれるものがありました。完成の暁には、プレミアム会員にもなって、noteの機能をもっと使いこなそう、などと刺激されたのでした。
しかし、2024年も押し詰まってきているのに、マガジン化は暗礁に乗り上げたかのように、あるいはマガジン山頂登頂前に、九合目あたりで悪天候にみまわれ、ビバークしたまま一歩も動けないといったような状態です。
ここを打開するには、自分を一度振り返ってみるしかない、と思うところまできています。何か動かされるテーマがあって、それに向かって叙述していくような組み立てではなく、マガジンに対する動機を検証するための探索の方法として、この文章を書き始めています。
複数ブログの活用
まずLINE BLOG、はてなブログ、noteの三つについて述べることを予めお伝えします。
2019年9月からLINE BLOGで制作を始め、2022年8月から制作主体をnoteに移行しました。2023年のLINE BLOGの終了を見越していたわけではなく、およそ1年前のたまたまタイムリーな乗り換えにはなりました。
私がLINE BLOGを離れようと思ったきっかけは、もう思い出せません。デジタルコンテンツでの制作を始めて3年経ち、見直したい気持ちになっていたと思います。見直そうとする中で、一番noteに惹かれるものがありました。(この辺は「ノーティストの夢」に書き込んでいます)この時の感覚はよく覚えています。
2022年8月noteでの制作が始まりましたが、その時点までのLINE BLOGの過去記事は、その終了告知に接してから、別にアカウントのあるはてなブログに移そうと思い、実際そうしています。
はてなブログの引越し先として推奨リストにnoteが登場したのは、LINE BLOG終了告知があってからのことだと思います。私がnote利用開始後、すぐ、過去記事をnoteへ総引越しできるとは思っていません。この間、noteに持っていきたい記事については、はてなブログから単品ごとに移行しているものです。
2023年、LINE BLOG終了の告知が伝わってそれを私が目にした折、推奨移行先としてnoteが出ていて、しめた、と思ったものです。はてなから残記事全部をエクスポート、noteにインポートすればいいとなったわけです。
こうした経緯を逐一辿っても無味乾燥かと思いますので、私と複数ブログの関係を概観したおきます。
●2019年9月 LINE BLOG開始
●2020年8月はてなブログを一部記事の著作権対応のため活用※①
●2022年8月ブログ制作3年目を迎えるにあたり、
他ブログを模索する中、noteで制作・投稿しよう
と決め開始
●過去記事をはてなブログに集約。LINE BLOGからの撤収
●2023年1月LINE BLOG終了の告知為される。6月
29日終了。先行してはてなブログに移しておいたので、終了にまつわる影響はなし。
●2023年8月13日note投稿開始
●はてなブログの過去記事をすべてnoteに移行したいと着想
●2024年夏頃noteマガジン化開始
●2024年11月noteマガジン化という絶壁にぶちあたり立ち往生、今に至る
noteマガジンという絶壁
私にとってのマガジン化完了とは、過去記事から残すべきものをすべてnoteへ移行し、それをマガジンとして組み込むことです。今、ほぼ九割方マガジンに収納できていますが、秋頃から立ち往生したままです。しかも、あれほど欣喜雀躍してマガジン化に着手したはずなのに、この期に及んで意欲が萎えてしまったのです。
今私は、マガジンを完成させるために、萎えてしまった意欲をどうにかして回復できないか、という壁に突き当っています。
意欲を減退させるほどの作業がどんなものかというと、
①インポートでのネックあり
②ハイパーリンクはずし
③レイアウトやり直し(画像、文章)
④ヘッダー画像設定(スムーズにアップできない)
⑤過去記事の精査
などであり①〜④が物理的な作業であり、⑤は過去記事をマガジン化(=note化)するに値するかといった内容の質的な精査のような作業です。実際は⑤が一番最初になるべきかもしれません。

白い花粒たちがコクーンのように私の夢想を
懐胎させているかのよう…
私は、「ノーティストの見た夢」(24.6.15投稿、マガジン『男とスコーン』所収)と、「私自身のための広告」(24.7.12投稿、マガジン『男とスコーン』所収)の中で、マガジンのことにも触れていますので、このあたりが私の中でマガジンが沸騰していた頃、と振り返ります。2022年8月以降noteで制作していた記事を、今年マガジン化するのは、楽しいくらいでした。これらのnote記事を「SungerBook」と称したレーベル7種類のマガジンに振り分ける作業です。
ここで甚だ難航していると口説いているのは、noteを始める前に書いた過去記事のうち記事単品ごとに、手間はかかってもnote化できているものはいいのですが、noteにインポートしたものの下書きの状態で待機している過去記事達です。
②〜⑤までの点で、まず、note化作業が重くなるのです。ですから、厳密にはマガジン化というより、note投稿の停滞に見舞われているということになります。しかし、ぜひnoteにしたいという記事については、そこを乗り越える力が出てきます。自己記事について、自分なりに評価作業をしているのかもしれません。
今、私の公開中マガジンは以下の7セットです。マガジンタイトルと、リード文、収納記事数になります。
・キャッツアイ
「突き詰める、問い詰める」論考 7本
・カラーグラス
「こんな見方もあるさ」社会文化評論 17本
・燕返し
「斬らずにいられない」クリティーク 3本
・舌鼓
「どこまで味わい尽くせるか」文芸批評 14本
・男とスコーン
「生活に抒情を求めるとき」エッセイ 8本
・ファンタジーの小径
「誘われていく宇宙がある」創作 0本
・萌え町紀行
「暮らした町を愛してる」エッセイ 10本
マガジンへ未収納の0本とは、単記事でnote投稿していてもマガジンへ入れていなかったり、下書きのまま何本が眠っているという状態です。
ここで述べているマガジン化にたじろでいるとは、下書きをnote再投稿(マガジン化)できずにいるということで、その記事数10数本とは、そもそもの構想ではこれらマガジン7種のいずれかに振り分けるつもりでいたものです。
何がやる気を削いでいくのか
noteで投稿済み、noteで下書きのままの未投稿含めて総記事数は約100本になっていました。そこから機械的にマガジンに振り分けるわけではなく、2019年から書き溜めたものですから、noteにアップするには、やはりちょっと内容を見改めることになります。
今となっては、何のためらいもなく自動的にnote化し、マガジンに振り分ければよかった(A)、と思わないことはありません。逆に、九割方note化しマガジン化しているなら、下書き残は廃棄してしまえばいい(B)、という選択もある、と思うこともあります。
しかし、それができるならこの記事を書いていません。ここにある障害は、過去記事を評価する難しさから来るのだろうと思われますが、そこに関わっていると時間が流れ、早く新記事制作に取り組みたいと焦ることになります。
そもそもはてなブログからnoteへの引越しは、エクスポート、インポートが一発でできたわけではありません。インポートエラーが複数回ありました。note社の運営さまの手を煩わせることにもなりました。このあたり全く知識がなく、よくわかっていないのですが、旧記事中のhtmlでの不具合らしく、その記事をまるごと廃棄することで、インポートできています。
また、インポートでnoteの下書きに貼り付いた、
はてなブログからの記事には、何故かハイパーリンク下線がやたらと付いているのです。これも、運営さんに相談、しかしスマホではうまくいかず、PCでなんとか解除できています。
しかし、このあたりも絶対noteにしようとする過去記事については、行なえています。写真のレイアウトやり直しや、ヘッド画像の設定も、なんとか済ませています。それらが、今現在私のnoteにマガジンとして上がっているわけです。
このように、物理的な作業が発生するものですから、残記事については、余計に気が重くなるようです。2024年中に完成という自分を急かす締切設定も、私を動かさないときています。
タイムリーという切口などなど
無為に時間が過ぎていく中、除外しようとマーキングしたある記事に、「ネットカルチャーの時代」がありました。そもそも2019年9月15日にLINE BLOGで投稿したものです。はてなブログに引越して後、今noteの下書きとなっています。
これは新技術に疎い私にも、インターネットの普及は空気のように日常的になる中、立花孝志現象と虎ノ門ニュースの台頭が、かなり力を持ち始めている実感をネタに、世の中を概観してみたものです。オールドメディア凋落を感じさせる動きと期待してみていたわけです。
虎ノ門ニュースはDHCがスポンサーを下りる事件があって後、放送頻度は減ったもののだいぶ当初の論調を復活させていることと、一方立花孝志氏については兵庫県知事問題で、一気に表舞台に帰ってきた感がありました。
立花孝志氏については、新しい選挙手法の台風の目となっていて、ドギツさはあるもののこの天才的行動力は先々大化けする可能性を感じていたものです。ただ、マツコ・デラックスでの空騒ぎと早々に参議院議員を辞めたあたりから、関心が失せていたところでした。しかし、昨今の沸騰ぶりはご承知の通りです、というだけでなく、私は斎藤元彦氏の当選への牽引力よりも、むしろ、立花孝志として自らの再生の機会として動くその論理的一貫性に注目しています。
つまり「ネットカルチャーの時代」は、時事的テーマ過ぎた腐食が感じられ、noteへの再投稿を見合わせようとしていたのですが、世相の方にうねりが生じてきて、再投稿価値がありそうに思えてきたのです。

ヘッダー画像。マガジン『カラーグラス』所収。
また、2020年1月11日にLINE BLOGにて投稿した「藪の外へ―伊藤詩織氏の可能性」という記事があります。しかし、躊躇するものがあって早々に投稿を取り下げました。批判ではなく、女性文化論的な建てつけです。これは、今年2024年10月6日にnote再投稿しました。伊藤詩織氏の動きに最近新たな展開※②があって、再び話題が露見してきて、投稿タイミングの招来を感じました。あらためて読みもして、内容的な構成と写真の仕上がりに、当初あった逡巡は消えていました。兵庫県知事問題で立花孝志氏絡みの話題が波立って来る直前だったと思われます。
時事的なテーマは、腐食しやすく否定的に思えていたのですが、時代の方で変化がありタイムリー性が影響を受けるという意味では一概に捨てられないという思いに見舞われたのでした。また、記事ネタの扱いとして、ニュース的なものは流れやすく、題材とのスタンスのとり方、表現世界の構築設計により、時事性の奥を照射できれば「時」を超えることができるのではないか、とあらためて感じいることになったわけです。
マガジン化作業の意欲が停滞するまま、個別記事の制作意欲が蠢く中、私に突飛な着想が生まれました。制作に着手したい気持ちを活かし、制作の過程にマガジン作業意欲を蘇生させるテーマを持ち込むやうな企画ができないか、というものです。これは、私にとっての「立花孝志」再来が起きていることを捉え、「ネットカルチャーの時代」
に再び光を当て、マガジン化しnote投稿しようという、そこを源泉として一気に邁進するようなイメージです。
「不易流行」はどうだ?
一方、時流の変化に影響されて記事の賞味期限が
なくなることがあるなら、「不易流行」をテーゼ
として書くようにすれば、あとあと起きる、このような経年劣化を心配しないで済むのではないか。しかし、不易流行は芭蕉の俳諧についての理念であって、note記事とは形態、スタイルが違い過ぎて無理があるように思えてきます。
「ネットカルチャーの時代」については、時代の現象にインターネットの文化的な定着感と、立花孝志氏と虎ノ門ニュースの先鞭性に着眼しているそのあたりを表現しようとしています。しかし、「コラム」的ではあっても、今ひとつの感が拭えないものがあります。一方、「藪の外へ―伊藤詩織氏の可能性」は時事的なネタを扱いながら、自己満足ながら批評性の表現を成し得ているように思われます。記事のスタイルの違いを超えた、表現の深みのようなものです。
自分のnote記事に芭蕉的「不易流行」を導入して、変転する世の中の現象を追いかけても、それがノーティストのめざすところではありません。
「不易流行」は多様な解釈の幅があるようですが、
新しみを生命とする俳諧においては、その動的な性格 ― 新しみを求めて変化を重ねてゆく流行性こそが、そのまま蕉風不易の本質を意味することになる。結局、「不易」と「流行」の根本は一つのものなのであり、芭蕉はそれを「風雅の誠」とよんでいるのである。
という辞典的理解を踏まえた上で、時代の現象面
に現れるトピックという「流行」の奥に潜む、根本的原初的なものを照射する視線という「不易」にこそリテラシーの価値と考えるに至っています。それがニュース性やジャーナリズムを超えて「文学的なるもの」に肉迫できるのではないか、それが私の「不易流行」です。変化の中に風雅を見出す不易ではなく、変化の奥をあぶり出す透徹の不易。

メッセージ性が感じられるものの、パルコは何もかも
トレンディな味つけにしてしまう。
「ネットカルチャーの時代」を書き直してその流れの勢いで、一気にマガジンの完成に持っていく
道はあっても、ちょっと違う感じがします。その制作にマガジンへの再起を織り込むことは、なんとなく難しそうです。これを企画倒れとかたづけるのではなく、意欲喪失を徹底的に見つめる手段として思考の闇をたどっていくのはどうか。そのプロセスを文章に定着させながら考えていこう。
当てのない旅?
述べたいテーマがあってそこへ向かって論理的に積み上げいくことを行き先のある旅とすれば、自分の意欲喪失を訪ねてあわよくばあらためて動機を再生させるとは、行き先もわからず出発意欲を懐胎させようとする難しさがあります。
画家が啓示を受けて、独創的な方法論を見つけ歴史的な大作を実現してしまうような主題と手法の獲得は、観覧者が絵に接して受ける感動にも、その作品のもつ制作者の達成を別角度から追体験する側面を併せもっているような気がします。
もし、私が、この拙文の制作に、そのような達成を夢見ているとしたら、あまりにも身の程知らずというべきで、そもそもそうした思いは浮かんだにしろ、それは夢のまた夢とは修辞に過ぎず、要は思いつきというものです。
そもそも、可能かどうか定かでないことを訪ねて、ひたすら悪戦苦闘しているだけなのです。
芸術的構築とコラム的記事における企画レベルの
頭でっかちでは間尺が合わないでしょう。
文章の彫琢を通じて、情念的なエネルギーの充電、それがあと一合目先のマガジン完成という頂上に一歩踏み出させる力となり得るか、そんなことは考え過ぎに落ちることのたぐいでしょう。
そもそも、私にとってnoteとは何か?
最近、私がつかんだ自分とは「書く者」です。そうです「物書き」ではなく「書く者」です。note
のURL入りで作る名刺には、そのように書きたいと考えています。作家、ライター、物書きのように生活収入を得ることとはかかわりなく、書くことに精進するような生き方です。noteの私のプロフィールに、その片鱗を表現していますが、客観的なものです。そうではなく、私の主体の意志として発現させたいところです。その私の主戦場がnoteであり、それがノーティストです。
当初私がマガジンに惹かれたのは、仮に自家出版するとしてその自分全集のような形にできる道として見えたからです。そのような発想が生まれてのち、今年の6月頃からすでに触れたように「ノーティストの夢」や「私自身のための広告」を書いたことは、マガジンによる刺激が大きかったと思っています。その後私のレーベルを開発し、七つのマガジンを組み立てたことは、繰り返しになります。
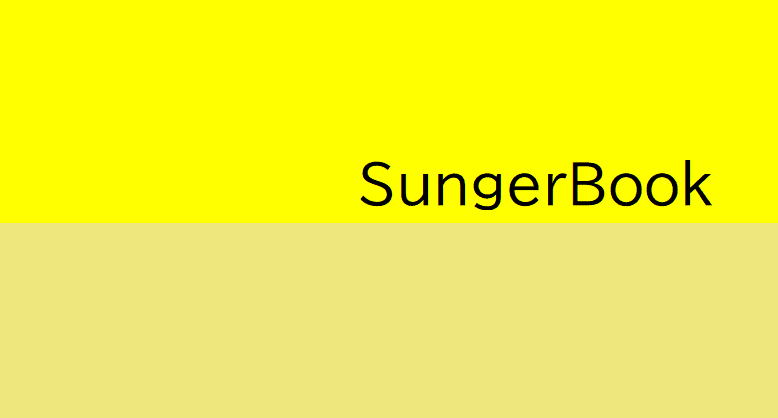
この他6種のマガジンは、同系異色のツートンで構成。
私が、過去記事をnoteに再投稿する時のチョイスには、自ずと自己批評的視点を通過しています。
どこかでテーマと仕上がりを見ているのだと思います。すでにピックアップした分については、「ネットカルチャーの時代」を選択する時のような迷いは生じなかったものです。投稿タイミングを気にするようなテーマではなかったからだと思います。こういう問題は、そのときどきにだしていく
note記事はその事象の只中にいるわけで、気にすることはないでしょう。しかし、このようなことから、あまりニュース記事的なフォローは賞味期限が早くなるかもしれません。事件的な現象面にバリューを求めるのではなく、そこで蠢く人間を
捉えているかや、私の「不易流行」を実現することや、エッセイに新鮮な感覚表現が達成できれば、時間が経っても読めるものになるような気がします。
何が私をnoteへ仕向けるのか
noteに関わっている以上、絶対書きたいと思っている、奇抜なネタがあります。公開性というデジタルコンテンツの一義的な機能をまず行使するのです。それは二つあってひとつは懺悔節で、もうひとつは怨念譚です。
懺悔節とは、人生を歩んでくると、いろんな人との関わりが生じます。私は自分を清廉潔癖な人間だとは思っていません。嫌なところのあるヤツです。自分でもそれはよくわかります。誰でも自分に対する思いにそのようなものがあるものなのか、それはわかりません。
小学校2年の時、定規を持ってスカートめくりをしようとする級友が私を誘ってきて、一緒になってつきあったことはよく覚えています。これは、事実です。いやいや、こんなかわいらしい程度の話ではありません。このたぐいなら、私はもっともっと恥ずかしいショーを自ら行なっています。まるで、その場の写真を後から見たかのように、鮮明に憶えています。
·····というようなことではなく、高校生の時級友に
失礼なことをしてしまったという、絶対傷つけてしまった、私にそんな気は毛頭ないものの、結果的にたぶん誤解させてしまっているエピソードがあります。それは、同じ高校になって通学上、駅まで時間とルートが同じになるので、一緒に通学することになった友人があります。義務教育の中学から受験して同じ高校に行くことになり、ある意味新鮮な高校生活への慣れなさを共有するというか、紛らわすというか、そんな若干の精神的相互補助的背景があったような気がします。
しばらく、朝の駅までの同行通学が続いたのですが、私はある日彼に「これからは一人で通学したい」と宣言したのです。これは、人とつるむことが嫌いとまでは言わずとも、一人でいることが苦にならない性分であったり、一人でいることが好きな人にはわかると思いますが、人と一緒でいることが鬱陶しいのです。ある時、そのことに気づいた私は、彼に唐突にそれを言い放ったのでした。現状変更する以上、それを宣言する気持ちの集中を伴う分微妙に強いニュアンスが混じったかもしれません。そのことについて、何か言い方を考えるような余裕はありませんでした。子供だった思います。後年、絶対傷つけてしまったことを
私は後悔しているのです。
○年卒業○○中学校同窓会という場があれば、そこで彼に会えれば私はそこで謝りたいと思っていいました。「一人でいること好き」は本心でも、
そこは少し言葉を加えなければ伝わらないものではないか、と思っているのです。誤解を晴らす機会を待ちましたが、再会できずいまだにそれはやって来ていません。絶対誤解を与えてしまっている·····
私はデジタルコンテンツの表現媒体には、どこの誰が見ているかわからない、とも、どこの誰も見ちゃあいない、とも、思っています。しかし、見る可能性としてはあり得ることが大きいのです。
彼のことは、本名を出せばいいのです。名字だけで十分です。私は本名をもじった筆名にしているし、顔出しもしているし、本人が見れば絶対わかるはずです。もう、何十年も前の話です。しかし
私の心のシミのようなものを、いま届け得る可能性をnoteが持っていることは間違いないわけで、そこに賭けたい思いがあります。
すでに、実情を書いてしまっていますが、この文脈では目に触れにくいかもしれません。そこは、
新たなマガジンレーベルを加えるなどの工夫があった方がいいかもしれません。自分がどれだけ嫌なヤツか、「ざんげの値打ちもない」という昔の歌謡曲がよみがえります。
読まれる機能の可能性を使う
note記事の傾向のひとつに生活や文章表現上の合理性、機能性のジャンルというものがあると思います。noteに限らないかもしれませんが。という言い方をするのは、私自身はnote記事のそこに重点を置かないという意識があるからなのでしょう。(と言いつつ、今年はそのジャンルに関わっていますが。)しかし、あえてそこに踏み込むテーマのひとつに怨念譚があります。上述の懺悔節と同様にです。
怨念譚とは、懺悔とは逆に私の怨念をnoteで晴らそうという企画です。私が嫌なことをしたのではなく、人にされたことを書きまくって積年の怨みを晴らしたいのです。主に会社勤め中の体験に多いのですが、ほんとうに怨んでフッと湧き上がってくることがあるのです。これは、一般的にあることなのでしょうか?

この深度はポスターのキャッチコピーの比ではない。
一念の信をもって制作という文章表現に向かう。
実は、これに関わるエピソードについては、今年の春に投稿した「尊敬の思想」(マガジン『キャッツアイ』収容)の中に出てきます。ただ、タイトルの通り切り口が怨念譚にはなっていません。仕事で精神的に押し潰れそうになった状態を脱出するのに体験した、道元の世界とのことを書いたのです。このネタも、相手の本名は出さずとも、私を苦しめた相手への怨念をぶつけ、滅多打ちにしたいのです。このようなダークサイドのメンタルをエンジンにして、怨みを犯罪的な行為で相手を抹殺するほど度胸もなく、また理性がないわけではありません。文章の表現世界への構築を通じて、完成、達成、解消を成し遂げたい、と夢想しています。理想的には、文学作品に昇華したいものです。
甚だ身の程知らずなのですが、「金閣寺」を例に出させてもらいます。私は、この作品には三島由紀夫の怨念が燃え盛っていると思っています。まあこれは夢のまた夢ですが、私はいまいち小説志向ではないし、しかし、工夫すればやりようはあるだろうと考えているのです。たとえば、ノンフィクションやルポルタージュの領域、あるいはそれに近いイメージです。もう少し具体的にすれば、
週刊新潮の「黒い報告書」のような感じと言えば
これ意図する例えとして合っているかは自信がありませんが。事件を書くわけではないのですが、あくまでイメージです。
これも、一つのマガジンにしてしまって、有料化記事にしてしまっても、いいかもしれません。ですから、怨念相手のことは、本人がもし読んだら
気がつくように赤裸々にリアルに書くわけです。
こうした機能をnote制作に持ち込むという構想です。万人に読まれなくてもいいという気持ちが、
有料記事へのハードルを下げてくれます。これは、私の最近の大発見です。私のnoteが売れるなどとは到底思えなかったのですが、「有料」の意味も多面的に捉える必要がありそうです。
マガジンに気がついてからは、noteプレミアムは視野に入っていました。一定量の文章作品を書いている実績と実感も、おそらくその気にさせているのかも知れません。このように思ってみると、
私のマガジンの意味は、私という「書く者」像を
表現できるかもしれません。私は、「私自身のための広告」で、文章は人で読まれるという考えを表わしています。その点では、無料マガジンが私の「書く者」としてのイメージが、有料記事への回路を開く契機になることがあるかもしれません。
ということを、マガジンを作る時に考えていたわけではありませんが、今、そんなことを想う境地になっています。
noteプレミアムへのアプローチ
そもそも、私は書いたものを本にできないか、と思っていたわけでした。自費出版を考えていたというわけではありません。65歳で定年退職後、同一業務を週3日程度のパート勤務で済むという、極上のライフスタイル環境の到来に、本一冊分の原稿を書くことを日課にしたことがあります。このことも、「なぜ、その本は読まれるのか」(マガジン『キャッツアイ』収容)で触れています。詳細は繰り返しませんが、執筆時間のブルーオーシャンに放たれたあの気分は忘れもしません。私に、書くことに専念できる生活環境が到来したのでした。そうした中で、2019 年からブログに突入したわけです。
記事が積み上がってくる中で、ブック化の夢想は
やはり源泉の動機からきているようで、昭和の文学的志向は捨てようとも思いません。といって、同人誌、自費出版、自費出版業界の企画出版、その領域は今のところ望まず、比較的簡易にできそうな電子出版もダイレクト・パブリッシングも、まだ、踏み込む何かが欠けています。

私は自分のnoteコンテンツの建築計画を考えているのかもしれない。
とりあえず、身近で現実的なブック化を引き寄せるものとして、マガジンに突入したわけでした。
私の、ブログを経てnoteに至り、マガジンへの着手は過去からの経緯の上に成り立っていることに
今更気がつけば、マガジン化の仕上げにうろたえ、たじろいでいることは、なんという浪費、己の初心を放擲したあげくに、道草をしているだけではないか。
また、noteには記事のバックアップというありがたい機能もあることを念頭に進んできたわけであり、早々に一旦の完成を見て、バックアップをとらなければなりません。LINE BLOGの頃、一記事ごとにワードでコピーによるバックアップをしていたことは、もう繰り返したくなく、結構手間なのです。
このように思い至ってみれば、マガジンの完成に道草を喰っている暇などないことです。noteプレミアムへの着手も、もうそこです。金銭化ということでなく、最近始まった有料記事への「高評価」づけというしくみも魅力的です。金銭化収入化ということではなく、有料記事が買われるとは、大きな実績であり、手応えとして感じられる筈でしょう。
私はプレミアムにした時に、記事へのコメントが付いてきたらどうつきあおう、耐えられるだろうか、とぼんやり浮かべていました。無料noteにこそコメントが書かれることであって、プレミアムにすればそれを拒否する機能があるとは、最近気づいたはずかしい話です。
ある日突然、何で私にチップが!?
一週間前のこと、スマホのメールを見ていたら、
noteからの通知があり、私の記事にチップが届いたことがわかりました。「佐久間宣行∞福留光帆」副題「ゴッドダンとシンデレラ」にです。これは晴天の霹靂であり、こんなうれしいことはありません。これは、SungerBook「舌鼓」のマガジンに収容していて、広い意味での文芸批評扱いとしています。このような評価を実感できる体験は、なんということでしょう。「豚もおだてりゃ木に登る」でこれは、あらたな制作にガソリンをぶち込んでいただきました。しかも、これは、言葉だけの評価ではないという意味でハイオクです。
マガジン「SungerBookナンバー1」の先を視野に入れなければなりません。もっともっと記事の堆積を構成してこそ、新たな可能性が拓けるはずです。もう躊躇するというような悠長さから脱出し、ネクストステージへ歩を進めなければなりません。★
註釈
※①
音楽の歌詞を題材にした記事があるのですが、著作権をクリアする為、JASRACの許諾のあったブログを活用したという経緯があります。noteにあげています、ご参照「WAKE UP―抒情の意味」(マガジン『舌鼓』収容)。
※②
性暴力被害を公表したジャーナリスト・伊藤詩織さんの初監督作品『Black Box Diaries』をめぐり、無断で映像や音声が使用されているとして、伊藤さんの元代理人らが「取材源の秘匿が守られていないなど人権上の問題もある」などと映画の内容変更を求めている。
