
[特別無料公開]『木更津キャッツアイ』が成し遂げたドラマ史の転換|成馬零一
成馬零一さんの新著『テレビドラマクロニクル 1990→2020』発売を記念して、本書から宮藤官九郎編の初期の代表作『木更津キャッツアイ』についての章を無料公開します。
「地元」と「普通」を主題にした本作は、一部の識者からバブル批判の文脈で称賛されます。しかし、そこで本当に描かれていたのは、均質化した郊外と「普通」すら困難になりつつある時代の訪れでした。
2002年の『木更津キャッツアイ』
『池袋ウエストゲートパーク』で高い評価を得た宮藤官九郎は、翌2001年、織田裕二主演のドラマ『ロケット・ボーイ』(フジテレビ系)を手がける。アラサーの青年3人の自分探し的な物語は、山田太一脚本の『想い出づくり。』や『ふぞろいの林檎たち』を彷彿とさせる青春群像劇。『池袋』を見て、宮藤の本質は家族愛や友情を描けることだと思ったプロデューサー・高井一郎による抜擢だった。
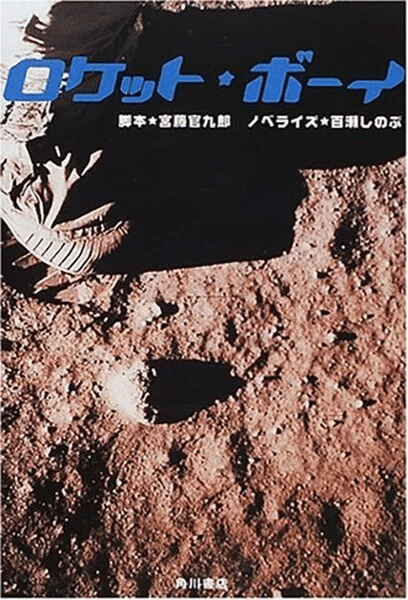
▲『ロケット・ボーイ』(小説版)
残念ながら本作は、放送中に織田裕二が椎間板ヘルニアで入院してしまったことで、話数が全11話から7話に短縮されてしまう。そのこともあってか、宮藤の作家性が存分に発揮されていたとは言えず、ソフト化もされていないため、今では幻の作品となっている。
後の『ゆとりですがなにか』(日本テレビ系、2016年)にも通じるシリアス路線だったため、完全な形で仕上がっていれば、今のクドカンドラマの傾向とは違う流れが生まれていたかもしれない。『池袋』は原作モノでチーフ演出の堤幸彦のカラーも強く、『ロケット・ボーイ』は不完全燃焼。そのため宮藤の評価は保留とされた。
その意味で、ドラマ脚本家としての作家性が正当に評価されたのは、翌2002年に放送されたドラマ『木更津キャッツアイ』(以下『木更津』)からだと言えるだろう。
本作は千葉県木更津市で暮らす若者たちを主人公にしたコメディテイストの青春ドラマだ。実家の理髪店「バーバータブチ」を手伝いながら、毎日ブラブラしているぶっさん(岡田准一)、一人だけ大学に通う童貞のバンビ(櫻井翔)、プロ野球選手を目指す弟と比較されコンプレックスを感じている実家暮らしで無職のアニ(塚本高史)、学校の先輩と結婚して居酒屋「野球狂の詩」を切り盛りする子持ちのマスター(佐藤隆太)、神出鬼没で何を考えているかわからないうっちー(岡田義徳)。彼ら5人は、高校時代に同じ野球部だった仲間で、高校を卒業しても地元に残り、草野球をしながら仲間たちと戯れる日々を送っていた。ずっと続くかと思われていた彼らの日常だったが、ある日、ぶっさんが余命半年の癌(悪性リンパ腫)だと判明する……。
劇中では、ぶっさんが自分の死を受け止めた上で、地元で「普通」に生きようとする姿がコミカルに描かれる。
高校卒業後も地元に留まり仲間たちと学生時代の昔話ばかりしているぶっさんたちのライフスタイルは、2014年に『ヤンキー経済 消費社会の主役・新保守層の正体』(幻冬舎新書)でマーケティングアナリストの原田曜平が定義した〝マイルドヤンキー〞の姿を12年前に先取りしていたと言える。
一方で描かれるのが、ぶっさんたちが結成した怪盗団「木更津キャッツアイ」の物語だ。
彼らが毎回、何かを盗むことで、それが結果的に、美礼先生(薬師丸ひろ子)を筆頭とする、日々の生活で心を病んでいた人たちを救う結果になるという、アクロバティックな物語が展開されていく。
脚本の構成は野球の試合に倣い「表」と「裏」の二部構成の全9回となっており、表でちりばめられた伏線が、裏で回収されるというパズル的な作りとなっている。
うまいと言えばうまいが、ご都合主義的といえばご都合主義が続く強引な展開の連続だが、ベースにあるのがコメディなので、笑っているうちになぜか納得させられてしまう。クドカンドラマの中でもっともチャーミングなとっ散らかった魅力があるのは、この『木更津』だと言って間違いないだろう。
プロデューサーは磯山晶、演出は金子文紀と片山修、宮藤自身も第7回の演出を担当している。後のクドカンドラマを支える座組がここで完成しており、視聴者がイメージするクドカンドラマのスタイルは、この『木更津』からはじまったと言えるだろう。
磯山と宮藤は、『池袋』で楽しかったオリジナルエピソード(第7〜8話)のような作品を作ろうと考え、後から主人公が死ぬことや泥棒といったモチーフが追加されていった。その際に参照されたのがガイ・リッチー監督の『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(1998年)とホ・ジノ監督の『八月のクリスマス』(同)。前者は時系列が錯綜したポップなクライムムービー、後者は難病モノの静かなラブストーリーだ。
そこに宮藤が野球という養素を持ち込んだ。彼が手がけた舞台『熊沢パンキース』をたたき台とし、『ロック、ストック』と同じガイ・リッチー監督の映画『スナッチ』(2000年)の泥棒モノというテイストを混ぜることで、『木更津』の骨組みは作られていった。(1)
『パンキース』から『キャッツアイ』へ
『熊沢パンキース』は1995年に大人計画の部分公演で、宮藤が手がけた演劇で、2003年には『木更津』の成功を受けるかたちで『熊沢パンキース03』として再演もされている。本作は田舎の居酒屋を舞台に、バリ島で伝染病に感染した草野球チームの監督の元に部員たちが集まって騒ぐことで感染が広がっていく様子を描いた一幕モノの物語。2020年7月にWOWOWで放送された『熊沢パンキース03』の映像作品を久しぶりに観たのだが、田舎の閉鎖的で乱暴な人間関係を悪意に満ちた笑いで見せており、じわじわと感染症が広がっていく様子は、コロナ禍に見ると妙な説得力があり、改めて宮藤の先見性に驚かされた。
本作について宮藤は、「野球チームのメンバーたちが飲み屋に集まってグズグズしてる話です」と語り、当時アルバイトをしていた飲み屋の「閉鎖的で馴れ合いの関係に対して、すごく悪意を持っていた頃」に書かれた作品だと答えている(2)。宮藤はスナックや草野球チームといったコミュニティに対してアンビバレントな感情を抱えている。それが悪意に振れると『熊沢パンキース』や『鈍獣』となり、憧れ目線でポジティブに描くと『木更津』や『あまちゃん』になる。これはマーケットの規模が狭い小劇場演劇と不特定多数の視聴者を対象にするテレビドラマで書き分けているとも言える。
興味深いのは、こういった田舎の小さな共同体を描く際に宮藤が必ず「死」にまつわる要素を盛り込んでいること。『熊沢パンキース』では伝染病、『木更津』では癌、『鈍獣』では「殺しても死なないゾンビ的な男」と描かれ方は違うものの、狭いが心地良い人間関係の奥底で、死の影が刻々と胎動しているという物語を宮藤は描いている。
これは、日本の地方、もしくは日本そのものに対する宮藤の認識なのだろう。一見、時間が止まっているように見える狭くて心地よい世界だが、実は終わり(死)が刻々と迫っている。そのことにいち早く気づいてしまったのが、『木更津』のぶっさんだ。被害者遺族を主人公にした『流星の絆』(TBS系、2008年)を筆頭に、宮藤の作品には常に〝死〞というモチーフが見え隠れするが、大きな転機となったのは『木更津』だろう。
宮藤は、ぶっさんを演じた岡田准一の演技に対し「僕の本に足りなかった部分を補ってくれた」(3)と以下のインタビューで語っている。
一番印象的だったのは、ドラマ1話で「野球狂の詩」に集まって、「俺死ぬんだよ」って告白するところ。僕はもっとさらっと言って、みんなにちゃらっと流されて、どんどんどんどん怒りがヒートアップしていくみたいなのを想像していたんですけど、岡田君は、もっとウエットに、死ぬっていうことにリアルにこだわりたいって言ってて。「どっちがいいのかなあ?」って思ったんですけど、オンエア見たらぜんぜん岡田君のやり方の方が正解だった。(4)
ユリイカ「特集 テレビドラマの脚本家たち」(2012年5月号)のインタビューでも、宮藤はこのシーンについて語っている。(リハーサルを見学した時に)5人の演技のトーンが重かったので、「軽い方に作ってください」とお願いした宮藤だったが、岡田准一と櫻井翔の真面目な芝居のやりとりだと、どうしてもトーンが重くなってしまう様子を見て、考え方を改める。
参ったな、どうしようかなって思って、でも待てと。これって俺が書こうと思っても書けないものだから、これはこれでいいんじゃないかって。まあひとつには、これを最初にやっておけばそのあといくらでもふざけられるって思ったのと、自分が想像した通りにならなかった時、そこで無理やり押し通さずに、この重いシーンをふまえて次の回からまた本を書けばいいんだってことに気がついたんです。(5)
俳優たちの演技が、作品の方向性を変えたことがよくわかる発言だ。同時にドラマ脚本家としての宮藤のスタンスもよくわかる。一貫した強固な作家性を持つ松尾スズキに対して宮藤には強烈な作家性はない。強いて言うならば、あらゆるものを咀嚼して自分の世界に取り込み許容してしまう混沌こそが宮藤の作家性なのだろう。ジャニーズアイドル主演の青春ドラマを難病モノでやるという制約の多い枠組みの中で『熊沢パンキース』をセルフリメイクしたことで、メジャーな明るさへと反転したのだ。
バブル批判としての「地元」と「普通」
評論家の浅羽通明が2008年に上梓した『昭和三十年代主義 もう成長しない日本』(幻冬舎)は、『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』(NHK、2000〜05年)や映画『ALWAYS 三丁目の夕日』(2005年)といった作品のヒットに見られるノスタルジーブームを肯定的に考察した評論集だが、『木更津』についても「地元つながりと普通」という題で分析されている。
浅羽は本書の中で、2000年代に起きたノスタルジーブームの背後には、経済成長の魅力が失われ、昭和30年代的な堅実な生き方へのゆり戻し願望が現れているのではないかと語る。中でも興味深いのが宮部みゆきの小説『模倣犯』(小学館、2001年)に対する考察だ。浅羽は『模倣犯』に登場する劇場型犯罪をおこなう殺人犯ピースの中にある「自分は特別な人間である」という「肥大した全能感」は、1980年代のバブル経済が生み出した面白主義の行き着いた末に登場したものだと指摘する。そして、『模倣犯』は、ピースの(80年代的な)面白主義を、豆腐屋を営む老職人や実家の蕎麦屋を手伝い堅実に生きる高井和明ら昭和30年代的価値観を生きる「普通」の人々が打ち破る話だと捉えている。
浅羽はこの構図を、『木更津』にも、そのまま当てはめている。浅羽は、ぶっさんたち『木更津』の登場人物を「根拠なき全能感、上昇志向を身上とするバブリーな世代の対極を、日々生きている人々」だと語る。そして『木更津』のキーワードは「地元」で次に「普通」があると指摘。この二つは「ひとつながり」で「キャッツ」のメンバーには「地元から東京そのほかへ駆け上がってゆこうとする上昇志向がきれいにないのです」と驚く。
「地元」と「普通」を肯定的に描いているという観点から、『木更津』と宮藤を絶賛する声は少なくない。宮藤が脚本を手掛けた映画『ゼブラーマン』のコミカライズを担当した漫画家・山田玲司もその一人だ。山田は「宮藤官九郎の登場は文化面においてひとつの事件だ」と語り、宮藤のオリジナルドラマには「中心を目指さない主義がある」(6)と絶賛する。
誰もが東京やアメリカを目指したがる世の中において、『木更津〜』では、まさに木更津だけで生きている奴らの〝東京に行かなくても楽しくやってるも〜ん〞という意識がしっかりとつくり込まれてるでしょ。みんな根がヒッピーなんだよね。オレは、こういう世界をつくれる秘密がどうしても知りたくて、宮藤君に「キミ、田舎出身であることを恥じてないよね?」って訊いたら、やっぱり「恥じてません。東北の、それも仙台からもすごく遠いところに住んでいても、毎日が楽しかったから」なんて言う。そのときの原体験が『木更津〜』には生かされているんだなぁ、と。(7)
浅羽も山田もバブル批判として『木更津』を評価する。「東京」に対する「地元」、バブルの豊かさがもたらした「肥大化した自意識」に対する「普通」という見立てだが、残念ながらどちらも、1980年代のバブル景気に対する批判意識が強いあまり、『木更津』と宮藤の評価を少し見誤っているように感じる。バブル批判として「貧乏」を配置するやり方は、1990年代前半に野島伸司の一連の作品で展開されていたもので、別冊宝島『80年代の正体!』で展開された1980年代批判や、橋本治の『貧乏は正しい!』(小学館、1995年)などで展開される考えに近い。
高度経済成長が終わり、バブルが崩壊したのなら、再び貧乏な生活に戻ればいい。東京で暮らせないのなら自然に囲まれた田舎で自給自足をすればいい、というノスタルジー志向の意見は1990年代初頭にも囁かれた。しかし残念ながら、バブル崩壊後の日本に訪れたのは昭和30年代的な貧乏ではなく〝貧困〞であり、東京という大都市と対になるのは人情溢れる共同体としての田舎や下町ではなく、ショッピングモールとファストフード店が立ち並ぶ均質化した〝郊外〞だった。
元々『木更津』は、高校野球のレベルが高い千葉県を舞台にしようと考えており、当初は西船橋や松戸が舞台の候補地だったという。ちなみに当初のタイトルは『西船橋死ね死ね団』だった。(8)
逆に言うとこれは、千葉県の郊外ならどの街でも良かったということである。映像の力で印象深いロケーションは多数あるものの、舞台となる木更津は、日本全国どこにでもある寂れた町として描かれている。
確かに『木更津』はホームレスのオジー(古田新太)が町の守り神として住人から愛されていたり、「やっさいもっさい」のような町の名物となっている踊りを木更津市民が全員で踊ったりと、地縁共同体のつながりが強く『ALWAYS 三丁目の夕日』のような昭和的な温かい共同体のような描き方もされている。そのため、町の持つ固有性が引き立ち、魅力的な舞台となっているが、漫画的なファンタジー性や民話的なレイヤーを外した時に見えてくるものは、本来はどこにでもある郊外であり、だからこそ、当時の若い視聴者が、これは自分たちの物語だと思えたのだ。
『木更津』と『ヒミズ』
また、『木更津』のテーマと言える「普通」だが、確かに浅羽が指摘するように、「普通」と「地元」は本作ではセットで語られる。しかし「普通」が一番と言うのが余命半年の(普通の日常が失われようとしている)ぶっさんだということは忘れてはならない。つまり、ここで言う普通とはある種のやせ我慢であり、むしろ普通(平常心)であろうということそれ自体が一種の抵抗なのだ。
『木更津』と同じ頃、「普通」であろうとする中学生を主人公にした漫画があった。週刊ヤングマガジン(講談社)で2001〜02年にかけて連載された古谷実の『ヒミズ』だ。
本作の主人公・住田は物語冒頭「オレは「自分も特別」などと思い込んでいる「普通」の連中のずーずーしいふるまいがどうしても許せん」「ぶっ殺してやりたくなる」「要するにだ‥‥普通ナメんな!普通最高!!‥‥‥‥っていうお話だ」と言い、漫画家を目指している同級生を激しく批判する。だが、そんな住田は両親が離婚しており、家は貧乏。やがて母親は男と駆け落ちして家から出ていってしまう。そして離婚した父親は600万円の借金をして、そのお金を住田が払わなければならなくなる。追い詰められた住田は、家に来た父親を撲殺してしまう。『ヒミズ』は、大ヒットしたギャグ漫画『行け!稲中卓球部』(講談社、1993〜96 年)などで知られる古谷実の作風が、ギャグからシリアスな暗黒青春漫画へと転換した作品として知られている。
元々、古谷は『僕といっしょ』(講談社、1997〜98年)でバブル崩壊以降の日本の荒涼とした空気をダメ人間同士の馴れ合いという形で描いていたが、『ヒミズ』でシリアス路線に舵を切って以降は、特別な力を持たない男たちが、どうやって普通の人間になるのかを真剣に模索する物語と並走する形で、普通の生活からあっけなく転落して強盗や殺人に手を染めてしまった人々の姿を描くようになっていく。『木更津』のぶっさんは末期癌の中で本当にやりたいことを探しながら普通に生きていこうとし、『ヒミズ』の住田は殺人犯となった後の「おまけ人生」の中で、自分より悪い人間を殺して自殺しようとする。二つの物語は一見真逆に見えるが、「普通」という枠組みから外れてしまった若者の物語という意味でとても似ている。
浅羽や山田が言うように「普通が一番」という価値観が、バブル世代に対する批判であり、特別な人間になりたいという自意識が肥大した若者に対するある種のカウンターであることは間違いないだろう。しかし「普通」が真面目に働けば誰にでも手に入るものという認識は、もはや失われている。
宮藤も古谷も、2000年代の日本から、かつて一億総中流社会と言われた豊かな社会が崩壊し、格差や貧困という言葉が飛び交う新しい時代がはじまっていることを肌感覚で理解していたのだろう。どちらも20年近く前の作品だが、この認識は、今もまったく古びていない。
『木更津』はドラマ業界に、どのように受け止められたのか?
宮藤の出世作となった『木更津』だが、放送当時はどのように受け止められたのか?

脚本家の岡田惠和は「宮藤さんがドラマ界に現れた頃のことはよく覚えてます」(9)と語っている。『木更津』の第1話が放送された翌日、当時仕事をしたドラマチームでの飲み会で、本作が話題になった際、ベテランと若手で意見が真っ二つに分かれたと、岡田は回想する。
「何喋ってるのかさっぱりわからん」「いったい何の話なんだ? あれは、ふざけすぎ」 ベテランプロデューサー達には理解できなかった。なのに皆が面白い! と絶賛するので、悔しかったのかもしれませんね。
対して若手は、言葉には出さないけど、「あれがわからないんじゃ終わってんな、このおっさん」 と顔に書いてある感じ。でも「どこが面白いんだ?」 と問われると、うまく言葉にすることが出来ない。そんな感じでした。(10)
そんなベテランと若手の反応を見ながら、岡田は「よわったなぁ」と思ったという。宮藤の新しい作風に脅威を感じながらも、それ以上に「かなり好きだなこれ」と混乱し、自分がやりたかったのはこういうことだったのかもしれないと、憧れを抱いたという。しかし「今から下の世代に憧れるってのもな、ちょっと辛いしな」と思い、「忘れよう、影響受けるのやめよう」と決めて、その後、宮藤と同じジャンルのドラマを書くことは、絶対にやめようと考えたという。(11)
同業者の先輩に、ここまで言わせるのだから、すごい才能である。
だが、宮藤の登場によりドラマ界の空気が一変し、世代交代が起きたかというと、そうはならなかったと岡田は振り返る。宮藤の世界が「ダントツに個性的」で主流にはならなかったからだ。(12)
ドラマ界は宮藤さんを受け入れた。でもそれはある意味、出島的な特別区みたいなポジションです。ドラマ界の地図を塗り替えるというよりは、地図にひとつ島を増やしたような変化。そこに関してはベテランたちもどこか寛容です。なぜなら出島なんで、自分たちの領土は守られてるから。そこでの活動は許す、みたいな。まさに「クドカン特区」ですね。「クドカンだからねえ」 「あぁクドカンでしょ? はいはい」みたいな許され方とでも申しましょうか。
爆発的に人気あるけど、どうも世帯視聴率はさほど芳しくないという、だからどこか長老たちのプライドも犯さないという、独特なチャーミングなポジションも獲得しました。嫌ですね、そんな長老。(13)
『木更津』が放送された2000年代初頭は、視聴率という評価軸がまだまだ絶対的だった。『踊る大捜査線』や『ケイゾク』のような視聴率は高くないが、放送終了後に映画化されて大ヒットするという作品も現れはじめていたが、これらの作品は、視聴率が低いと言っても、10%台前半は獲得していた。
しかし『木更津』は野球の構成に合わせた全9話で平均視聴率10.1%(関東地区・ビデオリサーチ)で、これ以降のクドカンドラマはシングル(一桁台)が当たり前になっていく。近年のドラマは、シングルが常態化しており10%台で成功作と言われるぐらい合格ラインは下がってしまったが、当時のシングルは、打ち切りでもおかしくない数字である。思うに『木更津』とクドカンドラマの登場は、視聴率一辺倒だったテレビドラマの評価が、DVD等のソフト消費とネットで話題になるSNS消費へと大きく分裂していく始まりの作品だったのだろう。
『キャラクター小説の作り方』に書かれた木更津キャッツアイ論
テレビシリーズ終了直後に語られた、もっともクリティカルで早かった『木更津キャッツアイ』論がある。大塚英志の『キャラクター小説の作り方』(講談社現代新書、2003年)だ。
本書はまんが原作者や小説家としても知られる評論家の大塚が、ライトノベル専門誌「ザ・スニーカー」(角川書店)で連載していた、ライトノベルの書き方についてのレクチャーをまとめたものだ。
本書ではライトノベルのことを「キャラクター小説」と呼んでいるのだが、キャラクター小説について大塚は、以下のように定義している。
①自然主義的リアリズムによる小説ではなく、アニメやコミックのような全く別種の原理の上に成立している。
②「作者の反映としての私」は存在せず、「キャラクター」という生身ではないものの中に「私」が宿っている。(14)
そして「自然主義の立場に立って「私」という存在を描写する「私小説」が日本の近代小説の一方の極だとすれば、まんが的な非リアリズムによってキャラクターを描いていく」小説が「キャラクター小説」(=ライトノベル)であると、大塚は語っている。(15)
なお、筆者は生身の俳優が、まんがやアニメのキャラクターを演じる作品をキャラクタードラマと呼んでいる。そして、この連載で堤幸彦の演出とリミテッドアニメの方法論の類似性を指摘したが、この〝キャラクタードラマ〞という着想は、本書で書かれた大塚のキャラクター小説論が下敷きとなっている。中でも大きな影響を受けたのが、「第一〇講││主題は細部に宿る」で語られる『木更津キャッツアイ論』である。
大塚は『木更津』を、新海誠の自主制作アニメ『ほしのこえ』(2002年)と双璧を成す良質な作品だと評す。そして「細部」をいかに描くかという今回の問いに対して正常な答えを用意している作品は「近頃の作品ではまんがやアニメ、小説を含めても『木更津キャッツアイ』ほど良く出来た作品はない」(16)と絶賛している。
大塚が『木更津』を評価する理由は大きく分けて二つ。一つは、作品の細部(映像やギャグ、小ネタ)が作品のテーマを語る手段としてつながっているという手法面の評価。
もう一つはその手法によって語られる『木更津』の「テーマ」についてだ。
大塚は、『木更津』と押井守監督のアニメ映画『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』を比較し、主人公のぶっさんが生まれてから一度も東京に行ったことがない(木更津の外に出たことがない)ことに注目。地元で自己完結している『木更津』の世界は『うる星やつら』の主人公たちが友引町という町で文化祭前日という日々を繰り返している「外側のない世界」を生きていることと同じだと喝破する。
生まれた街から未だに出たことのないぶっさんが象徴するのは彼らの仲間たちが共有する「このままずっと今の宙ぶらりんの状態でいたい」という気分でしょう。高校を出たものの大人にはなりきれず、そしてできることなら大人になることをなるべくなるべく順延していきたい││木更津という街は彼らのそんな甘えを許してくれる街として描かれます。木更津の外に行ったことがない、というぶっさんの設定はそんなふうに作品の主題を暗示しているわけです。(17)
映画版『ケイゾク』のサブタイトルにも引用された、『ビューティフル・ドリーマー』は、1984年に作られたオタクアニメの金字塔的な作品だ。ヒロインのラムの夢の中に閉じ込められた主人公たちが、文化祭前日を延々と繰り返すというループ構造の世界観は、後のオタク向けアニメに大きな影響を与えた。
この時間の止まったユートピアとしての友引町は、1980年代に誕生した高度消費社会の象徴であると同時に、自分の好きなものだけに囲まれたオタクの理想郷である。『木更津』もまた、サブカルチャーの集積で成立する夢の世界だ。例えば、第5回には、ぶっさんが大ファンの俳優である(本物の)哀川翔が木更津を訪れる。
木更津という「閉じた街」は外側の現実からぶっさんたちを守る一方で、Vシネマというフィクションの世界とは地続きなのです。そもそも木更津キャッツアイなどと名乗ってしまうことが(無論、北条司さんのまんが『キャッツアイ』からの借用です)大人になりたくない彼らが「現実」ではなく「フィクション」の上で遊んでいたいという心情を示しています。前の講義で記したように、アニメやフィクションの中では人は現実の中で強いられるように成長したり死んだりする必要はないからです。だから「木更津」は『うる星やつら』のように閉じた世界である必要があるのです。(18)
フィクションの世界の住人でありながら〝いち早く自分が死ぬことに気づいてしまった〞ぶっさんを主人公にすることで「終わり」はいつかやってくるという現実を描いたことを、大塚は高く評価する。
最終話。ぶっさんは死にそうになりながら、何度も生き返り、死にそうで死なない状態のまま生き続ける。そしてその後については、「それからぶっさんは1年以上しぶとく生き延びて、22歳でこの世を去りました」と、うっちーの英語のナレーションであっさりと語られる。ぶっさんの死の瞬間を描かなかったため賛否が分かれた最終回だったが、大塚は以下のように評価する。
アニメやまんがのように「死なない身体」と「壊れゆく身体」の間を宮藤官九郎氏は最後にぶっさんを行き来させます。そのプロの技術にぼくは最大の賛辞を贈りたいと思います。
こんなふうにして、アニメやまんがや映画のルールとしてある死なない身体、記号的身体でドラマを最後まで構成しながら、けれども「成長を保留する世界」の外側の、人が成長し、あるいは死んでいく「現実」の所在をきっちりと示して「木更津キャッツアイ」は終わりました。(19)
ただ死を描くだけならば、リアリズム的手法で作られた難病モノのドラマと変わらない。記号的な「死なない身体」というキャラクター的表現を用いて「死」を描いたからこそ、大塚は『木更津』を評価したのだろう。
「アトムの命題」と、ジャニーズアイドルのキャラクター的身体
『多重人格探偵サイコ』(角川書店1996〜2016年)などのまんが原作者としても知られる大塚英志は、記号的な絵柄で描かれた非リアリズムのキャラクターが傷つき死んでしまう身体を持つという戦後漫画の矛盾を、手塚治虫の『鉄腕アトム』(光文社、1952〜68年)に登場する心を持ったロボット・アトムの名から「アトムの命題」と名付けた。アトムは天馬博士の死んだ息子・飛雄を模して作られた少年型ロボットで、成長しないことを理由にサーカスへ売り飛ばされてしまう。「アトムの命題」には、ダグラス・マッカーサーに「12歳の少年」と言われた未成熟な日本人がいかに大人になるかというテーマが込められており、だからこそ戦後の漫画やアニメに脈々と受け継がれていく。
『木更津』を読み解く大塚の目線は「アトムの命題」と同じものである。しかし、実写映像であるテレビドラマで展開された際に『木更津』で起きていたことは、生身の人間(岡田准一)が記号的な死なないキャラクター(ぶっさん)を演じた際に起こる矛盾という「アトムの命題」とは真逆の現象である。
これが「アトムの命題」と同じ印象をもたらすのは、ぶっさんを演じる岡田准一がV6、バンビを演じる櫻井翔が嵐というアイドルグループに所属するジャニーズアイドルだったからだろう。
ジャニーの命題
おそらく、男性アイドルという生身の少年の身体を用いて「アトムの命題」に挑んでいたのが、ジャニーズ事務所を設立したジャニー喜多川だったのではないだろうか?
ある日、ジャニー喜多川は自身が運営する「ジャニーズ少年野球団」と共にミュージカル映画『ウエスト・サイド物語』を観劇する。映画に触発されたジャニー喜多川は、1962年にチームから選抜された4人の少年(真家ひろみ、飯野おさみ、中谷良、あおい輝彦)によるジャニーズ事務所初のアイドルグループ・ジャニーズを結成した。(20)
「歌って踊れるミュージカルスターのいる少年版・宝塚を作る」それこそがジャニー喜多川の夢だった。当初は10代の若い女性に限定的だったファン層はテレビ出演にともない人気を年々拡大。1990年代にSMAPが登場したことでその人気は国民的なものへと変わっていった。アメリカのミュージカルにあこがれて、少年たちの帝国を目指したジャニーズ喜多川の歩みは「12歳の少年」と言われた戦後日本の歩み、そのものだった。
ジャニー喜多川がミュージカルの世界を目指したのは、虚構性の高いミュージカルの空間ならば「成長しない少年たちのユートピア」が体現できると思ったからだろう。だが、戦後日本の娯楽産業はテレビという新興メディアを中心に回りはじめ、ジャニーズアイドルもまたテレビの世界に進出していく。しかし、テレビは成長していく身体が生々しく露呈してしまう身も蓋もないリアリティショー的な空間でジャニー喜多川の理想とは真逆の世界だった。そんなテレビの世界で山口百恵や松田聖子といった女性アイドルは、少女から女に成熟し、やがて母になるというシンデレラストーリーを体現した。
ジャニーズの男性アイドルも、1980年代までは大人になると卒業する期間限定の存在だった。しかし1990年代にSMAPが登場して以降、ジャニーズアイドルは、少年(アイドル)のまま大人になることを要請されるようになる。
これこそがジャニーズに課せられた「ジャニーの命題」とでも言うような矛盾だった。(21) アイドル、特にジャニーズ事務所に所属する男性アイドルの特殊性は、アイドルという不安定な立場のまま、俳優、歌手、バラエティタレントといった多様な仕事を務めることにある。元々、アイドルは、歌手や俳優といった本業を決める前の若いタレントの暫定的な立場、つまり、子どもが大人に移行する前のモラトリアム期間である。その意味でアイドルとは未成熟で中途半端な存在なのだが、岡田たちジャニーズアイドルは、アイドルという立場を保ったまま様々な仕事に取り組む。今や、30代40代の中年男性でありながらアイドルであるという立場は当たり前の状態となっている。
成長できない少年の肉体を保ったまま、成熟した大人になることが要求されるという、ジャニーズアイドルが抱える「ジャニーの命題」は、大塚の提唱する「アトムの命題」を生身の肉体で体現する存在だと言えよう。
『ワールドシリーズ』が描いた「ばいばい」
『木更津』は、放送終了後、DVD -BOXのセールスやレンタルで人気に火が付き、翌2003年には映画『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』が公開される。

本作はテレビシリーズのその後を描いたもので、なかなか死なないぶっさんが、ユッケ(ユンソナ)という韓国人女性と結婚したり、木更津でロックフェスを開いたりする中で、オジーに変装した村田ジョージ(内村光良)という偽札作りを行っていた男とキャッツが対決するといったもの。物語はお祭り騒ぎの連続で、なぜか南の島に漂流したり、ゴミから生まれた怪獣が登場したりといった荒唐無稽な展開が続いていく。物語は30年後におじさんとなったキャッツの面々がぶっさんに似た若者に昔話を聞かせるという回顧形式ではじまり、ぶっさんが医師に今までの話を聞かせていたという形式で終わるため、どこから本当でどこから嘘かわからない虚実入り交じったホラ話だったようにも見える。
テレビドラマの中心にあった「ぶっさんの死」というテーマは後退し、コメディとして楽しかった側面を拡大させたイベントムービーとなっていた。
そして、2006年に制作された完結編となる映画『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』(以下、『ワールドシリーズ』)は、「ぶっさんの死」をしっかりと描いた別れの物語となっていた。
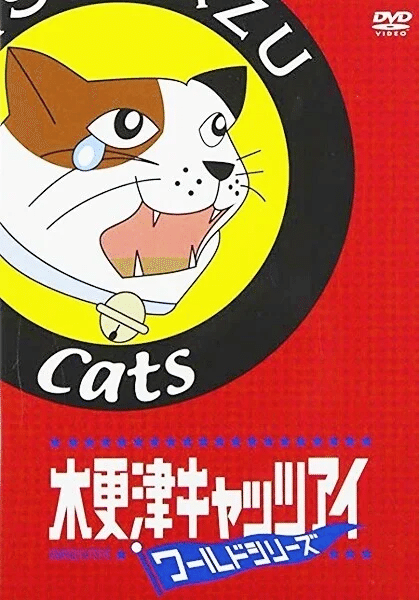
舞台はぶっさんが死んで3年後。木更津市役所の職員となったバンビ以外のキャッツのメンバーは木更津を去り、みんな別れて暮らしていた。ある日、ぶっさんの声を聞いたバンビは、アニとマスターに会いにいく。アニは秋葉原でフリーター、離婚したマスターは大阪でたこ焼きを売っており、それぞれ冴えない日々を送っていた。
3人はぶっさんの死を看取れなかったことを後悔し、「ばいばい」と言いたかったと後悔していた。「それを作れば彼はやってくる」というぶっさんの声に従い、映画『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)のように、ショッピングモール建設予定地に野球場を作り、ぶっさんの復活を目論む3人。しかしそこに現れたのは自衛隊から逃亡したうっちーと外国人野球選手のゾンビ軍団だった。
成り行きから、うっちーを追いかけてきた自衛隊教官の杉本文子(栗山千明)と彼女が率いる女子野球チームと試合をすることになったキャッツのメンバー。そこに、死んだはずのぶっさんとオジーが現れる……。
物語は成長したバンビの視点で始まる。キャッツのメンバーはバラバラになり、モー子(酒井若菜)はバンビと別れて先輩の猫田(阿部サダヲ)と結婚。美礼先生は木更津の市長選挙に立候補。テレビシリーズでは永遠に変わらないかのように見えた木更津は、たった数年で変貌していた。
宮藤はいつまでも変わらない閉じた世界を描いているように見えるが、自分で作った作品内ルールやキャラクターの設定を容赦なく破壊してしまう作家でもある。
『木更津』の後に書かれた恋愛ドラマ『マンハッタンラブストーリー』(TBS系、2003年)には宮藤が抱えている「何も信じていない」刹那的な感覚が強く現れていたが、この『ワールドシリーズ』の導入部は『木更津』の世界が好きだったファンであればあるほど、やりきれないものがある。
もしも『木更津』が、漫画やアニメだったら『うる星やつら』のような時間の止まった世界を描くコメディ作品として今も延々と続編が作られていたのかもしれない。しかし本作は生身の俳優が演じる実写作品である。
テレビシリーズが放送された2002年から4年が過ぎ、出演俳優は皆、人気者となっている。スケジュールの都合もあったのだろうが、おそらく彼らの年齢が若いうちに作り手はシリーズを終わらせたかったのだろう。
テレビシリーズに比べるとキャッツの俳優たちの演技力は大きく成長している。特にバンビを演じた櫻井翔の成長はめざましい。序盤に一人で登場する場面には画面を支える安定感があり、それがそのまま童貞で青臭かったバンビが社会人として落ち着いた姿ともシンクロして見える。一方、ぶっさんは3年前に死んでいるため、22歳のままである。ぶっさんは、キャッツの面々と楽しくはっちゃけるのだが、やがて、生きているキャッツと時間が止まったままのぶっさんの齟齬が見えてくる。
テレビシリーズのぶっさんは、フィクションの住人でありながら、いち早く「自分が死ぬこと」に気づいてしまった存在であり、ぶっさんを看取る木更津の住人たちの方が時間の止まった世界を生きる(変化しない)キャラクターだった。
しかし『ワールドシリーズ』では逆に、木更津の住人たちはみんな、時間と共に変化する人間として描かれており、ぶっさんは一緒に復活したオジーや、過去に日米親善野球に参加した外国人野球選手のゾンビたちと同様、時間の止まった死者なのだ。
物語は生者(成長する人間)と死者(時間の止まったキャラクター)の対比で進んでいき、やがて死者であるぶっさんを野球という儀式によって成仏させることで過去と決別するという話になっていく。
アニ「ごめんな……俺らもう大丈夫だから……こんなこと言ったら悪いけど……もう俺らにはぶっさん……もう必要ねぇっつーか、いても、申し訳ねえけど合わせらんねえっつーか」
公平「……言いたいことはそれだけか?」
一同「……」
公平「で? 結局なにが言いてえんだよ、アニ」
アニ「……わざわざ呼んどいてなんだけど、ぶっさんそろそろ帰ってくんねえ? 」(22)
延長10回。杉本の打ったボールを追って森の奥へと走っていくぶっさん。キャッツのメンバーが追いかけると、ぶっさんの姿はなくミットだけが置かれていた。ミットの中にあるボールにはサインペンでバイバイと書かれていた。
キャラクターでありながら、いち早く自分が死ぬことに気づいたぶっさんは、命を落とした後は、キャッツの人々を見守る守護霊的存在となり、やがて彼らが大人になると「バイバイ」と別れを告げられる存在となる。そんなぶっさんの変遷は、アイドルの在り方そのものである。
アイドルの身体を用いることで、(結果的に)「アトムの命題」をテレビドラマに持ち込んだ宮藤は、その後もアイドル主演のドラマを作り続けることでその作家性を発展させていく。
(了)
【公式オンラインストアにて特別電子書籍つき限定販売中!】
ドラマ評論家・成馬零一 最新刊『テレビドラマクロニクル 1990→2020』
バブルの夢に浮かれた1990年からコロナ禍に揺れる2020年まで、480ページの大ボリュームで贈る、現代テレビドラマ批評の決定版。[カバーモデル:のん]
詳細はこちらから。
成馬零一(なりま・れいいち)
1976年生まれ、ライター、ドラマ評論家。テレビドラマ評論を中心に、漫画、アニメ、映画、アイドルなどについて、リアルサウンド等で幅広く執筆。単著に『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)、『キャラクタードラマの誕生 テレビドラマを更新する6人の脚本家』(河出書房新社)がある。
(1)宮藤官九郎『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』(角川書店)「今だから話せるあとがき対談 磯山晶×宮藤官九郎」
(2)松尾スズキ『星の遠さ 寿命の長さ〜「大人計画」全仕事〜』(太田出版)「熊沢パンキース」
(3)(4) 『木更津キャッツアイ 日本シリーズ公式メモリアルブック』(メディアファクトリー)インタビュー宮藤官九郎(脚本)
(5)「ユリイカ 特集 テレビドラマの脚本家たち」(2012年5月号)「メタドラマの技法ーーテレビは娯楽の王様なのか?(聞き手=岡室美奈子)」
(6)(7)『別冊宝島 宮藤官九郎全仕事』(宝島社)「漫画家・山田玲司が語る『ゼブラーマン』の世界と宮藤官九郎」(文:友清哲)
(8)『木更津キャッツアイ 日本シリーズ公式メモリアルブック』(角川書店)「GAME1 [リーグ戦]2002.1.8-2002.3.15 『西船橋死ぬ死ぬ団』はいかにして『木更津キャッツアイ』になったか?」
(9)(10)(11)(12)(13)宮藤官九郎『え、なんでまた?』(文春文庫)「解説 岡田惠和」
(14)(15)大塚英志『キャラクター小説の作り方』(講談社現代新書)「第一講││キャラクター小説とは何か」
(16)(17)(18)(19)同書「第一〇講││主題は細部に宿る」
(20)ジャニーズ結成のきっかけに少年野球チームと『ウエスト・サイド物語』という街の不良チームの抗争を描いた映画が関わっていたことを考えると、宮藤が手掛けた『池袋』と『木更津』がジャニーズ・アイドル主演で作られたことの必然性のようなものを感じさせる。当初は、ミスマッチに見えたジャニーズ・アイドルと宮藤官九郎の作家性だが、実は根底にある「男の子らしさ」の起源をたどると同じものだったのかもしれない。
(21)「ジャニーの命題」という矛盾を抱えたSMAPは、30代は何とかやり過ごしたものの40代となり破綻した。彼らの解散は事務所内のゴタゴタが大きな要因だが、そもそも40代になってもアイドルで居続けること、それ自体が限界だったように思う。そしてSMAP解散以降は多くのジャニーズ・アイドルが様々な理由で事務所を辞めており、2019年のジャニー喜多川死去以降、その流れは加速している。堤や宮藤のドラマが、ジャニーズ・アイドル主演で作ることが可能だったのは1990〜2010年代にかけて成立したジャニーズ・アイドルが置かれていた特殊な環境の産物で、それはそのまま平成というモラトリアムの時代背景とも重なっている。
(22)宮藤官九郎『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』(角川書店)
