
昔の人はちゃんと指摘している!
ひとまとめにできた、と思う時もある。しかし、事柄によっては、次々に話を継いでいくことがある。あぁそうだ、このことも触れるべきだなと思い、関連した話を続けることもある。
先週、WAR(戦争)には、外交を考えておかなければと書いた。いかにもアッサリと(苦笑)書いたかも知れない。
日本は、アメリカを始め西欧社会から、二つの力を与えられた。一つは、軍事。もう一つはデモクラシー。
この両者に、長い時間をかけて築いてきた日本の伝統文化がかぶさる。日本人が長く格闘してきたこの問題には、専門的な研究者や並々ならぬ関心を払う人がいることだろう。
しかし、今注目したいのは、外交ということだ。外交は国益のために、うまく戦略・作戦を立て、他国と交渉することに他ならないだろう。
確かにそういうものだと思うが、ルールもある。何をしてもいいってものではない。外交と詐欺、策略、裏切りを一緒にはできない。外交能力の欠如、欠落も問題だ。
思い返すと、昔、陸奥宗則(1844~1897)という外務大臣がいた。日本の国運を考えた時、ある意味では、今よりずっと厳しく難しい時代にあって、安政年代から続く不平等条約を撤廃する道筋をつけた人だ。
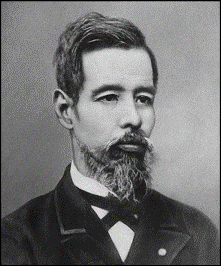
『蹇蹇録』(けんけんろく)って聞いたことがありますか?1895年(明治28年)と言えば、約10ヶ月続いた日清戦争が終わった年だ。外務大臣の陸奥は、自身の経験から、この戦争に至る「外交」を中心に、自身の見解、感想等を書いた。坂本龍馬(1836年~1867年)の海援隊に加わったり、西南戦争(1878年、明治11年)に直接かかわったりと、波乱万丈の世を渡った人物だ。
『蹇蹇録』が公刊されたのは1928年(昭和3年)のことだという。第一次世界大戦からすでに10年である。言わば次の大戦のはざまである。治安維持法が緊急勅令とやらで改まったのもこの年だ。
彼を帝国主義の一翼を担ったと一蹴する人もあるだろうが、そう単純に割り切ってしまえない。
例えば、愛国心を古来からのものとしても、彼は、「徒に愛国心を存してこれを用いるの道を精思せざるものは往々国家の大計と相容れざる場合あり」と考える。この時、三国干渉の動きに対して、国民!が戦争継続を叫んだということを陸奥は例えとして挙げている。
関心のある方は、当時の歴史に関するものを読んでいようが、少なくともこの陸奥の言が、後の日本には通じなかったことを、忘れるわけには行かないだろう。

外交と前回述べたのには、こういった事情がある。その思いで今のきな臭い話と報道状況に接していると、徒(いたずら)に正義感を刺激されてはいかんなぁ、と思うのである。
平和は勝つことによって達成されると、敵対する双方が同じことを述べ、勝つまで戦う、のである。その戦いで無垢の人びとが殺害され、人間や文化のよりどころの建造物や施設が無残に破壊され続ける..…。
軍事的勝利や、経済的制裁というような方法で相手側の悲鳴を喜ぶのは、チカラの発想しかないでであろう。最早、古過ぎて、時を後退している。幼稚でもある。それを脱却する思想が、すでに数々生まれているにもかかわらず、自陣営の国民や市民の共感(思考の仕方もこれに左右される)に訴える。そのためにもマスコミをコントロールし、軍事や関係組織体が潤う方向で、ウマクやる能力と組織が尊ばれる。
まぁ、こうなる傾向を少しでも止めようと思うのだが。
和久内に連絡してみようと思われたら、電話は、090-9342-7562(担当:ながの)、メールhias@tokyo-hias.com までご連絡をお待ちしています!
いいなと思ったら応援しよう!

