
萩原雄太(かもめマシーン)さんからコメントが到着。──スクリーンに映し出される映像とはほとんど無関係に、当時のほとんど忘れていたような感覚が立ち上がってきた。
萩原雄太(かもめマシーン)さんから寄稿文が到着いたしました。萩原さんは映画『ピアニストを待ちながら』の公開前シンポジウム「演劇を待ちながら」に登壇していただきました。
映画『ピアニストを待ちながら』は事前知識なしでも楽しめますが、「コロナ禍と表現」を主題にしています。多くの人が表現活動を制限され、待たされたこと、それらをわたしたちは今どう考えているか、映画を通して語るきっかけが生まれればと思います。それとも「ピアニスト」は「すでにきたことにする」というのも、わたしたちが生きるということでしょう。
萩原雄太(かもめマシーン)
演出家、かもめマシーン主宰。1983年生まれ。愛知県文化振興事業団「第13回AAF戯曲賞」、「利賀演劇人コンクール2016」を受賞。主な作品に、原発事故後、福島の路上で行った『福島でゴドーを待ちながら』、サミュエル・ベケットの『しあわせな日々』、ひとりの観客に対し、俳優が電話回線を通じて1対1で上演を行う『電話演劇シリーズ』など。
2018年、ベルリンで開催されたTheatertreffen International Forumに参加。19-20年、22-23年、24-25年セゾンフェロー1に採択。23年、Asian Cultural Council New York Fellowshipに採択され、ニューヨークに滞在。24年、中国の演出家・王梦凡、キュレーター・张渊とともに日中当代表演交流会を開始。 ジョージタウン大学・Laboratory For Global Performance & Politics 2024-2026のGrobal Fellowに採択される。
一本の木が自生する田舎道にいるひとりの男。時刻は夕暮れ。彼は靴を脱ごうするが脱げない。そこにもうひとりの男がやってくると、靴を脱ごうとしている男が「どうにもならん」とつぶやく……。不条理演劇の名作として名高い『ゴドーを待ちながら』は、このようにして幕を開ける。脱げない靴のように、あと少しでどうにかできそうなのに「どうにもならん」。2人の男はそんな隔靴掻痒の感覚とともに、ゴドーを待っている。
サミュエル・ベケットの作品は、なにか危機的な状況に直面したときに召喚される。『ゴドーを待ちながら』は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争下のサラエボや、ハリケーン・カトリーナが猛威を振るった後のニューオリンズでも上演されたし、私もまた、2011年に福島県双葉郡の路上で、この物語を翻案した作品を手掛けた。「どうにもならん」状況に直面したときに、人はこの物語を召喚するらしい。
わたしたちは普段、わたしたちの暮らしを「どうにかなる」ものとして捉えているし、実際に「どうにかして」いる。けれども、それらは戦災や台風であっけなく吹き飛んでしまうものであり、ひとつの小さなきっかけによって、無慈悲なほどに「どうにもならん」状況はむき出しになる。そこで、ベケットの書いた「どうにもならん」ときの言葉が必要となるのだ。

その意味で、パンデミックとは、まさにベケットにとってお誂え向きの状況であった。「どうにもならん」状況の中で、わたしたちは3年をかけて、その状況を恐れたり、やり過ごしたり、なかったことにしようとしたり、絶望したりした。その状況が終わることに希望を見出そうとしたり、逆に、終わらないことにこそ希望を見出そうとしたりもした。でも、そんなささやかな感情の揺れ動きは、そのほとんどが記録されたり言語化されないまま、感染症5類への移行とともに過去に置き去りにされた。
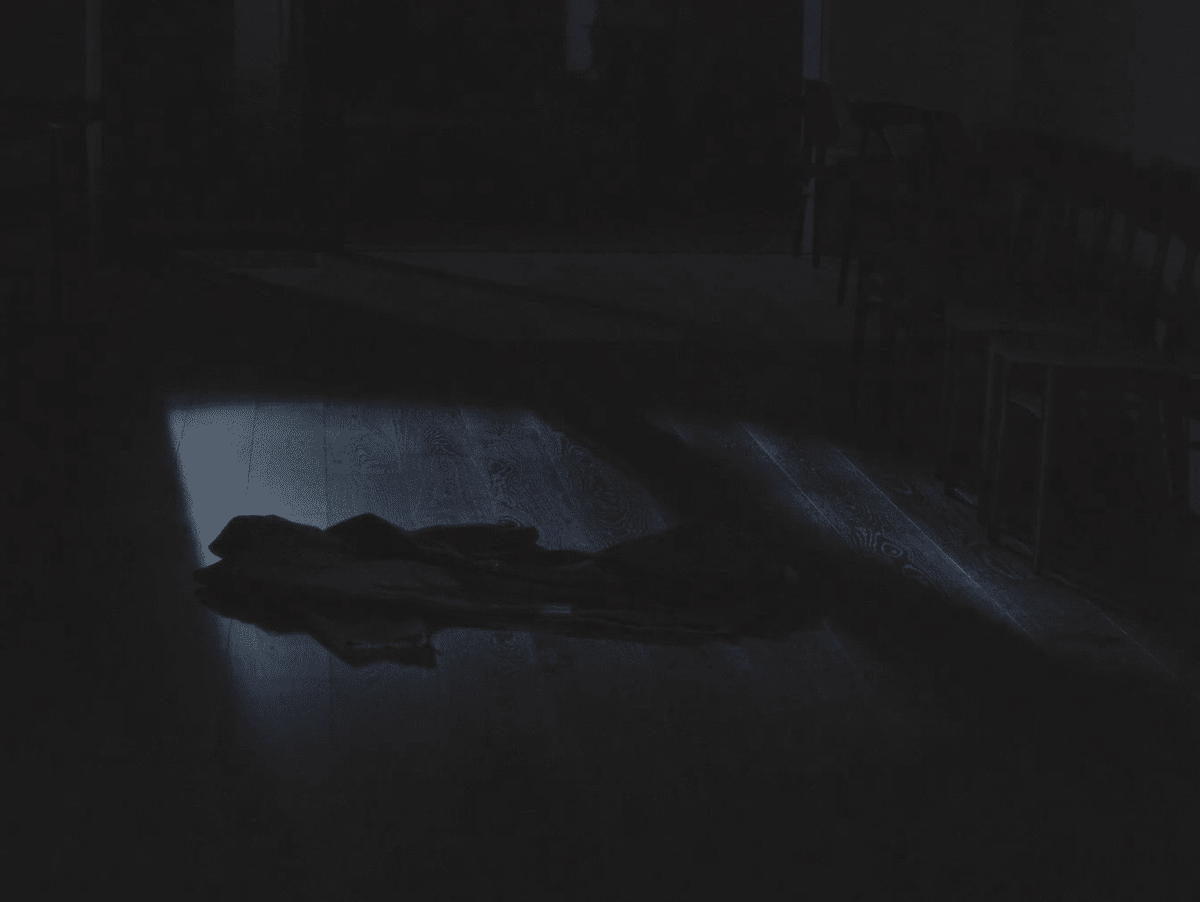
もちろん、病原菌への感染という状態は恐ろしい。しかし、パンデミックの本質とは、病原菌の拡散によって引き起こされる集団感染だけでなく、それとともに拡大するある気分への感染でもあった。気軽に家から出られない状況の中、感染した気分を抱えたわたしたちは、それをこじらせていった。そして、こじらせた気分は、今でもまだ寛解していない。
おそらく『ゴドーを待ちながら』から少なくない影響を受けて制作されたであろう七里圭の『ピアニストを待ちながら』もまた、「どうにもならん」状況を描いている。それを通じて、わたしたちは「どうにもならん」日々に去来した胸中を思い出すことになる。屋内が不安なので公園の中を歩いたこと、人混みの中でくしゃみをしてしまったときに射すように眼差されたこと(あるいはその逆)、わずかな体調の変化にいよいよ来たかと恐れたこと、実際にそれが来たときのこと。スクリーンに映し出される映像とはほとんど無関係に、当時のほとんど忘れていたような感覚が立ち上がってきた。わたしたちがこの映画を通じて出会うのは、ストーリーや登場人物だけではなく、当時の中に置いてきたわたしたちの気分だろう。

🎹 映画『#ピアニストを待ちながら』🎹
— 映画『ピアニストを待ちながら』絶賛公開中🎹|監督/脚本:七里圭,主演:井之脇海✊ (@pianistmovie) October 20, 2024
💃追加アフタートーク開催決定!💃
★ゲスト×七⾥圭監督
▼10/23㊌21:00~上映後
山本浩貴(小説家/デザイナー/批評家/編集者/いぬのせなか座主宰)
▼10/25㊎21:00~上映後
関田育子(ユニット[関田育子]代表/脚本家/演出家)
▼10/26㊏11:00~上映後… pic.twitter.com/bRdac2lCnY
