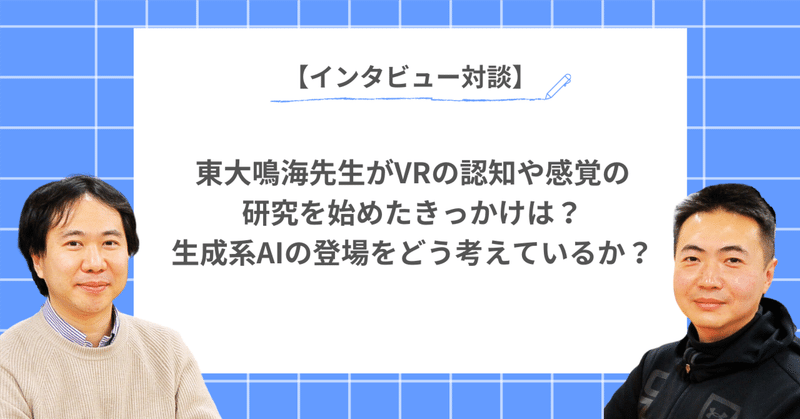#アバター
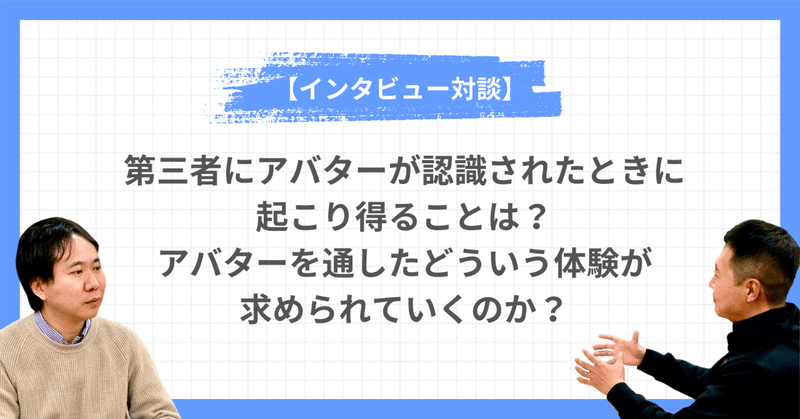
【インタビュー対談】第三者にアバターが認識されたときに起こり得ることは?アバターを通したどういう体験が求められていくのか?
前回に引き続き、東京大学の鳴海准教授へインタビュー対談という形でお話を伺います。VR・AR研究の第一人者である鳴海先生に様々なテーマでお話しいただいております。 前編では、研究を始めたきっかけや感覚や認知のお話、生成系AIの台頭についてなどお話しいただきました。 後編では、アバターを第三者に「自分」と認知されるとそれは自分だけのものではないというお話や、アバターのもたらす良さ、今後の展開予想などをシェーと共にしていきます。 ■アバターを第三者に「自分」と認識された時に起こ