
【特別対談 vol.1】データが変える広告の未来 "VOSTOK NINEとニールセンが語る広告投資の新展望"
VOSTOK NINEは広告投資プランニング(メディアプランニング)に特化した会社です。投資戦略を立案するだけで無く、広告枠の買付戦略立案や広告効果の可視化手法の研究、広告投資に関係する様々な設計・戦略立案を行っています。
そんな広告投資戦略は関連する技術や研究の進歩により日進月歩で進化し続けています。我々も多くの知見や見識を吸収し広告投資戦略をアップデートしていますが、今後もそういった有益なインプットはぜひ皆さんにも共有し議論していきたいと考えています。
今回は当社代表でメディアストラテジストの三宅が "気になる会社や人" を訪ねて最新の動向をじっくりとお話を伺い、メディアプランニングの未来を模索していく様子をお届けしたいと思います。
今回お伺いしたのは「ニールセン デジタル株式会社」です。広告の透明性、公平性だけでなく、計測が何をもたらすのか、今後どのような展望を見据えているのか、広告効果検証サービスを提供している「ニールセン デジタル株式会社」営業統括本部長である大瀧氏にお話を伺いました。
ニールセン デジタル株式会社について ---
ニールセン デジタル株式会社は、広告の透明性と公平性を追求するデジタル広告効果測定分野のグローバル企業。クロスプラットフォームでの広告視聴データを提供し、広告主がデータに基づいた投資最適化を実行出来るようサポートしている。リアルタイムで広告効果を把握できる最新の測定ソリューション「ニールセンワン」を展開している。
I. データの意義:それは会話のきっかけ

三宅:
ご無沙汰しています。VOSTOK NINEの三宅です。本日はお時間いただきありがとうございます。
大瀧:
改めまして、ニールセン デジタルの大瀧です。よろしくお願いいたします。
三宅:
まず最初に、大瀧さんの広告への想いや原点のようなものを伺っても良いですか?
大瀧:
以前在籍した広告会社では当時オンラインゲームのプロモーションに特化したチームにいました。それがデジタル広告の自分の原点であったりしますね。
それ以降デジタル広告に限らず、クリエイティブに携わったり、CMを制作したり、雑誌広告を作ったり、その後インド支社に転勤になるのですがその頃には(何でもやる・やれる)フルサービスプレーヤーになってました。笑
(インドの)彼らのクリエイトの考え方ってイギリスが源流ということもあって、すごく本格的なんですよ。
確かジェイ・ウォルター・トンプソンが95年前に拠点を作った(注 : JWT Indiaはイギリスの大手広告代理店グループWPPの中核企業だったが、現在は統廃合によりVMLとなっている)背景もあって、本当にクリエイティブの考え方が欧米式。
日本(のクリエイティブ)に一番欠けているかなと思うのが、感情に刺さる、エモーショナルなクリエイティブを如何に作るかだと思っていて。
CTRやコンバージョンのためのクリエイティブもあるとは思うんですが、中長期的にブランドを作る場合は、裏にあるストーリーがちゃんと見えるかどうかって事が、まだまだ大事だと思っています。
三宅:
本当にその通りだと思います。私もプロダクトやブランドには必ず物語があって、それをうまく(広告等によって)伝える事で、消費者がファンになって末永くそのブランドを伝え続けていくような良い流れが生まれると思うんです。
大瀧:まさにそうですよね。USP(注 : Unique Selling Proposition) から入らない。感情やストーリーから入る。
インドでは、USPを打ち出してなんぼ!な提案するとマジで(広告主から)怒られるんですよ。笑
で、僕、調べていたら「日本にもインサイトや共鳴という考えがある」って事を改めて知って、絶対に日本でも感情やストーリーから入るクリエイティブ開発は出来るはずだって思いました。
三宅:
私達広告マンも決して表面的な反応率だけを求めて(クリエイティブ)開発している訳では無いと思うんです。
デジタル上でブランドの思いや物語を紡ぎたいっていう意思はあるけど、そういった表現をやっていざ評価しようとなったときに、評価方法がごく限られてしまっているという。結局はCTRやCPCみたいな簡単に評価出来る指標で評価をされがちになってしまう。もどかしいですよね。
大瀧:
(CTRやCPCも)それはそれで持っておかなくちゃというべき指標だと思います。
ただ量的なパフォーマンスとは別にもう一つ常に持っておくべき指標はあるんじゃないかなと思いますね。それは単純なリーチやエンゲージメントより、もう一歩補踏み込んだ指標であるべきだと感じています。
三宅:
例えばしっかりと然るべきポジティブな認知や理解を獲得しているからこそ「あ、これいいじゃん!」って、ヒューリスティックな反応をしてもらえる。最後の反応を追いかけるだけじゃなく、その為のリフトが事前にちゃんと起こせているのかどうかみたいな。
大瀧:
そうです、つまりは「ブランドリフト」という観点ですよね。
パフォーマンスベースのキャンペーンであれば(一般的なデジタル広告パフォーマンス)レポートを見たらいい。ただどうしてもブランディングキャンペーンにおいてはそれだけだと広告効果を把握しきれません。その先に対して疑問を持つクライアントにとって調査は必須だと思います。
実際に調査してみると広告の接触グループと非接触グループで(期待した結果に対して)逆転現象が起こるときもあるんですが、その要因がなにか一つ一つ丁寧に考えていく事が今後にとって大切で、そのきっかけを作る意義は大きいと思います。
データとか数字が手元にあって、何か変わるわけじゃない。ただ、やっぱりあるとないとでは全然違うと思うんですよね。データと人は会話できないじゃないですか。人と人がいて初めて会話ができるので。そうやって考えるべき人達が本気になって考える瞬間を作る、みたいな。それのキッカケがデータだと思うんです。
II. リアルタイムのデータ提供がもたらす価値
大瀧:
「ニールセンワン」という、クロスプラットフォーム(計測)プロダクトがあります。要はマルチチャネル(現状はPC、モバイル、CTV。将来的に地上波TVも。アメリカでは既にTVも計測可能。)をワンプラットフォームで計測して、そのプラットフォームの中で予算アロケーションや、キャンペーンアクティベーション(の次の一手)を考えていく事が出来る。それがこのプロダクトのコンセプトです。

三宅:
我々メディアプランナーにとっては喉から手が出るくらい欲しい(有益な)データですね 笑。
大瀧:
ちょうどこの前ローンチしたばかりなのですが、YouTubeコネクテッドテレビ広告(CTV)の測定ができるようになりました。
詳細まではまだ言えないのですが、新たな計測メソッドが加わる形でCTV面の重複リーチ、つまりパソコン、モバイル、CTVの3つの統合リーチが測れるようになります。まずはYouTubeのCTVから。
データは元々過去のものじゃないですか。大体のデータはキャンペーンが終わってやっと出てくる。
(そういった現状に対して)ニールセンがこれから実現したいことは「ストリーミング」。即ちリアルタイムにすぐその場でデータを提供する。即時性とかリアルタイムとか、そういった想いをストリーミングという言葉に込めて、そんな世界の実現に向けて動いています。
三宅:
広告主にとってはメリットしか無い世界ですね。
大瀧:
"デジタルのここの数字、テレビのここのリーチが伸びているね"、"バイイングパターンを来週で切替えよう"。データを反映していく事でテレビのバイイングをリアルタイムにどんどん改善していく。そういった流れを作ろうとしています。
三宅:
我々(メディアプランナー)も、事前のプランニング段階で万全を期していますがどうしても「思ったようにいかない」事はあります。OA期間中にもそのズレを修正出来るのは大きなメリットですよね。
大瀧:
デジタルのみならず、将来的には(地上波)テレビも含めてそういった事が出来るようになります。それがニールセンが今やろうとしてる事です。
" データは過去のものじゃない、リアルの今の為のもの "
この未来を楽しみにしてください。頑張ります。
三宅:
期待しています!
III. デジタルメディア活用の偏りとその課題
三宅:
今の日本の広告メディア環境で、何か課題感を感じたりしていますか?
大瀧:
それで言うと、" 使用するデジタルメディアが偏ってるな "という印象はありますね。多くのクライアントさんのデジタル広告をDAR(Digital AD Ratings : デジタル広告がターゲットとするユーザーに正しく到達しているかを確認出来るツール)で測定している中で、使用メディアの偏りは感じます。もっといいメディアがあるのになって思ってしまう。
三宅:
具体的にどういったメディアが? 笑
大瀧:
公平な視点を持つ第三者調査機関であるっていうのが、僕たちのポジションなので、ここで媒体名は出せないです。笑
少なくとももっと色々な媒体を試すべきだと思います。そして一度でもいいので、オンターゲット率向上を図るといった取り組みをしていただいて、実際にターゲットとする年代に何割リーチしているか、どれだけフリークエンシーが積み上がっているのか、そういったものを正確に把握してもらいたいと思います。そういった取り組みは、次のより良いメディアプランとか、次の戦略とかそういったものに必ず繋がると思います。
三宅:
なるほど。
大瀧:
あと、ご存じの通りやっぱり代理店さんもクライアントさんも基本的に、" リーチ拡大の為にこうする "とか、" このチャネルミックスが認知形成に最適だ "と色々と試行錯誤されてるんですよね。
三宅:
はい。でも結局プランのタイミングでは、(シミュレーションに耐えるだけの直近の詳細データが無い事が多い為)一年も二年も前のデータを引っ張り出してきてシミュレーションをする事が多いので、大体の場合「今この瞬間」のデータは反映されていないプランになっています。
やむを得ない部分ではありますが、今日の話を聞いているとそういった "今までのメディアプランニングの当たり前" にちょっと違和感を覚えてしまいますね。
大瀧:
その通りです。"今"をプランニングに反映して欲しいんです。
ニールセンが提供しているデータを活用すればプランニングに"今"を反映出来る。そう言えるようになると良いなと思っています。
三宅:
「昨日のデータから明日のプランを作りましょう」、そういうプランニングが出来るかもしれないと考えるとワクワクしますね。
大瀧:
そうですね。やっぱり、1年前に見たCMと、昨日、一昨日に見たCMだと時代も内容も違うので当然心への残り方も違う。昨日リーチした消費者の気持ちを可視化する。そこが(メディアプランニングの精度を上げる為に)重要だなと思いますよね。
それがデジタルデバイス上の接点であれば、ある程度リアルタイムに可視化出来る環境になっています。今、CTVも(可視化)出来るようになってきた。近い将来テレビもそこに加えられたら、と思っています。そこまでのロードマップは描けているので、それを一つ一つ実現させていきます。
三宅:
大滝さんの定年(退職)までには何とかなりそうですか? 笑
大瀧:
いや、ぼく短気なんで、ほんと来年ぐらいには(テレビのリアルタイム可視化も実現したい)と思ったんですけど。ちょっと来年はまだ無理そうです。笑
三宅:
笑
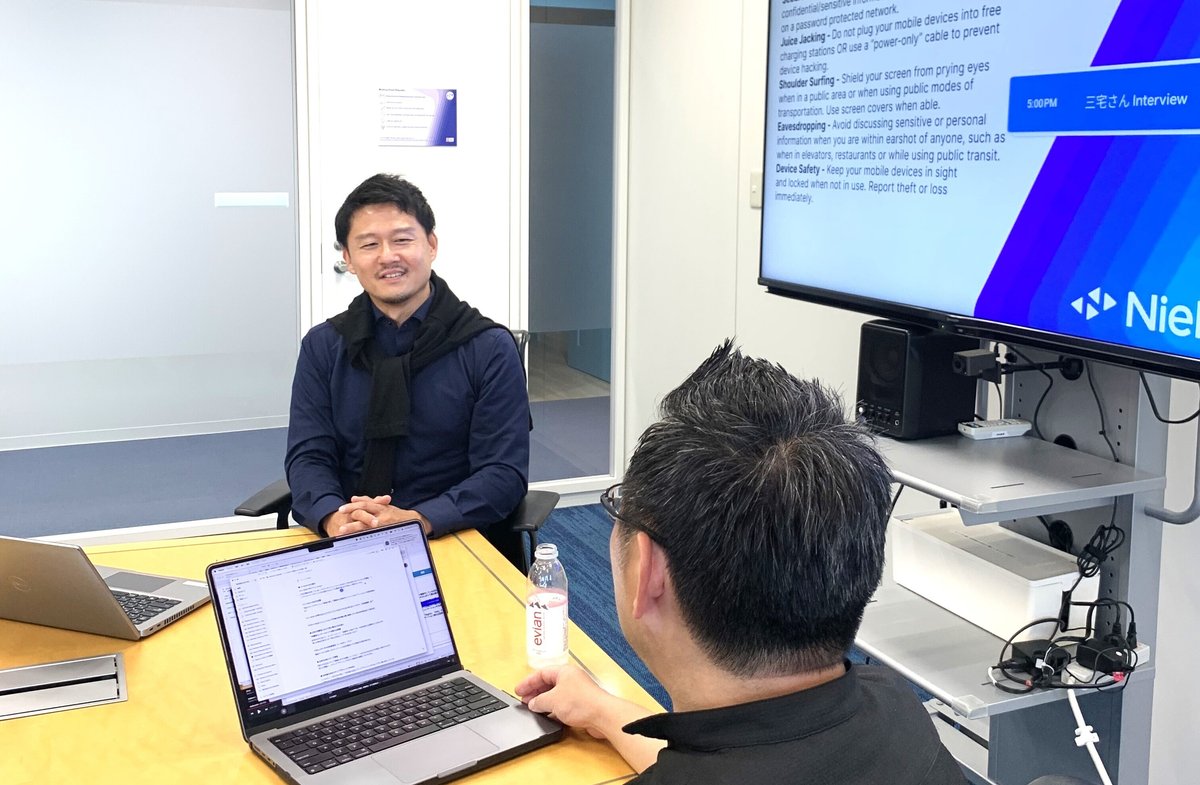
IV. データと人間の感覚が生み出す未来のメディアプランニング
三宅:
最後に伺いたいのですが、例えば最近だったらAI活用なんかがそうですが、そういった新しいテクノロジーとの融合であったり、10年後、20年後のニールセンのメジャメントっていうのはどういったところに到達してるのか、イメージはあったりしますか?
大瀧:
さきほどの繰り返しになりますが、ある程度主要な動画広告面の計測が機能するようになって、(デジタル広告の)バイイングのスピード感と計測の歩調が合うようになってきました。
そこの歩調から合った今の状態でクライアントさんや代理店さんに使ってもらうっていうのが、まず一つ目指すところかなとは思いますね。
三宅:
歩調を合わせるって、たしかに御社の立場としては、一番大切なところですよね。
大瀧:
そうですね。これからも僕たちがまず頑張って(歩調を)合わせる。
ただ今後テレビの計測も出来るようになった時、テレビバイイングの手法やスピードといったところを変えないことには、データが出て今こうすべきという事が分かっても、結局買えるの1か月後でしょ。って事にもなってしまう。
そうなってしまうと意味ないですよね。お互いにそこの歩調があっていくっていうところが重要だと思います。
後もう一つ、やっぱりマニュアル(手作業)とデジタル(自動化)を組み合わせるっていうところは今後も欠かせないなと思いますし、最後は人の手とか人の目線とかの人間的感覚を無視していては良いプランは一生できないとは思いますね。
マーケターやプランナーが議論するキッカケを作るのは先に言った通りですが、その人達の決断を必要に応じて最後に後押しする。(ニールセンは)そういう存在でもあるかなと思うんですよね。
逆にそれ以上できないので。笑(三宅さんのように)プランニングもできないし、クリエイティブを作れる訳じゃないので。
ただ、決めるための最後の一押しをする。そういうキッカケには(ニールセンが)なれると信じていて、その為に必要なのはメディア視点なのか、クリエイティブ視点なのか…それは模索中ではありますが、でも挑戦し続けていこうと思っています。皆さんの決断を応援し後押しする。そういうところでも役に立てるといいかなと思いますね。
三宅:
私達のようなメディアプランナーにとっても本当に心強いです。結局、コミュニケーション設計ってメディア視点だけで生まれるものでは無くて、色んな角度から沢山の意見を出し合いながら作り上げていくものだと思っています。今日の話を聞きながら、御社と議論出来る領域というか範囲は思っていた以上に" 実は "広かったんだな…と感じました。これからも色んな局面で一緒になって議論させてもらえると嬉しいです。
今日は本当にありがとうございました!
大瀧:
こちらこそありがとうございました。議論はいつでも待ってます。笑
V. 編集後記
一般的に調査というと広告効果のオーディット(監査)の側面が強いですが、あくまで「コミュニケーションを良くする為に」という姿勢で一貫している点が特に印象的でした。又、メディアプランニングの定石は「(過去を見て)統計的に確からしい組み合わせを選ぶ」ですが、「今」をプランニングに活かすという考え方はとても興味深く、当社でもこの考えを実際のプランニング現場に実装出来ないか議論していきたいと思っています。
また、メディアプランニング作業において、調査会社は通常、第三者的な立場で関与することはあっても、活発な議論を交わしながら一緒にプランを組み立てる機会はほとんどありません。しかし、こうした関係性を見直し、" 調査会社とプランを共創する "というスタイルがあっても良いのではないかと感じさせる、終始ワクワクする1時間でした。
今回お伺いしたのは…
大瀧 直文氏
ニールセン デジタル株式会社 Director Sales, Analytics
2006年より一貫して広告業界に従事。コロナ前は日系広告代理店インド支社長を務めAutomotive, Tourism, FMCGクライアントを担当。外資系広告代理店にて、クリエイティブ制作、オンオフ統合型メディアキャンペーンを担当。
株式会社VOSTOK NINE
VOSTOK NINEは2024年現在、国内で唯一(※)の「広告(6媒体)メディアプランニング」に特化した会社です。所属する全員が一定(目安10年以上)の経験を持ったメディアプランナーのみ、という一風変わった組織です。広告が社会にとってより役に立つ存在になる未来を目指し2022年1月にメディアプランナーである三宅と江口の2名で立ち上げました。メディアプランニングに関する知見はブラックボックスになりがちですが私達は” 可能な限り広く共有されるべきである “という「メディアプランニングの民主化」を掲げて活動しています。その為、これからも様々な考察や自主調査データをnoteで公開していきたいと思っています。詳細はこちら。
※VOSTOK NINE調べ
