
[導入事例] - 業界変革にチャレンジするMoTのカルチャー醸成の秘訣
Voicyでは、社内向けに音声配信を行う「声の社内報」として活用する方法があります。今回は、タクシーアプリ「GO」を開発・提供するMobility Technologies様(以下、MoT、現在:GO株式会社)が、「声の社内報」としてVoicyを導入したきっかけなどについて会長の川鍋さん、広報 萩尾さん、高堂さんにお話を伺いました。
[サマリ]わずか3か月で軌道に乗り、楽しく運用
【導入背景】
・きっかけは「GO」のタクシー乗務員とのコミュニケーションチャネルの検討
・リモートと出社のハイブリッドな働き方における社内カルチャーの醸成
【活用方法】
・アンオフィシャルな場としてのトップからの発信
・社員や現場にフォーカスした発信
・エンジニアが聴きたい技術者向けの勉強会の音声をVoicyにも展開
【導入後の社内の変化】
・役員が身近な存在に感じられるようになった
・全国の各拠点メンバーにとって、経営陣や東京本社が近くに感じられ、仕事のモチベーションにつながった
・一次情報である現場の声から問題解決に繋がった例も
[事業紹介]株式会社Mobility Technologies(現在:GO株式会社)

事業:タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業
従業員:約400名(2023年1月時点)
企業サイト:https://goinc.jp/
お話を伺った担当者
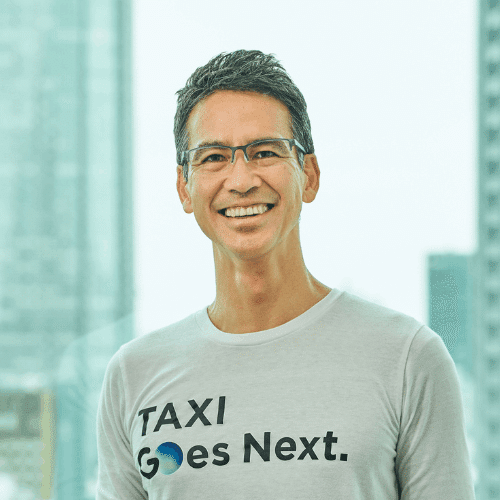


[導入背景]タクシー乗務員を通した顧客体験の向上とリモートと出社のハイブリッドな働き方における社内カルチャーの醸成
—— 声の社内報としてVoicyを始めたキッカケを教えてください。
川鍋:背景としては2つあります。ひとつ目は、ユーザー体験を上げる重要なステークホルダーであるタクシー乗務員さんに対して会話できるチャネルに音声がいいのではないかと思ったことです。我々が提供するタクシーアプリ「GO」は、アプリを利用した先にいる乗務員さんのサービスがあってはじめて、お客様に満足な乗車体験をお届けできます。挨拶をする、道を間違えない、などは基本的な部分ですが、その他にも「GO」のアプリを使いこなしてもらうこともとても大切です。どうしても目の前で手を挙げるお客様に目が行きがちですが、「GO」でタクシーを呼ぶお客様も、目の前にはいないけれど実質手を挙げているのと同じです。アプリに対する我々の熱量を乗務員さんにも伝播させて、一緒にお客様の体験向上を目指したいと思っていました。これまでもタクシー会社の皆さんに「GO通信」というポスターを貼り出していましたが、もう少し直接届けられないかなという気持ちはありました。
もうひとつは社内のカルチャー醸成のためです。MoTは、元々ライバル企業だった2社の事業部門が合併して誕生した会社で、約3年が経った今、ようやく落ち着いてきました。そのため当初より社内カルチャーは感度が高い部分ですし、最近では毎月10人程が入社して人数が増えています。リモートベースの働き方が主流で、会社の半分を占めるエンジニアはほぼ出社していません。インフォーマルなやり取りをする場があまり多くないでしょう。そのため、他部署のメンバー5人1組での日帰りワーケーションや部活動を会社として後押しし、業務以外でのコミュニケーションの接点を作ることを推奨しています。
以前、動画を撮って社内向けに発信を始めようと考えたんですが、動画編集に労力がかかり諦めました。声だけだと編集は必要ないですし、何より発信側の気持ちが乗っているのは声で伝わりますから。
そんなこともあり、「声の社内報」のサービスを聞いた時にこれだ!と思いました。声を通じて熱量を届け、放出することができますし、聴く側も耳だけでいいのでスキマ時間に聴けますよね。
将来的には全国の乗務員さんに届けたいと思っていますが、まずはクイックに始めたかったので社内向けにスタートさせました。現在、400名強の社員がいますが、その8割が社内報を聴いています。

[活用方法]コミュニケーションの基本は相手を知ること。そのためにも人にフォーカスした放送を心がけている
—— 最初はどのようにスタートしたんですか?
萩尾:まずは社内の中の20名程度に展開して、どんな放送だったら聴いてもらえるかテスト的に始めました。そこでポジティブな反応を得られたので、2か月目からそのまま全社展開しました。
現在は毎週2〜3本の放送を続けています。開始から3か月で累計30本以上の放送ができました。思ったより聴いてもらっている手応えがありますし、月間聴取率も31%と他社より好調だとVoicyさんから聞いています。
現在の放送テーマは主に3つだが、単発でも他メンバーが配信している。
「なべレポ」会長 川鍋さんがいま考えていることを伝える
「わかレポ」広報 高堂さんがメンバーにインタビュー
「MoT Tech Radio」エンジニア 水戸さんを中心にZoomで行う勉強会を声の社内報でも展開

「MoT Tech Radio」は多くのエンジニアに聴かれています。最初からあったテーマではないのですが、元々エンジニアのリスナーが少ないという課題もあり、Zoomで運営されていた、最新の技術紹介等をしている「MoT Tech Radio」の音声をこちらにも出してもらいました。その結果、エンジニアのリスナーが増えましたし、エンジニア以外のメンバーもこの放送を聴いています。
施策ごとに新しいコンテンツを作るのは大変ですが、こうやって一部でやったものをVoicyにチャネル展開できるのは便利でいいなと思っています。
—— テーマはどのように見つけていますか?
川鍋:改めてそう聞かれると難しいんですが、気持ちが動いた話じゃないと面白くないと思うんです。正式名称などの固有名詞は間違えないように収録前に確認しますが、内容はあえて整理して伝えるのではなく、自分の頭の中にあるものの熱量を届けることにフォーカスしています。それが声で伝わる魅力だと思うので。(2022年11月にあった)15年ぶりのタクシー運賃の改定に関しては1年がかりで取り組んできたのがようやく実現したので、その放送はMoTメンバーにも想いを伝えたくて気持ちがこもりました。
萩尾:川鍋からの発信頻度は、SlackのチャンネルやZoomによる週1全社定例とコミュニケーションのチャネルはこれまでも少なくなかったです。ただそこに、Voicyが加わったことで話の裾野が広がった感覚があります。全社会議等ではオフィシャルな決まった情報が発信される場ですが、Voicyではわざわざ資料やテキストに起こす前段階の柔らかい話が多いです。川鍋の声を通して、見ている視点やどんな考え方を持って動いているかを知れるので、社員からも川鍋の考えをより深く理解することができたという声も出ています。
川鍋:それはありがたい。全社の定例では、もっと伝えたいことがあってもその10分の1も出せていない感覚があって。で、Slackに雑談っぽく書くにもある程度ネタになってないと読みづらいので、そういう意味でも自分の考えを声で自由に伝えられるのは伝えやすいですし、伝わりやすいのかなと思います。

—— 人にフォーカスした放送が多いですね。
川鍋:コミュニケーションの基本は人を知ることだと考えています。役員や社歴の長い社員にインタビューして「昔はこんな人だったんだぜ」という放送はよく聴かれますね。「◯◯さんはこういう人なんだ」と頭に残っていれば、オンラインで会っても全然違う距離感で話せると思うんです。コミュニケーションは精度より量だと思っていて、複数人での日帰りワーケーションや部活動もコミュニケーション量を増やす施策ですが、オンライン・オフライン問わず、社内のコミュニケーション量を増やすことは推進しています。
高堂:私自身もそうでしたが、役員も多い中で キャラクターが分からなくて話しかけにくいというようなシーンは他の社内メンバーにもよく当てはまるんじゃないかと感じています。その点、声の社内報で人柄がみえるリアルな話を聴いて声をかけやすくなったと、入社半年の同期メンバーから言われることは増えました。
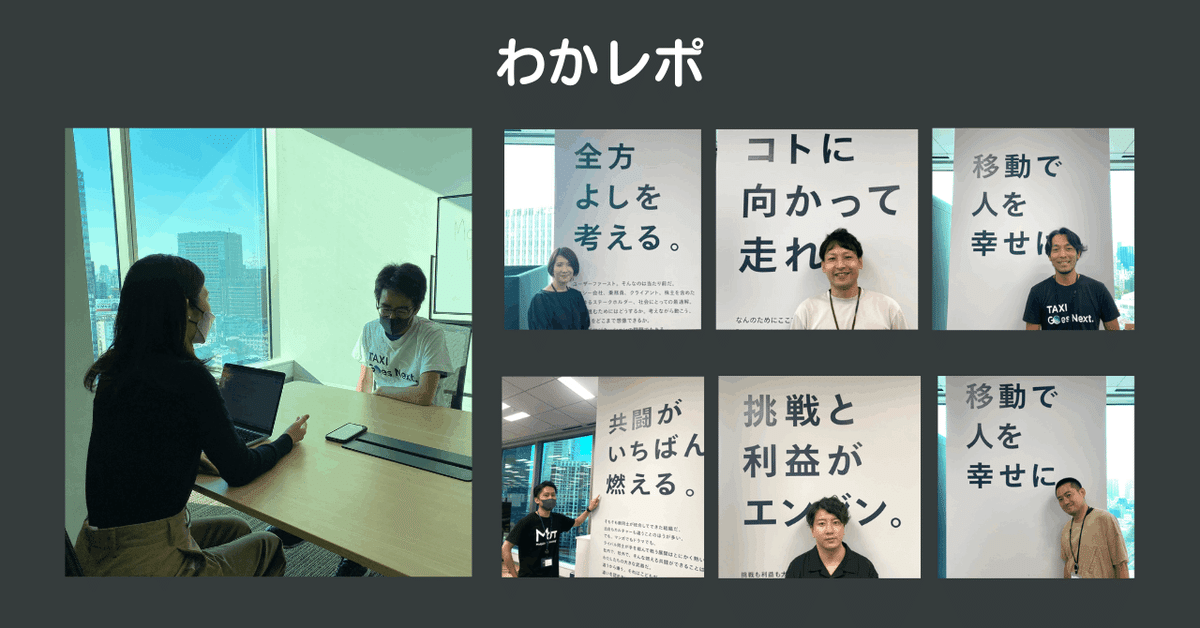

[導入後の変化]仕事のモチベーションにつながるとの声。一次情報に触れる大切さ
—— 声の社内報を3か月程続けて放送も30本程になりました。なにか変化は感じますか?
高堂:東京含めて全国に6拠点あり、外出先で聴いているメンバーが多い印象です。やはり東京と他の拠点との距離的なハードルがある中で、 声の社内報を聴くことで「本社で起こっていることや経営陣の考えが身近に感じられて、仕事のモチベーションに繋がる」と言ってくれる地方拠点メンバーがいたりします。会社の理念が距離の離れたメンバーにも届いていると感じれて嬉しかったです。
川鍋:Voicy上でコメントがやりとりされることはあまり多くないですが、以前ある放送で「現場が困っている」という話をした時に、放送を聴いたメンバーがSlackに書き込んでくれて、すぐに皆が集まって問題解決に向かったということがありました。現場感がダイレクトに伝わったから動こうと思ったメンバーがいたと思うので、それもいい動きだと感じました。
ある時はタクシー会社の所長さんにも登場してもらいましたが、現場の声を知りたくてもなかなか機会がないメンバーもいます。一次情報に触れることは気づきになるので、それが無理なくできるのは大事にしていきたいですね。
[今後の展望]無理なく続けることで、聴く側にも心地よく届く。いずれタクシー乗務員の方にも聴いてもらう放送に。
—— 今後やりたいことなどあれば教えてください。
川鍋:まずは、無理なく続けたいです。しゃかりきになってやるものでもないので、ちょうどいい脱力感というか、聴いている人も何かの合間に聴けるようなコンテンツを発信していきたいですね。
あとは、やっぱり全社員に聴いてほしいです。サービスが向かっている方向や考え方なんかを柔らかい状態でキャッチアップできますしね。そういう意味で、新入社員には必ず「Voicy聴いてる?」って聞くようにしています。そして、今はMoT社員に閉じていますが、いずれはタクシー乗務員の方々にも聴いていただける放送にしていきたいです。「GO」を使わない乗務員さんも含めて、勤務中のお供になりたいです。
Voicyを声の社内報として検討中の企業の方へ
—— 声の社内報を検討中の企業へ向けたアドバイスをお願いします。
川鍋:社内発信についてはノーリスクだからまずはやってみたらとお勧めしますね。もし自分が話すことが苦手でも、得意な人やフィットする人が社内にいると思うのでそういう人を通して社内に熱量を伝えていけばいいと思います。声しかないから伝わることがあると思います。
高堂:運用メンバーとしてお伝えできることとすると、声の社内報を始めた当初は緊張しました。しかし、テキストにその人の想いをのせるのは結構大変だと思いますが、声だったらその人の熱量や人となりもそのまま伝わるので社内コミュニケーションの手段としては手が出しやすいと思います。動画のように編集する必要もないので発信側にもやさしいです。
お問い合わせはこちら
最後までご覧いただきありがとうございました。
Mobility Technologiesさんは、タクシー業界変革のキープレイヤーです。新しいチャレンジをしているからこそ、社員との理念の共有やこれまでの歴史を伝える必要があり、それをメンバーも求めていると感じました。
そんな担当者の熱量が声にのって伝わる「声の社内報」で、理念に共感する社内カルチャーをつくっていきませんか。お問い合わせは以下よりお待ちしております。
