
"問い"が事業を強くする、プロダクト組織成長の鍵 #食べチョクチーム
2022年にビビッドガーデンとしては初めてのエンジニアマネージャーとして入社した中西と先日CTOに就任した西尾。
二人が考える開発組織の理想像とそこに至るための成長の鍵を、じっくりと聞き出してみました。
「まだまだ発展途上」CTOとEMの現状認識
ーー事業をより進めるために、現状認識している課題はどこになりますか
西尾:この1年で多くの仲間が増えましたが、成果を最大化しつつ早いスピードを保ち続けられているかというとまだまだ発展途上だと思っています。組織としても解きたい問題の粒度が大きく、解像度をより高めていく必要があります。一方で、さらに大きな解くべき課題を探すためにディスカバリーの動きが出てきたのは良い動きだと捉えています。
中西:人数が増えるとどうしても一時的にスピードが落ちてしまうことがあります。入社1年以内のメンバーが多いこともありチームの認知負荷は今が1番高い状態だと感じています。半分は在籍期間によって解消されていくと思いますが、もう半分は解くべき課題を特定するために組織として共通のフレームワークを持てるかがポイントになってくるだろうなと感じています。

メンバーの”鏡”となって問いとフィードバックを重ね続ける
ーーそのために中西さんはどんなアプローチをしているのでしょう?
中西:1on1や半期に一度行っている目標設定で「課題」を意識してもらうことからはじめています。ビビッドガーデンの良いところは誰もがプロダクト愛に溢れていることとデリバリーが速いことだと思っています。一方で、「なぜ今それを行う必要があるのか」という課題設定力が弱く、「自分が課題だと思っているから」以上の理由が出てこないことがしばしばあります。なので、日常的に「本当の課題は何なのか」を問うようにしています。
ーーそのような問いかけを通して、どのような行動変容を期待していますか?
中西:最終的には、全員が課題の発見から解決までを担えるようなチームを目指しています。問われることで思考が加速する側面はあると思っていて、最初に出た仮説というのはあくまでスタートラインという認識です。そこに問いが重なり、仮説の推敲を重ねていくことではじめて磨きこまれた仮説になると思っているので、問うことを大事にしています。
ーーメンバーに対する問いかけとメンバー自身の行動変容を見ていく中で、気にかけていることはありますか?
中西:メンバーの考えや行動を映す鏡でありたいと思っています。「あなたはこう考えたんですね」「先週との差分はこうですね」「いま、ここにいますよ」と。ストレートに結果をフィードバックして、相手が納得できるかというとなかなかそうはいかないことも多いと思っています。その点、鏡は事実を映し出すものなので相手に気づいてもらいやすい。人は自分で気づいたものは素早く修正できますが、相手から言われたことは時として思想の対立を生みかねません。これではマネージャーとしては本末転倒だという思いがあるので常に鏡であることを意識しています。

「個人個人が自立していく組織にしなければ」 今求められているもの
ーー理想の組織状況のイメージとそれを実現するために必要なことは何になりますか?
中西:課題の発見から解決までを担えるメンバーが組織の中からどんどん出てくる状態が理想だと思っています。私のミッションは、その環境作りを通して事業成長に貢献することだと考えています。
西尾:中西さんが言っていたことに近いですが、個人が自立していく組織にしなければならないと思っています。技術領域だけではなく、ビジネスやプロダクトのような大きなものに対して組織で同じ方を向いて、ちゃんと目線を合わせて、それぞれで成果を出していけるような組織にしないとなと。
中西:技術領域といわゆるプロダクトやビジネスの領域で何が決定的に違うかというと、スコープの広さだと思っています。技術領域を相手にしてる時はステークホルダーが全員エンジニアなことが多いので、思考が揃っていたり共通言語があるので話が進みやすいです。一方でプロダクトやビジネスの領域になるとPOもいる、CSもいる、生産者サポートもいるとなって、見ている観点が全然違うメンバーが揃います。この環境で何か1個のものを作り上げるのは相当難易度が高いと思うんですよね。
その時に何が必要になるかと言うと、話を揃える力と、意思決定力だと私は思っています。
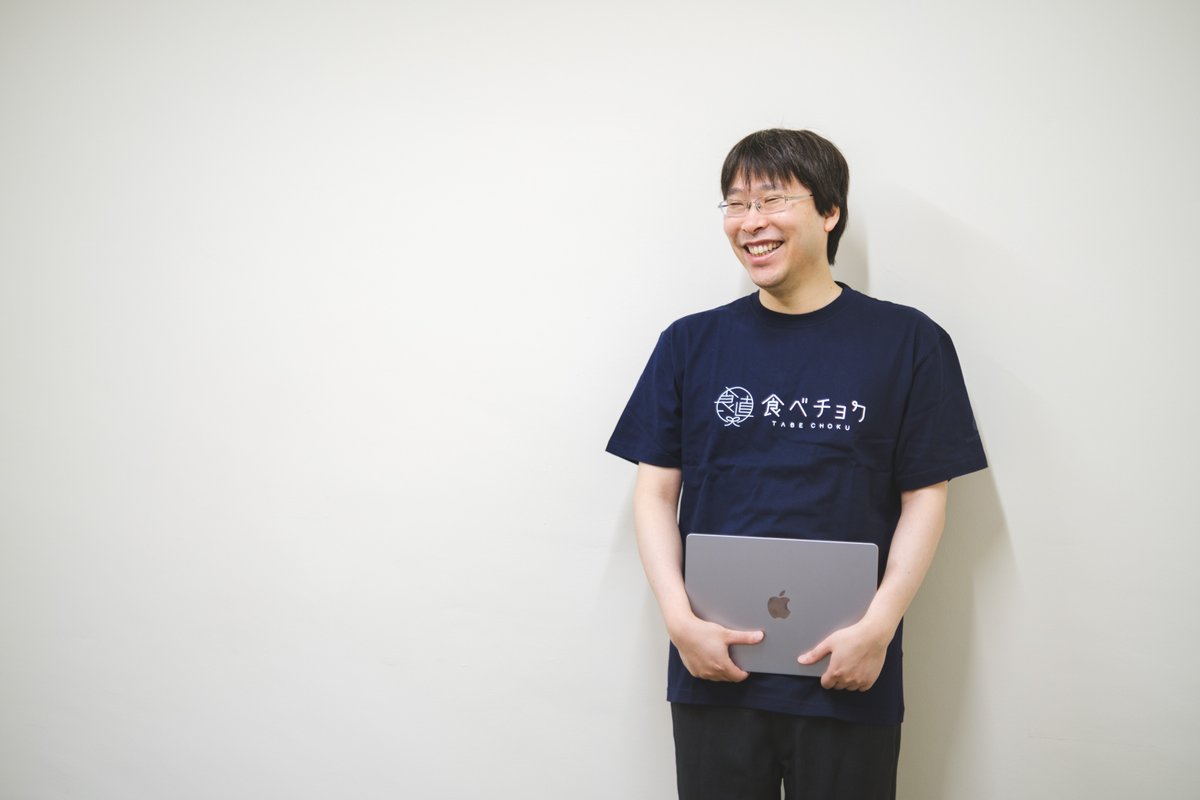
課題解決を通して事業を成長させる組織へ
ーー 組織やメンバーに期待することとそのためにマネージャーができることは何でしょう?
西尾:ライブラリ変えたいとかデリバリーを早くするために仕組み変えますとかはどんどんやってもらっていると思っています。今後はさらに解決すべき重要な課題を見つけ、把握するところをもっと進めていってもらいたい。会社もプロダクトも大きくなっているので難易度は高いですが、そこに対する積極性みたいなものはめちゃくちゃ期待したいです。
中西:課題設定を自分でできて、自分でドライブできる人がもっともっと増えてほしいというのは同意ですね。それを期待する中ですごく大事なことがあって、我々のようなマネージャー職についてる人間は、必ず機会の提供をしなきゃいけないんですよね。
CTOから「こんなアウトプットを期待しているよ」という「ゴールはここだよ」という期待を明確にした上で、道中口出しはしない。同時に「困ったらいつでも頼ってほしい」というメッセージも伝える。この安全性を保ちながらチャレンジできる環境をいかに作れるかが大事だと思っています。
西尾:ただ「やって」ではなくて、ゴールを明確にする。そこに至る過程である課題の設定などはお任せする。だけど最後はちゃんとフィードバックする。これはやらないといけないですね。
ーー最後に、会社としてこう見られたいな、こんな会社にしたいなというビジョンはありますか?
中西:最初に少し言ったのですが、ビビッドガーデンの良いところは「プロダクト愛に溢れている」ことです。とても大事だと思っているし、これはあんまり後天的には作れない。課題解決ができる組織とこの想いが掛け合わさると、一気に事業成長が加速すると思っています。
課題解決を通して、事業を成長させている企業だよね、一次産業に貢献してるよね、ビビッドガーデンいいよね、と言われる組織を作っていきたいです。
ーーありがとうございました!
西尾 慎祐 執行役員CTO
山梨大学大学院医学工学総合教育部を修了後、SI企業に就職。Rubyエンジニア、開発チームリーダーとして動画配信サービスのフルリプレイスに携わる。2018年3月より株式会社ビビッドガーデンに1人目のエンジニアとして入社。食べチョクのプロダクト全般において開発方針の策定・実行をリードし、現在は40名を超える開発組織を統括。2022年5月より執行役員CTOに就任。
中西 晶大 エンジニアマネージャー
新卒で大手ISPに就職。バックボーンネットワークの保守・運用業務を担当。その後、株式会社リブセンスにてインフラエンジニア、エンジニアリングマネージャー、採用責任者を担当し、2022年1月より株式会社ビビッドガーデンに入社。プロダクト組織のエンジニアマネージャーに従事。
開発組織はプロダクトの事業価値を最大化すべく、さらなる進化を目指しています。
ご興味ある方、ぜひぜひ一度お話しましょう!
また、今後こちらのマガジンでリアルな社内情報をお届けします。是非ご覧いただけますと幸いです。
