
パーツ説明 「エンドピン」
私が誰だかわかりますか?

私は、ヴァイオリンのお尻に差し込む「エンドピン」です。
いつも弦の張力を一人で支えているのに、あまり気が付いてもらえない。
だから今日は、私の仕事を少し紹介しますね。
以前、ヴァイオリンの祖先は「弓」から始まっているとお話しました。
弓の竿は、弦に引っ張られて内側にしなることが特徴です。
だから、ヴァイオリンも内側にしならせる仕組みが必要なのです。
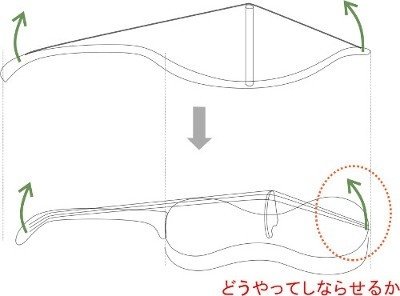
しかしヴァイオリンのボディは箱のようになっていて、
曲げるのは簡単ではありません。
どうすればしならせることができるでしょうか。
この対策として考案されたのが、ブロックとエンドピンを使う方法です。
エンドピンをブロックに差し込み、
弦の張力①は、サドル経由でエンドピンを持ち上げます(②)。
この時、エンドピンはサドル経由でブロックを内側に押し曲げることで
裏板を内側に押し曲げるのです(③)。
この仕組みの特徴は、エンドピンがヴァイオリンの外にあることです。

ここで、もう一度私を見てもらえますか。
エンドピンは、ひもで引っ張られる力をスムーズにブロックに伝えるため
ひもからブロックまでは、まっすぐ刺さっているんです。
そして、ほんの少し「しなり」も必要なのです。
だから、ペグに似てるでしょ。

先っちょは「ハート型」なんですよ。
でも、大きくすると演奏者の首を傷つけるといけないんで
ちょっとつぶれてますけどね。
後ね、ペグと同じように、穴が空いてるでしょ。
なんでか解りますか。
それはね、ニスを塗装する時に、「すずめ」さんに
持っていかれないためにひもを通して、どこかに結んでおくんです。
突っつかれるぐらいならいいんですけどね。
私を作るために、細川さん、結構苦労してるんですよ。
小さいのに1週間以上かかってる。
だから、試奏会に参加した時は、少しでいいので見てくださいね。
縁の下の力持ち「エンドピン」より。
