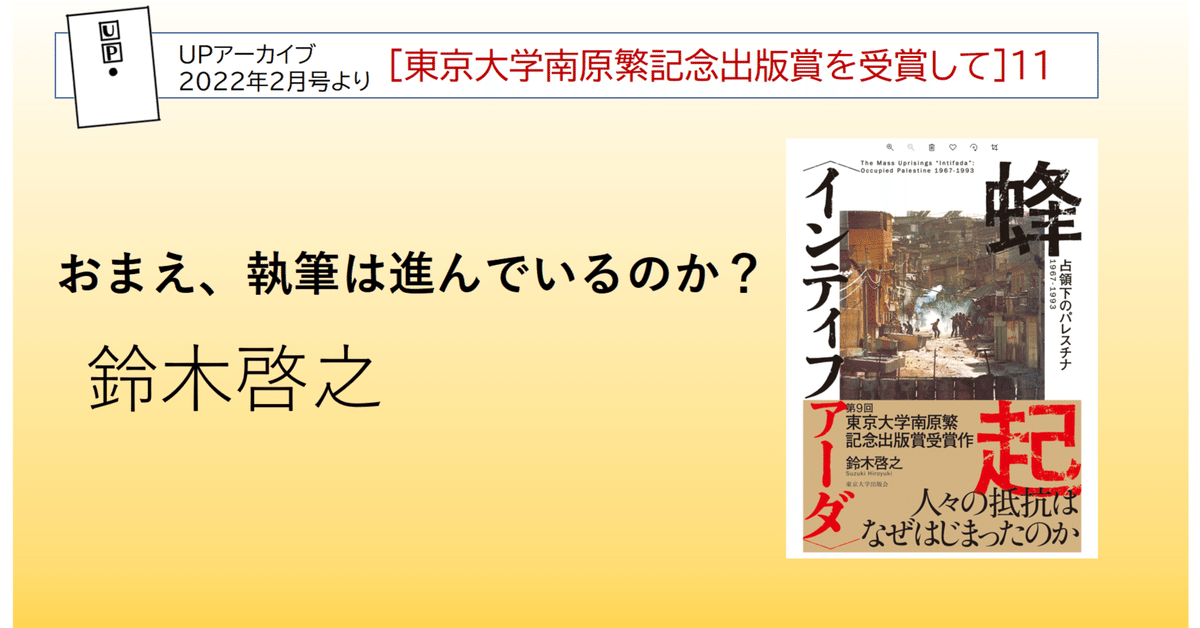
おまえ、執筆は進んでいるのか?/鈴木啓之
最後に、今回頂きました賞にその名前が冠されている南原繁ですが、彼が内務省の職を辞して学問の道に踏み出しましたのは31歳の時であったようです。奇しくも同じ歳でこの場に立っております私は、ここに学び、今日の受賞を到達点としてではなく、始まりとして受け取りたく思います。
2019年3月の授賞式には、スピーチ用の原稿を持ち込んでいた。指導教官や博論審査員、賞への推薦者の名前を言い忘れないことが大目的だったが、他にすこし縮こまるような思いがあったからだ。そのため、こうして3年ほど経ってからも、当日に自分がなにを話したのか、文字通り「一字一句」再現できる。随分と肩に力が入っていたようだ。賞に名前が冠されている南原繁の人生に自分を重ねる後半の部分など、一見すると謙虚に見せつつ虚勢に近い言葉運びになっている。
私がこうして思わず虚勢を張ってしまったのは、もちろん東京大学南原繁記念出版賞の名前の重みに起因するところが大きい。東京大学の学籍を離れてから4年後に、戦後最初の総長の名前を冠した賞を得たことの緊張は察して欲しい。また、過去の受賞者の著作を読んで、不安を覚えてしまったことも正直に述べなければならない。格調高い式典で、とんでもない知識人たちにジロジロと見られ、品定めされるようなことになるかもしれない。想像するだけで恐ろしかった。
ただし、これは杞憂であった。式典は穏やかな雰囲気で進み、第8回受賞者の江本弘さんからは、指導教官と私の名前が同音であることから、「すごく緊張する」と声をかけて頂いた。その一言で、自身の緊張が解けたことを覚えている。また当時はコロナ禍以前であったので、懇親会や2次会─実のところ3次会にも行った─に、本郷の町へと繰り出した。歴代受賞者から、執筆時の苦労話や、出版までの道のりを聞き、励ましの言葉もかけて頂いた。文字通り、贅沢な時間であった。その時の昂揚した気持ちのまま、私はエルサレムに「帰国」した。当時、日本学術振興会海外特別研究員として在外研究をしており、生活の拠点がエルサレムにあったからだ。
エルサレムに戻った私は、文章全体の校正と終章の加筆を進めた。特に終章は、博士論文審査の時に、「もう少し踏み込んで論じた方が好ましいのではないか」との意見を受けていた箇所で、編集担当の阿部俊一さんからも「終章を重点的に」とアドバイスを頂いていた。ところが、いざ書き始めると、賞の名前に相応しい文章にしたいという思いが強くなり、キーボードが打てなくなった。「東京大学南原繁記念出版賞」の名前に見合った名文が、すいすいと思い浮かぶはずもなく、本郷の居酒屋で得た自信は、エルサレムの丘の上でみるみるうちにしぼんでいった。本郷で、「頑張ります」、「良い本にします」などと口走った自分の言葉が重くのし掛かり、あの場でもっと身の丈にあった言葉を選ぶべきだったと後悔を覚えた。
文章が進まない以上、来訪者の観光ガイドを買って出ることにやぶさかではなかった。実際に気分転換にもなったし、地の利を生かして少しばかり自信を取り戻す機会にもなった。そのような経緯で、日本から来た数名を「引率」して、エルサレム市内の観光名所を同じルートで案内することが続いた。
その時である。エルサレム旧市街の菓子屋に、博士論文で取り上げたパレスチナ人リーダーの一人、ファイサル・フサイニーの写真がポツリと飾られているのが目に留まった。いつも歩いている通りなのに、まったく迂闊なことだった。1987年からの大衆蜂起インティファーダの頃のものか、またはイスラエルとパレスチナの和平交渉が続いていた頃のものかは定かではない。両手を顔の横にあげて、抗議とも呆れともとれる表情を浮かべていた。「おまえ、執筆は進んでいるのか?」と咎められたような気がして、写真を2枚ほど撮った。そのうちの1枚は、無事に刊行された拙著『蜂起〈インティファーダ〉』の終章に載せている。もちろん、著作のなかでの文脈は別にあるのだが、今振り返れば終章改稿の第一の立役者は、この写真であったのかもしれない。この写真に「怒られて」から、私はとにかく原稿を読み返すことにした。終章だけを加筆するつもりだったものが、「あれも、これも」と欲が出たことは、予想に違わないことだった。せっかくパッキングした荷物を、また広げて詰め直しているような状態だったが、6年近くかけて書いた原稿と向き合う幸せな時間になった。
この書き直しと並行して、私は就職活動を始めることになった。日本学術振興会の海外特別研究員は、任意の起点から2年間の任期が定められている。私は2018年4月20日に出発したので、厳密には2020年4月19日が任期満了日であった。ただ、日本の学事暦を考えれば、2020年4月1日着任を目指すことが必要だった。南原賞は大きな励みになったが、それがどれほど公募に役立つものか、当初は半信半疑であった。就職していく先輩らの姿を多く見てきたが、それと同じく最終面接で落選となった話や、「君の能力や経歴は申し分ないんだけど……」という決まり文句で、学内の事情か何かで選考から外れてしまった話も聞いてきたからだ。また、コロナ禍以前の「オールド・ノーマル」の通例として、2次審査や最終審査で直接面談を課す公募が多かった。テルアビブと成田の往復は、最安値で14万円ほど、繁忙期になると20万円台に迫ることもあったので、頻繁に帰国することは金銭的に難しかった。そうした事情から、私の場合は応募先をそれなりに絞っていく必要があった。
ただし、これも今から振り返れば杞憂であった。実のところ、いまの職場─東京大学中東地域研究センター(UTCMES)─には、就職活動の比較的早い段階で応募し、数ヶ月後には手応えを得るに至っていた。採用の際に、南原繁記念出版賞が考慮されたことは想像に難くない。当時としては「最先端」のオンライン面接だったことも、その後の引っ越しを考えると有難かった。こうして、授賞式で「始まりとして」と放った言葉は、はたして半年と経たずにその通りになった。改めて賞の重みを思い知った瞬間である。
UTCMESへの着任は2019年9月中頃と決まり、残りの任期を切り上げて帰国することになった。博士論文の「再パッキング」よりは気楽なことだったが、一年半の生活で意外なほどたまっていた身の回り品や資料、書籍などを梱包し、日本に少しずつ送っていった。在外任期の切り上げについては、少し勿体ないような気持ちが当初あったことを、ここに告白しなければならない。エルサレムでの生活は、学術的に得るものが多かっただけではなく、何より楽しかったからだ。ただ、その気持ちは半年も持たなかった。イスラエルで最初にCOVID─19感染者が確認されたのは、2020年2月21日のことだった。客船ダイヤモンド・プリンセスから横浜に下船したイスラエル人観光客が、帰国後に発症した形だった。また、時を置かずに、パレスチナ自治区を訪問した韓国人観光客の感染が明らかになり、パレスチナとイスラエルも世界的パンデミックに巻き込まれていった。国外との航空便や郵便業務がストップしたので、もし海外特別研究員としての任期を全うしていたら、自身の帰国すらままならなかったはずだ。
コロナ禍の到来とともに、私の「ノーマルな東京生活」は終わりになった。ほぼ同時に、採用後の試用期間(6ヶ月)も終わり、担当する授業が少し増えた。すべての授業がオンラインに切り替わったのは、予定されていた新学期まで日付が残っていないタイミングだった。はじめて担当する授業の設計に追われ、オンライン化への対応は、ほとんど後手に回ったような状態になった。シラバスを入稿していたころの自信が、嘘のように消えていった。
この時、かつてのアルバイトの経験がすこし役立った。そのように言うと、南原繁に呆れられてしまうかもしれない。戦後の学生アルバイトの問題─戦後復興の混乱のなか、学生が学業だけに集中できない課題─を論じた文章で南原は、「『働きつつ学ぶ』という言や美しいけれども、出来るならば修業時代は学問の研究に、教養に、学生としての本来の課業に徹するにまさることはない」と述べているからだ(『日本の理想』215ページ)。週1回から2回のアルバイトで研究を疎かにした自覚はないものの、少し耳が痛い言葉だ。ただ、オンライン授業の手法が学内で説明されるなかで、「リスナーと対話するラジオ番組」という言葉が出たときに、「腕に覚えあり」との気持ちが湧き上がったのは事実である。私のアルバイトは、ラジオ放送のアシスタントだったからだ。ここで、駒場キャンパスでオンライン対応の先頭に立っていた一人が、南原賞第1回受賞者の鶴見太郎さんだったことは言及しておくべきことだろう。詳しくは、最近になって東京大学出版会から刊行された『駒場の70年』に記されているが、「ラジオのように」と教員に説明していたのは、他ならぬ鶴見さんだった。皆でこの前代未聞の危機を乗り越えていこうという、教職員の不思議な一体感が生まれていたことも、モチベーションを保つ原動力になった。
もっとも、実際に授業が始まってみれば、学生に励まされることも多かった。オンラインで実施される授業を「授業」、対面授業を「オフライン授業」と呼んでいる場面に遭遇したときには、その適応能力の高さに頼もしさすら感じた。いま、来期の授業が対面授業になるか否か、各所で検討が続いている。学部前期課程生(一~二年生)のなかには、オンラインでの授業しか経験がないため、教室での授業に不安を覚える者もいるように聞いている。私も、その気持ちを幾分か共有しているつもりだ。ある特定の講義科目に関しては、私も「オフライン授業」の経験がないからである。オンラインでの蓄積を教室でどのように生かすのか。これまでの常識とは逆の課題に、遅かれ早かれ取り組む必要がありそうだ。
UTCMESでは今年度、オンライン連続セミナー「遺産と中東」を全13回の予定で開催している。第1回目の報告者は私が務めた。ちょうど、イスラエルによるガザ地区への空爆が収まり、それに関連した原稿や取材などへの対応─これは過去に経験をしたことがないものが大半だった─を終えた6月初旬のことだった。この連続セミナーは、「遺産」をキーワードに中東を考えてみたらどうだろうかという試みで、記憶や伝承、建築、料理など、多岐にわたるテーマが─企画者が言うべきことではないのだが─参加者の好評を得ている。この成果論集を来年度はまとめていくことになるが、エルサレムの路上で遭遇したフサイニーの写真を頭に思い浮かべながら、執筆を進めていきたい。
来期からのセミナー企画についても、いまUTCMESのスタッフで検討中だ。一つ決まっているのは、可能な限りオンラインでの参加が続けられるように工夫することである。誰でも参加しやすい空間を、引き続き作っていきたいと考えている。駒場キャンパスに地理的、時間的、その他さまざまな事情から足を運ぶことが叶わない参加者に広く門戸を開き、皆が講師の話に耳を傾ける場を維持することに、大きな意義を感じている。もちろんUTCMESに限らないことだが、「中東」に関心を持つ研究者、学生、社会人、実務家が集う場があることは、中東情勢の分析や情報交換、文化や芸術への理解の促進において大きな強みになるはずだ。
こうした日本社会に向けての活動のほかに、国外との学術交流もUTCMESでの大切な仕事の一つである。特に私(特任准教授)と特任助教は、UTCMESのなかでもスルタン・カブース・グローバル中東研究寄付講座という、オマーン・スルタン国からの寄付講座に所属している。講座に名前が冠されているスルタン・カブースは、オマーンの前国王で、独立後の近代化に多大な足跡を残した人物である。こうした事情から、在京オマーン・スルタン国大使館とのやり取りや本国の担当部局との連絡も、私と特任助教の職務になっている。また、東京や広島などで活動するオマーンとの友好協会のメンバーと意見交換や情報共有をすることも多い。研究の発展を志すことは言うまでもないが、東京大学を社会に対して開かれた場とする取り組みの一つとして、UTCMESでの仕事には楽しみを見出している。
ところで、教養学部のスルタン・カブース・グローバル中東研究寄付講座を省略した結果らしいが、学内郵便物の宛名が「教養スルタン 鈴木啓之殿」になることが、たびたび起きている。言わば「東大王」を凌ぐインパクトの称号を与えられたような形で、こればかりは身の丈を調整することが難しい。諦めることも肝要だと自分に言い聞かせている。
(すずき・ひろゆき 地域研究[中東地域]、中東近現代史)
初出:『UP』592号 (2022/2)

