
【痛風・偽痛風】激痛発作から身を守る方法
「関節が破壊されてしまうこともあります。怖いんです」
今回は【痛風・偽痛風】激痛発作から身を守る方法をお届けします。
痛風、めちゃくちゃ増えてるんですよ。
※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。
ときどき出てくる「ふんぞり男」とは、その名の通り、ふんぞり返って態度がデカい患者さんです。
痛風の患者さんが増えている!?

こちらの2020年の報告(*1)によると、30年で痛風の患者さんは4倍に増えてるんです。
男性に限れば5倍です。もう急増ですよね。
その増加傾向は2042年頃まで続くだろうと予測されています。
さらに「偽痛風」というニセの痛風と書く病気も増えてくるだろうと予測されます。

なぜなら、ニセの痛風こそ年齢とともに増える病気だからです。
どんどんご高齢な方が増える日本においては、偽痛風で関節が痛いという患者さんは増えると思います。
ここ十年以上、整形外科医として診察してきた実感でも偽痛風はとっても多いです。
ふんぞり男「ほぉ、ほぉ、恐怖感を煽って患者さんを集める気だな!?騙されないぞ!年に何回か、来る激痛に耐えれば良いだけだろ」
いや、勘弁してください。
僕は痛風患者さんも偽痛風患者さんも今の外来では、ほぼ拝見してません。
もし、そういう患者さんが集まってきてくださっても、お近くの整形外科で治療してくださいねとお伝えすることになります。
それよりも、ぞり男さん・・年に何回かって、多くないですか?
それも激痛って・・
でも、確かにぞり男さんのように、痛風なんて激痛のときはつらいけど、それ以外は症状がないから気にしないという患者さんは少なくないです。
しかし、痛風の原因である「尿酸値」が高い状態が長く続けば続くほど、痛風発作は増えます。
古い論文ですが、こちらの報告(*2)によると

以下は、1年以内に痛風発作が発生する割合と尿酸値です。
9mg/dl以上 → 4.9%
7.0〜8.9mg/dl → 0.5%
7.0mg/dl未満 → 0.1%
高くても5%くらいじゃないかと思われるかもしれませんが、1年間の発生率です。
それが何年も続けば・・・
どうなるか、わかりますよね。
そして、なにより僕は整形外科医として、痛風発作のなれの果てともいえるお辛い状態を拝見しています。

痛風発作とは
「尿酸結晶という物質が関節に増えて、最終的には関節軟骨がすべて尿酸結晶で覆われてしまっていて、炎症が治まらないという状態」
そういう患者さんは手術で徹底したクリーニング手術をしないといけません。
嫌ですよね・・?
また、尿酸値が高い状態は、痛風発作のリスクが高い状態であることの他にもたくさんのリスクがあります。
「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」(*3)によると、数多くの怖い病気のリスクになることが明らかになっています。

慢性腎臓病
高血圧
狭心症
心筋梗塞
脳卒中
心房細動
メタボリックシンドローム
脂肪肝
糖尿病
やはり、これらはどれも防いでいきたいですよね。
今回は痛風の基礎知識と発作時の激痛にどう対処するか、偽痛風とはどう違うのかにフォーカスして解説してまいります。
痛風って何?

痛風とは、誰もが一度は聞いたことがある病名だと思うんですが、それもうなずけるのが歴史の長さです。
なんと遠く遡ると、紀元前5世紀のヒポクラテスの時代から明らかになっていた病気で、その治療薬としてコルヒチンを使っていたそうなんです。
それを未だに使っているというヒポクラテスの凄さとともに、日進月歩の医学において驚くほどに進んでいないとも言えるかもしれません。
痛風とは、身体の中に尿酸という物質がたくさん溜まってしまう病気です。
尿酸は普段は尿として身体の外に出ていくものですが、たくさんたまると固まって結晶になり関節にたまります。
結晶が関節に溜まる・・・
ちょっとイメージしにくいですよね。
例えば、想像してみてください。
冬の日に窓ガラスに霜がつく様子を・・。

霜は小さな氷の結晶でできています。
これは、窓の表面の水分が冷えて固まり、小さな氷のかたまりができるからです。
水という物質「H2O」が結晶化したわけですね。
痛風の場合も似ています。
体内の尿酸が固まって、小さな結晶を作ります。
これらの結晶は、本来関節の中にはないものです。
ですから、身体は異物と認識して排除しようとします。
これが「炎症」ですね。
例えば、喉にウイルスが入ってきたら、炎症を起こして熱を出して排除しようとします。
これは風邪の場合ですね。
そういう意味では、関節の中に尿酸の結晶が入り込むことによって起こる「関節の風邪」と言えるかもしれません。
ふんぞり男「お前、喩えを使いすぎて、余計に分かりにくくなっているぞ!」
適切なアドバイス、ありがとうございます。
そうですね。このくらいにして、痛風発作が起こったらどうするか?についてお伝えしていきますね。
痛風発作で激痛になったらどうする?
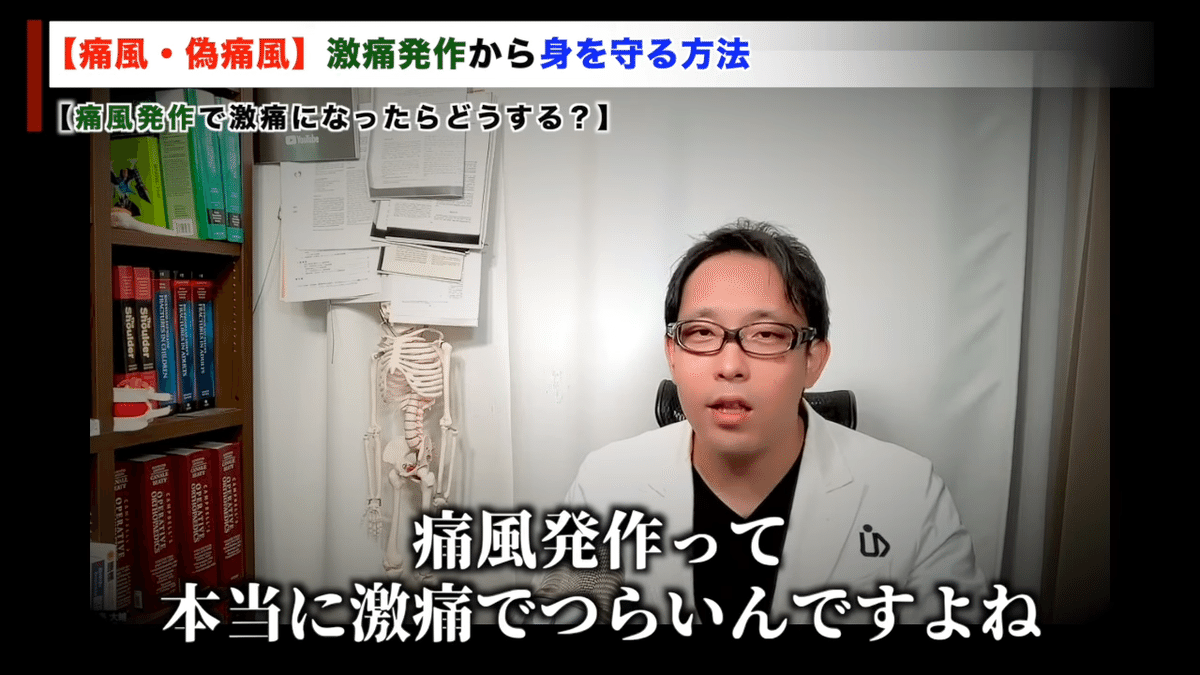
痛風発作って、本当に激痛でつらいんですよね。
ですよねと言いながら、僕は経験ないんですが・・
ふんぞり男「は?お前、ないのか?俺は、今絶賛発作中だ。足が痛すぎる。マジで泣きそうになるからよう、早く痛みが治って、尿酸値も低下するっていう施術を受けてきたんだよ。お前、何も変わらねぇじゃねぇか。どうしてくれる」
また、クレームを言う相手を間違えてますが、施術で良くなるってどうして思ったんですか?
その食生活で尿酸値を下げようと思うのは、虫が良すぎるんじゃないですかね。
実際に検索してみると、整体師の先生が「うちでは、特殊な施術で痛風を治療します」
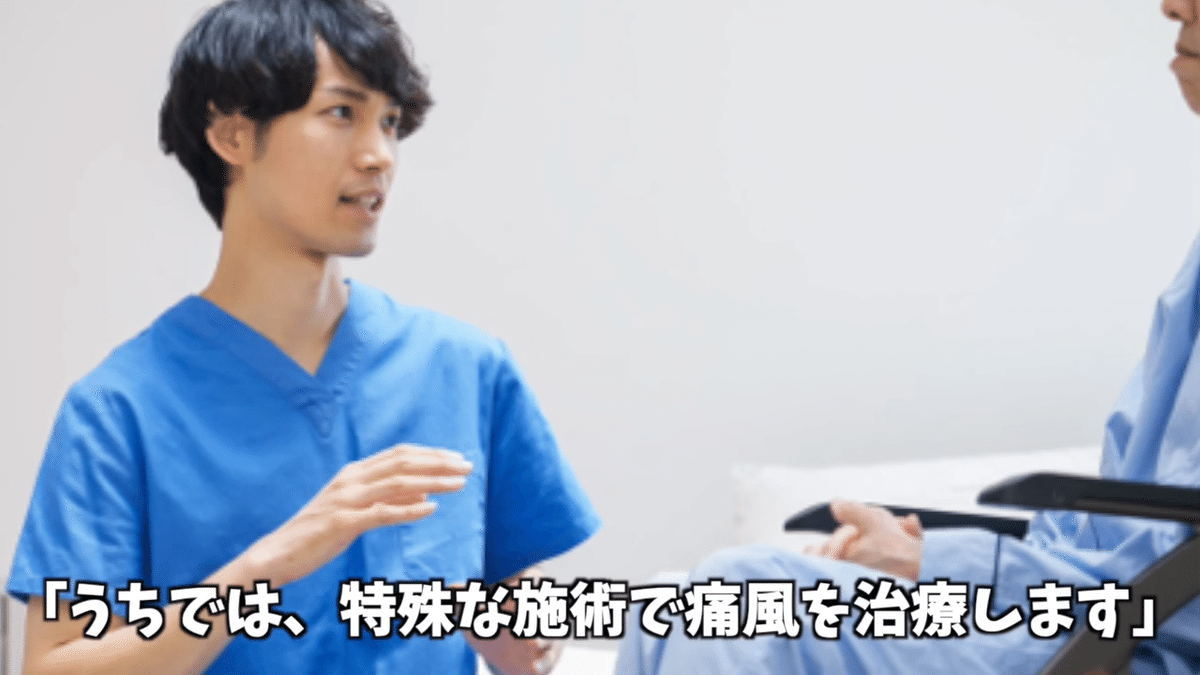
みたいなことをおっしゃっているケースをお見受けします。
しかし、痛風の医学的なメカニズムを知ると、施術で治すのはほぼほぼ無理です。
治せるという理屈が意味不明です。
僕は治療家さんの施術をすべて否定したいわけではありません。
というか、オンラインサロンに治療家さんがたくさん入ってくださっていたり、本当に一緒に学んでいる珍しい整形外科医です。
なので、世の整形外科医の何倍も治療家さん寄りの立ち位置になります。
ただ、それも実は表面上の見え方かもしれません。
僕はどちらよりでもなく

「医学」を大切にして、根拠がない治療を否定します。
根拠があるなら、その根拠を学びます。
とことん、医学に真摯にいきたいと思っていて、それはなぜかと言えば「患者さん」のためです。
つまり、僕は医者寄りでも治療家寄りでもなく、患者さん寄りです。
そうなったときに、根拠がない治療をしていれば、医師だろうが治療家だろうが批判します。
その比率が残念ながら治療家さんの方が遥かに多いのは、僕が医師だというバイアスを考慮しても、明らかすぎる事実です。
ふんぞり男「また、お前はその話になると暑苦しい!俺もそうだが、患者は根拠とか良いんだよ、治りゃよ〜」
おっしゃるとおりですね。
僕も「治りゃいい」と思いますよ。
だから、例えば東洋医学はなかなかメカニズムが解明できない理論構築をしているので、医学的根拠がないと言われがちですが・・
例えば、東洋医学の「〇〇治療」で痛風発作が3日で治った。
それに対して、ロキソニンを飲んだだけの場合は7日だった。
というデータが、たくさんの患者さんを集めて統計的に証明できたら、これも立派な医学的根拠です。
東洋医学の「〇〇治療」のメカニズムがちょっと意味不明だったとしても、その治療結果がちゃんとした研究のもと統計学的に証明できたのであれば、それは「治りゃいい」の範疇に入ります。
しかし、ぞり男さんが言う「治りゃいい」というのは、思いっきりランダムで運頼みです。

例えば、痛風発作が痛すぎて、ロキソニンが処方されたとします。
しかし、痛すぎて全然ツラい。
そんなツラい5日目、ワラにもすがる思いで東洋医学の〇〇治療を受け、その翌日に痛みが引いてきたとします。
ぞり男さんはきっと、その〇〇治療で治ったんだと言うでしょう。
でも、その〇〇治療をしなくてもロキソニンを飲み続けていれば、または飲まなくても炎症が自然と治まって来るタイミングかもしれません。
全然あり得るタイムスパンです。

つまり、ちゃんと研究して統計データを出さないと、1人の経験では有効な治療かどうかなんてわからないんですよね。
そして、そのわからないまま、効く!有効だ!と言っている治療を「根拠がない治療」と言っています。
ぞり男さんが言うとおり、この話は暑苦しくて止まらなくなってしまうので、このくらいにしますが、医学的根拠から目をそらさないでください。
医学的根拠とは丁寧に医学研究論文を積み上げて、これだけの根拠がある治療ですと言わないといけません。
でも、そんなの判断できないと思われるとしたら、診療ガイドラインを参考にしてください。
ガイドライン上推奨される治療なのかそうじゃないのか。まずそこからです。
痛風にも先ほどご紹介したとおり、治療ガイドラインがあります。
痛風発作の激痛はできるだけ早くお薬を使う

ガイドライン上推奨されているのは、発作が出たらできるだけ早く炎症を抑える薬を使うことです。
基本は「非ステロイド系消炎鎮痛剤」です。
それも十分量を使うことが推奨されていて、有名な鎮痛薬であるロキソニンであれば1日3回、さらにより副作用が心配だけど、消炎鎮痛効果が高めとされているボルタレンなどのジクロフェナクを使用することも少なくないです。
さらにステロイド自体を内服したり、時に注射することもあります。
これはより炎症が強い時に使われることが多いです。
そして、昔から使われるコルヒチンという薬もあります。
これは、発作が起きてから12時間以内に飲み始めるべきとされていて、かつ量が多すぎると、胃腸の問題が起こったり、血液中の白血球数などが減ってしまいます。

骨髄抑制・横紋筋融解症・末梢神経障害などの副作用に注意をしないといけません。
僕自身はほとんどコルヒチンを処方することはありませんが、リスクをしっかり説明した上で、使い慣れた医師が処方する分にはガイドライン上も推奨されているお薬です。
いずれにしても、お薬を早くしっかり飲んで、発作を早く抑えてしまうことが基本ですね。
さらに大事なのは、尿酸値を下げる治療をしていない人が、はじめて痛風発作を起こしてしまったときに、発作中に尿酸値を下げる治療をしてはいけません。

発作をしっかり鎮静化させてから、尿酸値を下げないといけません。
さて、この痛風と似て非なる偽痛風について、次に取り上げます。
偽痛風ってなに?

偽痛風とは面白い名前ですよね。ニセの痛風ですよ。
何がニセなのか、何が似ているのかという視点で考えると理解しやすいのですが、まず似ているのは症状です。
痛風発作と同様、関節の激痛と腫れですね。
そして、結晶が関節に溜まるのも同じです。
しかし、違うのは溜まる結晶の物質そのものです。

痛風は尿酸だったわけですが、偽痛風はピロリン酸カルシウム、英語で略すとCPPDが溜まります。
正直、この名前は覚えなくても大丈夫です。
違う物質が溜まるってことが大事ですね。
ですから、痛風のように採血で尿酸値が高いかというと、そこは関係ないというのもポイントです。
さらに大事な違いは、起こりやすい場所ですね。

偽痛風は膝が半分くらいで圧倒的に多いんですね。
さらに股関節、肩など、大きな関節に比較的起こりやすいのも特徴です。
僕も肩を専門とする外来をしていますが、時々偽痛風だなという患者さんに出会うことがあります。
それに対して、痛風はご存じの通り足の親指の付け根ですよね。
偽痛風と痛風ってどう見分ける?

自分の痛みは、痛風なのか偽痛風なのか見分けるにはどうしたらいいのかですが、当然ですが、一番は整形外科医の診察を受けてください。
正直、僕自身の経験として「これは痛風かな、偽痛風かな」と迷った経験は記憶がありません。
それほど、痛風も偽痛風もわかりやすく違うと思っていて、さきほどの起こりやすい関節の問題もあれば、レントゲンの所見の特徴、さらに偽痛風の方がよりご高齢な方に多いという特徴などからわかりやすかったりします。
そういう意味では、痛風や偽痛風と対処法が大きく異なる2つの病気との鑑別がとっても大事になります。
痛風・偽痛風と軟骨のすり減り(変形性関節症は?)・感染

ご高齢の方に多い関節の痛み、腫れの最も典型的な病気というのは「変形性関節症」ですよね。
いわゆる、軟骨のすり減りです。
痛風や偽痛風はどちらかと言うと、発作的に急性の痛みに襲われます。
ですから、その激痛の期間をなんとか強めの消炎鎮痛剤やステロイド注射などで対処するというのが基本作戦になるわけです。
しかし、変形性関節症は慢性的な症状であることが多いので、長くどう痛みに対処していくかということが大事です。

痛いからと言って、ステロイド注射を何回も延々と受けていれば、軟骨のすり減りが急激に進むリスクもあります。
ですから、ここを見分けるのは大事ですね。
見分け方はこの症状や対処法とも関連していて、痛風・偽痛風は急性の炎症なので、体温が上がって発熱したり、採血上もCRPという炎症反応が上がっていることも多いです。
これらは変形性関節症では逆に稀です。
しかし、この急性炎症という特徴がある、もう1つの重大な病気が細菌感染・いわゆる化膿です。
例えば、肺に細菌が入ってしまえば肺炎、正確には細菌性肺炎。
膀胱に入ってしまえば膀胱炎という病名になり、多くは抗生物質で治療したり、軽症なら自らの免疫で治るのですが、関節に細菌が入ってしまう化膿性関節炎はもっと大変です。
たいてい手術して細菌を外に洗い出さないと治りません。
ですから、化膿して腫れて激痛なのにも関わらず、痛風や偽痛風だと思って消炎鎮痛剤を飲んだり、ステロイドを注射していても良くならないどころかどんどん細菌が増えて、関節が破壊されてしまうこともあります。怖いんです。
ふんぞり男「お前、怖すぎるじゃねぇか。でも、症状は急性炎症で同じ。もうお手上げだ!」
おお、一生懸命聴いていただいているようで嬉しいですが、そうなんです。
外から見ただけでは鑑別できないこともあります。
そんなときに大事なのは、関節の水を抜くことです。

その抜いた水の中に、痛風だったら尿酸結晶、偽痛風だったらピロリン酸カルシウムがあり、化膿だったら細菌がいるんです。
ですから、直接腫れている関節に注射をして水を抜く、これが最も大事な検査であることが多いです。
毎回注射するわけではなくて、化膿すらあり得るなと思ったときに注射をして水を抜くことが多いと思ってください。
まとめ
ここまでのまとめをスライドで見ていきましょう。
まず痛風を解説しましたね。

そして、名前はめちゃくちゃ似ている偽痛風。

診断は医師の大事な役割、仕事ですので、まず早期の受診をお勧めします。

本日の一言
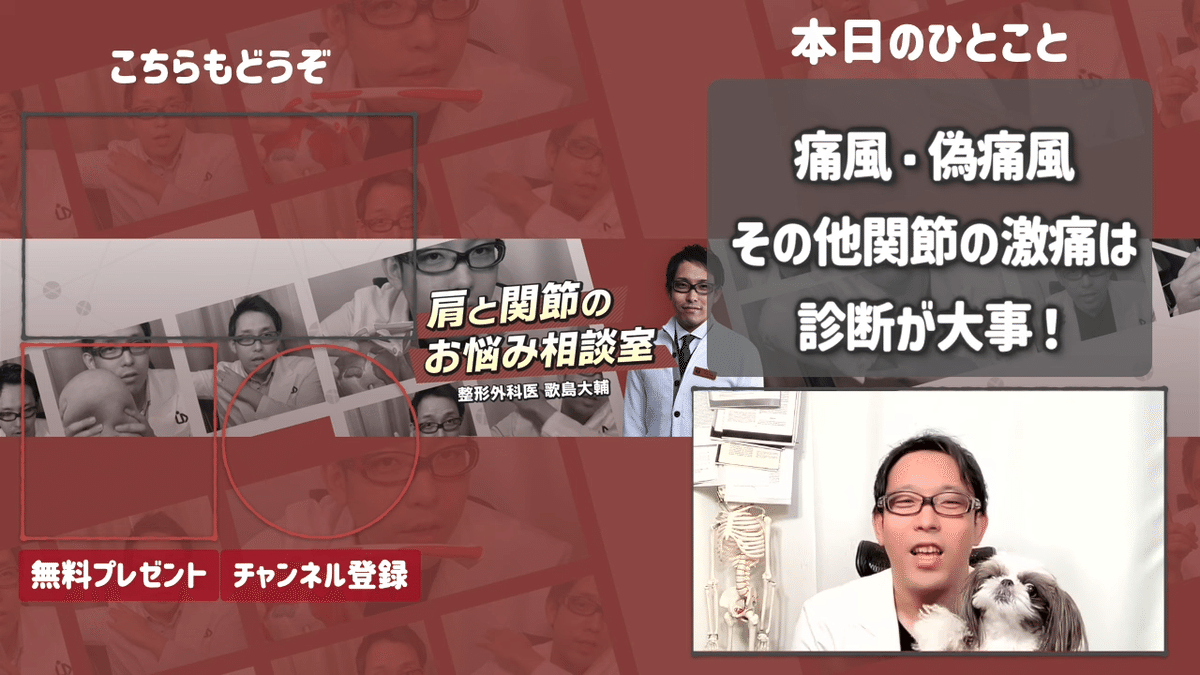
痛風・偽痛風、その他、関節の激痛は診断が大事!
🎁動画講座「寝たきりリスク TOP10セミナー」プレゼント

人生100年時代・・・寝たきりの可能性が高まってしまう「恐怖の習慣」をまとめた「寝たきりリスクTOP10セミナー」をプレゼント中です。詳細はこちらから▼
🎁治療家さん向けプレゼント
電子書籍「レッドフラッグ100選」

危険な兆候・症状・疾患を一気に学べる▼
参考論文
(*1) 箱田雅之ら、 Gout and Uric & Nucleic Acids Vol.44 No.1 (2020) 我が国における痛風患者数の今後の動向について
(*2) E W Campion, et al. Am J Med. 1987 Asymptomatic hyperuricemia. Risks and consequences in the Normative Aging Study
(*3)高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版 2022追補版 日本痛風・尿酸核酸学会 ガイドライン改訂委員会
