
写真は語られるべきなの?どうなの?長島有里枝さんの写真集「SWISS」について。
ね、どうなんでしょうね〜。笑
写真作品における言葉の要不要論って難しいですよね〜。
写真家の中には自分の作品について、又は作品の狙いや確信について言葉で語ることをしない方も多くいらっしゃいますね。
ステートメントにしろ、外側の事にしろ「言葉で説明できる事なら最初から写真なんか撮っていないよ!」って言う意見も分かるなぁ〜としみじみ思うんですけど、僕自身は好きに語っていいんじゃない?と言うか、写真みたいな不完全な媒体の力など全く信じて無いので、基本的に写真だけで僕の好奇心は満足できませんよ〜!と言いたい派です。
写真評論家の飯沢耕太郎さんとか写真作品についてめっちゃ調べてめっちゃ語ってますね。
しかも写真家の友人や家族の方にインタビューまでしたりして、さすが評論家は規模が違う!と思いつつ、多分彼自身の好奇心の強さの成せる技なのではないかとも思います。
飯沢さんを含め、美術系の雑誌の写真評論で見かける清水穣さんや、倉石信乃さんとか、彼らの文章は読んでて時々何言っているか全然分からんこともあるけど、評論家って凄いなぁ〜と率直に思います。
「この作品は○○だから、こう評価するよ!」って事を書いて、その文章に価値があって、仕事になるんだもの。
いや〜、すごい事ですねぇ〜。

さて、今回の本題なんですけど。
長島有里枝さんの写真集「SWISS」について。
2001年に蜷川実花やHIROMIXらと共に第26回「木村伊兵衛写真賞」を受賞した、長島 有里枝さんが2010年に赤々舎という写真集専門の出版社から「SWISS」という写真集を出していまして。
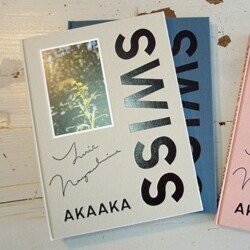
引用元:http://www.akaaka.com/publishing/books/bk-nagashima-swiss.html
書店で何度か手に取ったものの、買わず、今やプレミアがついて中古本でも結構なお値段になっております。
あの時に買っていればよかったーと僕が後悔している写真集の一冊です。
内容は、長島さんが、西欧の国スイスで息子さんと一緒に過ごした日々、(カラーネガフィルムで撮られているのかな?)優しい色合いと光の光景、見てて極めて心地の良いスナップショット群と、長島さんのおばあ様が残したポジフィルムで撮影されたお花の写真が並べられていたり、L版の写真を壁に貼ったものを複写されていたり、さらに日記のような文章も織り交ぜられておりました。
第一印象としては非常に繊細で美しい写真集だと感じました。
そんな「SWISS」という写真集との出会いがあり、のちに長島さんご本人のお話しを聞く機会がありまして、(今思うとめっちゃ貴重な時間でした)長島さんはこの写真集は、女性が強いられている役割に対する違和感についての作品でもあると仰っていました。
長島さんのおばあ様はお花を育てるのが好きで、咲いた花をポジフィルムで撮影していたそうです。
当時のポジフィルムって広告写真に使われるようなもので、ラチュードが狭い(明るいと真っ白になりやすいし、暗いとそこだけ真っ黒になる)ぶん、カラーネガフィルムより扱いが難しく失敗しやすいのですが、当時の主婦の感覚でポジフィルムかネガフィルムなんて分からなかったのでしょうね。
おばあ様がフィルムの種類を知らず(或いは、知り得る経験と出会えずに)にそのまま写真を撮らざるを得なかった事、強いては「女性」であるというだけで、家庭に入って家事全般をするのが当たり前だった、その人生の中での細やかな喜びが「お花を育てること」である事に対して、「女性の選択肢の狭さ」や「不条理さ」を覚えたそうです。(そんなふうに仰っていたと記憶しているが、8年前の事なので記憶違いが無いかちょっと心配…)
そのような意味を込めて、おばあ様の撮られたお花の写真が有り、更にスイスでおばあ様の写真をなぞるようにお花の写真を並べていらしゃったそうな。
でもそんな事は写真集の中で言葉ではっきりと語られて居ないんですね、でもそういったお話を聞く前と聞いた後では写真集を見る目線がちょっと変わってきます。
だから、できれば作品の周辺の情報やステートメントが言葉で欲しいな〜と思ってしまうのは罪ですかね?笑
(当時、学生だった僕は結構、若気の至りで…奔放に振る舞って居たので、少し斜に構えて聞いていたと言いますか、長島さんのお話しをもっとちゃんとメモとか取っておけばよかったとかなり後悔しています。)
-----------ここから身の上話なので飛ばしてもOK

ちなみに僕は2021年現在28歳で、1993年生まれの男子なんですけど、僕の生まれるよりもっと昔の1985年には「男女雇用機会均等法」が制定されていて、この80年代〜90年代で男女共同参画の意識は一気に広がったらしいです。
で、今も尚、社会全体で進めていこうと言う流れになっているらしいのですが…。
少子高齢化社会だからか、慣習の意識は根強いですし、政治の舞台でも男性ばかりなのが不思議ですね。
個人的に男女共同参画についてはちょっと関心がある部分です。
僕は父親が利己的であり亭主関白気味の人で、幼少期に母親に対するセクハラやモラハラ見ていたので、父親や、男の友人の女性に対する扱いにずっと何かモヤモヤする気持ちがありました。(僕が5歳くらいの頃に両親は離婚しています)
父は利己的でキレやすいものの、自分の許容範囲内で人を楽しませることも好きな人だったので、家庭内に暴力が無かっただけでも感謝すべき事なのかも知れないと今では思います。
高校が男子校だったので、クラスメイトの「俺の女が〜」とか「女が」的なセリフを聞くと、人は所有物じゃないんだがなぁ〜と思いながら、はいはいと聞き流していました。
思想は様々あれど、僕個人としては性差や性的指向を起因とする社会的な不平等が早く無くなれば、より良い社会になると信じています。
が、欧米などでは男女平等の意識が日本よりも進んでいるものの、それが故に子育て中の夫婦間で役割の分配がうまくいかない事も多くあるらしいですね。
子育てにおいて、身体的な理由から女性でしか叶わない役割が存在する為ですかね、僕は実際に子育てした事がないので、よく分からんのですが。
ぶっちゃけ男女平等とかカッコいい事言わずに、生活の中で互いのやりたい事と足りない部分を補い合うように話し合いで役割を決めれば良いんじゃないかな〜って思います。
要するに、選択肢や様々な権利を性差を理由に狭められては良くないよね〜って思うんですわ。

ちょっと記憶が曖昧なんですけど、アメリカ人批評家のスーザン・ソンタグが、著書の中で、男性が自分の性器を銃(マグナム?とかリボルバー?)と称し、男性性と強さを履き違えて誇示したがる事に対して、「は、馬鹿じゃねえの?」的なことを語っていたのを読んだ時に、ソンタグが大好きになりました。
あぁ、わかるわかるwww、と。
--------------

さーてさてさて、写真の話に戻ります。
冒頭で写真は不完全な媒体と称した事は、どう言う理由からか説明しますね〜。
まず、フィルムで撮っているから写っているものは絶対に事実だ!実態だ!改竄されていないんだ!って思っている人はいるかも知れませんが、実はそんな事ないんです。
撮影や印画紙上にプリントする技術の中で、多重露光、トリミング、スポッティングなど様々なテクニックでフィルム写真も改竄可能です。
テレビの心霊番組で時々出てくる昔の心霊写真とか、そう言ったものが多いですね。
現在の心霊写真や心霊映像の方がデジタル加工であからさまでわかりやすいですけどね。
歴史的にも旧ソ連が意図的にトリミングした写真をプロパガンダで使用したなんて話も有名ですよね。
フォトショップを扱ったことがある人はわかりやすいかも知れませんが、デジタル写真も同じように、編集で撮影された意図と違うイメージに作り替える事が可能です。
故に、写真から得られる情報やイメージが実態であるという保証はない、ということが言えると思います。
しかし、実際に警察の証拠写真や裁判などで現場の実態を表す証拠として写真が使われて居ますね。
写真はご存知の通り、光を使って像を成します。
故に、過去そこにその光が無ければ、その像は存在し得ません。
写真はその場の光を利用し作られた像であるという技術的な特性から、そこに写されたものが嘗てそうであったと言える程の信用性はあります。
・光が像を成すという写真の技術的な特性から、写っている物や事象が過去に実在したという信用性がある。
・写真の成す像(情報)は後から改竄する事が可能であり、写真から得られるイメージや情報が実態である保証はない。
という矛盾する点を同時に内包しているという事です。
故に、写真は情報を伝える媒体として不完全だと考えています。
と、まぁ不完全な媒体であると前置きした上で、記号としての役割において優れていたりもします。
「コード(記号)無きメッセージ」と称されるくらい、よく伝わります。
例えば、リンゴの写真があったとして、日本人の僕がその写真に写されたものがリンゴであると言うことはすぐに認識できますが、ケニアの子供やリトアニアの老婆などが見てもリンゴの記憶さえ持ち合わせていれば、それがリンゴだと言う事が認識できると思いませんか?
しかし、それが日本語で「リンゴ」と書かれた紙だった場合、そうはいかないでしょうね。
そういったところに写真という媒体は記号としての優秀さもあったりします。

ちなみに僕は、写真作品を鑑賞する時に、「これは実態かどうかは分からないし、本当の意味で同感することは不可能だが」という前置きのもと作品の中に「なぜ撮られたか」「何を伝えたかったか」と言った疑問に結論を得て、納得できた時に読み終えます。
故に、読み終わらない写真集が多くて楽しいですね。
買って何年か経ってから突然に納得できた作品もあります。
そういった理由により、できるだけ作品の情報が欲しいのですが、まぁ、情報が少ない方が作品に費やす時間が長いと言うのも事実なので、そういった意図を持って情報を減らされると作家の思う壺なんですけれども…。
写真ってややこしい媒体なんだよ!
わかりやすいけど、わかりにくいんだよ!
だからちょっとした願いとして、作品を楽しむ為に、言葉で写真を形容しない程度に、言葉でステートメントくらい頂戴したいです!って思います。笑
以上の理由により僕は写真作品において、言葉は必要であると考えています。
長くなってしまって申し訳ないですが、お付き合いありがとうございました。
