
ちょっとの工夫で、読書の効果をあげよう
読書してます?
3ヶ月前に読んだ本の内容、
覚えてます?
そこで読んだ内容は、ちゃんと身になってますか?
今日は、
ちょっとの工夫で
読書で得た知識がより身につくようになる
というお話。
読んでも読んでも、
すぐ忘れちゃってたんです。
でもここ1ヶ月くらいで、
ちょっとした工夫をすることで、
より知識を身につけやすくなったので、
ここでまとめておきたいと思います。
読みはじめる前に、そのテーマについて知っていることを書き出しておこう
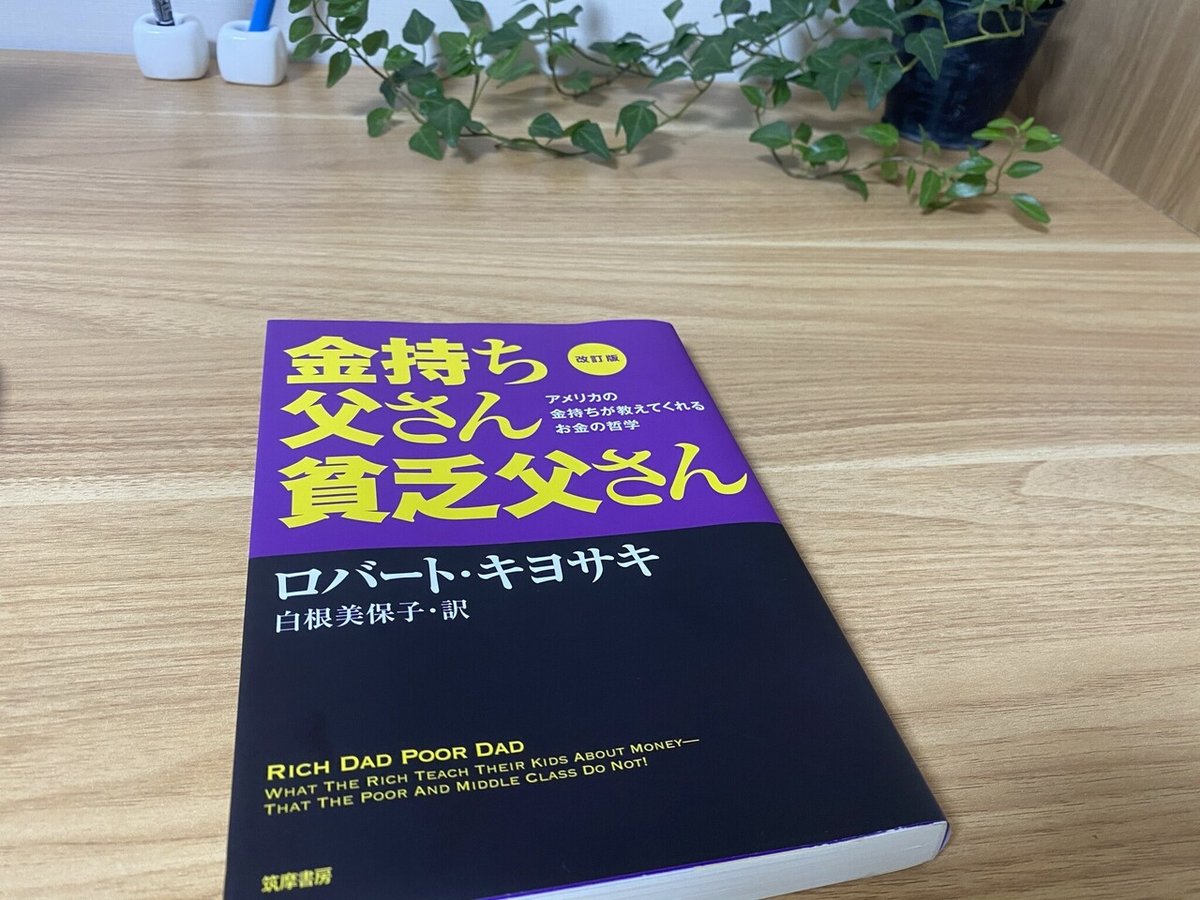
5分とかそれくらいでいいお思います。
読みはじめる前に、
その本のテーマについて
知っていることを書き出します。
人の脳は、
新しい知識を覚えるときに、
既に知っていることとむすびつけて、
記憶するそうです。
なので、
知っていることを書き出すことで、
記憶がスムーズになります。
ついでに、
知っていることを書き出すと
知らないことや知りたいことについて
頭の中で整理がつくので、
その本の中で
何に注目して読めばよいか
ポイントをつかみやすくなります。
「思い出す」を繰り返す

本の内容を記憶に残すには、
「思い出す」という動作が大切です。
ぼくはこの動作を次のような形で4回やります。
①読んでいて興味と思ったら、本をとじて思い出しながらメモする
②翌朝、そのメモした内容をツイートする
③1冊読み終わったら、感想をまとめて、ブクログに投稿する
④1ヶ月後にリマインダーを設定して、投稿した感想を読む
以前は、
読んでいておもしろいと感じたことを
本を広げたままメモしていました。
書き写す感じです。
本をとじてメモをとると、
短い内容でも意外とむずかしい。
それだけ本の内容が頭に入っていないということです。
理解があいまいなところも、
これで気づけます。
ツイートをするときは、
だれかに教えるつもりで発信します。
教えるつもり勉強法です。
ここでも、
理解が曖昧なところがあれば、
気づくことができます。
「超効率勉強法」メモ
— よしあき@プログラミング学習中ウーバーイーツ配達員 (@rea1i2e) March 26, 2021
新しい知識を学ぶとき、そのテーマについて知っていることを書き出すなどして、事前に思い出しておくとよい。ヒトの記憶は、古い情報に新しい知識をむすびつけて、覚えるようにできてるんだって。
#読書 #メンタリストDaiGo #Dラボhttps://t.co/aXKHr67J9T
メモする、
ツイートする、
感想を投稿する、
投稿した感想を振り返る
という具合に、
意識的に思い出す作業を繰り返すと、
記憶に残りやすくなります。
脳は、
繰り返し思い出した情報を
重要な情報と認識して
記憶するそうです。
何も考えない時間をとる

読書をしたあと、
意識的になにも考えない時間をとると
よいそうです。
ぼくは、
25分読書をしたら、
5分休むことにしています。
休憩中は、
スマホをいじったり、
ほかの用事をするのではなく、
瞑想したり、
寝転んでぼーっとしたりします。
そういう時間に、
脳は記憶を整理するそうです。
なので、
寝る前の読書なんかもよいかもしれません。
まとめ

今日は、
ちょっとの工夫で、
読書の効果をあげる工夫を紹介しました。
読みはじめる前に、
知っていることを書き出して、
4回以上思い出す機会を作って、
休憩をはさみながら、
上手に脳を使って、
記憶しましょう。
あとは、
実際に行動することですね。
それが一番。
おまけ

今日まとめた内容は、
メンタリストDaiGoさんの
勉強法に関する本を参考に、
書いてあることを採用したり、
それをヒントに思いついて実践したことを
まとめました。
今日ご紹介した内容以外にも、
役に立つ実践的な内容が
たくさん詰まっています。
オーディブル版もあります。
