
ダイスエクスマキナ、デザイナーズノート
はじめに
本記事はゲームマーケット2024秋にて頒布する2人用TCGライクカードゲーム、ダイスエクスマキナのデザイナーズノートである。
まだ前編をご覧になっていない方は以下を先に一読ください。
バランス調整について
ゲームを作るにあたり、悩む人が少なくないのがバランス調整だろう。デジタル、アナログとまぁまぁな数ゲームを作っているが、そんな自分がバランス調整に関して達した結論が「面白ければいい」である。
もちろんバランス調整を放棄するわけではないく、優先順位の話である。「面白い」と「バランスがいい」のどちらを優先するべきか、それは即断で「面白い」である。
反対派の人のために最高にバランスが整ったゲームを紹介しよう。
何人でもでき、勝率は2人なら50%、3人なら33.3%と人数を等分した割合だ。インストもほぼ不要、仮に必要でも1分で終わる。費用もかからず0円で何度でも遊べる最高のゲームだ。
その名はじゃんけん。バランス絶対主義の人は一生これをやっていてもらいたい。
この逆で「最高に面白さを追求しバランスが崩壊しているゲーム」も存在しており、そちらの方に価値を感じる人が多いだろう。
極端な例を挙げてしまったが面白さとバランスは完全独立事象ではないことは十分わかっている。そのうえで面白さを出すことにやや傾けた方がゲームとしては良さそうだ。
プレイヤーがやりたいものは「ゲーム」であり「出来のいいシミュレータ」でないことが多い
面白いゲームの作り方
2デッキ組み合わせ制について
この2デッキ組み合わせ制だが、ガンナガンなどでおなじみのシステムである。1箱に数デッキ入っており、そのうち2つを組み合わせて即席デッキを作る仕組みのことだ。拙作グリッツでも採用しており、5デッキあれば60通りの対戦組み合わせが可能なので、ボリュームやリプレイ性を出しやすくて重宝している。今回もう一度やるにあたり、かなり再現性が高く仕組み化出来たので共有したい。
結論から言うと、やったことはmtg(マジック:ザ・ギャザリング)のカラーパイの再発明だった。
最初にすること、それは現在できているルールの分割である。現状のままで構わないので、このゲームの構成要素を分解しよう。一番最初のバージョンで既にダイス周りのルールと、TCGライクであること、なんとなくのカードタイプは決まっていたので以下のように分解できた。
ダイス
・ダイスのレベル
・ダイスの個数
・出目(最小値、最大値、偶数、素数)
TCG
・デッキ(山札)
・手札
・場
・墓地
・ライフ
カードタイプ
・メインになるカードタイプ(クリーチャー→アクション(呪文)に)
・フラッシュ
・置物
可能であれば10以上には分解しておきたい。そのうち何個かを組み合わせてデッキの候補を作っていった。メイン要素とサブ要素を決めてガチャガチャといじっていく。こんな感じで最初のプロトタイプが出来上がった。
・連打(場のカードの枚数×ダイスの個数)
・ランプ(ダイスのレベル×アクション)
・装備品(置物×手札)
・占術(フラッシュ×出目)
・自傷(ライフ×墓地)
個性を作ろう
カードをなんとなく作っていきながら方針を考えていく。ここで意識するのは出来ないことを作ることだ。
10個の要素に対して得意、不得意、普通をどれぐらいの割合で決めればよいだろうか。これは自分は4:2:4(得意/不得意が4、普通が2)がいいと思っている。
苦手と言うのは「全くできない」位で丁度よい。全く装備品が入っていないデッキ、全くダイスに関連しないデッキなどだ。逆に得意な方は同様に振り切ってデッキの半分以上それに関連したい。
得意や不得意の要素がデッキごとに完全にかぶらないようにすると、どのデッキを組み合わせてもそれで個性が生まれていく。各要素で見ると2デッキが得意、2デッキが不得意、1デッキが普通になる。
得意と得意を合わせると大得意が生まれ、得意と不得意を合わせて普通、不得意と不得意を合わせて大不得意になる。イメージとしては+1~-1を組み合わせると+2~-2になるようなイメージだ。先ほど得意不得意はかなり振り切るという話をしたが、これは2つを組み合わせると薄まってしまうからだ。
天敵を作ろう
とはいえ大得意を止められるような手段は用意しておきたい。装備品が並んで何をやってもリソース差で潰される、フラッシュが全部そろって何も出来ない、それは気持ちいい体験だが相手からしたらたまったものではない。では対抗手段、天敵はどれぐらい用意したらいいだろう。
全5デッキなら天敵は2以上である。こう言い切れるのは鳩の巣原理というのが存在しているからだ。相手がある要素2つに寄ったデッキを選んだ時が問題なので、残りのデッキは3つである。その2つをどう選んでも天敵が含まれるのは2以上のみだ。
同様に8デッキから3つずつ選ぶようなゲームがあったとしたら3(5-3+1)以上になる。これを全ての要素に反映していくと、どうやっても対抗手段を持てるようになる。

そのデッキにしか出来ないことを作ろう
今まで書いてきたのは組み合わせた時の話であり、デッキ単体にも目を向けておきたい。
カードゲームというのはルールに対してカードで例外を作るゲームである。カードを使うにはダイスが必要、ダメージの蓄積により勝利する、などのルールに対して「ダイスを使用せずに出せるカード」「ダメージ以外の手段で勝利するカード」などがある。やりすぎない程度に例外を作っていくと楽しいゲームになる。
ドラゴンクエストにはメタルスライムという敵がいる。これは他の敵よりも経験値が多いが、ただし攻撃を失敗してダメージ0ということがある。結果的には1攻撃当たりの経験値は他の敵と変わらない。これにプレイヤーは熱狂しひたすらメタスラ狩りをするのだ。
今のは見せ方の話ではあるが、ズルをしている感があると楽しいのだ。これにより、以下のような効果を作った。
・ダイスを使わずに装備品を出せる
・ダイスを使わずにフラッシュを出せる
・特殊勝利
・山札(ライフ)を回復
・何もしなくてもダイスが増えていく
これらをリーダーに付与したり、デッキの軸になる枠(1デッキ当たりの枚数を増やし、イラストを豪華なアクション)にし出会う可能性を上げた。これは1~2回しか遊ばれないことが多い同人ボドゲであることを意識している。

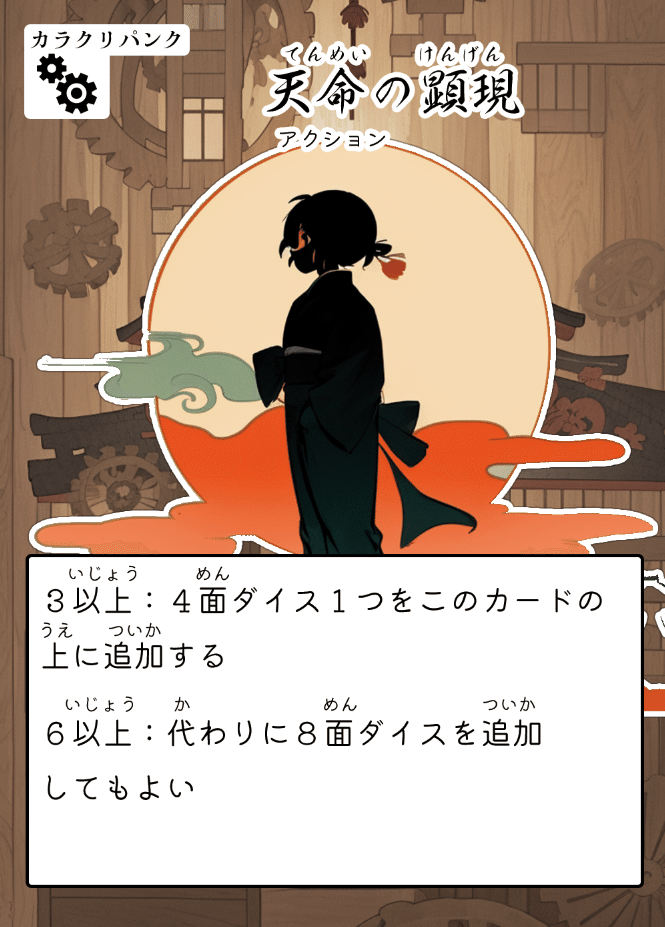

相手のコンボに驚けるゲームを
うやむ屋は「相手のコンボに驚ける」ゲームを目標にしている。これだけだとピンと来ないかもしれないが、
①同じカードプールで
②自分の想像を上回るコンボを
③相手から受けたい
のだ。未知とコンボ好きの複合であり、ゲームを楽しむための道具として認識している傾向がある。面白さ重視と勝利重視が8:2ぐらいである。その「面白さ」の中でもとりわけ自分はコンボを重視している。
この原体験となったのはおそらくドラゴンクエストというデジタルゲームだろう。このゲームは相手と自分の呪文が共通である。相手が使える呪文は大体自分も使える。相手の回復手段が自分も使えるし、自分の攻撃手段を相手も使用してくる。
冒険も中盤に差し掛かるころ、スクルトという呪文を覚える。チーム全体に防御力アップ、ふーん地味だなと思ってしばらく進めると「スライムつむり」という敵が現れる。相手はスクルト、スクルトとその地味な呪文を連発しているが2~3ターンもすればおかしいことに気づく。やたら硬いのだ。
そこで自分もボス相手に使ってみた。確かに硬くなった。一番弱い回復呪文で十分なほどだ。ここで自分はそのスクルトという呪文の価値を知ったのだ
とはいえ相手からコンボを受けるのは非常に簡単である。コンボをたくさん用意するだけで良い。ここで言うコンボはおおよそ3種類ある。
・相乗効果で両方を強くする
・デメリットを弱くする
・デメリットをメリットに変える
自分は「デメリットをメリットにする」ことに気持ちよさを感じるのでこれを重視して作っていく。
手札を捨てる+墓地利用、ダイスを置く+ダイスを回収する、などルールの範囲でデメリット(コスト)と相性のいい効果を配置していく。これをデッキ全体に散らすことで、どのデッキを選んでもコンボが成立するようになるのだ。
カラーパイについて
結果、出来上がったものはカラーパイだった。mtgには色と言う概念があり、全ての要素に対して色ごとに得意不得意がある。概要を書くと
・色により出来ることがある
・色により出来ないことがある
・同じ要素でも色によりカードの種類数(登場頻度)が違う
・同色同要素でも色によりコスパが変化する
という感じだ。まぁ意図せず車輪の再発明をしてしまったが自分としては満足している。
詳細については、本家の記事を紹介するのでそちらを参照していただきたい。
今までのものを無視しよう
再度になるが、プレイヤーがやりたいものは「ゲーム」であり「出来のいいシミュレータ」でない
バランスは面白さを作るためのツールでしかないことを意識し調整していこう。バランスもある程度大事だが、特定のカードが強ければ別のカードを弱くすることで最終的な勝率は調整できる。
おまけ
やや余白が出来たのでこのゲームの名前の由来を書いていきたい。
このゲーム、ダイスエクスマキナの元になった単語は「デウスエクスマキナ(機械仕掛けの神)」である。名前だけ、響きだけ聞いたことのある人も多いだろう。
デウスエクスマキナという言葉は元は演劇の単語だ。これは作中の状況が非常に混乱した時に「神」が無理やり解決するシナリオのことを指す。
死んだ恋人を神が生き返らせてくれました、悪い王様を神様が懲らしめ王は改心しました。といったように劇中の人物ではなく万能な○○によって状況が全部解決しました、とくくれるものを指す。
本作に「神」は存在せず、代わりに「ダイス」がそこにある。制作中に仮決めとして置いたが、完成が近づくにつれこの作品を表現するようになったので気に入っている。
宣伝
何度も申し訳ないが、本作はゲームマーケット2024秋にて頒布する作品のデザイナーズノートである。気になった方はぜひ足を運んでほしい。
