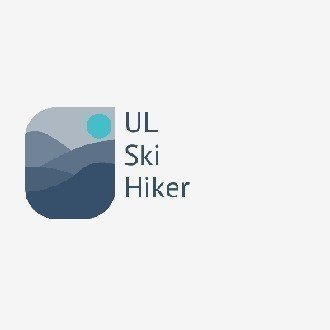厳冬期の結露対策・実践編 ツェルトダブルウォール化と寝袋システム
Day 2021.01.25-26 平標山
ようやく仕事も落ち着き時間が出来たのでテストに行ってきました。事前にある程度のシミュレーションはできていましたが、試作したギアが厳冬期の低温下(マイナス10度〜20度以下)でどのように機能するかは正直未知数です。
前回までの記事
温暖期のテストを経て追加で施した改造は1点。通気性に課題があった為、ツェルト1の庇(ひさし)のカットで換気性能を向上。迷っていた底面のカットは先送り。とりあえず結露の量をチェックするのが今回の目的です。結露と言っても氷点下だと水分は全て凍りますが、朝に調理で火を使えば溶けてしまうので、機能面のチェックだけでなく、テント内での行動パターンとの関連性も重要な見極めポイントです。
換気性の向上。5g。床はまだ残しておいて、この状態で一度テストします。 pic.twitter.com/fwIcRSSUaH
— UL Ski Hiker (@greenliftgo) November 12, 2020
シェラフカバーの改造
新調したシェラフに関しては良いに決まっているので心配無用。本来はインナーであるOMMコアライナーを改造したシェラフカバーはツェルト内の結露(凍結した水分)から寝袋を物理的に守るための物です。通常の防水透湿素材のシェラフカバーやビビィでは内部結露でかえって寝袋を濡らしてしまうため、この方式を採用しました。
以上2点、結果は以下の通りです。ツェルト内の結露は予想以上となりましたが、改善策は既に考案済みです。
ようやくテスト。 pic.twitter.com/bl3tjvMsu4
— UL Ski Hiker (@greenliftgo) January 25, 2021
ツエルト1内部の結露状況と行動パターン
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?