
やってみると意外と難しい、良いリサーチのコツ!【企画の道具箱 #20】
■はじめに
みなさん、こんにちは!
仕事をしている中で、上司や先輩から「次の会議資料に必要だから、食品業界市場の動向を調べておいて!」や「清涼飲料水の競合についてリサーチよろしく!」といった指示を受ける場面がありませんか?
いざ張り切って情報を集め、整理して提出したものの、上司や先輩からの反応は、「なんか違うんだよな~、これだと具体的な数字やデータが足りないんだよね」や、「いや、競合他社の戦略じゃなくて、競合他社の清涼飲料水の事業規模、商品ラインナップや顧客層を知りたかったんだよ…」といったような指摘を受けて、最初からやり直し…なんて経験はありませんか?
リサーチとは、特定の目的にもとづき、必要な情報を収集・分析し、その結果をもとに意思決定や次の行動の根拠を与える活動です。
今回の記事では「リサーチ」に焦点を当てた内容で、初めてリサーチを実施する方を主な読者としています。
さらに、本記事の後半では、調査のコツや検索等で使えるウェブサイトの情報を公開していますので是非最後までご覧ください。
■ダメなリサーチと良いリサーチ
▶ダメなリサーチ
リサーチは一見簡単に思えるかもしれませんが、実際には奥が深く、注意して進めなければ落とし穴にハマる可能性もあります。ダメな例をいくつか列挙してみました。
<ダメなリサーチの例>
調査結果の活用先が曖昧で微妙な成果
調査によって何の問い(論点)を解いているのかが曖昧で、とりあえず業界動向をWeb検索した結果をサマリしただけで完了とした
統計局の大量データを取得し、ある時点のデータでサマリしてグラフ化しただけ
何のため?を忘れたただの作業
求められるアウトプットを意識せず、リサーチをすること自体が目的となってしまった
調べたものの、自分が興味・関心を持つ情報を整理しただけで何の価値も生み出せていない
リサーチ迷子に入り込み時間を浪費
情報を手あたり次第集めた結果、時間を浪費してしまった
リサーチの終わりが分からずに延々と探し続けた
調査した結果が活かされないようなアウトプットになってしまったり、とにかく検索、検索、検索で何をゴールにしているのか分からなくなったり、目的を忘れて作業に没頭してしまうようなリサーチは、ダメなリサーチと言えます。
▶良いリサーチ
一方で良いリサーチとはどんなリサーチでしょうか?
リサーチは単なる情報収集ではありません。その本質的な目的は、「行動を変えるための根拠を提供すること」です。
つまり良いリサーチとは、リサーチによって得られた結果が、意思決定や行動を検討する際のインプット情報となり、その先の具体的な行動変化に繋がるインプットや示唆を提示できることです。
良いリサーチ=【調査】+【示唆】→【意思決定/行動】
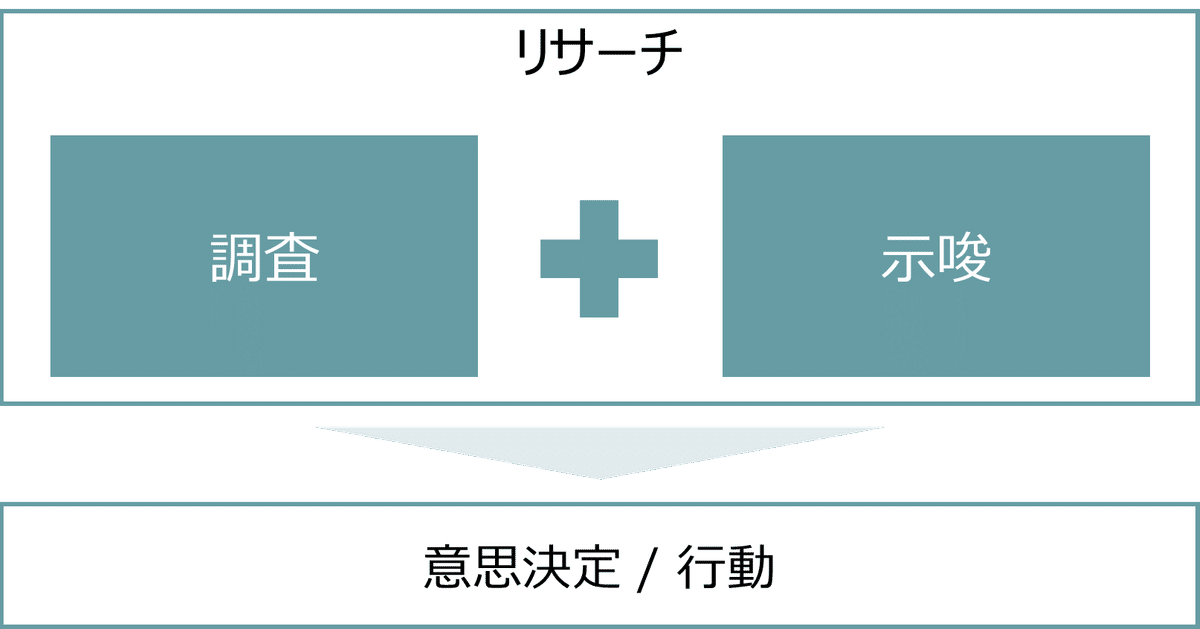
もう少し分かりやすく具体例で説明しましょう。
例えば、自社の製品改善プロジェクトで、顧客の満足度調査をしたところ「配送遅延が主要な不満要因という結果から、配送プロセスを見直すべし」という方向性が出てくれば、配送センター増設や他社配送事業者との協業といった次の検討に繋がる。
と言ったような具合で、調査から得られる示唆をもとに、検討という次の行動に繋げます。

■良いリサーチとなる調査の進め方
良いリサーチとするためには、「示唆出し」および「示唆につながる“良い調査”」が必要です。
【示唆につながる良い調査】+【示唆】→【意思決定/行動】
「示唆を出す」ところは容易に導けるものではなく、経験や訓練が必要な要素であり難易度が高いため、ここでは取り組み方次第で誰にでもできるようになる、「調査」の部分に主に焦点を当てて話を進めます。
調査を進める手順を3つの流れで説明します。

▶1. 調査設計
「この調査はなんのために実施しているのか?」「何をどこまで調べたら終了と言えるのか?」を明確にするために調査設計をしていきます。
【目的を確認】
取り組みの背景やなぜ調査に至ったのかを確認して理解することから始めます。
【調査の論点出し/仮説出し】
調査をするときには、「何を知りたいのか?」の前に解決したい課題や、それを知ることでどんな判断がしたかったのか?があるはずです。 そのために調査の論点を明確にします。
論点を明確にすることは、冒頭のダメなリサーチにあるような何のためのリサーチなのか?がはっきりしますし、調査を通して論点を解くためのネタをアウトプットすることがゴールとなります。結果として、無駄な時間を浪費しなくて済みます。
Tips💡:論点とは
論点とは目的に到達するために「解くべき問い」のことで、この問いを全て解くことで目的に到達することができます。論点は「問い」であるため疑問文の形で書きます。
論点に唯一の正解は無く、目的を達成する確度を上げられるような論点設定ができるとベストです。
論点を考えるときは、まずは与えられた「問い」そのものからスタートします。とはいえ、ビジネスにおいて上司や先輩から明確な論点を渡されることはほとんどありません。
例えば上司からSDGsを背景とした案件において「プラスチックフリー包装の市場調査をしておいて」と指示されたとします。
そこで唐突に「”プラスチックフリー包装の市場調査”をするぞ!」とPCに向かってWeb検索を始める前に、以下のような具合で論点を設定します。
<論点設定>
論点を、例えば「プラスチックフリー包装市場の現状とこの先の動向は?」としたいところですが、そうではなく、なぜ上司がこの調査指示をしてきたのか?を考えます。
調査指示の背景として「自社で新たなビジネス立ち上げを検討するための材料にするのだな」や「そういえば来週ビジネスプランを提示する会議が予定されていたな」といったように思考を張り巡らせるわけです。
もちろん上司と話をして目的をすり合わせた上で、調査の論点を設定すると、例えば以下のようになります。
論点:プラスチックフリー包装市場への参入は魅力的か?
まずはこのように「論点」を立て言語化することが最初の一歩になります。その上で論点の答えを作るための下位の問いとして、「サブ論点」を立てていきます。
<サブ論点設定>
サブ論点を立てる際の型はいくつかあるのでいくつか使えそうな例を紹介します。迷ったら全ての型でサブ論点を立てるというくらいのスタンスで取り組むと良いでしょう。

(再掲)<論点>プラスチックフリー包装市場への参入は魅力的か?
この論点に対して、先ほどのサブ論点の型である、6W5Hの型を使いながら考えていくと以下のようになります。
<サブ論点>
・この市場の大きさは?(市場規模)【How many】
→主要な市場はどこか?(地域性や文化)【Where】
→どんな商品があるのか?【What】
→誰が主なユーザーや消費者なのか?【Whom】
・この市場は伸びるか?(市場成長性)【How long】
→流行っている地域とそうでない地域の差や特徴はあるのか?【Where】
・この市場は儲けやすいか?(収益性)【How much】
・この市場における既存プレイヤーは誰か?(競争環境)【Who】
etc…
実際には上記以外にも、法規制や地域の条例等もあり得ると思いますので、リスクとチャンス型も使いながらサブ論点を洗い出していくと良いでしょう。
<仮説設定>
論点が定まったら、その論点に対するそのとき時点の解=仮説を出します。
先ほどの例で言えば、以下のように調査の論点と仮説を考えながら調査のストーリーを組み立ててていきます。
「プラスチックフリー包装の市場規模は、環境意識が高い消費者が増加しているため今後伸びていくのではないか?ということは、包装製品を消費者が利用するシーンにも着目するとより精度の高い調査ができるかもしれない。」
「さらに、世界的に見て環境意識が特に高いであろうヨーロッパ諸国と、そうではない地域の市場成長の違いもありそうだな。それぞれの地域ごとの特性を考慮して市場成長の違いを調査していくか。」
「ということは、ヨーロッパ諸国において既に同じ考えで取り組んでいる企業もいるだろう。それらの企業を競合と見立てたとき、彼らはどのような商品を誰向けに、いくらで、どう提供しているのだろうか?」
「消費者や地域特性に着目してみたが、他には…」といった具合で論点と仮説を整理しながら目的に沿うように考えていきます。
【調査の深さを確認】
どこまで調査するか?やどのようなアウトプットとするか?は取り組みの目的や検討のタイミングによって異なります。
新規事業を題材として、リサーチのタイミングが「着手段階」「仮説立案段階」「仮説検証段階」とあった際、それぞれのタイミングにおけるリサーチの目的、調査の深さの一例を示します。

▶2. 調査実施
調査設計に基づき、そのときの目的に見合った情報を収集します。調査には様々なやり方があります。その一例を記載します。
情報源
業界レポート、政府統計、インタビューの実施など。
手法
Web活用による情報検索、定量調査(市場データ)、定性調査(顧客インタビュー等)など。

Tips💡:調査の質を高めるコツ
・Web検索等で簡単にヒットするような情報は誰でも知っている情報とも言え、それだけでは価値が低い、すなわち質の低い情報です。
・リサーチをする際は複数のソース情報を組み合わせて示唆を出すか、簡単には手に入りにくい情報の希少性で質の高さを出すかが考えられます。前者はスキルによるところもありますが、後者は取組み次第で誰でも可能です。
<簡単には手に入りにくい情報の希少性で質の高さを出す取組み例>
■一次情報へアクセス
Web検索でヒットする情報の多くは、第三者の意見や考えが入った、加工された情報であることが多いです。一次情報を取得するために足を動かし、実際の現場を観察するのも一つの手です。
例えば、toC向けの製品やサービスであれば、実際の店舗の状態や消費者の反応を観察する。toB向けであっても工場見学ツアーへの参加、アルバイトやパートタイムで実際の業務の雰囲気を掴むといったことが考えられます。
■希少な繋がりや専門家へのアプローチ
業界専門誌を複数読み漁り、不明点を掲載されている著者へ問い合わせしてみる。SNSで業界の専門家っぽい人にDMで質問することやコミュニティへ参加して質問を投げかける。等も実施する価値があります。
▶3. 調査結果の整理・アウトプット
調査で収集した情報を整理し、リサーチのアウトプットとしてまとめます。
アウトプットは、調査設計の際に立てた目的に沿った形に整形します。
以下にいくつかの例を掲載します。

Tips💡:ファクト調査の際に必ず記載すべき項目2つ
ファクトとなる情報を整理する際には、「①いつの情報か?」、「②どこから得た情報か?」の2点は必ず確認し記載しておきましょう。
①いつの情報か?を明記することで情報の新しさを判断できます。
②どこから得た情報か?を明記することで情報の信頼性の把握ができ、再度情報を確認する際に必要となるためなるべく具体的に記載することをお勧めします。
■リサーチのコツや参考情報
リサーチの進め方は前段で説明しましたが、ここではコツや参考情報としてWebで公開されている有用であろうサイトを紹介します。
▶リサーチを効率よく進めるコツ
Web調査の際、イチから全てのサイトを拾い上げ、一つ一つ確認していく方法もありますが、もっと効率よく実施するコツがあります。
<画像検索の活用>
市場調査であれば、Googleで「○○市場 推移」と画像検索するとそれらしい図表が大抵ヒットします。そのヒットした画像が掲載されているWebページへ飛んでいくとソース情報や関連するキーワードが拾えることがあります。
<生成AIの活用>
最近では生成AIの活用も有効です。情報の信ぴょう性は自身で確認する必要はありますが、全く知らない業界等の調査をする際、関連するキーワードやトレンドになっているキーワードを拾ってくれるので、それらをもとに、Google等で検索していくことでより精度が高く、効率的な調査が可能です。
そのようにして、拾ったソース情報のサイトやキーワードで調べていくことで、調査の目的に早くたどり着く可能性が高いです。
▶リサーチの際の参考サイト
主に無料で検索、調査レポートの取得ができるサイトをピックアップしました。
<文献検索>
CiNii(国立情報学研究所)
https://cir.nii.ac.jp/
J-STAGE(国立研究開発法人 科学技術振興機構)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
<公的調査レポート・統計データ・情報取得>
■国内関連
・総務省統計局トップページ(総務省統計局)
https://www.stat.go.jp/
・e-Stat 政府統計の総合窓口(総務省/独立行政法人統計センター)
https://www.e-stat.go.jp/
・統計Dashboard(総務省統計局)
https://dashboard.e-stat.go.jp/
・各種統計(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/statistics/
・経済分析室(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/keizaikaiseki_toppage.html
・中小企業白書(中小企業白書)
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html
■海外関連
・JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)
https://www.jetro.go.jp/
<その他情報取得>
■テーマや各種資料を検索する
・リサーチ・ナビ(国立国会図書館)
https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi
■有価証券報告書の取得をする
・EDINET(金融庁)
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/
■金融機関各社による調査レポート
・みずほ産業調査(株式会社みずほ銀行)
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/industry/sangyou/index.html
・経済・業界動向に関するレポート(株式会社三井住友銀行)
https://www.smbc.co.jp/hojin/report/
・経済・産業レポートとマーケット情報(株式会社三菱UFJ銀行)
https://www.bk.mufg.jp/rept_mkt/index.html
■おわりに
リサーチは単なる情報収集ではなく、リサーチの結果、意思決定や行動を検討する際のインプット情報の提示です。
ぜひ本記事で紹介した手順やTipsも活用していただき、リサーチの質を高めてプロジェクトの成功に繋げてください。
この「現場で使える!コンサル道具箱」は、その名の通りすぐに現場で使えるコンテンツを無料で紹介しているnoteです。
あなたの欲しい道具が探せばあるかも?ぜひ他の記事もご覧ください!
ウルシステムズでは「現場で使える!コンサル道具箱」でご紹介したコンテンツにまつわる知見・経験豊富なコンサルタントが多数在籍しております。ぜひお気軽にご相談ください。
